
あの人に聞くデビューの話 第10回 前編 [バックナンバー]
Bialystocks・甫木元空が振り返る表現者としての原点
音楽家 / 映画監督という2つの顔を持つ異才のルーツとは?
2025年5月19日 19:00 24
音楽ライターの松永良平が、さまざまなアーティストに“デビュー”をテーマに話を聞く「あの人に聞くデビューの話」。この連載では多種多様なデビューの形と、それにまつわる物語をじっくりと掘り下げていく。第10回となる今回は、
取材・
ミュージシャンとして2019年にBialystocksを結成する以前から、故・青山真治監督のプロデュースで注目を浴びた映画「はるねこ」(2016年)の監督としてすでにデビューを果たしていた甫木元空。音楽か、映画か、の二者択一ではなく、彼の中では両方の表現が分かちがたく結び付いている。そしてその両方ともが、自分という存在の根源にあるものを見つめながらも、そこから紡ぎ出される物語を外の世界へと波及させてゆく力を持っている。
Bialystocksは2021年に自主制作アルバム「ビアリストックス」を発表後、翌22年にはメジャーデビュー。あっという間に大きな会場を埋めるほどの熱い支持を獲得した。そして、映画監督としては今年、青山真治が残した脚本を受け継ぎ執筆、監督した「BAUS 映画から船出した映画館」が公開されたばかり。「デビュー間もない」という表現が追いつくヒマもないほどずんずん先へと歩みを進めている甫木元空にあえて聞きたいと思った。あなたにとってのデビューとは?
父の舞台演出を手伝い物作りの面白さを知る
──「甫木元(ホキモト)」という名字は珍しいですよね。
そうですね。母方の名字で、高知と、あとは和歌山あたりにいるそうです。黒潮海流沿いに多い名字らしいです。
──多いと言っても、全国に数十人の超レア名字ですよね。僕も最初は、名前が正しく読めなくて。「ホキ」さんなのかなと思ったりしてました。
「ウラキゲンクウ」とか読まれたりもしてましたね(笑)。
──物作りにまつわる最初の頃の記憶といえば?
父親は舞台の演出家、母親がピアノの先生をしながら街の合唱団をやったりしていました。両親がそういう活動をしていたので、物作りに対するハードルは幼い頃から低かったのかな。母は、宮沢賢治の朗読に自分が書いた曲を付けたりしてました。昔、おやこ劇場という、子供の教育も兼ねて街の団体が劇団などを招くような取り組みがあったんです。うちの母親が所属している朗読劇を行う劇団もよく呼ばれていました。僕はそれについていって、小さい頃から舞台装置に必要なケーブルをさばいたりしてたんです。
──物心つく前から舞台制作の現場にいた。
自分の中で印象に残ってるのは、中学に上がった頃、父親が演出する舞台の中国公演にスタッフとして同行したことです。普通なら反抗期が来る時期だと思うんですけど。公演を手伝ってるときに大人が本気でケンカする場面を目の当たりにして(笑)。照明がちょっとズレてるだけで「何やってんだよ!」とか言い合いになったりする。大人たちが本気で物作りに取り組んでいる姿を見て、衝撃を受けたんです。傍から見たら「どうでもいいじゃん」と思えるようなことにも真剣に向き合って、ときにはケンカしながら力を合わせて1つの公演を作り上げていく。その過程を中学1年生のときに見て、「舞台というのはこうやって作り上げられていくんだ」と思ったんです。そこで物作りの面白さを知りました。
──思春期の頃に受けた影響って、音楽にしろ映像にしろ、聴いたり観たりした作品から衝撃を受けるパターンが多いと思うんですけど、甫木元さんは作品というよりその裏側、つまり実地から入っているわけですね。
その公演では、何かのきっかけでマイクの音量を上げるという役割をやらせてもらいました。すごく緊張したのを今でも覚えています。舞台ができあがるまでのいろんな過程を、そこで実際に見ることができたのは大きかったですね。ちなみに、その公演は、森村誠一さんの「悪魔の飽食」という小説(第二次世界大戦中の、中国大陸での日本軍の人体実験を告発するショッキングな内容)をミュージカルにしたものでした。
──そんな舞台を中国で! それは心身ともにハードだし、体験としては、すごく強烈ですね。そういう強烈な体験を経て日本に帰って来て、いきなり普段の日常生活に切り替えられるものですか? 友達と「昨日、何観た?」みたいな軽い話をしたりできないのでは?
さすがに、そういう体験は、同級生とは共有できなかったですね。僕自身も、舞台の内容というより、「物作りって面白いな」と、そのときは漠然と思っているような感じでした。
──むしろあとあとになって、経験の重要さに気付いた?
そうですね。あれが原体験だったというか。小さい頃から絵を描いたり、歌を歌ったりするのは好きだったんですけど、漠然と物作りをしたいなと思うようになっていきました……でも、どちらかといえば演者というよりも裏方になりたい気持ちのほうが大きかったように思います。
美大進学、実験映画の世界に
──その後、多摩美術大学に進学という流れですが、美大に行きたいという気持ちを持ったのはどういうきっかけですか?
通っていた高校は美大向きとかではなく、普通の大学に進学するのが当たり前みたいな感じでしたね。美大に進学する人も全然いなかったみたいで、普通の大学に進学したほうがいいんじゃないかと学校からも言われてたんです。僕自身も高校時代に何かやりたいことを自分の中で明確に見つけられていたわけではないし、何か特別な活動をやっていたわけでもなかった。ダラダラ過ごしていたら3年が経っていたんです(笑)。多摩美に行こうと考えたのは「映像演劇学科(造形表現学部映像演劇学科)」があると知り、その中で何か見つけられそうだなという気持ちがあったから。だけど、美大の試験というものを受験直前まで調べていなかったんですよ。「どうやらデッサンというものが必要らしい」ということも、美大に行きたい人はみんな美術系の予備校に通っているということも知らなかった。
──そんな状態から、どうやって試験に臨んだんですか?
多摩美の映像演劇学科の試験はとても変わっていて、「旅」がテーマだったんです。それぞれ受験生が旅に出て出会ったものを事前にゆうパックで送り、それが合否に反映されるという不思議な試験でした。
──へえ、面白い。
「旅」という概念も、どんなものでもいいんですよ。例えば、僕の同級生は、近所を歩いていた猫のあとをつけたみたいです。猫の「旅」を記録して投稿した。僕は「旅」といったら屋久島かなと思ったので、父親の知り合いが住んでいるというので行くことにしました。ところが行ってみたら、全然知り合いじゃなかった(笑)。結局、屋久島のマンゴー農園に住み込みで働いて。そこで撮影した写真を送りました。そしたら受かったんです。
──そんな試験なんですね。すごい。
受かったのは、たまたま運がよかったんだと思います。でも、映像演劇学科にはいろんな先生がいて面白かった。インスタレーションや詩を表現している人、役者や演劇のスタッフをやったりしてる人もいた。入学したら「とりあえず作品を作ってみよう」というのが授業なんです。僕が映画や舞台をちゃんと観るようになっていったのはそこからですね。
──そうなんですか! じゃあ、それ以前はご両親が関わっている舞台から吸収していた程度?
そうです。入学したら、みんな「ゴダールが~」とか言ってて、僕は「誰?」みたいな感じ(笑)。ヨーロッパ映画とか全然知らなかった。父親に話したら「そんなことも知らないのか」と言われました。
──でも、甫木元さんには裏方の世界を見てきた積み重ねがあるから、ちゃんと古典からの刺激を吸収すれば、アウトプットするまでは早かったんじゃないでしょうか。
どうなんでしょうか。とにかく、多摩美術大学の映像演劇学科はすごく特殊で。普通の美大は映画、演劇があって、その中のコースから撮影、録音、照明、演技などを選んで4年間が終わると思うのですが、まったく区分けがなく全員全部やるのが当たり前でした。映像作家で詩人の鈴木志郎康さんが立ち上げた学科なので、学科のあり方や入学試験自体がインスタレーションみたいな感じなんです。
──鈴木志郎康さん! 鈴木さんの著書「極私的現代詩入門」(1975年)は20世紀後半の大学生にすごく影響を与えたんですよ。僕も大学時代に講義に潜り込んで受けた記憶があります。そもそも「極私的」という言葉自体、鈴木さんが作り出したんじゃなかったかな。
僕が入学した頃、鈴木さんはすでに多摩美を辞められていて、学部長は萩原朔美さんでした。でも独特な雰囲気は残ってましたね。寺山修司の天井桟敷的な、いわゆるアングラ演劇や実験映像を観る授業が多かったし、卒業生にも実験映画の作家が多い。僕も「実験映画って何?」みたいに興味を持ちました。それが自分にとっては転機になっている気がしますね。
恩師・青山真治との出会い
──そして、甫木元さんの大学時代といえば、青山真治さんとの出会い。
僕が2年生のときは塚本晋也監督が1年だけ講師をされたんです。青山真治監督が多摩美に来たのは3、4年生のときでした。青山さんのことを「先生」と呼んでる人は誰もいなかった。みんな「青山さん」って呼んでたんですよ。講師は最初に自分のゼミのプレゼンをするんですけど、そこで青山さんは「映画を教えることに僕は懐疑的です」と言っていました。それを聞いて「この人の講義は面白そうだな」と思ったんです。青山さんのゼミは「とりあえず脚本を書いてみよう。他人と物語を共有して物作りをしよう」というもの。それが自分には合ってるなと思ったんですよね。自分のフィルターを通して映像を記録していく実験映画の、いわゆる「私映画」性も面白いなとは思いつつ、物語を共有することでいろんな人たちが介入してきて、私的な世界が外に開かれていくほうが面白い、という感覚が自分の中にあった。その面白さは青山さんが教えてくれました。やがて僕は青山さんの映画や、ほかの監督の作品にも助監督として関わるようになっていきました。
──具体的にはどんな授業だったんでしょう?
実際の映画には制作部、美術部、演出部など、いろんな部署があるので、僕らもゼミ内で部署分けして、みんなで1つの作品を作ってみようということになりました。最初に組織作りをするんです。毎年夏に青山さんが短編を撮影していて、スタッフも役者も全員学生で、青山さんが映画を撮っていくのを一番近くで見られる。その実践から組織としてのやり方をみんなが吸収していくわけです。その中で、青山さんからは「まず40分の映画を撮れるように」と言われました。それができたら、40分の物語をアルバムのA面B面じゃないけど合計80分で構成して、長編作品デビューすることができると。40分というタイム感を自分の中で築けたら、「これは80分の映画だな」「これは120分の映画だな」と、わかるようになる。そうしたら自分の時間軸で表現できるようになると言われたんです。なので、みんなまず40分の作品のシナリオを書き、青山さんに見せる。そういうやりとりを続けていくうちに、青山さんのほうも学校の中で堅苦しくやらなくてもいいよなという感じになっていって、当時借りていた事務所に、みんな自分が書いた脚本を持って押しかけるようになって。それが卒業しても延々続いたんです(笑)。僕も卒業して1年くらい、ずっと青山さんの事務所に通ってたんじゃないですかね。
──熱い師弟関係ですね。甫木元さんのプロフィールを見ると「青山真治に師事して」と数ワードくらいで簡単に書いてあるけど、実際には濃厚な時間を一緒に過ごしたわけですね。
そうですね。青山さんには2022年に亡くなるまで、何かあったらよく相談してました。僕だけじゃなくて、ゼミのメンバーはみんなそうだったんです。青山さんは「映画作りは4年間では教えられない」と、ずっと言ってました。4年やれば映画は完成するだろうけど、それを配給・宣伝するまで成就できるのかと考えてくれていたんです。そんな中で、青山さんに「甫木元くんは卒業したらどうするの?」って聞かれたんですよ。「助監督を続けることぐらいしか考えていません」と答えたんですけど、「脚本できたら持ってこい。俺がプロデュースする」と言ってくれました。それで映画のための曲を自分で作り始めて、脚本を書き進めていったんです。
──監督デビュー作「はるねこ」(2016年)へと結実していく過程ですね。
その前に、僕の卒業制作として作った「終わりのない歌」(2014年)を青山さんに観てもらっているんです。僕が大学3年生のときに父親が亡くなったんですけど、父が残していたホームビデオが家にたくさんあって。そこには僕が生まれるときから幼稚園に上がる前まで、ほぼ毎日、父が記録してくれていた映像が残されていた。それを再編集して、最後に今の僕が出てきて、弾き語りを1曲して終わるという、演劇と映画を混ぜたような作品を作りました。その作品を観たあと、青山さんは「とりあえずCDと脚本を持ってこい」と言ってくれたんです。
──ついにこの話に音楽が登場しました。
青山さんとはカラオケもよく一緒に行きました。青山さんはベロベロに酔っぱらって大瀧詠一の曲を熱唱してました(笑)。僕はQueenとかを歌ってたんですが、それを見て「その声を残したほうがいいんじゃないか」と思ってくれていたらしいです。その流れで「はるねこ」では自分で歌いました。その後、2019年にイベント上映をするときに、本編の上映と劇伴の演奏をすることになった。それで、劇伴に関わってくれたミュージシャンの日、自分と同世代のミュージシャンの日、みたいな感じでいくつかバックバンドを替えて演奏したんですよ。その同世代ミュージシャンのバンドが、Bialystocksの1stアルバムを作ったときのメンバー4人。現メンバーの菊池(剛)さんが集めてくれたメンバーでした。その日は劇伴を再演するだけの企画だったんですけど、せっかくだったらこのバンドのオリジナル曲を作ってみようということになった。そこでBialystocksがスタートしたんです。
<後編に続く>
甫木元空(ホキモトソラ)
菊池剛(Key)との2人組バンドBialystocksのボーカリスト。Bialystocksは映画監督でもある甫木元の初監督作品「はるねこ」の生演奏上映をきっかけに、2019年に結成された。フォーキーで温かみのあるメロディと、ジャズをベースに持ちながら自由にジャンルを横断するサウンドの組み合わせは、普遍的であると同時に先鋭的と評される。2021年にインディーズ1stアルバム「ビアリストックス」を発表。2022年11月にメジャー1stアルバム「Quicksand」をポニーキャニオン内のレーベルIRORI Recordsよりリリースした。音楽家と映画監督としての活動を併行して行っており、2025年3月には、青山真治の企画を引き継ぐ形で脚本・監督を担った映画「BAUS 映画から船出した映画館」が公開された。
Bialystocksオフィシャルサイト
Bialystocks(@bialymusic) | X
Bialystocks(@bialystocks) | Instagram
- 松永良平
-
1968年、熊本県生まれ。リズム&ペンシル。大学時代よりレコード店に勤務し、大学卒業後、友人たちと立ち上げた音楽雑誌「リズム&ペンシル」がきっかけで執筆活動を開始。現在もレコード店勤務の傍ら、雑誌 / Webを中心に執筆活動を行っている。著書に「20世紀グレーテスト・ヒッツ」(音楽出版社)、「僕の平成パンツ・ソックス・シューズ・ソングブック」(晶文社)がある。
バックナンバー
Bialystocksのほかの記事
関連する人物・グループ・作品



















































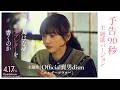






松永良平 / Ryohei Matsunaga @emuaarubeeque
2ヶ月ぶり。そして記念すべき第10回です。#あの人に聞くデビューの話 @natalie_mu @bialymusic https://t.co/K7tRXTPEw8