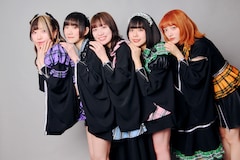森山直太朗がまったく異なるコンセプトを掲げたアルバム「⼸弦葉」と「Yeeeehaaaaw」を2枚同時にリリースした。そしてこの2作を携え、それぞれのテーマに沿った2本のツアー「森山直太朗 Two jobs tour 2025~26『あの世でね』~『弓弦葉』と『Yeeeehaaaaw!』~」をこれまた同時に走らせていく。
「弓弦葉」は、とある架空の古道具屋で流れている音楽をイメージして作られた、アンビエントな雰囲気のコンセプトアルバム。一方「Yeeeehaaaaw」は森山が自身のルーツをたどりながら、幼少期から聴きなじみがあるというカントリー&ウエスタン、ブルーグラス、日本のカレッジフォークなどを意識し、自分らしいスタイルを追求した1枚となっている。
「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw」、この対極とも言える異なる2つの世界を同時並行的に行き来するツアーには、森山のどんな思惑が込められているのか。各公演の初日を鑑賞したライター・森朋之のレビューで紐解いていく。
取材・文 / 森朋之撮影 / 山崎玲士
弓弦葉
日常と非日常、過去と未来、この世とあの世、前世と現世と今世。いろいろな“此方と彼方”の境界があいまいになり、それぞれの人のあるべき姿が浮かび上がってくる──。この日のライブを鑑賞しながら、筆者はそんなことを感じていた。ルールや常識に規定されているのが現代人だが、そこからこぼれ落ちるものこそが、人間の本質なのだと。
森山直太朗の全国ツアー「森山直太朗 Two jobs tour 2025~26『あの世でね』~『弓弦葉』と『Yeeeehaaaaw!』~」が、10月17日に神奈川・鎌倉芸術館で開幕した。
この日、森山は「弓弦葉」「Yeeeehaaaaw」という2作のアルバムを同時にリリースした。“アンビエントで静謐な旋律漂う内向的なアルバム”を志向した「弓弦葉」、“身体的な解放とともに祝祭的なブルーグラスサウンドあふれる外向的なアルバム”と位置付けられた「Yeeeehaaaaw」。対極であると同時に、互いを補完し合う2つのアルバムを引っさげ、まったく異なるコンセプトと世界観を表すツアーを2本同時に走らせる。それが「Two jobs tour 2025~26『あの世でね』」の意図だ。
「弓弦葉」の初日公演。JR大船駅から徒歩10分ほどの鎌倉芸術館に入ると、舞台の上には古い家具──ソファ、ランプ、テーブル、椅子、階段のような形をした大きな箪笥(?)──が置かれている。これらのほとんどは森山の私物。少しずつ買い集めたアンティーク家具をそのまま舞台美術にして、「とある架空の古道具屋で流れている、とある楽曲たちをイメージして作られたアルバム」である「弓弦葉」の世界をステージで体現するという試みだ。
開演時間を過ぎた頃、ゆっくりと会場の照明が落とされていく。客席のざわめきが収まっていく中、「弓弦葉」のサポートミュージシャンである大口俊輔(Piano)、須原杏(Viola)、田中康介(G)がポツポツと姿を見せ、それぞれに音を奏でる。穏やかで切ない音の重なりは、「弓弦葉」の音楽的なコンセプトそのものだ。
そして、ステージの後方に置かれたドアが開かれ、森山直太朗が舞台に上がる。いつの間にかサポートの3人は姿を消し、古道具屋の店主に扮した森山は、どこか所在なさげな様子でギターを手にして、1人で歌い始めた。
何曲か歌ったあと、再びメンバーが登場し、家具にかけられた白布を取り始める。直太朗はエプロンを着て、店の看板をひっくり返すことで、お店が開いたことをオーディエンスに告げる。曲目の中心はもちろん「弓弦葉」の収録曲だ。生きる理由、死ぬ理由もわからないまま生きるしかない我々の姿を詩情豊かにつづった「生きている」、だましだまし人生を過ごし、いつまで経っても何も起こらず、不安や希望を淡く抱きながら日々を送る様子をつづった「とどのつまり僕は」。寄る辺なさと確かな息遣いを内包した森山の歌にじっくり耳を傾けていると、コンサートに参加している、舞台を観ているという感覚が薄れていき、「ここもまた日常の延長なのだ」という思いが少しずつ強まっていく。先代から受け継いだ羊毛のほこりはたきを持って歌う姿も心に残った。
ピアノ、アコギ、ヴィオラによるアンサンブルも印象的だ。「弓弦葉」の音像は“アンビエント”という言葉で説明されている。環境音楽と訳されるこのジャンルには、ミニマルなリズムやフレーズの繰り返しを軸にした作品、つまりダンスミュージックの一種として制作されたものも多いが、「弓弦葉」においてはアコースティック楽器の音色に重きを置き、「ただ其処に在るもの」という風情を描き出している。それは“家具の音楽”を提唱したエリック・サティの音楽のようでもあり、音の響きそのものを追求した坂本龍一の晩年の作品などにもつながっているように感じた。
ライブの中盤では女性シンガーが加わり、「森の小さなレストラン」など、いくつかの楽曲を森山とともに歌った。とても特別な光景だったが、“雨に降られ、ふらりと店を訪れた女の人”という佇まいも相まって、どこにも不自然なところがなかった。“スマホを使って歌詞を共有しながら歌う”という演出もそうだが、これ見よがしの派手なステージングを抑え、舞台と客席の境をなくし、本当に豊かな音楽を共有する。これこそが「弓弦葉」のライブの本質なのだろう。
その中心にあったのは「あの世でね」だった。「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw」に共通して収められているこの曲は、あちら側に行ってしまった子供を思う曲。舞台の上で空気に触れることで楽曲に込められた思いは大きく広がり、観客1人ひとりの記憶や経験と結び付くことで、さまざまな感情を生み出していく。それは同時に、あの世とこの世の境目をなくし、大切な人に思いを馳せるという「弓弦葉」のもう1つのテーマ性ともつながっていたと思う。ライブ終盤のMCで森山は、少し言葉を詰まらせながら、スタッフ、仲間、観客に向けて、無事に初日を迎えられたことの感謝を述べた。また「この舞台を作っていく中で、もう会えなくなってしまった人との時間を思い出すことがありました。“会いたい”というとってもシンプルな気持ちに蓋をしながら生きてきたんだなということに気付きました」というコメントからも、このツアーに対する彼自身の生の思いが伝わってきた。
なんでこんな簡単なことに気付かなかったんだろう。こんなにも大切な思いがあったのに、ずっと知らないふりをしていたのはどうしてだろう。そんな経験をしたことがある方も、きっと多いと思う。
森山自身も音楽ナタリーのインタビュー(参照:森山直太朗×番場秀一監督インタビュー|「素晴らしい世界」はなかった)で「みんな多かれ少なかれ、止まってしまった時間の中に閉じ込められてしまったり、あるいはずっと考えないようにしてきたりした経験があると思うんですよね」と語っているが、それは言うまでもなく、彼のリアルな体験に基づく実感でもあるはずだ。
コロナに感染したときに死を意識したこと、そして、父を亡くしたこと。人生観を大きく揺さぶるような出来事の中で音楽を作り、奏でてきた森山。“弓弦葉”(ユズリハ)とは、新しい葉が古い葉と入れ替わるように出てくる植物の性質から転じ、「親から子へと代々続いていく」ことを意味する言葉でもある。生と死、あの世とこの世を超えるような手触りを持つアルバム「弓弦葉」は、現在の森山の死生観がそのまま音楽に昇華された作品なのだ。この日のライブを通し、筆者はそのことを自明のこととして受け止めることができた。
次のページ »
「Yeeeehaaaaw!」レポートへ