“リアル喜久雄”が活躍する歌舞伎界
白央 「リアル喜久雄」って、歌舞伎界に実は割といますよね。というのは親が歌舞伎役者じゃないけど、歌舞伎の魅力に取り憑かれて入ってきて、出世した方、脚光を浴びている方という意味で。現代ならまず片岡愛之助さん。
千葉 中村梅玉さんの養子になった中村莟玉(かんぎょく)さんも。
井嶋 そうそう、先日、歌舞伎「刀剣乱舞」を観に行ったんですが、中村莟玉さん、上村吉太朗さん、澤村精四郎さん、市川蔦之助さんなど、一般家庭から入った方々が大きな役について大活躍されてました。ちなみに、この作品は歌舞伎入門にまさにピッタリの作品なのでおすすめしたいですね(8月は京都の南座で上演中)。
千葉 部屋子*出身の役者さんだったら、市川猿弥さんを観てほしいです。先代猿之助さんのお弟子さんですが、古典もできるし踊れるし、とても達者な役者さん。
*一般の弟子と実子の間ぐらいの位置にあると認められた子役のこと。
白央 国立劇場の歌舞伎研修制度から歌舞伎界へ入った人もたくさんいますが、卒業生の1人、中村いてうさんはこれからどんどん欠かせない存在になると思う。中村京蔵さんとの勉強会では「綱館(つなやかた)」の渡辺綱を実に立派に務められていました。彼は行儀のいい役もうまいけど、歌舞伎の古怪味を表現できる人にも思うんです。
歌舞伎で味わう圧倒的な価値観の違いと高揚
千葉 「
白央 「国宝」効果か、「二人道成寺」も上映延長していましたね。そして歌舞伎って、初めて観るときは演目を選んだほうがいいと私は思ってるんです。ものすごく地味で暗い内容のものもあれば、非常にわかりやすく華やかな話もある。荒唐無稽で楽しいものや、きれいなものを最初に観てもらえるといいんじゃないかな、と。
千葉 ずいぶん昔、歌舞伎を観たことがない人を勘三郎(当時は勘九郎)と三津五郎(当時は八十助)の「勧進帳」と「半七捕物帖」の2本立てに連れて行ったんです。古典作品の代表かつ人気作と、岡本綺堂原作の新歌舞伎*で、早替わりも多い演目のセットで、すごく楽しんでもらえた。そういう組み合わせで観てもらえたら、理想的ですよね。
*明治時代中期から戦中までに書かれた作品を指す。
白央 いいですねえ。私は適度に短くて華やかな「吉田屋」とか、文字どおり七役早替わりで派手な「お染の七役」なんて演目が出会いなら、きれいで楽しくて、ハマりやすいんじゃないかと。まあ、だからといって毎月上演されてるわけじゃないのが悩みどころ*(笑)。
*歌舞伎の演目は月替わりで、レパートリーはごまんとある。観たい演目があっても、運が悪いと長年観られないこともあれば、間をさほどおかずに上演されることも。「観たいものは観られるとき、迷わず観ておく」をモットーにする人も少なくない。
井嶋 私は、歌舞伎初心者の方には、舞踊の演目をおすすめしています。ミュージカルやレビューのようなものですから、ややこしい知識抜きで感覚的に楽しめると思うんですよね。まずは目と耳をひたすら喜ばせて、理屈抜きで「なんだかわからないけど楽しかった!」という体験をするのが一番いい。
白央 歌舞伎役者で今、踊り上手といえば誰でしょう。
千葉 私は中村鷹之資(たかのすけ)くんに期待しています。
井嶋 私も鷹之資さんの踊りの大ファンです! あと、尾上右近さんも素晴らしい。先日彼が主催する勉強会「研の會」も拝見しましたが、同じく踊りの上手な中村種之助さんとの「三社祭」、すごかった。
白央 鷹之資くんのお父さんの中村富十郎さんは歌舞伎界でも屈指の舞踊名手で知られた人でしたね。
千葉 演目なら「棒しばり」なんかいいのでは。お酒が好きでいつも盗み飲みしている召使いの太郎冠者と次郎冠者を置いて留守をすることになった主人が、太郎冠者の腕を棒に縛り付け、次郎冠者は後ろ手に縛って出かけてしまう。でも2人は知恵を絞ってなんとかお酒を飲んでしまうという、とても楽しい踊りです。
井嶋 「身替座禅(みがわりざぜん)」も、恐妻家の夫とヤキモチを焼く妻の話でコミカルで楽しくて、海外の方にもウケのいい演目。
千葉 「釣女(つりおんな)」もいいけれど、あれはルックスがネタになっていますから、そのうちポリティカルコレクトネスで観られなくなるかもしれない。
白央 「常識」や「価値観」の変遷とともに上演されなくなる演目ってありますからね。舞踊でもいくつか思い出されます。でも、圧倒的な価値観の違いに接するのも、私は歌舞伎の魅力だなあ……と今感じてしまいました。仕えている主人のために、どうして我が子の命まで差し出さなければならないのか。そういう主題の演目ありますよね。おかしいよと感じながら、いつしか泣かされて深い感動を得る。そんなとき、歌舞伎の芸や厚みに呑み込まれたような快感があったりね。
井嶋 そうなんです! 今とはまったく異なる価値観の作品を観る、ということには、今ここから切り離される解放感があると思います。「妹背山女庭訓(いもせやまおんなていきん)」の吉野川の場なんかもすごいですよね。自分の娘を泣く泣く死に至らせて、その娘の首を雛人形の輿に乗せて、嫁入りさせるとか、もう意味がわからない(笑)。でも、観ると泣いてしまうんですよねぇ。
千葉 松本白鸚さんが幸四郎時代に伺ったことなのですが、まだお若い頃に「熊谷陣屋」の熊谷直実を演じたとき、客席のご老人たちが泣いていらした。それは戦死させてしまった息子のことを思い出していたからなんです。「あれは反戦のお芝居です」とおっしゃっていました。現代からそう遠くない時代に起きた出来事をリアルに感じさせる古典歌舞伎があったわけで、それだけの力を持つ演目だということですね。
白央 真逆になりますが、歌舞伎にはナンセンス極まれりな話もいろいろあって、そこがまた最高。八百屋お七(「伊達娘恋緋鹿子」)のお土砂の場とか、最初に観たときはびっくりしたなあ。もうむちゃくちゃな笑いの場で、「えっ歌舞伎ってこんなにもフザケちゃっていいの!?」と思った。「毛抜」の展開のアナーキーさにもあんぐり。近年だと坂東巳之助くんの「毛抜」がよくて、ファンになりました。
井嶋 「暫(しばらく)」なんかもむちゃくちゃですよね(笑)。どう考えてもその格好じゃあ身動きとれないよね? ということはどう考えてもここにいる誰よりも弱いよね?と思うようなとんでもない格好をしたヒーローが現れて、敵たちを一気に倒す。
白央 生首がゴロゴロ転がる演出、観てほしいですね。
井嶋 それで観客大喜び、っていう(笑)。くだらなすぎることを大真面目にやっているのが、私が歌舞伎においてもう最高に好きでたまらないところです。
白央 実にくだらないことを丹念にやったり、悲壮で深遠なる物語を長々とやったり。歌舞伎作品って、色合いがさまざまでカラフルな世界です。
千葉 「伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)」を通しで一度観てみると、面白いかもしれませんね。ニザ様が八汐と仁木弾正の二役をやるときなんて、女形と立役の両方を演じるってことにびっくりすると思います。歌舞伎役者のすごさを感じてもらえるのでは。
井嶋 私は小学生の甥っ子がいるんですが、小2のときから歌舞伎に連れて行ってるんです。最初に観たのが「義経千本桜」*の狐忠信の宙乗りで、「面白かった!」と大喜び。男の子って戦うヒーローとか強い悪役とか大好きじゃないですか。今では毎月行っています。子供って歌舞伎と親和性が高いと思うんですよ。テレビの戦隊もので、ヒーローが1人ずつ名乗ってポーズを決めたりするのも、「弁天小僧」にもあるように歌舞伎から来た演出だと思いますし。
*「仮名手本忠臣蔵」「菅原伝授手習鑑」と並ぶ歌舞伎三大名作の1つ。松竹創業130周年を記念し、今年10月に東京・歌舞伎座で通し上演が行われる。一般チケットは9月14日10時に発売。
白央 ああ、なるほど!……と、こんな話しているとキリがない(笑)。きょうはお二方、ありがとうございました。
映画「国宝」作品概要
原作:吉田修一「国宝」(朝日文庫/朝日新聞出版刊)
脚本:奥寺佐渡子
監督:
出演:
製作幹事:MYRIAGON STUDIO
制作プロダクション:クレデウス
配給:東宝
映画「国宝」本予告
関連記事
吉沢亮のほかの記事
リンク





























































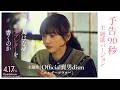







白央篤司 @hakuo416
映画『国宝』にちょっとハマってしまい、座談会なんか企画してしまいました。映画のことを前半で、歌舞伎に興味持った人に読んでほしい後半の2構成。古典芸能を見続けるライターの千葉望さん @cnozomi 日舞名取でもある井嶋ナギさん @nagi_ijima との鼎談です!
https://t.co/3crq3tzzrl