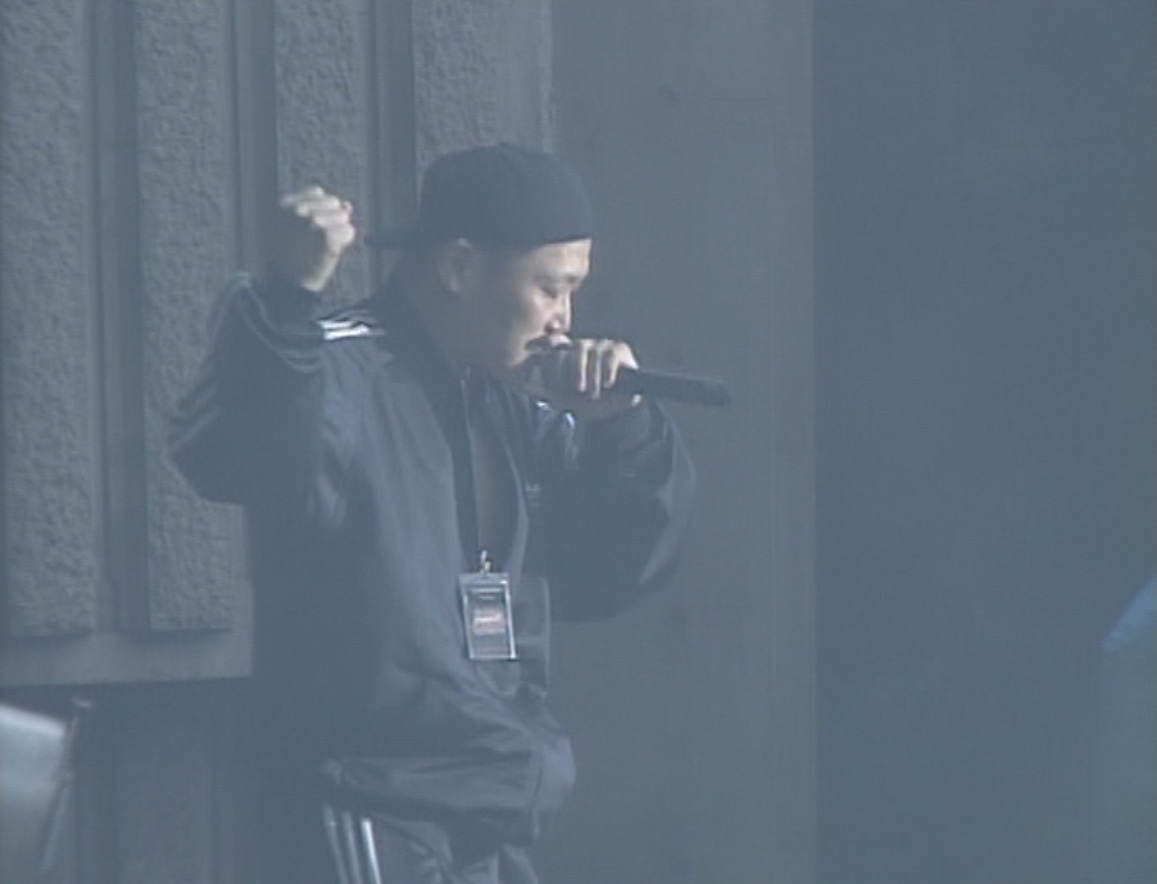
「さんピンCAMP」とその時代 第1回 後編 [バックナンバー]
「J-RAPは死んだ」ECDが発した言葉の意味とは?「さんピンCAMP」がヒップホップシーンに与えた影響
関係者が語る「さんピンCAMP」の裏側|本根誠×荏開津広×光嶋崇 鼎談
2025年10月2日 20:00 18
BUDDHA BRANDは松本隆の次の世代を担う存在になると思っていた
本根 でも、
──それは興味深いですね。
本根 BUDDHA BRANDの初期の曲って、ドギツイ内容もあるけど、人を懲らしめようとしてるんじゃなくて、結局は、みんなで楽しもうよと歌っているわけじゃないですか。だからハードコアなんだけど、パーティソングの側面が強い。特にNIPPSとCQのパートは、かつて松本隆が歌詞で提案したような若者のライフスタイル──つまり“その次の世代”の感覚をリアルに描いているんじゃないかと思っていたんです。このまま活動を続けていって、「人間発電所」を超えるシングルヒットが生まれたら、松本隆の次の世代の価値観を、このグループは提示できるかもしれないと思ったんですよね。もうディレクターの妄想力。でもそれぐらいの気概で作業していたんです。でも「ブッダの休日」はあまり芳しい反応がなくて、その次にトヨタのタイアップが決まっちゃったんです。
荏開津 「天運我に有り(撃つ用意)」ですね。
──NIPPSさんが脱退され、ラッパーは
本根 あの曲で、DEV LARGEのガンバリズムみたいなマインドがグループの歌詞を覆うようになったし、それをリスナーも求めるようになった。そしてDEV LARGEが、さらにガンバリズムみたいな歌詞を書くようになって、パーティソングっぽさがなくなっていっちゃったんですよね。そこで僕の心の中にあった「ブッダが松本隆を超える」という夢は、ついえてしまった。でもガンバリズムでさらに広く注目されたのも事実なんですが。
光嶋 なるほど。あと、これは30年越しに聞きたかったんですけど、「さんピンCAMP」のVHSって売れたんですか?
本根 売れたんじゃないのかな?(笑)
荏開津 なんで担当ディレクターが知らないの!(笑)
本根 ふふふ。社内では叱られもしなかったけど、「すげーすげー」と言われたことはないですね。
光嶋 でも、今の日本語ラップシーンの盛り上がりに直接つながってるのは「さんピンCAMP」だと思うんですよね。
荏開津 それは絶対そうでしょ。
光嶋 晋平太さんは「『さんピンCAMP』が決定的だった」みたいなことをYouTubeでも言ってくれていて。その晋平太さんを見て、フリースタイルを始めた人は確実にいるわけでしょ?
荏開津 そうそう。若者が何か言いたいことがあったら、韻を踏んで言えばそれがメッセージになり、音楽になるというのは、「さんピン」の時期に生まれた作品から広まった価値観だと思う。そして、それがより広まって、バズって、お金を生むようになっているのが今ですよ。
「さんピンCAMP」の頃には、リアルな現場でしか人とのつながりが生まれなかった
──すごく大づかみな質問になってしまうんですが、「さんピンCAMP」が開催された1996年は、どんな時期だったと思いますか?
本根 多忙だったせいか、覚えてないな……(笑)。でも1996年に比べて、2025年はものの見方が確定的になってると思いますね。やってみないとわからないということが今は少なくなってる気がする。
光嶋 数字が全部出ちゃいますからね。
本根 だからか、レコード会社にも、失敗はしないけれど大成功もしないディレクターが多い。僕がいた95、96年当時のcutting edgeのヒップホップアーティストで、しっかり黒字が出たのはBUDDHA BRANDぐらい。ブッダはとにかくカッコいいグループだったけど、それでも売れるかどうかの予測は不可能でしたよ。
光嶋 だからトライ&エラーが許された時代なんじゃないですかね。1996年って。
荏開津 僕自身はアシッドジャズをDJの中心にしていて、小林径さんや鄭秀和さん、スカパラの青木達之さん、ジェームズ・ ヴァイナーと「routine」というイベントをやってました。プラス、毎日どこかのクラブに遊びに行ってた。
本根 レーベルの人間も仕事が終わると「音、聴いてから帰るわ」ってよく言ってましたね。音楽を聴く場所として、クラブをすごく大事にしてた。
荏開津 今みたいにネットもないし、音楽好きな人が集まれる場所が限られてたから、自然とみんなクラブに集まってた。それは音楽の評価もホームリスニングだけじゃなかったということだと思います。
光嶋 今はインターネットでいろんな人とつながれるじゃないですか。でも「さんピンCAMP」の頃には、リアルな現場でしか人とのつながりが生まれなかった。
荏開津 そうだよね。あと、当時はストリートカルチャーと経済がリンクし始めた時期だった。自分が縁のあったロンドンのシーンもそれ以前のイリーガルなレイヴみたいなものがいろいろな理由で終わっていって、象徴的だと思うけど現代美術家のダミアン・ハーストが作ったカフェができたりした。ストリートのアンダーグラウンドカルチャーみたいなものが一旦終わる。でも、アンダーグラウンドを礼賛してるのではなく、例えば1980年代終わりのレイヴに持続性があったのかこれを読んでる人に残ってる映像とかを観てもらいたいぐらい。日本のヒップホップもそういう意味で、前衛として役割を果たす人たちもいれば、カルチャーとしてどう経済とリンクして持続していくのかを考えた人たちもいたということでしょ。あと東京は東京でラップを包含していたより大きなクラブシーンにいた人たちがそれだけに飽き足らず、スタイリストになったりとか、洋服を作ったりとか、そういう流れが90年代に始まった。タカちゃんの周りにいたNIGOさんとジョニオさん(高橋盾)が伝説的な店、NOWHEREを出したのはその時代です。
光嶋 そうですね。シンちゃん(滝沢伸介)もNEIGHBORHOODを立ち上げたり、周りの友達がみんな有名になっていった。僕もBMWに乗ってたし、ラジオもテレビのレギュラーもある、「さんピン」も撮ってるという感じで、今までで一番忙しかった。でも、ヒップホップ自体は流行ってなかったと思います。
荏開津 そうだね。
光嶋 流行ってる感じじゃないし、言っとくと「さんピン」のギャラが一番安かった(笑)。
(一同爆笑)
荏開津 僕が当時考えてたのは、「ラップがなんでメジャーにならないんだろう?」ということ。それはずーっと思ってた。ようやく最近メジャーになってきたけど、めちゃくちゃ時間がかかってびっくりしてる。
光嶋 今はラップという表現が普通になってますもんね。うちの子供もやりますもん。水曜日のカンパネラさんを真似して。
荏開津 もっと早くそういう状況になると思ってた。
「さんピンCAMP」が生み出したものとは?
──最後に、「さんピンCAMP」が生み出したものは、制作者としてはなんだったと思いますか?
光嶋 「LEGEND OF JAPANESE HIPHOP」という「さんピンCAMP」のサブタイトルは誰が考えたんですかね?
本根 僕なのかECDなのか……でも、そういう意識はあったんでしょうね。「伝説化するぞ」みたいな。
光嶋 僕が映像を撮ってる当時は、まさかここまで、のちのヒップホップシーンに影響があるとは思ってませんでした。でも今こうやって取材を受けているということは、「さんピン」というイベントが、開催から約30年という時を重ねることで、より伝説化しているということですよね。そして、その後のシーンに大きな影響を与えた人たちをフックアップしたイベントだったからこそ伝説になってる。
荏開津 僕は当時から「さンピンCAMP」は伝説のイベントになるだろうなと思っていました。ラップをすることが当たり前になってほしかったし、最初にライミングみたいなものを自分たちで工夫して作った子供たちが伝説になっていくのは、当然それに値する行為だと思ってた。
光嶋 うん、当の出演者はそう思ってなかったかもしれないですけど、本当にそう思います。
荏開津 タカちゃんは伝説(スチャダラパーのBose)が隣にいたからね。
光嶋 いやいや、生まれたときから一緒にいるからそんなこと全然思ったことないです(笑)。
荏開津 僕からすればタカちゃんだって伝説だよ。
光嶋 えー! いやいやいや(笑)。
荏開津 みんな伝説です、本当に。自分たちだけじゃないけど、みんなでヒップホップを作ったんだもん。
本根 僕も荏開津さんの意見に近いかな。The Velvet Undergroundって全然売れたバンドじゃないけど、ヴェルヴェッツのレコードを買った連中がみんなバンドを始めてるみたいなさ。イベント自体がそんな存在になったんじゃないかな。僕はフツーのポップ少年だったからシングルヒットも出したかったし、いい契約でラッパーのみんなが車を買える環境を作りたかった。それを当時は実現できなかったけど、結果的に「さんピンCAMP」を通して、いっぱいクリエイターが生まれたならそれはすごくうれしいことで。
光嶋 そうですよね。
荏開津 この対談を読んでも僕が「さンピンCAMP」で実際に何をしていたのかわからない人が多いと思う。最初にECDに方向性について相談を受けたのをサジェスチョンしたのと、あとは自分のDJの合間にただ現場にいただけだと言えるから恥ずかしいです。そんな自分については弁解もない。ただし「さんピンCAMP」の役割は歪なところがあったとしても日本のポップ音楽の歴史においてすごく大きかったと思いますし、自動翻訳機もないしYouTubeの解説家たちさえいなかった当時を振り返ると、歪な形でしかプロジェクトを実現できなかったのも仕方ないとも思います。「さんピンCAMP」は「ヒップホップとは何か?」をなんとか形にして提示したことだと自分は思っています。
プロフィール
本根誠
1961年大田区生まれ。WAVE、ヴァージンメガストアなどCDショップ勤務を経て、1994年、エイベックスに入社。cutting edgeにてディレクターとしてECD、東京スカパラダイスオーケストラ、BUDDHA BRAND、
本根誠 Sell Our Music _ good friends, hard times Vol.9 - FNMNL
荏開津広
東京生まれ。執筆家 / DJ / 立教大学兼任講師。東京の黎明期のクラブ、P.PICASSO、MIX、YELLOWなどでDJを、以後主にストリートカルチャーの領域で国内外にて活動。2010年以後はキュレーションワークも手がける。「さんピンCAMP」では、スーパーバイザーとしてコンセプトや構成に携わった。
荏開津広_Egaitsu Hiroshi(@egaonehandclapp) | X
荏開津広_Egaitsu_Hiroshi(@egaitsu_hiroshi) | Instagram
光嶋崇
岡山県出身。アートディレクター / 大学講師。桑沢デザイン研究所卒業後、スペースシャワーTV、レコードショップCISCO勤務を経て、ドキュメンタリー映画「さんピンCAMP」を監督。のちにデザイン事務所設立。スチャダラパー、MURO、クボタタケシ、かせきさいだぁ、BMSG POSSEなどのデザインを手がける。
designjapon.com
光嶋 崇(@takashikoshima) | X
光嶋 崇(@takashikoshima) | Instagram
※文中のアーティスト表記は、原則的に「さんピンCAMP」開催当時に沿っています。
バックナンバー
関連記事


























































![Mr.Children「Again」 from『CDTVライブ!ライブ!』[期間限定公開]](https://i.ytimg.com/vi/YPflXn7QZ4w/default.jpg)








showgunn @showgunn
「J-RAPは死んだ」ECDが発した言葉の意味とは?「さんピンCAMP」がヒップホップシーンに与えた影響https://t.co/e0rDFNnu65