小学館の週刊少年サンデー編集部主催によるイベント「サンデー文化祭2025」が、去る10月12日と13日に東京・神保町で開催された。コミックナタリーでは連載作家陣によるトークショーも実施された10月13日の様子をレポートする。
お宝品やマル秘情報、作者が選ぶ名シーンを展示
今年の「サンデー文化祭」は小学館ビル、一橋講堂、出版クラブホールなど神保町内の複数会場で展開。小学館ビルではサンデーの年表や各作家が大切にしている“お宝品”、ここでしか知ることのできない情報が記された「サンデーのマル秘展」などのコーナーが用意された。フォトスポットとして設置された「編集長机」に大嶋編集長が現れると、豪華景品が当たる“ガラポンタイム”がゲリラで開催され、来場者は長蛇の列を作り催しを楽しんだ。
そのほかにも連載作家陣によるライブドローイングも実施。出版クラブホールには、作者自らが選んだ名シーンをコメントとともに掲載する展示スペースも設けられた。加えてコラボカフェやスタンプラリー、「職業体験」をテーマとした描き下ろしイラストのグッズの販売などが行われ、幅広い年代の来場者が各企画を満喫している様子だった。
「尾守つみきと奇日常。」「写らナイんです」「廻天のアルバス」の制作秘話
一橋講堂では連載作家陣によるトークショーを3回にわたり開催。「サンデー新鋭連載陣!SPステージ」には「尾守つみきと奇日常。」の
作品について「尾守つみきと奇日常。」の森下は「『つみきさんがかわいい』と思ってもらえるように、自分の理想とギャップを大事にしながら描いている。友孝は“視点キャラ”。友孝くん視点で読んでいたときに、つみきさんがかわいく見えるように意識しています」と説明。青春とホラー要素を交えた「写らナイんです」について、コノシマは「オカルトが好きだったので、担当さんに『オカルト研究部の話が描きたい』と言ったら、『何かひとつオリジナリティがあったほうがいい。“熱血オカルト部”にするとか。全国大会を目指したらどうか?』という話になり、そこからお互いヒートアップしていって“スポーツマンガ”みたいにしたほうがいいという話になって、『写らナイんです』が生まれた」と振り返る。森下が「(文化部なのに)スポーツマンガ……?」と不思議そうに尋ねると、コノシマは「スポーツマンガを軸に考えて描いていったんです」と明かした。
「廻天のアルバス」の原作を務める牧は「最初は軽く読めるコメディを描こうという話だった。ファンタジーを絡めて“ファンタジーあるある”を無双していくのは、コメディとして面白いんじゃないかと。なぜ無双できるかといったら、ループしているから。なぜループするのかというと……ちょうどそのときリアルタイムアタックのゲーム動画をよく観ていたのもあって、ループしているのもスピードを競っているから、という思考の流れがあり、ループしながらリアルタイムアタックしている勇者が生まれました」と解説。「今考えると、アルバスのキャラクターも、リアルタイムアタックをしているゲームの実況者さんに影響されているのかもしれません。『スピードを競う』というストイックさがありながら、お茶目な感じもあって。そういうところに面白さを感じて、(キャラクターにも)反映されている気がします」と語った。
「面白い」とコメントしてもらえるのがエネルギーになる
「連載をしていてうれしかったことは?」というトークテーマに対して、コノシマは「全部。全部が輝かしい毎日」と発言し、牧も同意しながら「(連載を)続けられていること」と続ける。森下も頷きながら「こういうイベントに参加させてもらえるのもありがたい。読者さんとお会いできる機会もあまりない。見るとしたらネットの反応なので」と回答。「サンデーうぇぶりの作品ページのコメントは読みますか?」という質問には、3人とも“読む派”であることを告白する。森下は「笑っちゃったのが、言葉にならない言葉が書き込まれているというか。『尊い』って思ってもらえた気持ちが、文字になっていない(笑)。サーッて消えていくような顔文字があったりすると、楽しんでもらえているんだなというのを実感できてうれしいです」と微笑んだ。
一方でコノシマはホラーマンガを描いているが故か、「うれしいんですけど、たまにオカルト系の怖いコメントが来るんです」と話す。「『こういう怖いマンガを描いていたら危ないから、神社にお祓いに行ったほうがいい』とか、『霊に憑かれると体の左半身が痛くなる』と書いてあって、怖いなと(笑)。でも読んでいて面白かったです」と作品ならではの読者コメントに触れた。「前提として、どんなコメントがあってもいいと思う」と前置きした牧は「ただ……褒められてえ(笑)」と正直な思いを吐露。「やっぱり、『面白い』って書いてもらえるのが一番エネルギーになります」と思いを口にした。
関係性、テンション、ときめき……それぞれが聞きたいことを質問
トークショーの後半では、お互いへの質問が飛び交う。森下から牧には「アルバスからフィオナに対する“想い”の描き方を“恋愛”というくくりにしていないのは、何か狙いがあるのか?」という質問が投げかけられ、牧は「なぜアルバスがフィオナを助けたいのかと考えたときに、もちろん恋愛という感情を乗せるというのは選択肢としてありました。でも“恋愛”っていう感情が物語に与える影響がものすごく大きいと思って、その話にしかならない気がしたんです。なのであえて避けたところはある。今度どうなるかはわからないんですが、今は“みんなを救いたい”という勇者らしさが出ていいのかなと思っています」と答えた。
牧からコノシマへの「言葉選びのセンスがずば抜けていますが、どんなテンションで描いているんですか?」という問いに、コノシマは「ギャグが激しいときは、激しい音楽を聴いて、アップテンポでいこう!という感じでやっていて。音楽を聴かないと描けないかも」と返答する。森下からも「たくさんある小ネタは、思いつくままに入れていってる感じなんですか?」と聞かれたコノシマは「“めくり”を意識していて。次のページで面白くなるために、それまでにギャグを詰め込んで、次で『驚き』、また『ギャグ』、そして『ホラー』みたいな感じで。ページの“めくり”を考えている」と制作での意図を説明した。
コノシマから森下には「“ときめく”を描くにあたり最も注意していることは?」という質問が飛ぶ。森下も「ページをめくって、つみきさん(のときめきシーンが)ドンっと来るように意識している」と、コノシマと同様に“ページのめくり”を意識していることを明かす。また「友孝くん目線で読んでくれている人が、つみきさんと目が合うという疑似体験ができるように、友孝くんのドキッとした感情が読んでくれた方にも届くように、というのは気をつけて描いています」とコメント。しかし「落ち着いて見返したときに『えー? めっちゃ青春してるやん』って、もう戻ってこない青春を思って悲しくなる(笑)」と付け加え、3人で笑いあった。またイベントの最後には、3人の直筆イラストが描かれた色紙が、じゃんけんで勝ち残った来場者にプレゼントされた。
“滾る炎”の島本和彦が登場
次に行われたのは、サンデー編集部によるPodcast番組「少年サンデーのフキダシ」の公開収録。「少年サンデーのフキダシ」は雑誌の66周年企画として、少年サンデー編集部がマンガについての話を語っていく番組で、今回は「滾る炎のSP公開収録!」と題し、今年5月より「ヴァンパイドル滾」をサンデーで連載中の
少年サンデー編集部員でありパーソナリティの大塚氏が「ヴァンパイドル滾」について、「最近のお話も『これはどういう展開で、どういうことなんだろう?』と、説明はされないけど笑ってしまうところが“島本節”を感じる」と話すと、島本は「単におちゃらけたファンタジーではなくて、ちょっとした社会風刺を扱いつつ、でも暗くなってしまってはいけないので、ポップな感じで社会問題を扱えないかと思いながら挑戦している内容になってます。ギャグを読んでいるつもりで、『すげえ深く切り込んでるけど、大丈夫、この人!?』となっていけばいいかなとも思っています」と語った。
島本和彦のトークはまだまだ、青山剛昌の裏話も
関連記事








































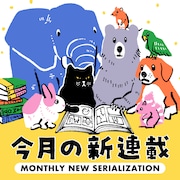

































geek@akibablog @akibablog
サンデー文化祭で「名探偵コナン」青山剛昌の貴重な資料とトーク、島本和彦らも登壇
https://t.co/HhzMqQPRN4