
アニメスタジオクロニクル No.22 [バックナンバー]
東映アニメーション 森下孝三(代表取締役会長)
創立70周年目前、生き証人が語る日本アニメのターニングポイント
2025年11月25日 15:00 19
アニメ制作会社の社長やスタッフに、自社の歴史やこれまで手がけてきた作品について語ってもらう連載「アニメスタジオクロニクル」。多くの制作会社がひしめく現在のアニメ業界で、各社がどんな意図のもとで誕生し、いかにして独自性を磨いてきたのか。会社を代表する人物に、自身の経験とともに社の歴史を振り返ってもらうことで、各社の個性や強み、特色などに迫る。
第22回には、現存する日本のアニメ製作会社で最も古くからの歴史を持つ東映アニメーションの代表取締役会長・森下孝三氏が登場。1948年生まれ、1970年に当時の東映動画に入社した森下氏は、東映グループ全社員の中でも“最古参”であるという。そんな森下氏が語る東映アニメーションのターニングポイントは、日本の商業アニメーションそのもののターニングポイントと言えるものだった。
取材・
戦後10年ほどで商業ベースのアニメ制作を始めて
「太平洋戦争が終わったのが1945年。驚くことに、日本が焼け野原になってから10年ほど経った1955年頃にはもう、商業アニメを作ろうという動きがあったんだよね。アニメーション的なものは日本はもちろんいろいろな国に存在したけど、いずれも小規模な存在で、その頃に商業ベースでアニメを製作する大規模な会社を作ろうと決断した東映の大川博さんはすごいですよ」
東映アニメーションの創立時について聞いたところ、森下氏はまず、戦後復興の最中で同社の創立に深く関わった東映の故・大川博社長への深い敬意を示した。大川氏は、1948年に設立された小規模なアニメ製作会社・日動映画の買収を決定した人物だ。これが現在まで続く、“東映”の名を冠したアニメスタジオの始まりとなる。
「1ドル360円という円安の当時、マルチプレーンカメラなどアニメ製作用の機材をかなりの予算を組んでアメリカから輸入してきて、『東洋のディズニーを目指すんだ』って言ってたそうで。今、大川さんが生きてりゃ、『なぜそこまでしてアニメをやろうとしたの?』って聞いてみたい(笑)。彼に関する本なんかによると『アニメで世界に出てドルを稼ぐ』という思惑はあったようだけどね」
1956年の買収時に日動映画は東映動画へと社名を変更し、処女作「こねこのらくがき」や日本初の長編カラーアニメ映画 として名高い「白蛇伝」を皮切りに、多くの作品を世に送り出していく。東映アニメーションという現在の社名となったのは、東映動画創立から40年以上経った1998年のことだ。
「僕も1980年頃から何度か海外を視察したけど、アニメーションを指す日本語の『動画』という言葉は全然通じなかった。だから海外でも意味が通りやすい東映アニメーションという社名に変更することになったんだよ。もちろん、長く会社にいる人には東映動画という名前に愛着を持っている人たちもいた。でも世界に展開するという点では東映アニメーションという社名のほうがいいよね」
生き証人が振り返るTVアニメ黎明期
森下氏は、1970年に東映動画に入社した。それからさまざまなポジションでアニメに関わりながら50年以上務め続け、今では東映グループ全体でも最古参。「54歳くらいからずーっと病気だったけど、よく雇ってくれているよね」と笑う。会社の、そしてアニメ業界の生き証人とも言える彼に、入社時のアニメを巡る状況を振り返ってもらった。
「1964年の東京オリンピックが開催される前後にカラーテレビが爆発的に普及したでしょ。それに伴ってテレビ局も増える中で、郵政省(現在の総務省)から新設の民放に対して『教育番組を一定の割合で流すように』といった指示があって、その時間にアニメを流そうという機運が生まれたんです。ただ、それまでテレビで流れていたのは「ポパイ」とかアメリカのアニメばかりだった。まあ当時はアニメだけでなく、ドラマとかもアメリカやヨーロッパのものが多かったけど。その中でアニメは『お金をかけてアメリカから仕入れるより、自分たちで作ったほうがいいんじゃないか』とみんな考えて、だんだんと国産が増えていきました。
そんなふうにTVアニメの需要が急激に高まったおかげで、アニメ業界は人手が全然足りなかった。一方で「白蛇伝」以降の10年とかで映画はどんどん衰退していたので、人手が映画からテレビに流れてきたんです。うちはもともと映画会社のグループだったのもあるけど、そういった歴史があったから、今も映画とほぼ同じような工程で、撮影や仕上げまで全部社内で完結できるような規模でアニメを作っています。東映動画の後にもアニメを作る会社はたくさん出てきていたけど、当時ここまでの規模の会社をいきなり作るのは資本的に難しかったでしょうね」
演出と企画、2つの側面から東映アニメに関わり続けて
1970年の入社後、森下氏は作品製作に演出と企画の両面で関わることになる。入社当初から1988年までの演出時代と、それ以降を振り返ってもらった。
「最初は演出助手として働き始めました。ほかの会社で言う助監督。うちの場合は映画製作を踏襲しているから助手って呼ぶんだけど、助手を5年とかやっても仕方ないんですよ。演出助手のプロなんて会社には求められないわけで。そこから演出になれなきゃ、演出としては振り落とされるだけだし。だから、演出助手を2年か2年半くらいやって初めて助手のない“演出”として手がけた『キューティーハニー』は思い出深いなあ。
それから39歳くらいまでシリーズディレクター(※他スタジオにおける監督)なんかをやっていて、その頃の『聖闘士星矢』とかは特に一番力を入れていたけど、そのへんで『いつまでもディレクターは続けられないな』と感じていて。新しい人がどんどん入ってくる中で彼らにもシリーズディレクターを任せなきゃいけない。でも自分が今さらローテーション演出(各話演出)をやるのも違うなと。50歳や60歳で演出をしている人もいるけど、自分は同じことをやり続けるとワンパターンになるだろうし、枯れちゃうのが嫌だった。
そんなふうに思っているときに会社から『企画部に来てほしい』という話があって、企画(※他スタジオにおけるプロデュース)側に回りました。と言ってもプロデューサーとしては『ドラゴンボール』しかやってないようなもんだけどね。あとは自分の趣味みたいな映画をやったくらいです」
それから2000年前半にいたるまで、森下氏は企画部でアニメ製作に関わり続けた。その30年以上のキャリアの中で出会った才能あるクリエイターについて、彼は具体的な名前を挙げて語る。
「アニメーターで言うとまずは荒木伸吾さん。あとオールマイティだった小松原一男さんと、発想力が豊かな湖川友謙さん。この3人はすごかったですね。ずいぶん勉強になりました。特にTVアニメの第1話やオープニングはそういった最高のスタッフで作るから、すごく勉強になるんです。もう、授業料をいくら払っても足りないくらい。
今でもいろんなプロデューサーに言うけど、結局そういったうまい人とやらなければ自分が成長しないんですよ。単にフィルムがつながったからって完成じゃない。自分が下手でも、本当に自分がやりたいことを見極めて、それに合った上手な人とやってフィルムの内容を引き上げてもらわないと」
フォローして最新ニュースを受け取る














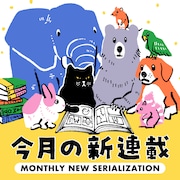
































geek@akibablog @akibablog
東映アニメーション 森下孝三(代表取締役会長) | アニメスタジオクロニクル No.22 - コミックナタリー コラム
https://t.co/3wzOAkLMo6