
木ノ下裕一の「わたしのアクセシビリティ日記」 第4回 [バックナンバー]
世相はますます暗く、排外主義や差別的な言説が強まる昨今ですが、そんな現代だからこそ、“やっぱり小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)”だわ!……と思い至ったという話
引き続き、ハーンとセツ
2025年10月27日 15:00 3
“推し活”という言葉が流行るずっと前から、世間のムーブメントに流されることなく、自身の好きなものを常に探究し続けてきた木ノ下歌舞伎主宰・
文・
2025年2月某日 三度の翻訳
やはり、ハーンの本ばかり読んでいる。
彼の著作だけでなく、伝記や評論など関連書籍にも手を伸ばす。
これぞ芋づる式!……というと、なんだか勉強熱心なようだが、実状は、こっちの本を数ページ読めば、あっちを数行、また違う本をパラパラめくり……と気が多くて、畑の芋を食い散らかす狸のようなものだ。
読むのはたいてい就寝前のベッドの中で、ネットサーフィンならぬ書籍波乗り。たちまち枕元は関連書籍で埋め尽くされる。おかげで最近、奇々怪々な夢をよく見るようになった。
さて、日本滞在中のハーンの創作スタイルが面白い。そこに「翻訳」というテーマが浮かび上がってくるからだ。
小泉八雲(ハーン)の再話文学には、たいてい典拠があり、たとえば「耳なし芳一」なら江戸後期の怪談集「臥遊奇談」の「琵琶秘曲泣幽霊」が種本になっている。
そして、典拠である種本とハーンの間には、妻セツがいる。
ハーンは日本語が堪能でなかったから、種本をセツが読み聞かせる。ハーンはセツの声を通してインプットする。ただの朗読ではなく「本を見る、いけません。ただあなたの話、あなたの言葉、あなたの考えでなければ、いけません」と注文を付けたというから、それらはセツによって、物語の要点がまとめられ、あるいは補足、肉付けされ、編集されたものになる(当然、音や声などの“語り”の要素も加わる)。
ここに一つ目の翻訳がある。
そのうえで、ハーンは英語で原稿を書く。日本語から英語へ、東洋的な思想や情感を西洋の言葉の器に移し替える。作品によってはかなり創作も加える。時に換骨奪胎も含めた、クリエイティブな作業(翻案と呼んでもいいのかもしれない)。とにもかくにもこれが二つ目の翻訳。
私は英語に疎いので、このあたりのことはよくわからないが、専門家によると、ハーンの翻訳能力はすこぶる高く、とりわけ引用する和歌や俳句、古文においては名訳だという。
さて、私たちが、今読んでいる小泉八雲の作品は、ハーンの英語原稿を誰かが日本語に訳し直したものだ。ここに三つ目の翻訳がある。
同作品に複数の訳文が存在し、当然、訳された年代と翻訳者によって持ち味が違う。しかも、今でも現在進行形で新訳が発表され続けている。
訳の読み比べも愉しみの一つだが、八雲作品が(たとえば、ほぼ同時期の一葉や鴎外や四迷の作品と比べて)常にみずみずしく感じられる理由のひとつはそこにある。
八雲の作品は、三度にわたる翻訳によって濾過(ろか)され、私たちの元に届けられているのだ。
2025年3月某日 文字のアクセシビリティ
ここのところ「平家物語」の現代語訳ばかりしている。一つはロームシアター京都での講座「伝統芸能入門講座~芸能の在る処~」用に、もう一つはラジオ番組(※1)で使用するため。
現代語訳しながら、日本文学の歴史は翻訳の歴史だよなぁと思う。
かつて文字を持たなかった日本人の元に大陸から漢字文化が渡来する。日本人は漢文をマスターすると同時に、漢字の音や意味に、(当時の)音声日本語を当てはめていく独自の表記方法を発明した。これを万葉仮名という。
やがて漢字からひらがなやカタカナを生み出し、和文や漢文訓読体から、現在の日本語表記の原型となる和漢混交文を作り上げていく。
変体漢文である「古事記」や万葉仮名で書かれた「万葉集」のよみ下しも試みられるようになる。私たちが普段、古典文学全集などで「古事記」や「万葉集」の“原文”と呼んでいるものは、実は、誰かがよみ下してくれたものだ。
そして、現代においては、現代語訳がそこに加わる。
文字体系や表記法や文体を新しく作り、刷新していく。ある種の“翻訳作業”が繰り返され、誰もが読めるカタチにひらかれていった。
「翻訳」とは、そのままでは伝わらないもの、アクセスできないものを伝達可能なものにしていく行為だともいえる。だから、その根本は、アクセシビリティの精神に支えられている。(※2)
(※1)ラジオ番組……木ノ下が案内人になって文学、詩歌、芸能など日本古典を紹介するNHKラジオ第2「おしゃべりな古典教室」(毎週土曜日)のこと。2020年4月に放送が開始し、番組パートナーは小芝風花(2020~2021年度)、小野花梨(2021~2024年度)を経て、現在は南沢奈央(2026年度~)。ビジュアルが伴わないラジオという媒体で、音のみで伝える面白さと難しさを毎週感じながら放送中(なお、放送から一週間はこちらで聞くことができる。
(※2)たとえば、舞台における日本語字幕や音声描写(音声ガイド)などの制作も、広い意味で「翻訳」に含まれるだろう。ただ、文学における翻訳は、異なる言語(文字)の間をつなぐのに対し、視聴覚の障害を越境することを目的としたそれらは、音声-文字、視覚-聴覚を行き来するため、よりアクロバティックな翻訳技術が要求される。
2025年3月某日 おんなたちの分かれ道
まだ小泉八雲のことをつらつら考える日々。われながらしつこい。
一つ、ハーンについて気になっていることがあった。
それは、ハーンの、妻セツへの愛情について。
大変な愛妻家であったことは数々のエピソードで垣間見ることができるが、さて、そこにいわゆる“差別心”はなかったのだろうか。
西洋を出自とする者がアジアの人間に向ける差別。男性が女性に向ける差別。
同時にセツのほうにも異国の人に対する偏見はなかったのだろうか。人種や文化が異なる者同士の結婚がまだまだ珍しかった時代、二人の関係性に差別の棘がなかったのだとしたら、それは、なぜか。
松江の記念館でセツを顕彰する展示を見ながら、そのことがとても気になっていた。
小泉セツは明治元年1868年生まれ。
ちなみに、かの唐人お吉(斎藤きち)は天保12年(1841年)生まれ。米国総領事のハリスの侍妾(身の周りの世話をする女性)となった彼女の、淵に身を投げ自らの命を終えるまでの48年の生涯は、絶えず後世の人の好奇な目と偏見にさらされ、虚実混ざりながら、講談や演劇のネタになってきた。
セツからすれば一つ上の世代だが、病気に臥せる外国の要人の看護人として白羽の矢が立ったところもセツと共通する。
思い立って、本棚から森崎和江の「からゆきさん」を引っ張りだし、読み始める。明治から昭和初期にかけて外国の娼館に売られていった少女たちを追ったノンフィクション作品だが、身売りという境遇の背後には常に〝貧困〟があった。独身時代のセツもまた、没落士族の娘として貧困にあえいだ少女だった。
森崎の「からゆきさん」にたびたび登場する重要人物“おキミさん”は明治27年(1892年)生まれだから、セツの子供世代にあたる。
年表上では、唐人お吉とからゆきさんたちに挟まれたセツ。一方は悲劇の人として人口に膾炙され、あるいは異国の地で無縁仏同然、骨をうずめた女たち。もう一方は稀代の文学者を支えた良妻として讃えられ、次期、「朝ドラ」ヒロインのモデルにまでなる(※3)。雲泥ともいうべき、その分かれ道はどこにあるのだろうか。
(※3)2025年9月29日NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」が放送開始。主人公のトキは小泉セツがモデル。毎日、楽しく拝見しております!
また、同じくNHKで、小泉夫妻を描いた先行作としては、山田太一脚本の「日本の面影」(1983年度放送・全4回)がある。こちらは檀ふみがセツを演じている。残念ながらオンデマンド配信もソフト化もされていない。再放送してくれないかな……。
2025年3月某日 母の面影と虫眼鏡
枕元に、唐人お吉やからゆきさん関連の本が詰まれるようになった。
芋づる式に、従軍慰安婦や遊郭にまつわる資料も集まってくる。どう考えても寝る前に読む本ではない。でも、戦後80年だからこそ腰を据えて考えたいテーマでもある。
見えてきたのは、差別の構造。個人間の差別から、コミュニティ間、地域や地方、性差、天皇と国民、社会的階級、人種、国家間に至るまで、大小さまざまな規模の“差別”が細かい幾何学模様のように入れ子になっているのが私たちの世界らしいということと、ほとんどの歴史的な悲劇は(無意識的なものも含めて)“差別”が引き金になっているということ。
そんな回り道を経て、再び、ハーンとセツに戻る。
まず、ハーンの複雑なルーツと生い立ち、とりわけ実母との関係について考える。
生まれ故郷のイオニア諸島(レフカダ島)は諸外国から侵略や占領をたびたび受けてきたギリシャの重要地点で、当時、反英感情が高まりつつあった。この地で、イギリス軍医の父、ギリシャ人の母の間に生まれたという事実がハーンの生涯と姿勢を決定づけたように思う。母ローザは、国、言語、風土、文化、風習、そして宗教の違いに苦しみ、やがて精神を病む。ハーンは7歳の時、母と生き別れてからついぞ一度も会うことが叶わなかった。
そのためハーンは生涯、母なるものを乞いつづけた。また、迫害されていたり、不幸な境遇にある女性に魅かれるという恋愛パターンも、母の面影の表出であったのかもしれぬ。セツに対する思い入れの深さもまたしかり。
ごくごく個人的な、深い、深い心の傷が、差別への抑止力になる、ということがあるのかもしれない。
ハーンは、どんなに親しくしていた友人であっても、その友人が妻を裏切ったり暴力を振るったり、愛人関係なども含めて女性そのものをぞんざいに扱っていると知った途端、問答無用で絶交したという。
「妻は夫の所有物」という通念が、法的にも感覚的にもまだまだ強固だった時代。ハーンの傷が、セツの明暗を分けたとするなら、男性の胸三寸によって、禍福を分かつ当時の女性たちが置かれていた立場の、なんと頼りなく危ういことだろうか。
ちなみに、セツは後年、「幼少の頃の思い出」という手記の中で、三歳の頃、砲兵軍曹として松江に赴任していたワレット(※4)というフランス人から虫眼鏡をもらったことを回想している。
「私がもしもワレットから小さい虫眼鏡をもらっていなかったら、後年ラフカヂオ・ヘルンと夫婦になる事もあるいはむずかしかったかもしれぬ」と語っている通り、この体験が、異邦人への恐怖感や先入観を取り払ったとするなら、ほんのささやかな触れあいもまた、偏見への抑止力になりうるのかもしれない。
(※4)フレット……正しくはフレデリック・ヴァレット(1834年~没年不詳)。明治3年に来日。翌年、松江を去っている。
2025年4月某日 ことばでつなぐ
桜が満開である。
出仕事があって、バスに乗る。
京都・嵐山は、外国からの観光客であふれかえっている。車中にも様々な国の言葉が響く。
英語、フランス語、韓国語、中国語。自分にとって未知の言語は歌のように聴こえて、心地がいい。けれど、もし意味がわかったらそれはそれで楽しいだろうなぁ、とも思う。
謡曲や浄瑠璃のことばが聞き取れるようになると、急に舞台の解像度があがるように、距離がぐっと近づくに違いない。
ハーンにとって、“翻訳することは生きること”だったのではないか。
被侵略、多神教、異邦人として、そして視覚障害者としての不安と孤独。複数のマイノリティなるものを小柄な身体の中に抱えて、マジョリティなるものへ抵抗するかのように「翻訳」しつづけるハーンの生涯は、相対するもの同士を、言葉の力によってつないでいく試みでもあった。
同時に、母ローザが越えることのできなかった数々の社会的な溝(国、言語、風土、文化、風習、宗教など)へ橋をかける行為でもあった。
数々の原稿を書きながら、「伝われ! 伝われ!」と念じていたのではないか。「迫害されているものの声、伝われ」「小さい声、伝われ」「文化的に劣っていると思われているものの本当の姿、伝われ」、そして「わたしの愛するものたち、伝われ」──。
在日中のハーンが最もつらかった熊本英語教師時代。その理由については彼自身が友人への手紙の中でいくつも挙げているが、やがて戦争へ突き進んでいく日本の、英語教育をめぐって語って繰り広げられる排外主義が大きな理由だったといわれる。
ハーンの書いた日本文化を紹介する数々の随筆や評論を読むと、そのフラットさに驚かされる。対等な立場で他国の文化に接し、淡々と紹介する。一方を蔑ろにして、一方を持ち上げるという安直な方法ではなく、両者を尊重し得る言葉を探し続けて、語る。
帝国主義や排外主義に抗う方法は、これしかないとでもとでもいうように。
西洋 / 東洋、支配/被支配、自国 / 他国、健常 / 障害……数々の分断を内面化したうえで、言葉を探し続けた“帰化人(あえてこの単語を使う)”が、かつて、121年前に、この国にいたのだという事実を、わたしたちはちゃんと思い出していいのかもしれない。
【日記後記】
なんとなんと前回から約二カ月も空いてしまいました。せっかくなら朝ドラの「ばけばけ」放送開始に合わせて……などという殊勝な商売っ気からなどではなく、すべては私の不徳の致すところなのであります。
「隔週くらいの頻度でアップずるぞ!」と息巻いていた連載開始当時の自分はどこへやらです。
ちょっと言い訳を。
確かにこの夏は、むちゃくちゃ忙しかったり、それに伴い体調を崩しがちだったりしたわけですが、なにより、資料を読むのに時間がかかってしまったわけです。調べものが必要な原稿はどうしても時間がかかります。
しかも、今回、扱うテーマがややセンシティブ。いざ、文章にしていくと、ちょっとした言い回しや言葉の選び方ひとつも気になってきます。「だれかを傷つけてはいないか」と、怖くなってくるのです。
そもそも、「アクセシビリティ」について書く時、障害や差別や偏見について触れないわけにはいきませんから、わかっていたこととはいえ、「いやはや、エライ連載をはじめてしまったものだ……」と改めて嚙みしめた次第。
いい塩梅に、軽めの話題──吉本新喜劇のお約束演出にアクセシビリティを感じる、とか、最近プラネタリウムにハマっている、とか、ラジオ番組「安住紳一郎の日曜天国」の安住アナの、視覚的なものを言葉で説明する話芸は見事だなぁ、とかとか──を交えながら、更新頻度を上げたいところです。
- 木ノ下裕一
-
1985年、和歌山県和歌山市生まれ。2006年に古典演目上演の補綴・監修を自らが行う木ノ下歌舞伎を旗揚げ。代表作に「黒塚」「東海道四谷怪談—通し上演—」「三人吉三」「糸井版 摂州合邦辻」「義経千本桜—渡海屋・大物浦—」など。また渋谷・コクーン歌舞伎「切られの与三」の補綴を務めたほか古典芸能に関する執筆、講座など多岐にわたって活動を展開している。「三人吉三」再演にて読売演劇大賞2015年上半期作品賞にノミネート、2016年上演の「勧進帳」にて平成28年度文化庁芸術祭新人賞を受賞。第38回(令和元年度)京都府文化賞奨励賞受賞。2024年よりまつもと市民芸術館芸術監督団団長を務める。
バックナンバー
関連記事
木ノ下裕一のほかの記事
フォローして最新ニュースを受け取る






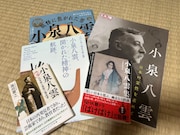



























































らくごえん着到マニア(めい) @rakugoen3355
木ノ下さんの小泉八雲考察です。とても面白い。 https://t.co/9fZPpoowNl