第38回東京国際映画祭のプログラムとして、「淵に立つ」「LOVE LIFE」などで知られる映画監督・
“アジア映画コンファレンス”の一環として実施された本イベント。本題に入る前に深田は、19歳で映画美学校に入学してからの来歴を紹介する。「入学した理由は、ただ映画が好きだったから。中高生の頃は成績が落ちるくらい映画ばっかり観ていました。映画美学校を知ったときは、まさか作るほうに回れる道があるんだと驚きました」と述懐。続けて、最初に自主制作した長編映画「椅子」に触れ、「当時アップリンク・ファクトリーという映画館の方にVHSを渡したら半年後くらいに電話があり、上映してもらえることになりました。しかしお客さんが来ず、連日0人。0人のまま15分経過すると上映が中止になるんです。ほろ苦い思い出ですが、作ることと見せることの難しさを同時に味わいました」と回想した。
今回、深田は「日本映画の業界構造について インディペンデント映画が生き抜くために」というテーマで講義を行った。深田は「なぜあえてこの場でお金の話をするかというと、映画においてお金をどう集めるかということは、どういう映画を作りたいかという問題と直結するから。映画は1本作るのに数千万円から数億円、数十億円というお金が必要になります。経済的なリスクをいかに下げるかということが重要になってきます」と説明。彼は経済的なリスクを下げる方法として「人気のある原作を映画化する」「スターを俳優として起用する」「共感しやすい内容にする」などを挙げ「このように話していて感じるのは不自由さ。リスクを下げるための一手が表現の幅を狭めている。つまり映画は、呪いのように本質的に保守的な表現なんです。多様な映画を作るためには、多様なお金の集め方が必要になります」と訴える。
深田は映画作りの資金を集める方法を「1. 映画製作会社などからの出資、金融機関からの融資」「2. 公的機関からの助成金」「3. 民間からの寄付・協賛」とし、「アート性の高い映画やドキュメンタリーなど、必ずしも興行成績に結びつかない映画であれば2と3の割合が増えていきます」と解説。続けて日本の文化予算の少なさを指摘する。「(2020年度の)政府予算に占める文化支出額の比率を見ると、日本は0.11%。フランスは0.92%、韓国は1.24%ですから、日本が文化を大切にしていないと言われても仕方ありません。ここ数年は経済産業省からの支援があり、とてもありがたいのですが、文化予算とは性質が違います。文化予算は多様性に貢献するお金。日本は“売れないかもしれないが多様性のために必要な表現”に割く予算が少ないんです」と吐露した。
さらに深田は「日本では(資金集めの)パッチワークが容易ではない。だったら面白い映画を作ってお金を回収すればいいと思う人もいますが、そうひとすじ縄ではいきません」と切り出す。彼は2019年度の興行収入成績をスクリーンに映し出し、トップ10本のうち7本が東宝の配給作品であることに触れる。「日本の映画業界では東宝・東映・松竹の大手3社が大きなシェアを占めていて、インディペンデント映画は残りの少ない枠の中で戦っていかなければならない。そうなっていくとどうしても低予算で映画が作られることになり、撮影日数が減り労働環境が悪化していきます」とコメント。続いて「ではどのようにインディペンデント映画を作っていけばいいか、具体的に考えていきましょう。文化の多様性は人間の多様性。映画の作り手は多様性の担い手ですし、多様な映画を作るための環境整備は私たちも考えるべき問題です」と次のテーマに話を移す。
インディペンデント映画を制作するために深田は「1. 娯楽性・共感性の高い作品作りを心がける」「2. 小さい撮影規模で作れる内容にする」「3. スタッフ・俳優をボランティアにして人件費を抑える」「4. 助成金・寄付を集める」「5. 市場を広げる」と、考えられる5つの方法を紹介。「1、2は表現の幅が狭まります。3はやりがいの搾取に直結しますから極力避けたい方法です」と前置きしつつ、自身の過去の監督作ではこの5つの方法をどのように組み合わせてきたのか1作ずつ説明する。そして「日本とフランス・韓国の大きな違いは、映画や映像に特化した公的機関が存在しないということ。そのためいろんな省庁の助成金を組み合わせる必要があり、使いづらいんです」と日本版CNCの必要性を伝えた。
最後に深田から、映画学校に通う学生に向けたアドバイスが。「新人時代を大切にしてください。各国の新人への助成は充実しています。新人部門でないと(助成金をめぐって)ヴィム・ヴェンダースやウォン・カーウァイといった監督たちと戦わなくてはならず、非常に厳しい戦いになってしまいます。新人の基準は年齢ではなく長編映画の本数になることが多いです。慌てて長編映画を何本も作ってしまうと、新人の資格を失うことがあります。まさに自分がそのパターンでした(笑)。短編を作って海外の映画祭に出品していき、キャリアを積んで長編を作るのがスタンダードな道筋だと思います」と呼びかけた。
第38回東京国際映画祭は11月5日まで開催。同映画祭のガラ・セレクション部門に選出された深田の監督作「











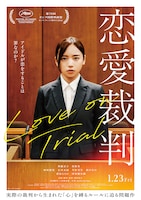


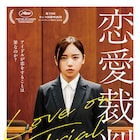









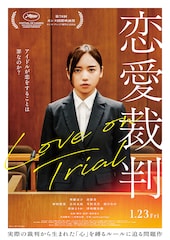







































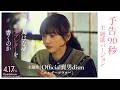








深田晃司 @fukada80
東京国際映画祭「アジア学生映画コンファレンス」にて僭越ながらマスタークラスを行いました。レポートがアップされています。お越し頂いた皆様に感謝します。
TIFFはまだ改善できる点は色々とあるのだろうと思いますが国内外の映画人が出会う場として少しづつ変化してきているのではないかと感じます. https://t.co/gMpBnkqS8y