映画「
映画「アイム・スティル・ヒア」あらすじ
第97回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した本作は、軍事独裁政権が支配する1970年代のブラジルを舞台とする物語。元国会議員であるルーベンス・パイヴァの妻エウニセは子供たちと穏やかな日々を過ごしていたが、スイス大使誘拐事件を境に政情が一変し、ルーベンスが軍に突然連行されて消息不明になる。フェルナンダ・トーレスのインタビューコメント
絶望の淵に立たされながらも声を上げ、時代を揺るがしていくエウニセを演じたトーレスは、本作での演技を高く評価され第82回ゴールデングローブ賞で主演女優賞(ドラマ部門)を獲得。「あまりに重い現実を、微笑と自制心で演じねばならなかった」と思い返す。撮影中に感情のたかぶりを抑えきれずリオの町を1人歩きながら涙したそうで「役が憑依したかのような感覚を覚えました」と明かした。トーレスは、本作が世界各国の映画祭で多くの観客に受け入れられていることについて「この映画が家族の物語だからじゃないでしょうか」と分析し、「ブラジルで軍事独裁を扱う映画というと、ゲリラや抵抗運動、権力に正面から挑んだ人々の物語になることが多い。でもウォルターは、家族を描こうとした。だからこそ観客の反応が驚くほど真摯で、胸に響くものばかりでした」と述懐する。また「失踪した家族を抱えていたり、兄弟姉妹の多い家庭で育ったり、アルツハイマーの家族がいたり。子供たちが登場することで、自分の家族と重ねる人も多かった。ある意味ではこの映画はファミリードラマなんです」と続けた。
トーレスは「私たちは“第2の冷戦”と呼びたくなるような時代を生きています。南米の軍事独裁は南米だけの問題のように語られることが多いけれど、あれも冷戦の一部だった。世界全体が緊張に覆われていた時代。そして今また核兵器の話が出てきて、戦争があり、人々は世界の終わりを恐れている。各地でナショナリズムが勢いを増し、“第2の冷戦”と言いたくなるような状況です。そんな時代に、エウニセは『変わるには時間がかかるけれど、もっと文明的でなくてはならない』と語りかけてきます」と述べ、「人々がこの家族の物語に自分を重ねるのは、今の世界があまりに暴力的だからかもしれません」「多くの人が友人や家族といった親しい関係の中に、自分の居場所を探そうとしている。エウニセもそうでした。弁護士として市民権を守り、新しい憲法の制定に関わるまで、長い時間をかけて内側に力を蓄えていった。それがこの映画の大きなメッセージの1つだと思っています」と口にした。
「黒澤明や小津安二郎が大好き」と語るトーレス。「以前、黒澤監督にお会いする機会がありました。皆で集まり、監督を囲んで言葉を交わしたあのひとときは、私にとって忘れがたい出来事となりました」と振り返り、「日本の歴史や文化、俳優たちの感情の表現には、いつも深く感銘を受けます。深い感情と少し不器用な不安定さが同居していて、それがとても魅力的です」と言及する。さらに「サンパウロで、“死”をテーマに多くの作品を残した舞踏家・大野一雄さんの息子、大野慶人さんが教えるクラスを受けたことがあり、自分に大きな影響を与えました。日本から学ぶべきことは本当に多いと感じます。“過去と未来を一緒に抱えて生きていく”という日本的な在り方には、私たちへの大きなヒントがあると思います」と述べる。
最後にトーレスは「『これが映画のメッセージです』と断定するのはあまり好きではありません。そう言ってしまうと、映画を1つの箱の中に閉じ込めてしまうような気がして。ただ、今の時代について強く思うのは、誰もが怒りを抱えていて、“あなたは間違っている、私は正しい”と指を差し合い、声を荒らげているという現実があるということ。世界は分断され、礼節を欠き、非文明的な状況にあります」とコメント。そして「エウニセが示してくれたのは時間がかかっても文明的な革命を選ぶ姿勢です。今の人々は、怒りをSNSに投稿して、それだけで何かをやり遂げた気になってしまう。キャンセルカルチャーは好きではありません。本来なら同じ側に立てるはずの人たちまで分断してしまうから。いらだちや怒りが支配する時代だからこそ、エウニセのような存在はとても大きな手がかりになると思っています」と伝えた。
「アイム・スティル・ヒア」は8月8日より東京・新宿武蔵野館ほか全国で公開。
映画「アイム・スティル・ヒア」本編映像
関連記事
フェルナンダ・トーレスの映画作品
関連する人物・グループ・作品





























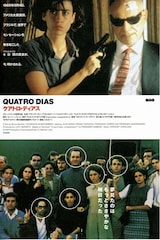






















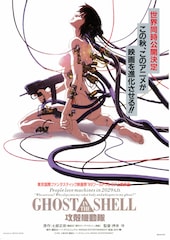




















tAk @mifu75
フェルナンダ・トーレスが「アイム・スティル・ヒア」語る「この映画はファミリードラマ」 https://t.co/uTRqc4JZkU