第26回東京フィルメックスのサイドイベントである「監督たちが語る:世界と交差する日本映画──国際映画祭の現在」が11月23日に東京・有楽町朝日スクエアで開催。映画監督の
今年のカンヌ国際映画祭では10本もの日本人監督作が上映され、三宅唱による「旅と日々」は第78回ロカルノ国際映画祭インターナショナル・コンペティション部門にて金豹賞とヤング審査員賞特別賞、藤元の「
深田ははじめに、映画祭という場について「世界に大小4000以上あると言われていて、映画祭によっていろんなカラーがある。イメージしやすいのはレッドカーペットをスターたちが歩く華やかな様子だと思いますが、それは氷山の一角。自分はよく“魚市場”と表現するんですが、つまりそこへ行くとその年に撮れた新作と出会うことができるので、関係者(=配給会社や映画祭のモデレーター)は自分の“店”に合った作品を探しに来ている」と説明する。加えて「完成した映画を上映するだけでなく、脚本段階の作品などの資金を集めるためにプロデューサーや監督が訪れるのも大事な側面。大きな映画祭であれば企画マーケットが行われ、映画の投資をしている人やプロデューサーとブッキングされてミーティングできる。映画祭を起点にして、1年間の映画作りや、完成した映画の市場への送り出しも行われるので、非常に重要な場所なんです」と伝えた。
国際共同製作では助成金の“条件”を綿密に調整
これまでの映画祭との関わりについて聞かれた石川。カズオ・イシグロの小説をもとに「
東京フィルメックスのコンペティション部門に出品されている畑の初長編作品「グラン・シエル」は、彼の拠点であるフランスと、ルクセンブルクの共同製作。フランスの国立映画学校La Fémisの映画監督科を卒業した畑は「フランスは映画大国なので、基本はできればフランス100%でやりたいと考える人が多く、合作する場合はストーリーなどで必然性がない限り(資金調達のため)“仕方なく”であることが多い。今回の僕の作品は、舞台がルクセンブルクの国境と近いエリアでもあったので組んでみようと」と経緯に言及する。苦労もあったようで「(製作費の)3分の1がルクセンブルクという割合。その分の助成金を得るには、(スタジオも含め)撮影の3分の1をルクセンブルクで行い、スタッフのほぼ半分と役者3人はルクセンブルクの人を使うという厳しい条件だった。そのうえ、ルクセンブルクの平均給与はかなり高いので、フランスのクルーの給与もその分上げなければならなくて。いいところもあれば制限も出てくるのは事実で、細かい調整で条件を満たしていきました」と語った。
フランスでのポスプロ作業で感じた、編集技師のアーティスト性
日本・フランス・マレーシア・ドイツの共同製作「LOST LAND/ロストランド」の監督を務めた藤元は、フランスで行ったポスプロ作業を回想する。「フランスのポスプロはよかったなと。日本国内だと時間に追われていて、あまりディスカッションせずに監督のトップダウンでどんどん決めていくような現場が多い。フランスではディスカッションベースで、“何が表現として最適か”という話し合いをしながら進めるのが前提なので、その分予算もかかってしまうんですけど、やりやすくて気持ちよかったです」と述べた。
同じくフランスでポスプロ経験のある深田は「日本でのポスプロは“監督のやりたいことを高い技術で実現する”という傾向がみんなではないにしろ強いけど、フランスの編集者は“自分はアーティストである”という感覚が強く、『こうしたほうが面白くなると思う』という意見をガンガンぶつけてくる。思いもよらない案が出てくるのは楽しい」と語る。続けて「『
海外における短編映画の存在感
続いて「そもそも映画監督として、国際映画祭を意識し始めたのは?」というトークテーマへ。藤元は「学生時代の授業の一環で、なら国際映画祭の学生部門をスタッフとして担当する機会があったんです。地域の人々に密着したしたスタイルがいいなと思い、自分も映画を作ったらそういったところに出したいと思っていました。ただ卒業制作の短編をドバイ国際映画祭に出したときに、『短編部門自体のヒエラルキーが下』といった内容でボロカスに言われてしまった。それで火が付いて、長編で獲ってやるぞ!と思ったんです」と語る。
深田も「20代はいろんな映画祭のコンペで片っ端から落ちて、“こんちくしょう!”という気持ちが強かったので共感します」と寄り添いつつ、「海外だと、短編映画を作って、それが映画祭で評価されて、プロデューサーが付いて、長編映画を作る、という流れがあると思う。ヨーロッパの映画祭に行くと短編で研鑽を積んでる人が多いんですが、びっくりするのが、自分の長編作品より分単位で言えばお金も時間も掛かっていることがあるんですよね」とコメント。畑は「フランスは短編も長編と同じような製作システムが小規模でありますし、自己資金で作る人もいるけれど、地方の助成などもある。人によっては2000万円ぐらい集めて(短編を)撮ることもできますし、確かに短編の産業があるのは事実ですね。テレビでも流してくれますし」と話し、石川は「ポーランドもそういう感じですね。銀行がシナリオコンペを開いていくらかもらえたりとか、テレビ局がお金を出してくれたりとか」と紹介した。
国際共同製作の作品で求められる“日本人らしさ”に葛藤
国際共同製作をするにあたり、海外の映画祭に出品する際に文化圏や“日本人らしさ”をどれぐらい求められるか?という話題では、深田が藤元に「『LOST LAND/ロストランド』ではキャストの多くはイスラム系少数民族・ロヒンギャですし、監督以外に日本人要素がまったくない。(周囲の反応で)何か感じることはありましたか?」と質問する。藤元は「映画祭の場では『日本からこんな監督が出てきた』という言われ方もしないですし、作品のことだけしか言われなかった。デメリットと感じたのは、配給が決まっているフランスの市場では『今流行の日本映画の文脈に乗せての宣伝が難しい作品』と言われたこと。日本人ということを打ち出していかないと難しいのかなと」と率直な思いを吐露。畑は「まだまだ葛藤がありますね。学校にいたときも『なんで小津(安二郎)みたいなの撮らないの? 日本の映画を観せてほしいのに』と言われましたし、それはつらかったです。国籍の問題は難しいですが、今はいろんな場所に簡単に行ける時代なので、これまで『これが日本映画、フランス映画、イタリア映画』と言われてきたものがどんどんハイブリッド化していくと思いますし、業界の人もそういう目で見ないといけないと思う」と持論を展開した。
外国映画が流行らないドメスティックな業界に危惧
イベントでは観客とのQ&Aの時間も設けられ、「日本映画が豊作で、興行的にもヒットしているが、外国映画が流行らない現状をどう捉えているか?」という質問が飛んだ。深田は「どこの国でもハリウッド映画が圧倒的に強いので、いかに国内の映画産業を守るかが課題になっている中、この現状は日本の映画人としては喜ばしいけど、どんどんドメスティックになっているのは危惧している」と述べる。続けて「映画とは“自分にはどう世界が見えているか”の大切なフィードバックであり、それは社会の多様性や民主主義を支えていると思っている。同時代の日本映画は感覚も近いし知ってる俳優も出るので見やすいと思う。でも食べやすいものばかりを食べていると栄養が偏るように、本来はいろんな国や時代の映画を観られる環境が整っているべき。日本のシネコンで多様な映画がかからず、ミニシアターもかなり厳しい状況。その状況も関係しているのではないかなと思います」と訴えた。
第26回東京フィルメックスは11月30日まで有楽町朝日ホール、ヒューマントラストシネマ有楽町で開催。
「第26回東京フィルメックス」開催概要
開催日時・場所・料金
開催中~11月30日(日) 東京都 有楽町朝日ホール、ヒューマントラストシネマ有楽町
前売料金 :一般 1700円~1800円 / U-30割 1200円~1300円
会期中料金:一般 2000円 / U-30割 1500円
関連記事
深田晃司の映画作品
タグ
























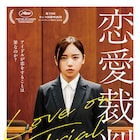

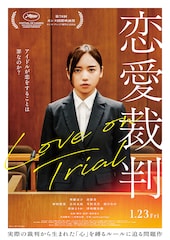












































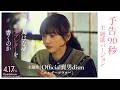







平田真人(真田仁平/筆客仕事人) @matrisanez
自分、この「#東京フィルメックス」サイドイベントを拝見させてもらいまして、記事の最後にある「日本映画が豊作で、興行的にもヒットしているが、外国映画が流行らない現状をどう捉えているか?」という質問もさせてもらいました。終了時間ギリギリでしたが、#深田晃司 https://t.co/tB7vuKqR3Q