
ナタリードラマ倶楽部 Vol. 17 [バックナンバー]
“何も起こらない物語”は日本の強み、韓国での「孤独のグルメ」ブームから見る日本ドラマの魅力を西森路代が語る
「架空OL日記」「今日は少し辛いかもしれない」「しあわせは食べて寝て待て」…元祖は小津安二郎作品?
2025年5月27日 12:00 12
ドラマについて取り上げる連載「ナタリードラマ倶楽部」。Vol. 17となる今回は、今年3月に発売された書籍「あらがうドラマ 『わたし』とつながる物語」の著者であるフリーライター・西森路代のインタビューをお届けする。
さまざまなドラマを分析・批評する中で、“何も起こらない物語”は日本の強みだと語った西森。主人公が何かを成し遂げるわけではなく、ただこれからの生き方を考えたり、結婚などに縛られずに今を生きていたり──そんな淡々とした日常を描く物語の元祖は
取材・
西森路代(ニシモリミチヨ)プロフィール
愛媛県生まれのフリーライター。主な仕事分野は韓国映画、日本のテレビ・映画についてのインタビュー、コラム、批評など。著書に「K-POPがアジアを制覇する」「韓国ノワール その激情と成熟」、共著に「韓国映画・ドラマ──わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020」などがある。
西森路代 (@mijiyooon) | X
“何も起こらない物語”の元祖は小津安二郎?
──西森路代さんの著書「あらがうドラマ 『わたし』とつながる物語」の中では数々のテーマが取り上げられています。その中でも「団地のふたり」(2024年)などにフォーカスした章「たたみゆく暮らし」に書かれていた「『何も起こらない物語』は、日本の物語の強み」という視点に興味を持ち、今回取材を依頼させていただきました。中年期・老年期の主人公が何かを成し遂げるわけではなく、これからの生き方を考えたり結婚などに縛られずに生きていたりするドラマが増えている印象ですが、その背景について西森さんはどう考えていますか?
日常を描く作品はいつの時代もあったと思いますが、私自身は数年前から「この登場人物たちの暮らしがフィクションの中だけじゃなくて、終わってからも続いているようなものがいいな」と思ってドラマを観るようになりました。この話をしていると思い出すのは、
──確かに、それまであまりなかった表現のような気がします。西森さんは韓国のエンタメにも詳しいですが、淡々とした会話劇や“何も起こらない物語”は日本特有の文化なのでしょうか?
韓国の人がそれをよく指摘してくれます。20年前ぐらいから、韓国の監督の皆さんが「日本の、淡々とした日常だけを描いているのに何かが残る作品はすごくいい」と言われていますし、大学で勉強してきた俳優さんたちも、
──日本人は知らず知らずのうちになじんでいたんですね。
バカリズムさんの作品が生まれるもっと前の、ホームドラマでのなんでもない食事シーンなんかも当てはまると思います。韓国の人たちはドラマを作る際には三幕構造をしっかりさせたうえで発展させたりして、場面場面で面白くするための技術を使ってきたから、“淡々としているのに面白い作品”というものに挑戦したいという気持ちがあるのだなと思いました。もちろん、韓国でも
──お話の中で、日本のどんな作品が例に挙がるのでしょうか?
以前であれば岩井俊二監督の映画「
2010年代半ば、韓国でヒーリングドラマが増加
──そんな中、韓国ドラマでも“何も起こらない物語”が増えているそうですね。
韓国では「大丈夫、愛だ」(2014年)とか「キルミー・ヒールミー」(2015年)などをきっかけに、2014年ぐらいから“ヒーリングドラマ”がはやり始めました。「椿の花咲く頃」(2019年)や「私たちのブルース」(2022年)といった、主人公が海辺の街や田舎町に行って疲れた心を癒やすようなドラマが増え、それはコロナ禍でさらに加速しました。「私の解放日誌」(2022年)のように日常のそこはかとない生きづらさとどう向き合うかを描く作品も多くなったと感じます。
──そもそもですが、西森さんがおっしゃっている“何も起こらない物語”の定義は?
何も起こらないっていうのはつまり、ちゃんと日常が描かれているということ。わかりやすく言えば、話を盛り上げるためのフックとしての事故や事件や死が出てこない感じですね。 韓国は中高年にもいい俳優さんがいっぱいいて、
──日本に、何も起こらない日常を淡々と描くドラマが多いのは、小津作品のほかテレビ東京のドラマの影響も大きい気がします。
2000年代初頭に「冬のソナタ」がはやったとき、日本では「“赤いシリーズ”だ」って言う人が多かったんですよ。赤いシリーズっていうのはTBSと大映テレビが共同で1974年から1980年にかけて制作・放送していたサスペンスドラマシリーズ。
──「赤い疑惑」「赤い衝撃」といった作品ですね。
「寂しさ」を“生きていく中で当たり前に訪れる出来事”として描く
──西森さん自身は、何も起こらない物語のどこに魅力を感じていますか?
気負わずに観られるというのはありますね。小泉今日子さんと
──著書には「団地で作られる関係性に癒されつつ、ふと『寂しさ』もよぎる」とも書かれていました。物語における“寂しさ”は、描き方によってシリアスな方向に物語を進める可能性もありますが、癒やしと寂しさを両立している理由はなんだと思いますか?
やっぱり日常は続いていくので、寂しさだけに焦点が当てられるのではなく、この先にいつかそういうことがある、みたいな形で示唆するくらいにとどめられていることかなと思います。「団地のふたり」も「阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし」(2021年)も、最近だとNHKのドラマ10「
──その人だけに起こる特殊な状況や病気などではなく、誰もがいずれ経験するであろうことのほうがほんのり寂しさを感じるのかもしれませんね。
放送中の「
──「しあわせは食べて寝て待て」では、給料日に素直に喜べず、支出を考えて落ち込んでしまう、という描写もあります。“貧困”とまではいかなくても、切り詰めて生活する人のリアルを描いた作品がNHKにはありますよね。
もっと東京以外に住むいろんな人の話があるといいな
──西森さんが今、「何も起こらない」「疲れない」ドラマの中でもこういう物語が観たい!という作品はありますか?
私が地方出身で、30歳を過ぎて上京したということもあって、地方に住む人の暮らしや気持ちに焦点を当てた話が観たいと、周りにも話しています。田舎から上京したい人の話や、地元に残っている独身の女性の話など、東京以外に住むいろんな人の話があるといいなと思います。ヒーリングドラマの部分があってもいいけど、そうじゃない部分も描かれてほしいと思います。田舎=ヒーリングっていうのも、住んでいる人からするとちょっと安直だと感じるのではないかと思うので。
──最後に、ドラマを普段から観る人と、あまり観ない人それぞれに向けて、“何も起こらないドラマ”のお薦め作品を教えてほしいです。
さっきも話題に出ましたが、「晩餐ブルース」はお薦めしたいです。1話からよかったけれど、3話くらいから「おー!」と思うことがあったので、まだ観てない人がいたらぜひ観てほしい。「日常の中にこそ大切なことがある」と思わせてくれる作品です。
──ドラマをあまり観ない人には、どんな作品を薦めたいですか?
やっぱりバカリズムさんなんじゃないですかね。全話しっかり面白い。私はこの前の「
刊行記念イベントではゲスト・小泉今日子とドラマトーク!
去る2025年5月1日に、東京・本屋B&Bで西森路代×小泉今日子「代田のふたり ~日本のドラマを語る夜~」を開催。イベント内容のレポートは追って映画ナタリーで掲載する。
書籍「あらがうドラマ 『わたし』とつながる物語」
西森路代著、303BOOKS、264頁、税込1870円
日々目まぐるしく変化する価値観や社会のあり方を敏感に捉えた日本のテレビドラマ 23作品が厳選され、「組織と労働」「恋愛の現在地」「性加害」「たたみゆく暮らし」などをテーマにさまざまな切り口で紹介。連続テレビ小説「虎に翼」の脚本家・吉田恵里香との特別対談も収録されている。
バックナンバー
- Vol. 19 縦型ショートドラマの初心者講座、GOKKO・BUMP・DramaBoxなどプロダクション代表者によるトークもお届け
- Vol. 18 小泉今日子が西森路代とドラマ談義、「最後から二番目の恋」トークも飛び出したイベントレポ
- Vol. 16 「御上先生」で学ぶ考えることの大切さ、「クジャクのダンス、誰が見た?」はラーメンが食べたくなるミステリー
- Vol. 15 「東京サラダボウル」がスポット当てる“多文化共生”に興味津々、バカリズム新作は「ブラッシュアップライフ」に気後れした人を救う…かも
- Vol. 14 柚木麻子と令和ドラマのヒロイン・ヒーロー像を考える、かつて愛されたドジっ子ヒロインの行く末とは
- もっと見る
関連記事
バカリズムのほかの記事
リンク
関連する人物・グループ・作品
タグ










































































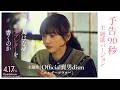







語学サービスANC 大阪市 講師派遣、翻訳、通訳、オンラインレッスン、語学スクールなど(新大阪付近) @ANC_Languages
ナタリードラマ倶楽部 Vol. 17 “何も起こらない物語"は日本の強み、韓国での「孤独のグルメ」ブームから見る日本ドラマの魅力を西森路代が語る (ナタリー)
https://t.co/9BsZqdIKv4
#日本 #大韓民国 https://t.co/vclFfVeTm6