
マンガ編集者の原点 Vol.17 [バックナンバー]
「花に染む」「銀太郎さんお頼み申す」の北方早穂子(集英社 ココハナ副編集長)
ベテランから新人まで、集英社の女性向けマンガを長年支える編集者
2025年4月7日 17:00 5
マンガ家が作品を発表するのに、経験豊富なマンガ編集者の存在は重要だ。しかし誰にでも“初めて”がある。ヒット作を輩出してきた優秀な編集者も、成功だけではない経験を経ているはず。名作を生み出す売れっ子編集者が、最初にどんな連載作品を手がけたのか──いわば「担当デビュー作」について当時を振り返りながら語ってもらい、マンガ家と編集者の関係や、編集者が作品に及ぼす影響などに迫る連載シリーズだ。
今回は、
取材・
「はいからさん」と「スター・レッド」の衝撃
北方氏の子供時代は「適度に外で遊び、適度に家でマンガを読む、普通の子」だったという。
「5つ上のいとこがいて、彼女からお下がりのマンガをもらうことが多かったです。最初は『ベルサイユのばら』(池田理代子)と『はいからさんが通る』(大和和紀)を小学校1年生の入学式のときにもらい、そこから4年生ぐらいまで新たなマンガを買い足してもらえず(笑)。2作品合わせて18冊なんですが、それを1日1回、ひたすら読んでいました」
「ベルばら」と「はいからさん」。最初に手に取るマンガにしては、子供向けとは言えない少女マンガである。
「最初、全然わかっていなかったんです。オスカルとアンドレの初夜シーンは『2人でかけっこした後に、疲れて寝てるのかな?』って思っていたくらいで(笑)。成長した後に読むと全然違って読めますね。いまだにこの2作品は好きで読んじゃいます」
2人でかけっこ! なるほど、何も知らないとそう読めてしまうのか──なんともかわいらしいエピソードだ。
「風邪を引くと親が 3巻完結くらいの作品を買い与えてくれるルールが我が家にあったんですけど、私自身があまり風邪を引かない子供で。小学校4年生になって萩尾望都さんの『スター・レッド』と萩岩睦美さんの『小麦畑の三等星』が加わってからは、毎日その4作を繰り返し読んでいました。
なぜその2作だったのかはわからないのですが、『スター・レッド』もすごく難しかったし、『小麦畑』もやっぱりSF系のお話。どちらも最後がハッピーエンドでめでたしめでたし、みたいな終わり方ではない。そういうマンガがあることに鮮烈な驚きを覚えて。そこから、世の中にはほかにもマンガがたくさんあるのではと気づき、親にお願いしてりぼんを買ってもらうようになりました」
確かに、特に「スター・レッド」はラストはもちろん全体のストーリーも、大人が読んでもかなり深淵で、小学生には難解だろう。ともかくこうした体験が「忘れもしない、小学4年生の出来事」だったと語る。そこから北方氏が毎月りぼんを買ってもらい、なかよしを買ってもらっていた友達とお互い貸し借りをして両誌読む日々が始まった。
当時、なかよしの看板作家はあさぎり夕で「ミンミン!」を連載中。北方氏のお気に入りはホラーの名手、松本洋子。りぼんは一条ゆかり、谷川史子、吉住渉、水沢めぐみを執筆陣に迎えた「黄金時代」だったという。
「マンガにはカラーページがあるとか、月に 1回雑誌が出て新しい話が増えるという文化があることを知りました。それまでは単行本でしか読んだことがなかったので、雑誌が売っていることも知らなかったし、書店でも児童書のコーナーにしか行っていなくて。マンガのコーナーは大人が行くところというイメージでした」
当時の「なかよし」は、武内直子が「美少女戦士セーラームーン」を連載する前。「ま・り・あ」やフィギュアスケートものの「Theチェリー・プロジェクト」を描いていた頃だった。
「ちょうどなかよしが付録にすごく力を入れだした時期で、あの頃のりぼんとなかよしは紙ものの付録の戦争でした(笑)。りぼんでは、作品の絵柄のトランプが付録でついてきたことがあって、後年吉住さんを担当させていただいたときに、当時私がすごく大切にしていたトランプの原画を見せていただく機会があってすごく感動しました」
北方氏と同じように、姉とりぼん・なかよしを毎月食い入るように読んでいた我が身としては、今回取材後にトランプの絵柄をネットで調べ、懐かしさに胸がつぶれそうになった。
「その頃になると、『はいからさん』で描かれていることも、『かわいい子が元気にがんばって暮らしている』以上のことを理解できるようになってきて。日露戦争、満州、関東大震災──いろんな言葉や歴史背景を教わりました。主人公の紅緒さんは職業婦人になっていくんですが、自分が働くようになってから、女の人が働くことについても実はしっかり描いていたマンガだったと気づきました。すごいマンガだったと思います」
「はいからさん」が教えてくれた「編集者の真の喜び」?
実は、北方氏が編集者を志したのにも、「はいからさん」が大きく関わっていた。
「編集者という存在を知ったのは『はいからさん』が最初でした。紅緒さんは職業婦人になるというお話をしましたが、それが雑誌編集者なんです。彼女は作家さんに原稿を頼みに行き、三顧の礼を尽くして丁寧にお願いするのですが、作家さんが『書きます』と言った瞬間に豹変して、締め切り守らせるためにムチを振るう、物理的に(笑)。『これぞ編集者の真のよろこび』とあって、どういうことだ?と思っていました。
紅緒さんがムチをふるったのは、純文学でくすぶっている高屋敷先生という作家さんで、彼女はその先生に娯楽ものの新連載を書かせるんです。すると話題になって人気が出て、廃刊寸前の雑誌が蘇る、といったストーリー。それを読んだときに、『物語の向こうには、誰か別の人がいるんだ』とハッとしました。本や雑誌は作家さんと編集だけでもできなくて、いろんな人がいて作品になっているということを『はいからさんが通る』で知ったんです」
「物語の向こう」に気づいてからは、編集者という存在を気にするようになった。
そうして、北方氏のマンガ好きはにわかに加速。中学生頃からは、貪るようにマンガを読むようになったという。秋田書店では「やじきた学園道中記」(市東亮子)、天城小百合、姫木薫里。白泉社では、「ここはグリーン・ウッド」(那州雪絵)や「ぼくの地球を守って」(日渡早紀)。小学館では「BANANA FISH」(吉田秋生)。加えて、大和和紀や池田理代子、萩尾望都の過去作を読み漁る日々だった。
「吉住渉さんの作品も大好きで。『ハンサムな彼女』の可児くんが好きなのですが、髪にトーンが貼ってある男の子に出会った最初の作品です(笑)。りぼんは毎月3日発売なのですが、毎月1日には、本当に具合が悪くなるくらい楽しみでした。2日には、もう売ってないかなって書店に見に行ったりしていました。
マンガは、自分のペースで読めるところが好きで、そこがいいところだと思います。アニメや映画だと一度聞き取れなかったり、いいシーンの余韻に浸っていたりするとそのまま物語が進んで置いてかれちゃったりする。映画よりも本よりもマンガが好きでしたね」
父との暮らしで、身をもって知ったこと
ここで、以前からずっと気になっていたことを聞いてみた。北方氏の父は、有名な作家。北方氏が編集者という職業を選んだのは、父親の影響が大きかったのでは、と勝手にストーリーを思い描きながら来たのだが、どうやらそうではないようだ。北方氏が編集者を目指すようになるまでの道のりに、父からの影響は「まったくない」という。
「父の作家業は、私が学校に入った頃にやっと仕事になってきたくらいでした。私がもともと小説は好きではないこともあり、父の作品はもちろん、家にある蔵書も読まなかった。6つ下の妹も同じで、妹にいたってはマンガも読んでいませんでした(笑)。ただ、父が自分の書いたものを読んでほしいと思ったのか、私たちがそれぞれ小学生のとき、小学館の「小学一年生」『子供向けの物語を書かせてくれないか』と持ち込み、連載させてもらっていました。
「父は、『マンガを読むのやめなさい』ってずっと言ってました。なんなら今も言ってます(笑)。私はマンガを仕事にしていて、働いているんだけどな、みたいな(笑)」
歴史は繰り返す、とは言うが、北方氏の父もまた、氏が小説家として身を立てていくことに最初は否定的だったという。その関係性と少し似ている気がする、と話すと、北方氏も「そうかもしれない」と笑った。
「本当にたくさんの方に父の作品を読んでいただいているんですよね。子供の頃は、だからこそ娘である自分はご飯が食べられる、と思っていました。『誰かが本屋さんでお父さんの本を買ってくれるから、家にお金が入って、私は学校に行けるんだ』って。だから、今編集として仕事をしていて父からの影響があるとしたら、もしかしたらその感覚かもしれない。誰かに作品を買ってもらわないと、そのマンガ家さんはご飯が食べられなくなってしまうという感覚が、一番の影響かもしれないですね」
「道成寺伝説」を突き詰めた大学時代
さて、北方氏の少女時代に話を戻そう。中学で本格的なマンガ好きになった北方氏は、高校生になると、「マンガを作る過程のどこかに関われる人」になりたいと思うようになった。
「自分でマンガを描きたいとは思わず、『いつかマンガのあとがきに書いてもらえるような人になりたい』という、幼い夢ですね。それこそ『アイドルになりたい!』みたいなのと同じぐらいの感覚でしたが、印刷する人、写植を打つ、デザインする人か……何かどうにかマンガに関わりたい、と思っていました」
そんな夢を抱きながら、大学は清泉女子大学の文学部に進学。そこにもストーリーがあった。
「高校3年生のときにその大学の先生の論文を読むことがあったんですが、すごく面白くて。私は高校で歌舞伎が好きになったんですが、歌舞伎や芸能の起源はどこにあるのかについていろいろ探って読んでいるうちにその先生にたどり着いて。万葉集、貴種流離譚、異類婚姻譚や芸能の歴史をはじめ古代の文学における恋愛観などについて研究している方でした。その先生に教えてもらいたいと思っていたら、ちょうどその本を見た叔母が『私が通った大学の先生だ、あなたにもぜひ行ってほしい』と勧めてくれました。
実際入学してみると、少人数制でいろんな研究を深くやらせてくれるところで。とある友人は、大学生活を通して“恋と愛とは何が違うか?”について研究していて、『日本には“愛”はもともとなかったに違いない』みたいな説を繰り広げながら4年間を過ごしていました。変わり者がたくさんいて刺激的でした」
清泉女子大学の設立母体は聖心侍女修道会という、スペイン・マドリッドで誕生した修道会であり、キャンパスは五反田にある旧島津家の本邸。北方氏の言葉通り、少人数制の教育を伝統として持つ大学だ。それにしても、高校で歌舞伎、そして万葉集──渋い、渋すぎる。そして北方氏は、一度好きになったらとことん突き詰めるタイプであるというのがわかってきた。
「ひと言で言うとオタクでした(笑)。高校の文化祭でも1人で歌舞伎や文楽の展示をしたり。今思うと渋い高校生だったなと思いますけど、当時、私の中で一番の萌えだったんです。超萌えていました」
そんな北方氏が大学で研究テーマに選んだのは、道成寺伝説。いわく、「元祖女性ストーカーの話です」。ところは紀州道成寺、旅の若い僧・安珍に懸想した女性・清姫が、安珍恋しさに追いかけるうち大蛇に姿を変える。安珍は逃げ込んだ道成寺で釣鐘の中に身を隠すが、大蛇になった清姫は鐘に巻き付いて炎を吐き、安珍を焼き殺してしまう。清姫自身も川に身を投げる──といった、女の執念のものすごさが描かれた昔話だ。和歌山出身の筆者も小さい頃から絵本や紙芝居で馴れ親しんだ。
「能や歌舞伎にも道成寺ものがあるのですが、これは後日談なんです。こういう成り行きで道成寺に鐘がなくなってしまったので、もう一度落成します、というときに、道成寺に清姫の霊が現れるというお話。大学では、もともとの話がどこで生まれてどういう変遷を経て能に入り、その後歌舞伎に入ったかという研究をしました」
YOU──レディースコミック色に戸惑った新人時代




















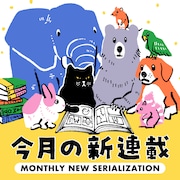

































geek@akibablog @akibablog
「花に染む」「銀太郎さんお頼み申す」の北方早穂子(集英社 ココハナ副編集長)
https://t.co/qNZVqoEQRx