「
内戦が発生したアメリカを舞台とする本作は、14カ月の間、一度も取材を受けていないという大統領へインタビューを行うため、4人のジャーナリストチームが戦場と化した道を進む物語。キルスティン・ダンスト、ワグネル・モウラ、スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン、ケイリー・スピーニーらがキャストに名を連ねた。
家族とプライベートで旅行をするほどの日本好きだというガーランド。1980年代にアニメ「AKIRA」と出会ったことがきっかけだったそうで「見たことのある世界でありながら、どこか知らない世界であるようにも感じていた。その奇妙さに惹かれたんです」と回想した。
そして本作のアイデアについて話が及ぶと、ガーランドは「空想を描いているわけではなく、世界で今繰り広げられていることをそのまま反映しているつもり。過激派が台頭してきたり、世界中のあらゆる場所で分断が起きています。問うべきなのは『これが本当なのか』ということではなくて『これはいつ、どこで止まるのだろうか』ということ」と語り、「近未来を描いているのでフィクションの部分はもちろんありますが、50%は現実だと思っています」と言葉を紡いだ。
町山は、もっとも保守的なテキサス州と民主党を支持するリベラルなカリフォルニア州が手を組んで、大統領の独裁政治と対峙するという物語構造に着目。「この設定にした理由とはなんでしょうか?」と聞くとガーランドは「思考実験の要素があり、観客の皆さんに問いかけているんです。この2つの州が結託するのは、はたして想像し難いことか?と」と回答。「大統領は法治国家であるアメリカを崩壊へ追いやって、市民を虐げている。そんなファシズムに彼らは抗っているのであって、僕は非常に理にかなったことだと思っている。“右対左”という構造が、独裁政権に対峙することよりも重要なのだろうか?ということを考えてもらいたい」と説明する。そして町山が「“ファシズム対デモクラシー”という構造を描いているということでしょうか」と改めて質問すると「まさにその通りです」とうなずいた。
「主人公をどちらかの勢力に属する軍人ではなくて、なぜジャーナリストにしたのか?」と町山が目線を送ると、ガーランドは「この時代の特徴として、ジャーナリストが敵視されがちだと思っている」と前置きしてから「それは腐敗した政治家がジャーナリストを矮小化しているからだと思います。デモを取材しようとすると唾をかけられたり、暴力を受ける状況にある」と言及。「これは本当に狂気の沙汰です。国を守るため、我々の自由な生活を守るためにジャーナリズムは必須。こんな世の中ですから、映画ではジャーナリストをヒーローとして描きたかった」と吐露した。
スピーニー演じるジェシー・カレンはフィルムカメラを携えた人物。「なぜフィルムカメラ?」と町山が首を傾げると、ガーランドは「まず『ジャーナリズムの対比を描きたかった』という思いがあります。彼女がフィルムで撮影する一方で、年長者はデジタルで映像撮影している人も。要は映像とスチルというメディアの対比をしたかった」と経緯を明かす。「また、古い時代のジャーナリズムを想起させる描写を入れたかったんです。彼女の報じ方は1960年、70年代のジャーナリストのスタイル。目の前の出来事を淡々と記録するという、リポーターとしてのジャーナリストを彼女を通して描いているつもりです」と打ち明ける。一方で「西洋諸国では今、“そのまま報じる”という原則が放棄されているように感じます。つまり“プロパガンダ・マシーン”に成り下がってしまっている。大手メディアはニュースを報じることよりも広告収入を重んじて、メディアの責任を放棄している。一番若いジェシーにそんな僕の思いを託しているのです」と言葉に力を込めた。
銃撃戦のシーンに話が移ると、町山は「僕が一番すごいと思ったのは、兵士たちの動き。とても俳優とは思えない」と感想を伝える。「登場する米兵たちはリアルに従軍した米兵なんです」と告白するガーランドは「なので、武器の構え方などのやりとりが戦場にいるようでもあり、監督としては非常にやりやすかった」と述懐。さらにホワイトハウスでの場面を挙げ「演出として伝えたのは『普段通りに行動してください』ということ。ダイアログも含めて、普段の会話をしてもらっただけなんです。なのでドキュメンタリーを撮っているようでもありましたし、そのときの体験が次回作の構想における着想点にもなりました」と振り返った。
「シビル・ウォー アメリカ最後の日」は10月4日に東京・TOHOシネマズ 日比谷ほか全国で公開される。
映画「シビル・ウォー アメリカ最後の日」予告編
関連記事
アレックス・ガーランドの映画作品
関連する人物・グループ・作品
タグ









































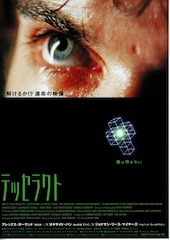














































tAk @mifu75
【イベントレポート】「シビル・ウォー」に込めた思いは?監督アレックス・ガーランドがメディアの役割に警鐘 https://t.co/OT54gMkssh