この個展では、西島のマンガ家デビュー以前の作品から近年行っている個人制作のゲームまでさまざまな作品を展示。新作の銅版画7点は、西島の年齢にちなんでエディション数が51に設定された。メインビジュアルの銅版画「セカイ系のノスタルジア」は、デビュー作「凹村戦争」をモチーフになっている。
なお西島は10月29日に、女子美術大学で講義「アートのきざし理論」をリモート開催。この講義は、同大学の学生以外も聴講可能だ。講義に関する問い合わせは、女子美術大学芸術文化専攻研究室まで。
梅津庸一(美術家・パープルーム主宰):ステートメント
西島大介は2004年に『凹村戦争』でデビューした漫画家です。とはいえ西島さんはわたしたちが思い描くような一般的な漫画家ではありません。作中に登場するキャラはかわいい二頭身であり物語の舞台設定も書き割りのようにペラペラであっけらかんとしています。執拗な描き込みも複雑なキャラ設定もないので比較的すんなりと読み進めることができます。しかしどこか言い知れぬ違和感が付きまといます。読者が窺い知れないところで作品が密かに外部の巨大なデータベースとアクセスし合っているような、そんな不気味さ、疎外感。少なくとも僕が20年前に西島作品と出会った時にはそう感じました。『凹村戦争』のタイトルがSF小説の金字塔『宇宙戦争』とオーソン・ウェルズからとられていることにも表れていますが、作中では先行する様々な作品の引用がいちいち説明されることなく変奏され展開されます。つまり西島作品は過度に批評やジャンルを前提として構築されているのです。また当時、文芸誌『ファウスト』との関わりも深く、『美術手帖2005年6月号「特集|物語る絵画」』にインタビューが掲載されるなど、かなり早い段階から隣接するジャンルへの越境に成功していた点は特筆すべきでしょう。私事で恐縮ですが僕は当時、『美術手帖』に掲載された西島のインタビューにたいへん感銘を受けました。自身をTV版『エヴァンゲリオン』以後の作家と位置付け、オタクが消滅した世界にはパクリのパクリのパクリ、つまり劣化コピーしか存在しないと説く。しかしそんな劣化コピーであっても誰かにとってかけがえのないコンテンツになり得るのだから僕はそれを引き受けた上でつくると。くわえて「スーパーフラット」を提唱した村上隆への言及も。オタクになれなかったアーティスト村上がオタク(アンチ)から批判されるという構図が崩壊しており、それは物語自体の消失を意味すると指摘しました。西島さんは現代アート界へも鋭く批評的な眼差しを向けていたのです。インタビューは大雑把にまとめるとこのような内容で、今となっては当時の西島さんの真意を推し量るのは難しいかもしれませんが20年経った今もなおラディカルに映ります。余談ですが僕が大好きなV系バンドの話に引き寄せればDIR EN GREYはもちろん素晴らしいけれども、そのパクリであると一部界隈で揶揄されたグリーヴァでしか得られない養分もあることと無関係ではないはずです。
ところで西島さんは僕が2009年に初めてキュレーションした展覧会「ZAIMIZAMZIMA エキシビジョン・フォーラム」にも参加しています。当時の編集部を通して展覧会への参加を打診したところ西島さんは「面白そう」と快諾してくれました。またこの展示は先日亡くなった映像作家の大木裕之さんをはじめとする異色のメンバーが集った無秩序で破滅的なものであり、僕のなかで黒歴史化していました。しかし今思えばプレ・パープルームと言える内容でした。
さて、本展は西島大介さんの20年以上に及ぶキャリアを総覧するものです。漫画家による美術展と言えば漫画の原画やグッズを陳列するものがほとんどです。例に漏れず本展にも漫画の原稿は展示されますがもちろんそれだけではありません。草稿、ドローイング、版画、油彩画、ぬいぐるみやフィギュアなどのグッズ、70年代のゲーム筐体に仕込まれた「GB Studio」というソフトウェアを用いてつくられたオリジナルのゲーム、音楽、分類が難しいマテリアルに至るまであらゆる形式のものが一堂に会します。
また今回、西島さんがパープルーム監修のもと初挑戦した油彩画は現在の美術シーンにおいて一般化したキャラクターを主題とするいわゆる「キャラクター絵画」とは一線を画します。「キャラクター絵画」は前述した村上隆VSオタクという構図が無効化しそれ自体も忘却されつつある状況下において生成された絵画群であり、一概には言えないものの作者の実存の投影、そしてキャラクターの記号性と表現主義的なジェスチャーが掛け合わせられたオーガニックな作例を指します。その一方で西島さんの場合は自身の漫画作品からキャラクターを召喚するため出典元が明確であり思わせぶりな物語を演出する必要がありません。
そして同じく初挑戦の版画作品は原画の複製ではなく町田の版画工房カワラボで西島自身がニードルを持ち描版したものです。このタイミングで印刷技術の始祖と言っても過言ではない銅版画(凹版)を用いて『凹村戦争』をはじめとする自作を再解釈する作品を版画工房から出版する意義はけっして小さくないはずです。主線とトーンの範囲指定は西島さん、漫画におけるベタやスクリーントーンはアクアチントに置き換えられ工房が担当しました。したがって、お金儲けのためにオフセット印刷のポスターにサインをするだけの現代アート作家の態度とは根本的に異なります。版画はもともと芸術を民主化するためのメディアでしたが現在は斜陽の一途をたどっています。一方で漫画は個人がつくる創作物として現在も絶大な訴求力を持っています。そんな漫画の世界において西島作品は一般大衆向けの娯楽でもアンダーグラウンドでもない独特の立ち位置を維持し続けておりきわめて稀有な存在と言えるでしょう。
また、西島さんはゼロ年代のポップカルチャーから生まれた「セカイ系」という区分、想像力を体現してきた作家でもあります。諸説ありますがセカイ系とは「きみ」と「僕」といった主人公周辺の自意識過剰の人物が半径2メートルのリアリティを諸々の事情をすっ飛ばし「世界の命運」といった壮大な物語と接続してしまうような飛躍、あるいはその物語構造と言えます。しかしセカイ系を批評史的に検証すると数名のキーマン、業界の力学に収斂していくことは避けられません。作品をつくる主体が何に依拠してきたのかを考えることは有益ですが、ジャンルや文脈を内面化する西島作品であっても即座にある特定のコミュニティやムーブメントに準じてラベリングし固定するのは得策とは言えません。それよりもセカイ系の想像力の射程を超えて西島作品はわたしたちに「そもそも作品をつくるとはなにか?」そして「作品における固有性の内訳とはなにか?」と問いかけているのです。
本展の会場はもので溢れかえり西島さんによる「ひとり文化祭」の様相を呈しています。謎に満ちた西島さんのこれまでの歩みと次なる展開の兆しが乱反射するように。そこには有形の作品に還元されない西島の思念すらも飛び交っているように思います。
最後になりますが、この度はパープルームギャラリー ダイエー海老名店で西島大介個展を開催できることをたいへん嬉しく思います。みなさま、是非お越しください。
西島大介個展「セカイ系のノスタルジア」
会期:2025年10月25日(土)~11月30日(日)※月、火曜日休廊
時間:12:00~20:00
会場:パープルームギャラリー
西島大介のほかの記事
関連する人物・グループ・作品
タグ














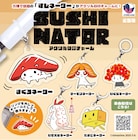












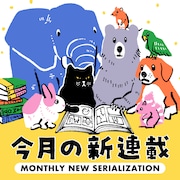

































geek@akibablog @akibablog
西島大介が個展開催、メインビジュアルは「凹村戦争」モチーフにした銅版画
https://t.co/CTxO3r0vJu