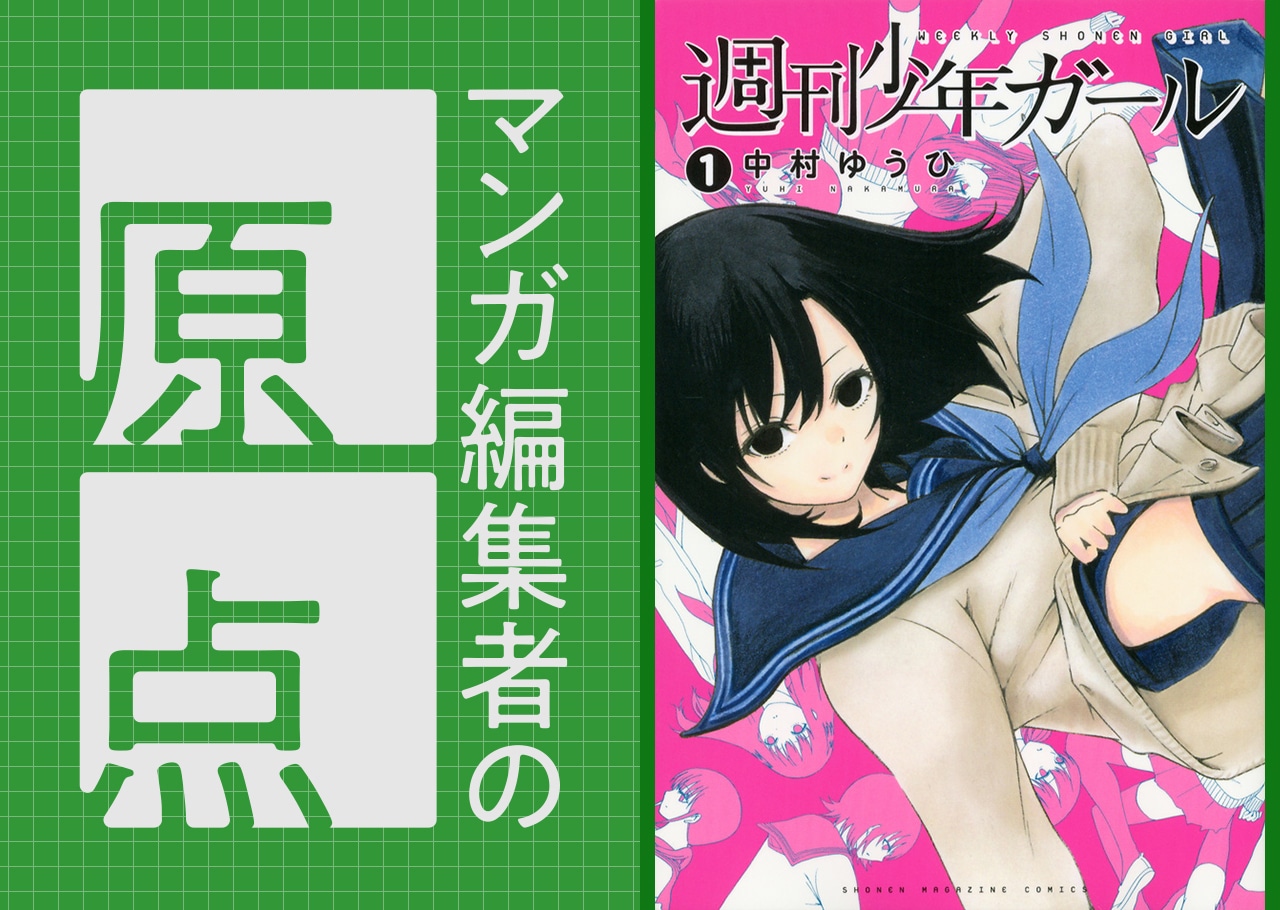
マンガ編集者の原点 Vol.20 [バックナンバー]
「ブルーロック」「炎炎ノ消防隊」の土屋萌(講談社 週刊少年マガジン編集部)
アオリ名人「担当・T屋」誕生前夜
2025年9月26日 15:00 10
異色のサッカーマンガ「ブルーロック」ができるまで
土屋氏が最も長く担当している作家は2人いる。「アルスラーン戦記」(原作・田中芳樹)、の
そんな金城が現在手がけるのが、2018年に連載を開始した「ブルーロック」。日本サッカーをワールドカップ優勝に導くストライカーを養成するために、ユース代表のFW300人を集めて“青い監獄”=ブルーロックに閉じ込め、サッカーで競わせる。最後に残る1人は世界一のストライカーとなるが、敗者は日本代表入りの資格を永久に失う──“史上最もイカれたサッカーマンガ”の異名を持つメガヒット作は、どのように誕生したのだろうか。
「まず金城さんとは、僕が入社1年目のときに別冊少年マガジンで『神さまの言うとおり』を先輩の下で担当させてもらい、その後週刊少年マガジンで続編『神さまの言うとおり弐』が始まりました。途中から自分がメイン担当となり、連載が終わったときに次回作はどうしよう、という話になって。そのとき、ご謙遜だとは思うのですが金城さんが『自分は邪道の作家で、メジャーなやり方には向いてない』みたいなことをおっしゃったんです。僕たちとしてはやっぱり売れる作品、それも一部の趣味の合う方に売れる作品ではなくて、広くメジャーに売れていく作品を描いてほしいし、描ける作家さんだと思っていた。
そこでご相談して、土台となる題材はメジャーなものにというお願いをし、じゃあファンタジーはとか、教師ものはどうだとか、パイが広そうなジャンルを金城さんと後輩の編集者と話し合っていきました。その中で、スポーツものはどうだろうという話が出て。金城さんはスポーツ観戦がお好きで、特にサッカーとテニスがお好きなので、まず雑談が盛り上がったんです。金城さんの目線では、『日本サッカーも最近面白くなってきてるんだけど、ヒーロー的なストライカーがいなく感じて、そこだけちょっと残念』とおっしゃっていて、じゃあそのテーマでやってみますか、となりました」
こうして、「世界一のストライカーを作る」ことをテーマに打ち立てた「ブルーロック」が動き出した。
「同時に『キャラクターがいっぱい出る作品にしたほうがいい』という話もしていました。というのも、『神さまの言うとおり』はキャラクターがすごく魅力的な作品なのですが、デスゲームマンガなので、キャラがどんどん死んでしまう。そうするとキャラのファンの方も『ここまで応援してたのに死んじゃった』と悲しいですよね。皆さんに応援してただくにあたりそれはもったいないと思っていたので、次はキャラが死なずにいっぱい出てくる作品を描かれたらすごいんじゃないかな、という気持ちがありました。金城さんももっと売れてたくさんの読者に作品を届けたいというお気持ちをお持ちだったので、僕が言うまでもなくキャラは多いほうがいいと思っていたのですが。
こういう感じで、金城さんのやりたいことがどんどん頭の中でできていきました。そのとき例として出ていたのは、『カイジ』シリーズ(福本伸行)とか『帝一の國』(古屋兎丸)だったと思います。ダーティな閉鎖空間で戦わされるイメージと、金城さんが実績のあるデスゲームのイメージが混ざり合っていき、『ストライカーを作るマンガの企画を持ってきます』と言って出てきたのが、『ブルーロック』でした。1話のネームは最初からほとんどあの形で、ものすごく面白くてびっくりしました」
「売れちゃったけどモチベない」の対処法
土屋氏が手がけるヒット作は20巻を超えるロングシリーズになることも少なくない。「七つの大罪」は全41巻、「ランウェイで笑って」(
「まさに最近、そういう話を作家さんとすることがあります。どの作家さんでも連載が始まった最初のうちは、雑誌だったら『アンケート1位を取りたい』とか、『雑誌の表紙になりたい』『あのマンガより売れたい』など、数字上の目標や身近な仮想敵みたいなものを作ってそれを超えていくのが最初のモチベーションになっていることが多いと思います。そこを超えると今度は、マンガ以外の形でもどれだけのお客さんに届くだろうか?というところで、アニメ化や実写化、グッズ化なんかが目標になったり。
例えば『ブルーロック』のおふたりとはすごく具体的な話をしていて、『100円ショップに売っているような商品になれたらいいね』とか『普通に生活している人が生活の中で1日1回みかけるように露出したいね』。つまりマンガ好きだけが行く場所じゃなくて、普通に生活している中に『ブルーロック』がある状態にしたいね、と。そのためにはじゃあこれが必要だ、と考えて作戦を実行してくというか。そうやってだんだん目標を広げてくという、2段階があるような気がしています」
とても具体的な“登山計画”のようだ。問題は、次の段階。
「売れることができた作家さんって、初期に見えていたものは一度全部手の内にできてしまったあとに、何をモチベーションにするかで悩まれたり苦しまれたりすることがあるように感じます。そうなったときのモチベーションの作り方・保ち方は特にその人独自のものが出るというか。例えばお子さんがいる作家さんでは、『今はまだ赤ちゃんだけど、いつかこの子に面白いって言わせたい』と思う方や、読者とその子供の2世代にわたり『“パパと息子で読んでます”と言われたい』と思う方も。
今出したのはキレイな例ですが(笑)、『◯億円の家を建てたい』みたいなことでもいいですし、その先に何か見つけられるかというのは、ロマンや忘れてしまっていた原初的な欲望の領域なのかもしれません。2段階目まではなんとなく皆さん近しいところもある気がするんですが、その先のモチベーションは人それぞれ。それを見つけるために僕たちは雑談をするわけですが、こういう話ができる相手って作家さんのプライベートの身の回りにはきっとあんまりいないんだと思うんです。『ぶっちゃけ、売れちゃったんだけどモチベないんだよね』って、友達とかご家族にもしづらい話かなと。でもクリエイターさんにとってモチベーションってすごく大事なことなんです。大ヒットを出した作家さんというのは実力は折り紙つきで、マンガ制作においてはお手伝いできる領域が減ってくることもあります。そういう方たちのお役に立つために、そこを話し合える珍しい相手として、常にモチベーションをなくさないお手伝いができればいいなと思っています」
「贅沢な悩み」と感じるかもしれないが、苦悩は理解できる気がする。メガヒットを経験した後は、ある種の「解脱」が必要になるのかもしれない。
「いろいろ例を挙げましたが、結局最後は『子供に読んでほしい』というところに行き着く人が、少年誌作家さんには多いような気がします。とはいえ、3段階目のステージまで行ける方がほんの一握り。実際は、 1段階に行けない、2段階ができないからどうしようと悩むことがほとんどです。僕の感覚では、3段階目になると、自分のモチベーションの持っていき方を自覚している方が多くなる印象で、『こういうときはこうすればいい』という方法論を持っている方が多いように思います。ちなみに『ブルーロック』では、『今読んでいる人が、いつかプロのサッカー選手になったらいいね』と話していますね」
作家の前で必要なのは「自己開示」
ここまで土屋氏と話してきて感じたのは、例えがうまく、話しているといつの間にか会話に夢中になってしまう、率直で、魅力的な人間性を備えた編集者だということ。作家との打ち合わせではどんなことを心がけているのか、気になった。
「編集者を12、3年やってる中でいろいろ変遷はあったのですが、最終的には、作家さんと仲良くなるというか、なんでも言えるようにならないとダメだなと強く思っています。これは作家さんと友達になるという意味ではなく。順を追って説明します。
売れている要素や絵柄を分析して、『じゃあこういう要素で作って売れる絵柄で描こう』と決めても、それが全部借り物だとうまくいかない。
じゃあ何がハマったときにうまくいったり、あるいは売れなくても悔いなし!となるかというと、作家さんの中にあるものを引っ張り出せるかだと思うんです。メインテーマでもいいし、小さなこと──例えば女の人の髪の毛を描くのがめっちゃ好きな作家さんなら、それが毎話出てくるだけでもいいし、とにかく作家さんの中にあるものを出したほうがいい。となってくると、『女の人の髪の毛を描くのが好きなんですよ』って、けっこう仲良くないと言ってくれないですよね。原稿を見ていてこちらが気づいて指摘できればいいのですが、そういうある種恥ずかしいことを含めて言い合える仲にならなければいけないと思っています」
相手から本音を引き出し、素顔をさらけ出してもらうためには、「自己開示」が重要だという。
「僕から先に変な話とか自虐っぽい話、失敗談とか恥ずかしい話をしたり、普通人に言わないようなことを言うことは心がけているかもしれない。そうすると、作家さんも恥ずかしいことでも言ってくれることが多い。売れている作家さんって『自分を作品に投影させるべき』ということがわかっているので、最初から話してくれたりするんです。なので、若い作家さんとも、まずそういう話ができるようになることが大事だと思います」
まずは自分の恥部をさらけ出す。目の前の相手と実のある関係になるうえで、とても大事な話が聞けたと思う。いつまでも気を遣ってうわべの話しかしなければ、相手も永遠に同じレベルの話しか打ち返してこないだろう。土屋氏流のコミュニケーション術は覚悟がいるが、誰かと一歩踏み込んだ関係になるには有用ではないだろうか。
「担当・T屋です!」爆誕の舞台裏
さて、そんな土屋氏の、とりわけ見逃せない一面にいよいよ迫っていきたい。土屋氏は、唯一無二のアオリ文職人としても名を馳せている。「担当・T屋です!」から始まり、作品の世界観をさしおいて自身の“モテ事情”を唐突にブッ込む名&迷アオリが登場したのは、「神さまの言うとおり弐」だった。その“ウザ面白さ”は、例えばこんなふうだ。
「担当・T屋です! この間一緒に飲んだ女子大生のMさん! 見てるー!? 約束通り書いたよー! 芋だって! 今度はジャーマンポテト食べにいこうか!」
「決まった! 明石×丑三弾(ダブル・シュート)!! 私事ですが担当・T屋も初彼女獲得秒読み(カウントダウン)状態です! 来週ご報告しますね!!」→その翌週:「ついに交わる『出席者』と『欠席者』! 空前の新展開スタート!! ※今週の担当・T屋ですが、プライベートな問題で本人が精神的に強く傷ついており、業務にあたれる状態でないため、お休みをいただきます」
マガジン愛読者にはお馴染みの個性的なアオリ文は、「神さまの言うとおり弐」のほかには、XのT屋氏アカウントでも同様のキャラが味わえる。一体どんなきっかけで、「担当・T屋」キャラは誕生したのだろうか。
「『神さまの言うとおり弐』が始まる際、先輩の編集といろいろ話していく中で、『編集者がアオリでわけわかんないこと言ったら面白いんじゃないか?』という話をしてくれました。そこからスタートして、『すごくモテると言っているが、実際はまったくモテてなくて、マンガそっちのけで自分の話してるヤツ』という、ある種のキャラができてきました。というのも、『神さまの言うとおり』は、デスゲームの中ではギャグっぽいテイストがある作品で、見る人によっては『人の命や死を茶化してる』みたいな見え方をしてしまうかもしれない。そのときに、怒りの矛先をこの“担当T屋”という架空のムカつくやつに向けてもらえばいいのではと。今で言う炎上商法というか、要は作品を守りつつ、話題にもなればいいなという思惑からスタートしました。
どうすればムカつかれるかを考えていく中で、ああいうキャラを作ってそのままTwitter (現X)も始めました。『ブルーロック』でも最初はそのキャラでやっていたんですけど、デスゲームとは相性がよかったと思うのですが、スポーツものでやると本当にただムカつくだけになっちゃったというか、うまくはまらなくて(笑)」
なんと、「担当・T屋」誕生の裏側には、編集者としての切実な思いが隠れていたのだ。
「『ブルーロック』は本当に読者にムカつかれているだけのような気がしたので、誰も何も得をしていないぞと反省し、今一旦やめています。一時期、Xで作品関連の投稿をリポストしたら、『こいつが担当ならこのマンガ読まない』と言われちゃったこともあるので、ジョークに受け取れない方には本当にムカついたと思うんですよ。担当作家さんたちはむしろ笑ってくれる人たちなので面白がってくれていたのですが、このキャラのせいで作品イメージに悪い影響が出るとよくないなとか思ってXの更新もやめているうちに、3年くらい経ってしまって。
素の僕はインタビューなどをしていただく機会もほとんどありません。当時、あのキャラでラジオとかテレビへの出演依頼も頂いたのですが、お断りしました。作品を取り上げて宣伝いただけるのであればありがたいのですが、自分にフォーカスがあたるのは苦手で。編集者は基本的には表に出ていくものではないと個人的には思っていて、ほかの編集者さんがやっているのはキラキラしてカッコよく見えるのですが、自分という編集者が表に出るのはカッコわるく思えてしまって嫌ですね(笑)」
作品との相性や変遷もあって、“T屋”からの供給が安定しないのはファンにとってはさみしいところだが、少なくとも作家からの愛されっぷりは、金城が2016年に描いた読み切り「担当・T屋物語~Yahoo! TOPの載り方~」でも確認することができる(マンガアプリ・マガポケで読める)。私たちはある意味、“担当・T屋”の手の平で踊る無邪気なピエロだったのかもしれないが、「ただ、ああいう部分が僕の中にもあるのかもしれないですね」と土屋氏は笑う──そして、注目を集めた分、過激なアンチも存在したようだ。
「ほとんどの方は楽しんでくれていたと信じているんですけど、お怒りの方からは犬の糞が送られてきたり、殺害予告とかも来ましたから(笑)。いろいろありましたが、作品の役に立てば表に出ていくこともあって、T屋はその形の1つだったと思っています。お嫌いだった方は、申し訳ありませんでした」
「よい少年マンガ」とは?




















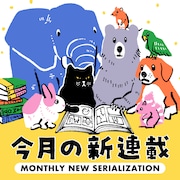

































geek@akibablog @akibablog
「ブルーロック」「炎炎ノ消防隊」の土屋萌(講談社 週刊少年マガジン編集部) | マンガ編集者の原点 Vol.20 - コミックナタリー コラム
https://t.co/8qmvz1QXiv