
アニメスタジオクロニクル No.22 [バックナンバー]
東映アニメーション 森下孝三(代表取締役会長)
創立70周年目前、生き証人が語る日本アニメのターニングポイント
2025年11月25日 15:00 19
「マジンガーZ」で会社の経営状況、業界の展開が一変
長年アニメに関わり続けるだけに、本連載における恒例の質問「御社のターニングポイントになった作品は?」に対する回答には頭をひねらせるかと予想されたが、森下氏は瞬時に、ある作品の名を挙げた。1972年に放送が始まり、ロボットアニメの金字塔として今も語られる「マジンガーZ」だ。
「ターニングポイントは完全に『マジンガーZ』です。と言っても『マジンガーZ』という作品というより、この番組でバンダイさんと組んだこと。『マジンガーZ』からはロイヤリティが、グッズが1個売れたらいくらというロット型になったんだけど、これはバンダイにも同じ考えの人がいたからできたんです。それまでは、例えば製菓会社に300万でお菓子にする権利を渡したりしていたけど、なかなか商売にならなかったし、おかげでずっと赤字だった。だけど『マジンガーZ』のやり方で経営がものすごく安定したし、その後も同様の版権商売がうまくいったんです。
あと『マジンガーZ』の何が画期的だったかって、テレビで放送されてすぐに、おもちゃ屋さんに行けばマジンガーZの超合金のおもちゃがあり、スーパーに行けばマジンガーZのお菓子があること。このスピード感はそれまで考えられなかった。アニメが当たるかどうかわからなくて、先に商品を作っておくのはリスクがあるから。
当たるかどうかわからない『マジンガーZ』で、永井豪さんとうちとバンダイさんがリスクを背負ってそういうシステムを作り上げたのはすごいと思う。今では放送されたタイミングでグッズを展開しているなんて当たり前の光景だけどね」
ライブラリーの膨大さこそ、東映アニメーションの最大の強み
東映アニメーションは、初のTVアニメである「狼少年ケン」をはじめとして、「マジンガーZ」はもちろんのこと、多くの映像作品の著作権を所有している。それを活用した版権ビジネスを最大化するのがライブラリーの豊富さだ。森下氏は、これこそが東映アニメーションにとって最大の強みだと強調する。
「東映アニメーションはテレビ作品の著作権を基本的に持っているんだよね。原作ものは原作著作というのが別枠であるけど、フィルムに関する著作権は100%保有する。だからグッズなどのライセンスビジネスや海外展開なども全部自社でやれて、ビジネスとして成り立っている。
例えば『一休さん』なんて7年間で350本ぐらい作ったけど、1社提供で製作費はすごく安かったから、作れば作るほど赤字だったの。でも最近、中国などですごい人気になって、製作費はほぼ回収できちゃった。そんなふうに今までの作品の90%は製作費を回収してるんじゃないかな。だから、もし作った時点でビジネス的に失敗しても、ライブラリーという資産を増やすことにつながっていればいいんです。
しかもうちは年間約50話の作品を5ラインで作っているから、1年で約250話分作る。これだけ資本を投下して、膨大なライブラリーを蓄積できていると言えるのは、うちと日本アニメーションとサンライズくらいじゃないですか。そういう大きな屋台骨があるのはすごくいいこと。そのおかげでチャレンジができる。入社してからずっと『ドラゴンボール』だけ描いています、あるいは『プリキュア』だけ演出していますという人が、『違う作品をやってみたい』と思ったときにも、別のチャンスを与えられるんです。そのチャレンジこそ社員のモチベーションになる。もちろんそうしてできた作品が確実に儲かるわけではないから、ビジネスとして考えるとリスキーではある。でもそういった作品だってライブラリーの1つにはなる」
過去のライブラリーという資産を活かした余裕があるためか、同社は今では当たり前となっている海外展開やデジタル技術の導入を早くから行っていた。後者に関しては1980年3月と、45年以上前にコンピューターによるアニメ製作の本格的な研究を開始したという。
「当社に研究開発室ができた頃は大型コンピューターしかない時代だから、机上の話が中心だったようだけど、そのうちゲーム開発なんかにも手を出していったんだよね。『北斗の拳』とかアニメを原作としたものを10本出してすごく売れたけど、オリジナルIPを出したらコケちゃったね(笑)。90年代からコンピューターの性能が上がったこともあり、アニメ製作のデジタル化が進み、『狼少年ケン』を白黒からカラーにする実験映像を製作したよ。コンピューターで1コマずつ色を塗ってカラーになったことはなったけど、ものすごい金がかかった(笑)。でも、それが研究でしょ。今だとAIとかも同じように研究しているけど。」
どんな作品にもある“面白い”部分を活かした展開を
「失敗した作品もライブラリーの1つにはなる」と語る森下氏にも、悔いが残る作品があるという。ジョージ秋山によるマンガを原作として、2012年にフルCGでアニメ化した映画「アシュラ」だ。同作に森下氏は企画・監修のほか絵コンテとしても参加していた。
「『アシュラ』は実はすごい低コストで作っててさ。それでもクオリティは高くて技術面を評価されて賞こそもらったけど(編集部注:第16回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞を受賞)、興行的にはコケてしまって。でも長い目で見れば、1作で終わりにするんじゃなくて何本か続けていけるようなIPとして扱わなきゃいけなかった。オリジナル作品でも、1作で終えちゃうと何億円って製作費をドブに捨てることになっちゃう。だから『2』『3』と続けて、そのうち火が付くよう展開しなきゃいけなかったということもあるよね。
1本作ってダメだったからといってやめちゃうのはもったいない。企画する人も作る人も、『面白くないものにしよう』なんて思ってる人はいないんだから、どこかしら面白いはずなんだよ。それでも失敗するのは宣伝が悪いのか、時代に合わないのか……ダメだったらなぜダメだったかを分析して、次はその作品のいいところを活かしながら展開していかなきゃ。東映アニメーションにはそういう会社であってほしいよ」
東映アニメーションは2026年に創立70周年を迎える。日本初の本格的なアニメ製作会社であり、今もトップとして走り続ける自社に、森下氏はどんな思いを抱いているだろうか。
「外から見るとうちは『ドラゴンボール』に『ONE PIECE』、『美少女戦士セーラームーン』や『プリキュア』とメジャーなものばかりやっているように見えるかもしれない。でもそうではないマイナーな作品や、コツコツと進めているものもあるんだよ。
例えば『THE FIRST SLAM DUNK』だって公開までにかなりの年数かかったんだから。『アニメ化は絶対やらない』という原作の井上雄彦先生に『やる』と言ってもらえるために、社内で作った企画を何本も没にして、パイロットフィルムをお見せして、ようやく『CGでここまでできるなら』と許可をいただいた。そんなふうに、今後もいろんなことに挑戦していく会社であってほしいね」
森下孝三(モリシタコウゾウ)
1948年7月17日生まれ、静岡県出身。1970年に東映動画(現・東映アニメーション)に入社し、演出助手を経て「キューティーハニー」「ゲッターロボ」などの演出を手がける。「聖闘士星矢」でシリーズディレクターを務め、製作途中に企画部へ異動、プロデューサーへ転身。その後「ドラゴンボール」シリーズのプロデューサーとして活躍した。2011年には「手塚治虫のブッダ-赤い砂漠よ!美しく-」で監督を務める。2022年に東映アニメーション代表取締役会長に就任。
バックナンバー
フォローして最新ニュースを受け取る



















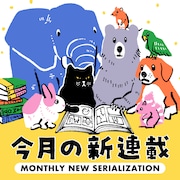
































geek@akibablog @akibablog
東映アニメーション 森下孝三(代表取締役会長) | アニメスタジオクロニクル No.22 - コミックナタリー コラム
https://t.co/3wzOAkLMo6