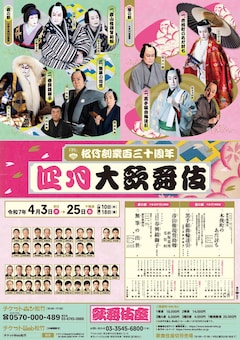生きてきた境遇がバラバラの人たちが“芝居でつながる”
──劇作者の篠田金治(幸四郎)、女方の芳澤ほたる(中村壱太郎)、小道具方の職人である久蔵(坂東彌十郎)とその女房与根(中村雀右衛門)……芝居を作る裏方たちも登場する物語は“バックステージもの”としての楽しさもあります。毎日裏方の皆様と接している役者さんたちにとっては、身近にいいモデルがいっぱいですね。
染五郎 稽古場でもまさに、齋藤先生が「ほら○○さん(裏方スタッフの名前)なんかがこういう口調で言うでしょ」「あ~言う、言う」なんて会話も(笑)。現在はSNSなどがあって人と直接会わなくてもつながることができますが、芝居小屋のいろいろな人と会って、対話して、影響を受けて成長していく菊之助の姿にはシンパシーを感じます。先生は今作での人間関係や世界観を、どう形作っていかれたのですか?
永井 大体の役割については、最後の仇討のシーンにどんな人物が関わるかを決めて、そこから逆算して考えていきました。あと、芝居小屋の中で展開する話ではありますが、その外側にどういった世界が広がっていたのか、江戸時代の社会的な問題や時代背景が多角的に見えるようにしたかったんです。貧富の差など「格差」からくる生きづらさは、現代にも通じるものがありますよね。読者の方にいろいろな楽しみ方をしていただけるようにもしたかったんです。
染五郎 確かに、キャラクターが置かれている状況はそれぞれ全く違いますね。齋藤先生も会見で「芝居小屋に生きる人たちのリアリティと緊張感がこの芝居を上演するうえで必要不可欠」とおっしゃっていました。
永井 江戸時代、武士は恵まれているように見えますが、そこに生まれた菊之助は、侍の世界だからこその生きづらさを抱えている。じゃあ町人だったら苦労がないのかというと決してそんなことはない。そんな彼らの共通点は、芝居に関わることによって昇華された経験を持っていることなんですね。私自身も気分が沈んだときにお芝居を観ると「明日もがんばろう」と思えますから、そこは実感を持って描けました。
染五郎 生きてきた境遇がバラバラの人たちが“芝居でつながる”のは、役者である自分にとってもグッとくるものがあります。
永井 彼らが“芝居でつながる”ためには、彼らが物語の構造に沿った役割を担うと同時に、生き生きと動いていなければならない。つまり書き手にとって“想定外”が起きないと面白くないんです。なので各人物の細かいプロフィールについては書き始めるまで決めずにいたんですね。時代背景の資料を頭に入れ、登場人物を決めたあとは、「さあ、この人はどうしゃべるかな」という状態で執筆をスタートしました。人物の前にICレコーダーをポンと置いて、おりてきた言葉を書き留めていく感覚ですね。
染五郎 言葉がおりてくる……すごいですね。
永井 例えば今回彌十郎さんが演じてくださる久蔵さんは、マイクを向けても無口であまりにもしゃべらなくて、かなり困ってしまって(笑)。それで最終的には、しゃべるのが女房になってしまいました。「そんなの自分の裁量で勝手にしゃべらせちゃえばいいじゃない」という話なのですが、「いいセリフを書いてやろう」と思って書いたときよりも、「こんなことを言う人なんだ」と発見しながら書いたほうが、最終的に「あのセリフ、すごく良かったね」と言っていただくことが多いんです。
──染五郎さんは演技をしていて「役がおりてきた」ご経験はありますか?
染五郎 舞台はセリフや動きの段取りを考えながら動くので、100%その人物になることは不可能だと思うんです。でも昨年、江戸川乱歩「江戸宵闇妖鉤爪」(2024年2月、博多座)で人間豹・恩田乱学をやったときは、自分が自分じゃなくなったような、わっと自分の中に役が入ってくるような瞬間があって驚きました。あの感覚をうまく言葉では説明できないのですが、1カ月の公演中に数回体験しました。
“白と赤のコントラスト”を舞台でも表現
──忠義を背景にした“仇討”を現代人にも腑に落ちるものとして描くのは大変な作業だったと思うのですが、この物語にはスッと受け入れられる“趣向”が用意されています。
永井 どういうラストだったら、仇討の醍醐味も残しながらスッキリするものになるだろう……?を考えていきました。約20年前、野田秀樹さんが歌舞伎「研辰の討たれ」を野田版として新たな視点で作った舞台を拝見したときに、「ああ野田さんは仇討を現代に描くことについて、深く考えられたんだな」と感じたんですね。あの印象的なラストシーンは、頭の中にずっと残っていました。
──ひとひらの紅葉が、討たれた研辰の胸に吸い込まれるように散る場面ですね。「木挽町のあだ討ち」の仇討場面も印象的です。
永井 ありがとうございます。あの場面では読者の方の頭に、赤と白のコントラスト、鮮やかな色彩が浮かぶようにしたかったんです。今作で直木賞を受賞した際、伊集院静さんから「華があるのがいいね。小説には華が大事だよ」とおっしゃっていただいたのもうれしい出来事でした。それにしても今回の染五郎さんの宣伝ビジュアルやティザー動画、もうもう素晴らしいですよね! まさしく私が見たかった、表現したかった仇討の世界観で、思わずSNSでもシェアしまくってしまいました(笑)。原作者という立場を忘れた“推し活”です!
染五郎 原作者の方にそう言っていただけると、ホッとします(笑)。白と赤のコントラストは自分の中でもこの作品のカラーだと考えています。仇討のシーンは雪が降り積もる冬の設定ですが、当初は転換の都合で白い布は敷けないことになっていたんですね。でもどうしても真っ白い雪景色の中で仇討を果たすという画がやりたくて、わがままを通させてもらいました。現代の方にとって“仇討”は、なかなか受け入れ難い部分があるかもしれませんが、その奥にある人間ドラマ、人と人が出会うことで動く感情を感じていただけたらうれしいです。劇中の道具幕には題字も書かせていただきましたので、そちらにもご注目ください。
──染五郎さんの思いがいっぱい詰まった舞台、目にするのが楽しみです。最後に、お二人が思う“フィクションの力”について伺えればと思います。
永井 どんな方でも日々いろいろな悩みがおありになりますよね。そういうときに、違う世界、違う時代、フィクションに触れることで、悩みのループからストンと抜けられることがあると思うんです。私自身も悩みごとがあるときに、劇場に足を運んだり、本を読むことで突破口を発見してきました。ぜひ歌舞伎座に来ていただいて、そして小説を読んでいただいて、思いっきり楽しんでいただければと思います。
染五郎 歌舞伎版「木挽町のあだ討ち」は、菊之助の目線で展開していく構成になっています。いろいろな人とつながっていく物語は、思わぬところにあった“居場所”の物語でもあります。どうぞ菊之助と一緒に登場人物1人ひとりに出会い、この温かさに触れて、改めて「芝居っていいな」と感じていただけたらうれしいです。
プロフィール
市川染五郎(イチカワソメゴロウ)
2005年、東京都生まれ。松本幸四郎の長男、祖父は松本白鸚。2007年に歌舞伎座「侠客春雨傘」にて初お目見得。2009年「門出祝寿連獅子」にて四代目松本金太郎を名乗り初舞台。2018年に高麗屋三代襲名披露公演「壽 初春大歌舞伎」にて八代目市川染五郎を襲名。
市川染五郎 (@somegoro_official) | Instagram
永井紗耶子(ナガイサヤコ)
1977年、神奈川県出身。小説家。慶應義塾大学卒。2010年に「絡繰り心中」が小学館文庫小説賞を受賞しデビュー。2023年に「木挽町のあだ討ち」で第169回直木三十五賞と第36回山本周五郎賞を受賞。4月22日に「女人入眼」の文庫版が中公文庫から発売される。
「歌舞伎座で会いましょう」特集
![“観劇はじめ”は歌舞伎座で! 坂東巳之助&中村米吉、尾上右近&中村壱太郎、中村隼人が語る「壽 初春大歌舞伎」]()
- “観劇はじめ”は歌舞伎座で! 坂東巳之助&中村米吉、尾上右近&中村壱太郎、中村隼人が語る「壽 初春大歌舞伎」
![父・中村勘三郎が“蔦重”演じた「きらら浮世伝」中村勘九郎&中村七之助がエネルギッシュに立ち上げる!2月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 父・中村勘三郎が“蔦重”演じた「きらら浮世伝」中村勘九郎&中村七之助がエネルギッシュに立ち上げる!2月は歌舞伎座で会いましょう
![「仮名手本忠臣蔵」の通し上演が開幕!泉岳寺駅近辺の「忠臣蔵」ゆかりツアー 3月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 「仮名手本忠臣蔵」の通し上演が開幕!泉岳寺駅近辺の「忠臣蔵」ゆかりツアー 3月は歌舞伎座で会いましょう
![襲名興行にはスペシャルがいっぱい!八代目尾上菊五郎、六代目尾上菊之助の誕生を見届けに、5月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 襲名興行にはスペシャルがいっぱい!八代目尾上菊五郎、六代目尾上菊之助の誕生を見届けに、5月は歌舞伎座で会いましょう
![八代目尾上菊五郎と六代目尾上菊之助が語る「襲名とは先人達の技や想いを受け継ぎ発展させること」6月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 八代目尾上菊五郎と六代目尾上菊之助が語る「襲名とは先人達の技や想いを受け継ぎ発展させること」6月は歌舞伎座で会いましょう
![市川染五郎と市川團子が「興味を広げてもらえる夏にしたい」と意気込む、7月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 市川染五郎と市川團子が「興味を広げてもらえる夏にしたい」と意気込む、7月は歌舞伎座で会いましょう
![“勘三郎の色”が染み付いた作品に新たな息を吹き込む、野田秀樹×中村勘九郎「野田版 研辰の討たれ」8月は歌舞伎座で会いましょう]()
- “勘三郎の色”が染み付いた作品に新たな息を吹き込む、野田秀樹×中村勘九郎「野田版 研辰の討たれ」8月は歌舞伎座で会いましょう
![自然体で菅丞相として“在る”片岡仁左衛門「菅原伝授手習鑑」 Wキャストの松本幸四郎が語る役への思い 9月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 自然体で菅丞相として“在る”片岡仁左衛門「菅原伝授手習鑑」 Wキャストの松本幸四郎が語る役への思い 9月は歌舞伎座で会いましょう
![坂東巳之助・尾上右近・中村隼人・市川團子が魅せる「義経千本桜」10月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 坂東巳之助・尾上右近・中村隼人・市川團子が魅せる「義経千本桜」10月は歌舞伎座で会いましょう
![三谷幸喜と松本幸四郎が強い信頼関係で生み出す三谷かぶき「歌舞伎絶対続魂(ショウ・マスト・ゴー・オン) 幕を閉めるな」11月は歌舞伎座で会いましょう]()
- 三谷幸喜と松本幸四郎が強い信頼関係で生み出す三谷かぶき「歌舞伎絶対続魂(ショウ・マスト・ゴー・オン) 幕を閉めるな」11月は歌舞伎座で会いましょう
![祝10周年!中村獅童が前人未到の道を進み続けた「超歌舞伎」の“軌跡と未来”を語る]()
- 祝10周年!中村獅童が前人未到の道を進み続けた「超歌舞伎」の“軌跡と未来”を語る