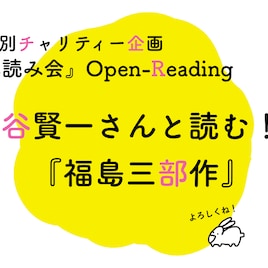演劇に関する残念な誤解がある。観客が作品を評価する際の「感情を揺さぶられた」、同様の意味で、つくり手の「観る人の心に何かを届けたい」。つまり、感情、心、あるいは熱量ばかりが評価の基準にされている。映画や本の宣伝も「○回泣いた」「感動して元気をもらった」が常套句になっているのは周知の通りで、演劇に限った話ではないが、いずれにしても弊害は大きい。泣いたり笑ったりすれば生理的なカタルシスが得られ、すっきりして観劇体験は終わる。けれども本当に良い作品は例外なく、感情と思考の両方を刺激する。心の揺れが治まってからも知のフィールドの振動は続き、劇場の外の広い世界、遠い過去や未来にも思考を及ぼす。それは、フィクションである演劇を現実に対して有効なものにする力にほかならない。
DULL-COLORED POP(ダルカラ)が、2011年に起きた東日本大震災と福島第一原発事故をモチーフに三部作を準備していると知ったとき、正直に書くと、私は良い印象を持たなかった。まず三部作というのが引っかかった。用意した長い時間を、被災者の声の丁寧な反映に充てれば“感動もの”に、起きたことを緻密に描くのに費やせば“取材をがんばったで賞”になる可能性が高いと懸念したのだ。
それだけではない。ダルカラ主宰の谷賢一は、もともと決まった色を持たない作・演出家で、著名人の半生、日本の家族、シェイクスピア劇、現代の海外戯曲と目まぐるしく題材を変え、演出のスタイルも固定していない。そのこと自体は良いが、いまだ2500人を超す行方不明者がいる現在進行形の災害を、次々と変わる興味の対象の1つとしてピックアップしたとしたら、災禍と被災者の消費につながらないか。時間をかけた取材はむしろ、「本当に起きたことだから批判できない」という空気を生みはしないか。いくつもの懸念から、2018年に先行して上演された第一部には足を運ばなかった。
けれども2019年の三部作一挙上演を観て、前述の不安は完全に杞憂だったことを知る。上演されていたのはカタストロフィの記録ではなかった。経済的な発展から取り残された地方都市が、中央のロジックに巻き込まれ、満身創痍になりながらも自分たちの存在意義を探し続ける土地の物語であり、ノーと言えない気の弱さと奇妙に強い責任感という矛盾を故郷に対して発揮する人間の物語だった。おそらく谷の興味は、地震と原発事故に見舞われた福島ではなく、なぜ福島で原発事故が起きなければならなかったのかにあった。それを取材するうちに、50年という時間の描写がどうしても必要で、三部作が必然だと思い至ったのだろう。興味の赴くままに1作ごと、自由にステップを踏んでいた演劇作家は、この作品でじっくりと、特定の町、そこに暮らす人々、中でも1つの家庭に焦点を絞って向き合うことに決めたのだろう。
この作品が演劇として非常に興味深いのは、過去の谷作品、また一般的な演劇作品でも圧倒的多数を占める、たとえ苦悩しながらも主体的に生きる人の話ではなく、やってくる事態に対してひたすら受け身の人々を主軸にしている点だ。その受け身ぶりは犬さえも理不尽に感じるレベルであることは第二部に詳しいが、ともかくこの三部作は、被災者ではなく受難者の物語なのである。
その点で、1961年から2011年までの日本の福島県の双葉町で実際に起きたことがベースではあっても、普遍的なドラマを内包し、ほかの土地でもシンパシーを生み得る柔軟性を持つ。中央政府と少数民族、宗派によって多数派と少数派に分かれる地域など、「福島三部作」の構図を置き換えられる場所は世界に少なくないからだ。日本と世界を結ぶ舞台芸術のプラットフォームである「TPAM」で、このローカル色豊かな作品が上演されるのは、日本が経験した稀有な災禍のディテールを演劇にした作品の紹介というより、その意義が圧倒的に大きい。
また、1961年を起点とする第一部、1986年を起点とする第二部、2011年を起点とする第三部それぞれで、当時の日本で流行していた小劇場の演出をはじめ、人形劇など演劇のバラエティが取り入れられている。これは、スタイルを決めず、さまざまな演出方法に取り組んできた谷だからできたことだ。1つのトピックを複数の作品で追いかけるとき、とりわけそれが社会的なら、普通は重厚なトーンに陥りがちだが、ところどころで顔を出す遊び心は、笑いだけでなく問題を俯瞰する眼差しを与えてくれる。加えて、それぞれの時代にメインだったメディアの変遷が巧みに織り込んであるのも見落としてほしくない。
それと関係するが、「福島三部作」は喜劇の要素も含んでいることも書いておきたい。原発は、政治と経済と科学の利権が複雑に絡み合う。そして政治も経済も科学も結局は人間の欲望だ。先に、これは巻き込まれる人々の話だと書いたが、双葉町の人々は言ってみれば、望んでもいないのに政治と経済と科学の正体を見せられ、相手から勝手に「見たからには仲間だ」とされてしまう。そこで起きる肩を抱かれた側の困惑と恍惚、そこからの変化は、人間の喜劇性の本質に通じると思う。
近年は、「TPAM」に限らず全世界的に、海外ツアーを意識した作品はコンパクト化、省エネ化が進んでおり、それに伴って上演時間も短いものが増えている。パンデミック下にあってその傾向はますます強まると予想されるが、同時に今こそ、人間の営みについて考えることが必要とされている。その土台にある政治と経済と科学のこれまでのやり方のほころびを指摘し、環境問題の大きな問いかけを含むこの作品が、三部作のまま広く紹介されることを願う。