「PLEASE PLEASE ME」で第34回ぴあフィルムフェスティバルの日本ペンクラブ賞を受賞し、上映会「発光ヶ所」にも携わった
「Lilypop」は、青石が授業を行う武蔵野美術大学で出会った美大生から着想を得て製作したもの。主人公は、美大で写真を専攻しているが、撮りたい被写体が見つからないりりかだ。授業では昔に撮った同居人エナの写真を提出するも、エナは心の調子を崩して部屋に引きこもっており、りりかとエナはかつての親密さを失いつつあった。そんなある日、りりかは街を歩くエナの“分身”と出会い、彼女に誘われて夜の街に繰り出す。そしてりりかは新たな出会いと別れの中で、見失った愛を探しに行くのだった。
出演に名を連ねたのは、鈴木理利子、渡邉龍平、松下絵真、秋田海風、大田晃。iPhoneのみで制作されており、キャストが実際に暮らしていた家を舞台に美大生の実態、コロナ禍の生活環境、早朝から深夜にかけての郊外の町の様子がホームビデオのように捉えられた。あわせて6種のチラシビジュアルも解禁されている。
青石は「豊かな共生を可能にするものを愛だとした時、伴う排他性とどう向き合うか、映画は主人公の『ポップ』という価値の感覚を頼りに探求します」と語った。加えて映画研究者・
青石太郎 コメント
この映画は前の映画制作を手伝ってくれた3人の美大生から着想しました。彼女らの強く独特な親密さに私は驚かされたのですが、どういう関係性なのかうまく言葉にできず、ただその交流の様子が豊かなイメージで浮かび上がるばかりだったので、映画として捉えたいと思っていました。しかし、楽しそうに見えた彼女らの実生活には自分が想像できない厳しさもあり、コロナ禍の混乱も相まって生活は乱され、私がようやく腰を上げた時にはもう3人の親密さはかつてと形を変え、消えつつありました。この映画は撮り逃したところから始まっています。現在の彼女達から撮るべき新たな物語を探しつつも、この撮影でかつての関係が取り戻されてほしいとも思ってしまい、過去/未来/現実/物語がその接続の危険性において緊張関係にありました。イメージはこれら4つの層で実感を持って現れ、時に撮ることの次元で生まれる楽しさや困難が撮られるべき物語の感情と交錯し、皆で正体のわからない時間を過ごしました。この撮影はそれらをそれはそういうものだとして見ていくこと、この正体のわからなさを現在の被写体間の固有のリアリティとして改めて映画として眼差すことであり、物語と共にその謎へ巻き込まれながらの、人と人が時空間を共にすることの喜びと困難の記録でありました。豊かな共生を可能にするものを愛だとした時、伴う排他性とどう向き合うか、映画は主人公の「ポップ」という価値の感覚を頼りに探求します。
新谷和輝(映画研究者)コメント
「関係性の幽霊」
冬の夜道を二、三人がぽつぽつ喋りながら歩いている。「Lilypop」を見た私のなかには、この時間がとくに滲んでいる。これまでに見てきた青石さんの映画でも、人々が歩く長い時間が印象的だったけれど、寒い夜をさまようこの映画の人々はとくにいい。実際に大学の同級生である彼女らが歩きながら交わす会話には、一般的な映画のつくり方からは浮かんでこない微温の親密さが感じられるとともに、その温かさが冷めていく、またはすでに冷めてしまったかもしれない寂しさも漂っている。
りりかが制作している写真集のタイトルは「Love&Pop」というらしい。写真のスタイルや人間関係において、りりかは重くて力(Power)を伴うLoveと、より自由で身軽なPopを両立させようとしている。けれど指導教員が「Loveに対して、Popは軽さでごまかそうとしている。だからPopとは逆の、他の人が目を背けるとことんパーソナルなものに向かうべきでは?」と言うように、周囲の人々はなんとなくLoveのほうを期待している。同居しているえなや、告白してきたみつるとすれちがっているのは、彼らがLoveをもとに関係を明確にしたいからだろう。りりかはそれに控えめに抵抗する。LoveでもPopでもある未分化な関係、愛おしいと思えるいまここの関係を引き延ばそうとする。けれど、そうした淡い時間が過ぎ去る予感はずっとある。
鏡やデジカメ、そして映画という複製装置がたびたび出てくるのは、時が経てば消えていく自分たちの関係を映し、複製し、保存しようとするりりかたちの欲望のあらわれだろうか。風呂に入ったり、怒ったりしているプライベートのえなを強引に写そうとするりりかにも、告白の代わりに映画を用いようとするみつるにも、どこかうしろめたさがつきまとう。彼らは自分たちの願望のために映像に頼ろうとしている。そのうしろめたさは、現実の人間関係をもとに本人たちに演じさせるこの映画が持っている一種の危うさにつながる。えなのドッペルゲンガーは、えなとの生活に対するりりかの願いが具現化したものだと思うが、この映画自体が現実の人間関係のドッペルゲンガーになろうとしている気がする。本人が自分のドッペルゲンガーに出会うと死んでしまうといわれているけれど、ドッペルゲンガーを探しに行く際にえなが「殺し合いや」と言うように、途中からどっちのえなが本体がわからなくなるように、この映画は現実と虚構をかぎりなく重ね合わせることで、両者を曖昧にする。
アフレコによる浮遊した音声がずっと気になる。もう過去のものになった映像に、違う時空にいる登場人物たちが声をあてているようで、彼らの存在はどこが現実離れしている。作中でたびたび霊感があるかないかという会話がされるが、彼らこそ幽霊のように不確かだ。この映画がずっと映していたのは、かつての関係性の幽霊たちのように思えてくる。りりかが終盤に写真をめくるとき、どの光景もついさっき見ていたはずなのにずっと遠くに行ってしまったようで、それでもその時その場所その関係が、過去も現在も、重さも軽さも、LoveもPopも区別をつけず、こちらに迫ってくる。いまここで私だけに見えているはずのものが、いつかどこかの誰かの前にふと蘇る、そんな幽霊的現前をこの映画は夢見る。りりかが夜道を歩いているときに不意に光るシャッターは、一体誰が炊いたのだろう。「Lilypop」は、人と人が寄り集まるときに生まれる言葉にできない関係を、その関係を再び映そうと願う映画の可能性を、暗い道をさまよいながら探している。
七里圭(映画監督)コメント
青石くんの映画にはいつも感心する。どこか微笑ましく思い、少し物悲しく感じる。
彼が撮るのは身近にいる美大生で、手軽な機材であるiPhoneを主に使う。まさにそんな映像の組み立てが、見事に映画になる。そして、不思議な厳格さをたたえている。深遠さ、と言ってもいいのかもしれない。大袈裟だが、名人芸だなと思う。
彼の映画には音楽が流れない、音楽に流されない。登場する人々の声は、アフレコという手法で、もう一度演じ直される。だからなのだろうか、近しい被写体であるのに親密さに頼らず、距離を置き、遠くから見ているように感じる。でも、突き放しているとか、冷徹に観察するということでもなく(いや、少しそういう部分もないわけではないのだが)、離れてそわそわしているような、近づくのを留まっているという感じだ。そう感じるのは、間にあるiPhoneのレンズがとても小さいからなのかもしれない。
映像はずいぶん前からデジタルで記録/再生・表現されるのが当たり前になり、巷にあふれて現実を侵食している。その一因が、スマホという便利なツールにあるのは疑いようもないが、例え高級機材を使って大掛かりな制作をしても、環境の変容は本質的に免れ得ない。それでも映画は、今もかつての形式を保とうと、旧来の制度に寄りかかっている。そのいびつさに僕は違和感があり、何もかもデータに置き換えられていく世界にも、そもそも馴染めず逡巡している。だから、青石くんは果敢だなと思う。
そのレンズは、彼と被写体を隔てるにはいささか小さい。しかし、レンズを介して世界と向き合うことは確かであり、その約束を律義に守って、彼は生真面目に見つめる。いや、あるいは見つめずに、生真面目にそこに居るのかもしれない。いずれにせよ、ミニマムな映画作りを従来のやり方に落とし込むのでなく、対人関係の手段として組み立て直す模索をしてきたのだと思う。その過程では、必ずしもいつも上手くやれたとは限らないはず。iPhoneの向こう側もこちら側も、多少なりとも辛酸を舐めて来ただろう。それでも青石くんは、近しい者たちのふる舞いや、さ迷いを描くことで、その中に希望のようなものを見出そうとしている。ひたむきだと思う。
現在の先には確実に未来が在り、それは過去から続いている。そんな直線的なイメージは、もう一概には信じられなくなった。データ化された世界はあまりに不確かで、酷薄で、ひょっとして唐突に分身が現れてしまうかもしれない。そんな日常を仮構しながら、青石くんはいつも若い人たちに目を向ける。そして、過ぎ去ったことや得られなかった何かへの思いをそこに潜ませる。彼はきっと現在の、その先に続くものを信じているような気がする。それが直線ではなくとも。そんな青石くんの映画は、ちょっと切なくて、僕は好きだ。




















































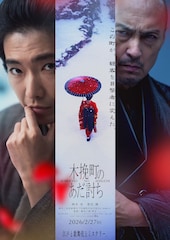




















奥山ばらば Barabbas Okuyama @BarabbasART
ひょんな現場で繋がってからどれくらい経つでしょう。
不思議な繋がりの 青石くん には、公演のスタッフに入ってもらったり、公演の宣伝写真を撮ってもらったりと色々お世話になりました。
#青石太郎 くん、映像製作のお仕事で様々活動を重ねてらっしゃいます。 https://t.co/yuFwpUTPZy