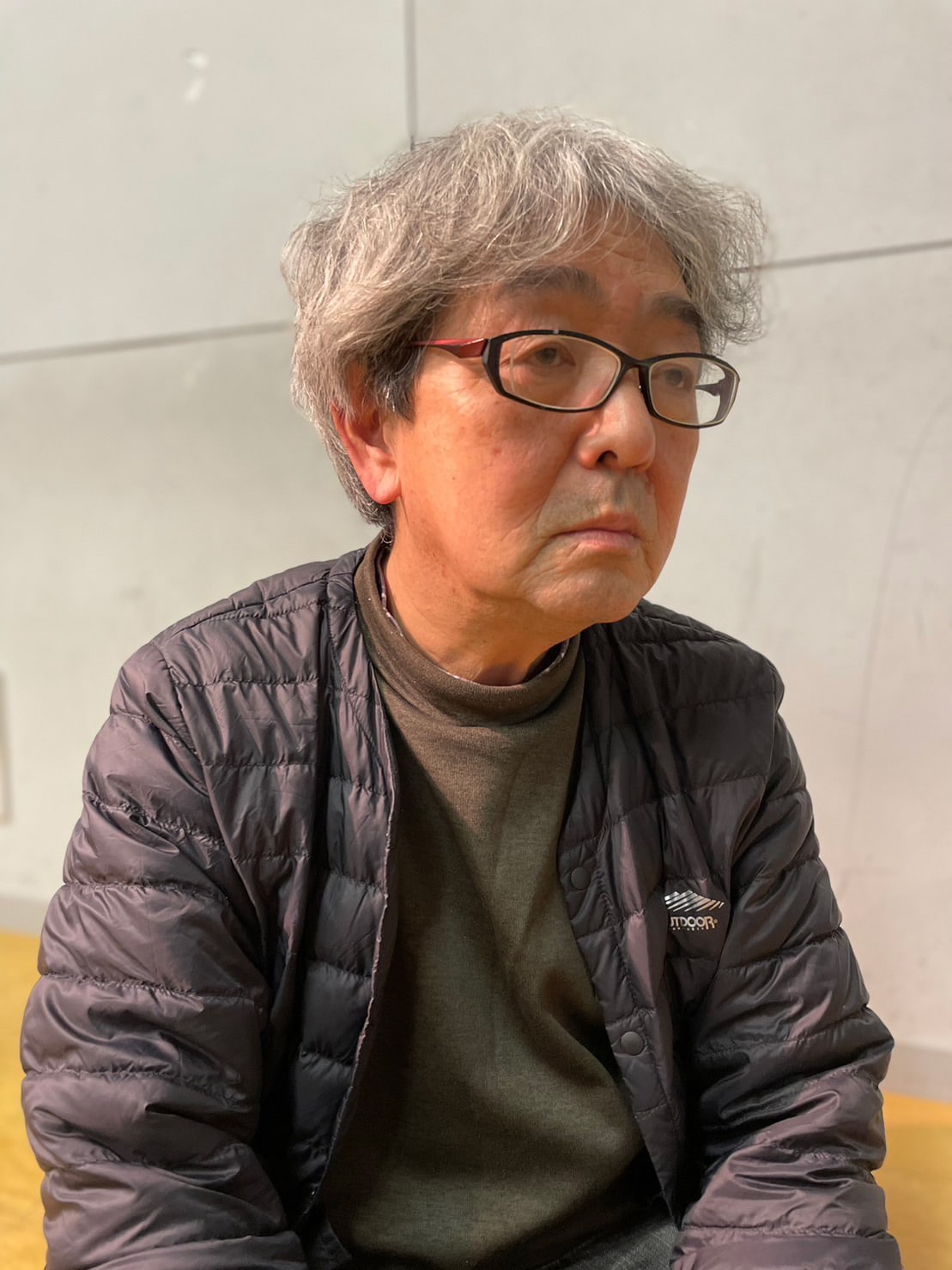三重県文化会館は、首都圏で人気の劇団から、近畿・東海を拠点とする近隣の注目劇団まで、舞台ファンの心を掴む幅広いラインナップが魅力の劇場だ。三重県文化会館が、観客はもちろん、舞台人にも広く愛される理由は、副館長・松浦茂之をはじめとする三重県文化会館のスタッフたちが、劇団とのつながりや発想力・機動力を大事に、劇団と丁寧に関係を作り上げてきたから。
座談会に集まった3劇団も、それぞれに三重県文化会館とのつながりが深い。創立40周年&ファイナルツアーを掲げる劇団ジャブジャブサーキットのはせひろいち、今回は戯曲講座の教え子で注目の劇作家・河合穂高の作品を演出する下鴨車窓の田辺剛、今年読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞した「養生」の再構築に挑む、「ミエ・ユース演劇ラボ」出身のゆうめい・池田亮が、松浦の司会進行のもと、劇場との思い出を振り返りつつ、今作への思いを語った。
取材・文 / 熊井玲
それぞれの三重県文化会館との接点
──三重県文化会館では毎年、旬の演劇作品が観られるラインナップを考えられています。2025年は4月に世界劇団、5月に三重・宮崎・島根を巡る縁結び旅「この物語」、8月にチェルフィッチュ「宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓」が上演され、この後も話題作が続きます。今回はその中から、劇団ジャブジャブサーキットのはせひろいちさん、下鴨車窓の田辺剛さん、ゆうめいの池田亮さんにお集まりいただきました。まずは三重県文化会館副館長の松浦茂之さんに、3劇団を選出された思いを伺います。
松浦茂之 はい。ジャブジャブサーキットは私のほうから仕掛けたといいますか(笑)。コロナ禍でだいぶ演劇界全体が弱っていた頃、ジャブジャブサーキットの活動が気になって、ときどき観に行っていたんですね。その頃割と小さめな作品をやられていたんですが、はせさんに「もう1回、フルメンバーでフルサイズの、ちゃんと美術を立てた作品をやりませんか」とご提案したところ、はせさんが「やりましょうやりましょう」とおっしゃって。それで今回、ジャブジャブサーキットのフルスケールの作品をオファーしました。そうしたらサブタイトルに「ファイナルツアー」と付いてびっくりしたんですが……。
田辺さんは、三重県と本当につながりが長くて、三重文が演劇事業をやる前、「C.T.T.(編集注:公共ホールと民間劇場による、シンポジウムを絡めた連動企画)」にうちが会場提供したことがあり、“京都の偉い先生”としていらっしゃいまして(笑)。以降、田辺さんは三重の演劇を気に留めてくださるようになりました。で、津あけぼの座とうちと頻繁に公演をやっていただくようになり、戯曲講座の講師も長年やっていただきました。現代の日本のことを書く現代作家が多い中で、田辺さんは時代性や地域性を超えた普遍的な作品世界が特徴で、貴重だなと思っています。今回は河合穂高さんの作品を田辺さんが演出するということで、本当だったら私は田辺さんの戯曲をやりたいのですが、田辺さんからオファーが来たらもう断れない構造になっておりますので(笑)、それでお受けしたという次第です。
池田さんは「ミエ・ユース演劇ラボ」(編集注:高校生以上25歳以下を対象に、三重で新しい演劇の創り手となる人材発掘を目指す期間限定の擬似劇団活動を行っていた事業)出身で、だからかわいいということもあるんですけれども(笑)、感心しているのは今、彼らの世代で全国ツアーをやる劇団がほとんどいないところ、彼らは今回、京都・三重・福島・北海道・高知・神奈川をツアーするんですね。そのことに尊敬の念を感じて、池田さんからオファーがあればぜひやりたい、と思っていました。
──ありがとうございます。ここからは松浦さんに司会をお願いして皆さんのお話を伺っていきます。
松浦 では皆さん、まずは三重県文化会館とのエピソード的なものがあれば、お話いただけますか?
はせひろいち うちは、三重文さんでは3回ぐらいやりましたっけ?
松浦 2010年から2012年のトリプル3演劇ワリカンネットワーク(編集注:2010年から2012年の3年にわたり、東海・関西エリアの3つの劇団と3つの公共ホールが取り組んだプロジェクト。劇団ジャブジャブサーキット、南河内万歳一座、劇団太陽族が参加し、三重県文化会館、愛知の長久手市文化の家、大阪のすばるホールで行われた)に参加いただき、劇団30周年公演の「非常怪談2014」も三重で上演してくださいましたよね。
はせ ああ、そうでしたね。以前から新作を上演するときは東京、大阪、名古屋でツアーをするスタイルでずっとやってきて今年が40周年なのですが、松浦さんに言っていただいた通り、徐々に公演のやり方が変わってきて、助成金をもらうには毎年新作を作らなければいけないんだけど、そのことがちょっとキツイなと思っていました。その時期にコロナが始まって、それを機に公演回数を減らしたり、大阪だけで単発の旅公演をしたり、プロデュース公演をやってみたりしました。
三重文さんのコトは、コロナのずっと前から「劇場に泊まれる公共ホール」として聞いていました。いくら助成金をもらっても、旅公演をするのは経済的にかなりきつくて、東京、大阪も劇場に泊まって続けてきたので、三重文さんからお声をかけてもらって、即刻お付き合いが始まったような気がします。で、たぶん、三重文でやった最後の公演のバックヤードでの雑談中、松浦さんに「実はうちがもうすぐ40周年なんですよ」というお話をしたら、松浦さんが冗談で「じゃあ40周年をうちでやって解散しましょう」とおっしゃって、そのイメージがずっと残っていました。で、コロナを挟んで40周年の年を迎え、めでたく“あの雑談”が実現しようとしています。ま、でも「ファイナルツアー」としたのは、解散公演ではなく、“新作=多都市ツアー”という足かせを外して、もう少し気楽に活動していこうぜ、という意味合いを含んでいますね。
松浦 ファイナルのあとには、リターンズっていう言葉も使えますね(笑)。
はせ 今、メモりました(笑)。
松浦 池田さんが参加してくださったのは2014年度の「ミエ・ユース」で、その後2022年に「あかあか」を上演していただきました。
池田亮 そうですね。2022年に上演したのは僕の父親も出演した「あかあか」という作品で画家だった祖父の絵を舞台美術に使った作品でした。2020年から2022年頃のコロナ禍は自分自身も演劇を続けていくかどうか悩んでた時期だったのですが、2024年に第68回岸田國士戯曲賞、2025年に読売演劇大賞優秀演出家賞をいただいて、うれしかったと同時に受賞作で700万も赤字を作ってしまい、「お金をかけずとも、演劇ってもっといろいろな可能性があるんじゃないか」と感じたんですね。そんなとき、「ミエ・ユース演劇ラボ」のことを思い出しました。
僕は岩井秀人さんが講師をされたときの受講生だったんですけれども、当時全然お金がなく、でも当然稽古は三重でやるから、最初の2週間はずっとネットカフェに泊まっていました。でもそのあとは本当に金銭的に苦しくなって、野宿をしたり、日雇い労働を探したり、ギリギリな金銭状況で作品を作りました。そのことがとても記憶に残っていて、“お金がなくても演劇はできる”ということ、あるいは“お金をそんなにかけなくても心に残る体験はあるんだ”ということを三重で実感したので、ゆうめい10周年の今年、もう一度三重で公演したいなと思いました。ちなみに今回、舞台美術を自分が担当していて、制作費は安いですが、最も工夫を凝らしたものになるんじゃないかと思っています。
松浦 「ミエ・ユース」の最初の2週間の話は、今聞いて初めて知りました。最後の2週間は、池田さん、うちのホールに泊まっていましたね(笑)。
池田 はい。劇場に泊めてもらうことで救われました。
一同 あははは!
松浦 田辺さんには戯曲講座を2016年、2017年とやっていただき、下鴨車窓の公演としては2015年に「漂着(island)」、2020年に「散乱マリン」、2023年に「旅行者」を上演していただきました。
田辺剛 そうですね。ちょうど10年前に初めて三重県文化会館さんで公演をさせてもらったのですが、松浦さんをはじめ三重の方たちと知り合ったのはもうちょっと前だったかなと思います。そのときどんな話をしたのか詳細を覚えていないのですが、「ぜひ一度三重でも公演ができれば」ということを多分、申し上げたんだと思います。そこからしばらく間が空いてしまったのですが、方々で「田辺さんはいつ三重に来てくれるんだろうと三重の方たちが言っている」と聞くようになり(笑)、「ああ、約束していたな、申し訳ないな」と思って、以降、三重で2年に1度くらい公演をするようになりました。私は京都で創作し、いろいろな場所で公演を行っていますが、三重県がトップクラスに多いと思います。京都と三重はすごく近くて、車で90分くらいの距離ではあるので、すごく行きやすく助かっています。
今回上演する作品は私が持ち込んだ企画で、受け入れていただけてよかったです。というのも、三重県文化会館さんは演劇の土壌を育てていくということをずっとされていて、劇場についているお客さんがたくさんいらっしゃる。年間ラインナップも、少し難解な作品から間口の広い作品までバランスを考えてプログラムされているので、三重文に観劇にいらっしゃるお客様はすごく目が肥えていらっしゃるんです。そこで厳しい評価をもらったり褒めていただくことは自分の作品を試すという意味でも大切で、だから単純に旅公演がしたいという思いもありますが、三重に持っていくということが一つの大きなステップだと思っているので、実現して良かったです。
松浦 ちなみに皆さんは面識があったり、お互いのことを情報として知っていたりはしますか?
田辺 池田さんとは本当に初めましてですね。もちろんお名前は存じ上げていますけれども、お話しするのは初めてです。はせさんとは、一番最初にお会いしたのはもうだいぶ前です。アトリエ劇研という、今はもうない京都の客席数100くらいの小劇場にジャブジャブさんが来てくださったり、私が名古屋で公演したときに観に来てくださったり、東京で「旅行者」をやったときのアフタートークに来ていただいたり……毎月会うような関係ではないですけれども(笑)、時々お会いするような関係性です。
松浦 はせさん、劇研のような小さな空間でもやったことがあるんですね!
はせ ええ。小作品で、一人芝居や出演者4・5人の短編を含めてやらせていただきました。あの頃、田辺さんは劇研さんのスタッフでしたよね?
田辺 そうですね。
松浦 それと今お話に挙がった下鴨車窓の「旅行者」、私大好きなんですよ。
はせ 僕も大好きです。松浦さんが言われたように、国籍や時代を超えて観られる作品ですよね。
田辺 ありがとうございます。
松浦 池田さんは、先輩2人のことは知っていましたか?
池田 僕は演劇を始めた頃に戯曲デジタルアーカイブをよく参考にしていて、お二人の戯曲はそこで読ませていただきました。ずっと僕は実体験をベースにした半径2メートル以内の戯曲を書いていたんですけれども、徐々に自分から少し遠ざけた話を書きたいと思い始めたときに参考になるものはないかと探ってたどり着いたのがデジタルアーカイブだったんです。またはせさんの戯曲本に最初に出会ったのは、飛騨高山のカフェで、妻が飛騨高山の出身で、そこで公演をやったときにお店に置いてありました。その後、こまばアゴラ劇場に観劇に行くとジャブジャブサーキットさんのチラシや舞台写真が貼ってあるのを目にしていて。なので、僕はどちらかというとインターネットや劇場の掲出物などでお二人と“お会いした”形だったので、今こうして先輩方と話しているということがすごく不思議な感じがします。
松浦 せっかくだからみんなで飲みに行けば良かったですね!
一同 あははは!