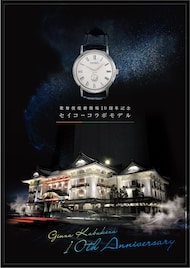目まぐるしく変化していく日々、ふと非日常的な時間や空間に浸りたくなったら、“ゆるりと歌舞伎座で会いましょう”。新開場10周年を迎えた歌舞伎座は、2月も華やかな演目がそろった。ステージナタリーでは第三部の「霊験亀山鉾」を“一世一代”で勤める片岡仁左衛門にインタビュー。芝居への尽きせぬ情熱を、ユーモアを交えた語り口で朗らかに語る仁左衛門が、歌舞伎座で初披露となる「霊験亀山鉾」にかける思いとは? また、没後130年を迎えた河竹黙阿弥にフィーチャーしたミニコラムでは、第一部の演目「三人吉三巴白浪」をピックアップする。
取材・文 / 川添史子
「霊験亀山鉾」は後世に遺しておきたい狂言
──「二月大歌舞伎」第三部は通し狂言「霊験亀山鉾 亀山の仇討」。元禄時代、28年越しに悲願を成就した実在の仇討ち事件を題材に、鶴屋南北がさまざまな趣向を織り込んで描いた物語です。仁左衛門さんが演じるのは、冷酷無比な藤田水右衛門と、軽妙さもある“悪い男”隠亡の八郎兵衛の2役。当り役として上演を重ねてこられましたが、今回が“一世一代”、演じ納めとなります。
歌舞伎役者という仕事は、“演じ切った”達成感が得られない職業で、演じ納めの公演が終わった途端に自分の中で「もっとこうすればよかった」とか反省が始まるんです。因果なお仕事ですね。内心寂しい気持ちもありますが、「前はもっと良かった」「仁左衛門も年を取ったね」と、お客様をガッカリさせるような舞台はお見せしたくないですし、体力のことも考えて、最後にしようと決めました。「これが最後」と言えば、足を運んでくださるかもしれないですしね(笑)。
──5年前、国立劇場で上演したときの取材会(参照:「霊験亀山鉾」、片岡仁左衛門「これが最後になるかもわからないという気持ちで」)では「もしかしたら今回が最後かな、とも思うけれど、ここで最後と言ってしまうと一生できなくなってしまうから、“かな”にさせてください」と揺れる気持ちをお話されていました。ご自分の体力を見極める客観性とやりたいお気持ち、双方がせめぎ合う、特別な演目なのですね。
「霊験亀山鉾」は播磨屋さん(二世中村吉右衛門)が国立劇場で57年ぶりに復活上演され(1989年)、その後、少し手を加えて2002年、2009年、2017年と私が上演を重ねてきました。そうしょっちゅう出せる演目ではないですから後世に遺しておきたい狂言でもありますね。
──仁左衛門さんがなさる形は、仇を討つ石井家とその所縁の人々の苦難や悲しみ、仇討ちされる水右衛門の巨大な悪に重点を置いてスリム&圧縮化した上演。石井側の人間を殺していく冷血無比な水右衛門の存在感から目が離せない展開となっています。水右衛門と“そっくりな男”の設定である八郎兵衛との早替りも鮮やか。それぞれのお役について伺えますか。
2役どちらも好きですね。私はどんな役でも演じると好きになってしまうんです(笑)。水右衛門は冷血で、八郎兵衛は悪い奴ではありますが、初めの登場ではお客様には悪人に見えない陽気な人物で後半に悪人の面が出てきて面白いお役です。同じ悪人でも陰と陽で、この演じ分けが楽しいですね。初演では当時の錦絵をヒントに役作りをしました。このお芝居は仇を討たれる側が主役ですが主役ではない討つ側の悲劇も充分に描いていて、仇を討つ側の悲惨さや悲劇も十分に描けているのも魅力です。
台本を読み込むことで、役の心理や輪郭が見えてくる
──大きな見どころである「焼場」の場面では、本水の雨が降る中、仇討ちの手助けをした芸者おつま、そして八郎兵衛が壮絶な立廻りを見せます。
実は山場らしい山場がない作品でもあって、何かインパクトを……と思案して、初演の稽古中に本水を使うことを思いついたんです。雨はライティングの加減で客席から見えなかったり、光の角度が難しいので、照明さんの腕の見せどころですね。稲妻が光って八郎兵衛の刺青が鮮やかに浮かび上がり、色の配分にも気を配ってこの場面を動く錦絵のように感じていただければと思います。余談ですけど、今回劇場の方から「水は常温で良いですか?」と聞かれて「良いですよ」とお答えしたのですが……よく考えたら2月の常温は冷たいんですよ(笑)。風邪をひかないように、ひと月がんばります。
──陰惨な場面ではありますが、音楽に乗せて展開する殺しの場はドラマチック。殺人現場を目撃しているような臨場感もあります。
ここでは殺しの場ではよく使われている唄い出しが「奇妙頂来」から始まる「地蔵経」というゆったりとした曲を使っていますが、原作にそんな指定はないんです。原作は、もっとリアルな殺しの場として描かれているんですよ。ある意味、今上演している形の方が“歌舞伎っぽい”演出というか、昔はおそらく、今で言う現代劇のようなテンポで、もっとリアルに演っていたと考えられます。
──その後、燃え盛る棺桶を破って水右衛門が出現し、おつまにとどめを刺しながら、これまで命を奪った石井家の人々の数を指折り数え高笑いする。夢に出そうな怖さです……。
おつまのお腹を刺した時点で水子は既に死んでいるわけですから5人まで指を折って勘定したあと、おつまの息の根が止まったのを確認して「これで6人目も殺した」と、小指をぴゅっと立てる(笑)。
──仁左衛門さんのご工夫が随所に光りますね。
初演時、数々の復活上演を経験されてきた奈河彰輔さんが監修してくださったことが大きかったです。同じ南北の「絵本合法衢」もあの方がいらしたから私はできたようなお芝居でしたし、埋もれた作品の復活上演や、市川猿翁の兄さんが復活させた狂言の脚本、演出を多数手がけられた方ですね。
──仁左衛門さんとの「霊験亀山鉾」初演に寄せて書いた奈河さんの文章を読むと、活字に飢えていた終戦後、表紙がちぎれるほど何度も読んだ「延若芸話」の表紙が古怪で色気あふれた(二世延若演じる)水右衛門で、「観たい狂言のトップだった」と書いています。いかにも南北らしい焼場の場面を「是非とも見せていただきたかった」ともありますし、情熱を持って取り組まれたのでしょう。焼場の場面のみならず、劇中、殺しの場面それぞれの色が違っているのも面白いです。
違いを出そうと特別に意識して拵えたわけではなく、台本を読み込んでいくと自然に変わっていきます。この作品に限らず大事なのはセリフを覚えたら台本を離すのではなくて、覚えたあと、何度も何度も台本全体を読み込んでいくことです。するといろいろなことが頭に浮かんで、その役の心理や輪郭が見えてくる。自ずと場面ごとの殺しの色も変わってくるんです。
──「石和河原仇討の場」での水右衛門は、毒薬を仕込んで相手を弱らせてから斬るというかなり卑怯な手を使いますが、刀を拭いた懐紙の束をパァッと空中にばら撒くダイナミックな所作に、観客は思わず拍手してしまいます(笑)。
ただ単にポンと捨てるだけでは寂しいし、それにこのやり方の方が水右衛門らしいし、見た目も面白いですよね。これも、自然に動きが生まれて今言った理由は後からついてくるんですね。
次のページ »
試行錯誤し、挑戦し続ける思い