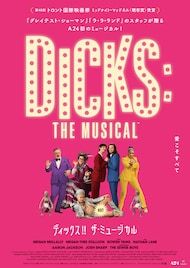心からうらやましく思う作品(園)
──園監督は「ミッドサマー」をご覧になられていかがでしたか?
園子温 「ヘレディタリー/継承」からさらに広く新しい展開があり、素晴らしくてジェラシーを感じました。僕もこういうものを作ってみたいと、心からうらやましく思う作品でした。観終えてから気付いたんですけど、147分と長めなんですね。観ているときはこんなに長いとまったく気付かないほど、楽しんで観ました。
アリ・アスター どうもありがとうございます。僕自身、園監督の大ファンなので、そう言っていただけるのはとてもうれしいです。でも僕のほうこそ、初めて園監督の「愛のむきだし」を観たときは強いジェラシーを感じました。特にオープニングクレジットが映画開始から1時間ほど経ってようやく流れたのは圧巻で、思わず拍手をしたくらいです。
園 それはうれしいですね。ところで「ヘレディタリー」もそうでしたけど、アリ監督は闇と光を実に効果的に使われていますよね。同じような画なのに、昼から夜へパンと変わったり。「ミッドサマー」では、前半は照明をガンガン落としているのに対し、後半はずっと明るい陽の下で見せるという、前作でやったことをさらに広げて撮られているように感じました。
アスター 今作では特に、光や明るさをかなり意識しました。僕たちの生きる時間軸とは違う場所にいるような光や明るさを生み出すことで、観客が「自分たちはいったいどこにいるんだろう?」と、視覚的にも時間的にもわからなくなるようにしたかったんです。そしてもう1つ、お客さんにカタルシスを感じてもらえる作品を目指しました。映画のラストでは不思議と気持ちが上がるような、でも劇場を去って考えるうちに「あれ? ひょっとしたらあまりポジティブな物語ではなかったのではないか?」と思うような作品ですね。僕はそういう絶妙なトーンの使い方こそ、園監督がとても長けていると思っています。素材がダークであっても、歓喜の気持ちやエクスタシーを感じたり。監督の作品には悪魔的なユーモアのセンスを感じますし、そういう作品にインスパイアされます。
物語はもちろん、美術にも感動した(園)
──「ミッドサマー」では、スウェーデンのキリスト教信仰以前の風習や民話が物語に取り入れられています。園監督は「愛なき森で叫べ」で、実際に豚を使って死体処理を自身で試してみたという話もされていますが、事実にインスパイアされた物語の場合、リサーチはどの程度されるのでしょうか?
園 ケースバイケースで、ものすごく取材をする映画もあれば、取材をしすぎて想像力を失いそうになって途中でやめてしまうこともあります。例えば実在する殺人鬼の話では、深く取材をしすぎて本当にがっかりして、夢がなくなってやめてしまったこともありました。ノンフィクションからフィクションに移る前に、どこかで捨てるものがある。そうじゃないとバランスが取れなくなってしまうので。
アスター ものすごくわかります。「ミッドサマー」では徹底的にリサーチをしたのですが、スウェーデンの伝統や風習だけでなく、ドイツやイギリスの宗教、スピリチュアルな歴史的背景など、物語に関係することはとことん調べました。すべて興味深いことばかりで、できる限り取り込みたいと思いつつも、映画の目的に合わせていろいろと削ぎ落したり変更したりして。それでも、脚本の第1稿は250ページにもなってしまいました(※編集部注:通常、約2時間の映画の脚本は120ページ程度)。そこからは、リサーチというノンフィクションから、さまざまな儀式を合体させて描いたりする想像の世界、フィクションへと変わっていきました。その後、リサーチをして取り込んだ要素をいったんすべて取っ払って、完全に自由に脚本を書いてみて物語として整合性があるかどうか、自分の中で話が成立しているかどうかをチェックしました。
園 物語はもちろんですけど、僕は今作の美術にも感動しました。素晴らしいですよね。例えば壁画がその1つ。壁一面に何かを意味する絵がびっしりと美しく描かれているんですけど、そこにカメラが全然寄らない。引き画の中で終わっているのが、ものすごくストイックでかっこいいなと思いました。
アスター それはうれしい! なぜなら、寄りの画を撮らなかったことを、僕自身も誇らしく思っているから。だって、本来あそこまで作り込んだら撮りたくなりますよね? でも、もともと大きく引きで見せたいと思っていたので、寄っていきたい気持ちをぐっとこらえたんです。そこに気付いてくれるなんて、本当にうれしいです。セットは2カ月ほどしかないスケジュールの中ですべてをゼロから建てたので、相当厳しい作業でした。それでも、イメージしていたものにかなり近いセットができたので、とても満足しています。
食卓では嫌でもお互いと向き合わなければならない(アスター)
──お二人は家族や共同体を作品のテーマにすることが多いと思いますが、その理由を教えてください。
園 まず僕は家族の集まる場所、みんなが集まる場所として、シンボリックに食卓を描くことが多いんです。家族というもっとも原始的でミニマルな共同体における食卓は、僕の作品にとって重要な役割を果たすんですけど、アリ監督も「ヘレディタリー」では映画の鍵となる家族の食卓シーンを登場させていますし、「ミッドサマー」でも大勢で食卓に着くシーンが何度も登場しますよね。
アスター ずいぶん前に気付いたんですけど、僕が書いた脚本は、いろいろな展開を経てようやく全部が解き明かされるもっともドラマチックなシーンがすべて食卓だったんです。
園 自分の人生経験によって、どうしてもそこを書きたくなってしまうのですか?
アスター 家族は顔を合わせず、内緒で自分の生活を持つこともできますが、食卓では嫌でもお互いと向き合わなければならない。たとえ関係が崩壊していて、もはやそこに何もないとわかっていても集まらなければいけないし、家族のふりをしなくてはいけない場でもあると思うんです。逆に言うと、食卓以外に家族全員が顔を合わせる場所がないからだったりもするのですが。
園 それはよくわかりますね。そして、まさしく僕のテーマでもある。僕はいつもなぜか家族が崩壊していく話を書きがちで、意識していなくてもそういうシナリオになってしまう。そのたびに、「あ、またやっちゃった」となっていますね(笑)。
──なぜ潜在的にそのテーマに惹かれるのでしょうか?
園 やっぱり自分の人生経験の中で、そこにトラウマがあったりするんでしょうね。僕自身は何も意識をしていないので、おそらくなんですけど。
アスター 僕は逆にほとんどの場合、家族や家族の崩壊といったテーマに関しては、自分の経験から来ているという自覚があります。ただ脚本にするときは、それを意識的に隠すことに多くの時間と労力を費やします。というのは、自分の人生に関わってきた人たちがそれを見たら、絶対に憤慨するような描き方をしてしまうから。
次のページ »
本能的に女性キャラへ自分を投影していた(アスター)
2020年2月20日更新