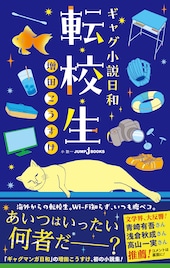Eveがマンガ原作とプロデュースを務める「虚の記憶」や、ポケモン公式X・ポケモン情報局で「雨のちヌメラ」を連載するネヲが絵を担当し、はみこまがおはなしを担当する「かけっこネウ」。同作はネコと十二支の動物たちが、山のむこうにあるという“すごいもの”を探して旅をするさまがゆるく描かれるWebマンガだ。そんな「かけっこネウ」が絵本化され、絵本投稿サイト・よみきかせキャンバスで公開された。さらに8月中旬より順次キャラクターたちを立体化したカプセルトイ「かけっこネウ ならぶんです。」も発売される。
コミックナタリーでは絵本化を記念して、絵本「かけっこネウ」のおはなし担当であり、「第1回よみきかせキャンバス えほん応募コンテスト」でグランプリを受賞した作家・みきたりりと、乃木坂46在籍中に小説「トラペジウム」を執筆し、2024年には絵本「がっぴちゃん」を制作した髙山一実のインタビューを実施。作家の視点から、絵本にかける思いや「かけっこネウ」の魅力を語ってもらった。
取材・文 / 岸野恵加撮影 / 星野耕作
よみきかせキャンバスとは
よみきかせキャンバスは、バンダイが運営する絵本投稿サイト。クリエイターが投稿した絵本を無料で読むことができるほか、投稿機能を使って自作の絵本を公開することもできる。クリエイターの活躍の場となること、そしてさまざまなジャンルの絵本を読むことで子供たちの豊かな成長や、親の笑顔につながることを目指している。人気絵本の読み聞かせ動画も公開中だ。
「仲間はいるよ」というメッセージを発信したい(みきた)
──まずは、おふたりの絵本への思いからお伺いしたいです。みきた先生は「第1回よみきかせキャンバス えほん応募コンテスト」でグランプリを受賞しましたが、どのようなきっかけで絵本を描こうと思ったのでしょうか。
みきたりり 私は昔から引っ込み思案で、人と話すのが苦手で、友達ができにくい性格だったんです。もしかしたら同じような人は世の中にたくさんいるのかもしれないな……と思い、「仲間はいるよ」というメッセージを発信したいと考えました。SNSを使うのが便利だとは思いつつ、運用することが苦手なので「どうしようかな」と思っていたときに、たまたま「よみきかせキャンバス」の募集要項を見て。絵本に思いを込めて、応募してみようと思いました。
──受賞作「よわもち」を執筆する前から、絵本を描かれていたんですか?
みきた いえ、もともと絵本作家を目指していたわけではないので、「よわもち」が初めての作品です。絵本という媒体を通して、自分のメッセージを広めていけたらいいなと思いました。
髙山一実 初めての作品とはびっくりです。Xで「よわもち」の4コママンガも読ませていただいて、タイトルのひらがなの優しいイメージが、そのまま作品の中に凝縮されているような感覚を覚えたんです。私は夏に水羊羹や水まんじゅうが恋しくなるタイプなので(笑)、すごく癒されました。
みきた ありがとうございます。
髙山 SNSは情報を広げるには便利なツールですが、いろいろ考え始めると怖さもありますよね。絵本というかたちに惹かれる感覚には、とても共感します。
──髙山さんは乃木坂46在籍中の2018年に小説「トラぺジウム」で作家デビューし、卒業後の2024年に初の絵本「がっぴちゃん」を上梓しました。絵本を描いてみたいという思いは、以前から持っていたんですか?
髙山 はい。でも「絵本を描くためにこうしよう」という順番ではなく、物語のアイデアが先に浮かんで、「これを絵本にしたいな」と形にしたのが「がっぴちゃん」でした。ある日、三重県の桑名ではまぐり専門店に行ったときに、はまぐりだけを食べているのにまったく飽きなくて、1つの生命に向き合った感覚があったんです。そこではまぐりに対してのリスペクトが高まりました。さらに、同じ日にメンバーと話していて、恐竜の話になったんですね。そこでふと、小学生の頃に車で幕張メッセの近くを通ったとき、両親に誘われた恐竜博を断って後悔した記憶が蘇ってきて。はまぐりと恐竜って交わらないものだと思うんですが、自分の中からするすると物語が浮かんで、翌日にはストーリーが完成していました。
──普段からそんなふうに、集中して一気に書き上げることが多いんですか?
髙山 そうなんです。移動中に過集中モードに入ってしまって、電車を乗り過ごしたり(笑)。iPhoneのメモにはそうして書き貯めたものがたくさん残っているんですが、次の日に読み返したときに「これは人に見せるべきものなのか」と考えて、やめてしまうことがほとんどなんですよね。でも「がっぴちゃん」はすごく気に入って、「これなら商品として、世の中に自信を持って出せそうだ」と思いました。
みきた 「がっぴちゃん」を読ませていただいて、最初はふわふわしていてかわいい世界だと思ったんですが、最後の展開にびっくりして……。
髙山 そうなんですよね。ちょっと悲しいお話になっていくので……。
みきた でも、最後に「思い出として残ったものが確かにあるよ」という感覚が残って。すごく素敵なお話だと思いました。
髙山 わあ、うれしいです……。ありがとうございます。
──おふたりは子供の頃、どんなふうに絵本に触れていたのでしょうか。特に印象に残っている作品はありますか?
みきた 小さい頃は母が絵本の読み聞かせをしてくれていましたが、10歳くらいから1人で黙々と読むようになって。登場人物に対して自分が何を思うかを考えることで、自分と向き合う時間になっていたように思います。特に印象的な絵本は「つみきのいえ」。それまでは明るいお話ばかり読んでいたので、初めて読んだときは衝撃的でした。海面上昇で水没しつつある街で、上に家を建て増しして住んでいるおじいさんの話なんですが、彼は下の階に潜っていく中で、亡き家族のことを思い出していくんです。私は約10年の介護生活を経て母を去年亡くしたんですが、母との記憶が「つみきのいえ」に重なる部分があって。最初は悲しいストーリーだと思っていたけど、大人になってから読んでみると、大切なものが書かれている作品だと思いました。
髙山 素敵ですね。私は「バムとケロ」が思い出深いです。母が好きな作品で、私も何度も読み返しました。主人公のバムとケロ以外のキャラクターが、物語と関係ないところでただアイスをこぼしていたり……そんな細かい描写も好きでしたね。今でも母とは「バムとケロ」のLINEスタンプを送り合ったりしています。あと、母と叔母と訪れたヨシタケシンスケさんの展覧会で出会った「にげてさがして」は、最近の自分に刺さった作品です。展覧会に親子で来ている方が多かったことも印象的で。家族について改めて考えるいい機会になりましたね。
読み聞かせは自分が一生懸命やらないと子供に伝わらない(髙山)
──「よみきかせキャンバス」は、クリエイターが投稿した絵本を無料で読むことができるWebサイトです。使ってみていかがでしたか?
髙山 サイトのデザインがすごくかわいいですよね。サムネを眺めているだけで、かわいいキャラクターがたくさん目に入ってくる。絵本を読む際に、紙の本のページをめくっているような視覚的な工夫があるのもいいなと思いました。
──紙のページをめくるときのワクワク感が再現されていますよね。
髙山 まさに! 絵本の世界をしっかりとデジタルに落とし込んでくださっているなって。同じ作品を何度も読みたい子がいれば、さまざまな作品をたくさん読みたい子もいると思うので、子供の好みに合わせて親御さんが作品を自由に選べることも素敵だと思います。
──そして「よみきかせキャンバス」では、人気作品の読み聞かせ動画を無料で公開しています。みきた先生の「よわもち」も小清水亜美さんによる読み聞かせが公開されていますが、ご覧になった際にどう感じましたか?
みきた 本当に素晴らしい方に繊細に読んでいただいて、大変光栄でした。収録現場に同席したんですが、小清水さんが「もう1回やってもいいですか?」と、すごくこだわってくださって……うれしかったですね。最初は読み聞かせの素晴らしさを私はあまりわかっていなかったんですが、完成した動画を観たら、言葉にできないくらい感動してしまって。自分の作品なのに、小清水さんの声が聴きたくて、何度も再生しています(笑)。あと、動画にちょこちょこと出てくるアニメーションは、私が自分で制作していて……。
髙山 ええ、そうなんですね! すごいです。
みきた いえいえ。アニメーションの経験はまったくないので勉強しながらですが、少しでも観ていただく方に楽しんでいただきたいと思って制作しました。
髙山 やはりたくさんのこだわりが詰まっているんですね。読み聞かせって、読む人それぞれで表現の仕方は自由ですが、公式の動画として発信するうえでは方向性を決める必要があるだろうし、いろいろと考えられたんだろうな……と思いながら拝見していたんです。絵と文字で物語に触れるのとは、また別のよさがありますよね。
──髙山さんは「がっぴちゃん」の刊行後、地元である南房総市の小学校や中学校で読み聞かせの活動をされていましたよね。
髙山 私は地元が大好きで、子供も大好きで。故郷のために自分が何かできることをしたいという思いと、子供たちに「がっぴちゃん」を好きになってもらえたらうれしいという思いで、読み聞かせを行っていました。出版前、仲のいい友人の子供たちにがっぴちゃんの絵を描いたら「これは何?」と気に入ってくれたことがうれしくて。それも読み聞かせをやろうと思うきっかけになりましたね。
──実際に読み聞かせをして、何か発見はありましたか?
髙山 自分が一生懸命やらないとちゃんと伝わらない感覚があって。どう読み聞かせるのがいいか、毎回ひたすら考えましたし、読み聞かせに無限の可能性を感じました。SNSで、生徒さんの親御さんから「素敵な読み聞かせありがとうございました」とメッセージをいただいたときは「お子さんが親御さんに話してくれたのかな」と、すごくうれしかったです。あとは読み聞かせをする中で「ああ、絵本のこの部分はもっとこうすればよかったな」と、改善点がどんどん浮かんできましたね。
──「もっと読むうえでのリズムを意識した文章にすればよかった」というような?
髙山 はい。擬音など、子供たちを惹きつける仕掛けをもっと入れたりもできただろうな……と。今後に生かしたいですね。
──なるほど。みきた先生は、読み聞かせることを念頭に置いて絵本の文章を書くことはありますか?
みきた そうですね。自分が読み聞かせをしてもらった記憶の中でも、擬音やポイントになる要素が入っているとハッとして、長い物語でも集中できたんですよね。そういうギミックや、声に出したときの語感は意識しています。
髙山 やはりそうなんですね。素晴らしいです……!