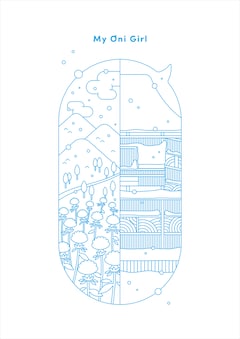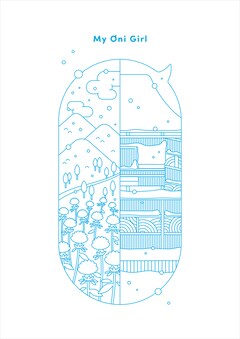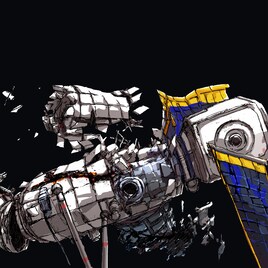スタジオコロリドが贈る長編アニメーション映画「好きでも嫌いなあまのじゃく」のBlu-ray / DVDが、5月28日にリリースされる。本作は、“みんなに嫌われたくない”という思いから頼まれごとを断れない高校1年生・八ッ瀬柊と、物心つく前に別れた母親を探す鬼の少女・ツムギが出会い、成長していく青春ファンタジー。小野賢章が柊、富田美憂がツムギに声を当てた。
映画ナタリーでは、監督を務めた柴山智隆にインタビューを実施。「自分の気持ちを隠さないで」という本作に込めたメッセージが生まれたきっかけや制作秘話、Blu-ray / DVDの封入特典であるスペシャルブックレットの見どころなどを語ってもらった。
取材・文 / 岡本大介撮影 / 小川遼
映画「好きでも嫌いなあまのじゃく」Blu-ray / DVD予告編公開中
そこで初めて「これなら映画にできる」と感じました
──まずは本企画の成り立ちについてですが、前作「泣きたい私は猫をかぶる」(以下、「泣き猫」)の制作後、すぐに構想が始まったのでしょうか?
そうですね。ツインエンジンの山本幸治プロデューサーから「企画の打ち合わせをしたいから何か書いてきてほしい」というお話を受けて、4つほどのプロットを提出したのが始まりです。今回の作品は、そのうちの1つがもとになっています。
──どんなところから着想を得たのでしょうか?
山本さんから「『泣き猫』と同じ方向性で、お面も出したい」というリクエストがあったので、まずはそこを意識しながら作りました。
──「お面」は「泣き猫」のキーアイテムでした。
そうなんです。なので初期のプロットには、柊が鬼のお面を着けるたびに若返っていって、歳下だったツムギとの年齢が逆転していくという案もありました。子供になり、やがては赤ちゃんになっていくという過程において、関係性の変化を通じて描ける主題があるのではないかと思ったんです。まあ、それは早々になくなりましたけど(笑)。
──そもそも「鬼」というモチーフはどのような発想から生まれたのでしょう?
4案のプロットを一気に作ったので、あまり深く考えずにお面から鬼の面を連想して書いたものでした。当時、鬼をモチーフにした作品が日本で大流行していたので、設定はひと工夫する必要があるだろうと思っていましたが。その後、「鬼」の語源を調べていくうちに、大昔は「隠(おぬ)」という字が使われていて、目に見えないものを恐れていたということを知りました。その「隠す」という文字に行き着いたことで、「気持ちを隠してきた繊細な人間は、やがて角が生えて鬼になってしまう」という設定を思い付いたんです。そこで初めて「これなら映画にできる」と感じました。
気持ちを押し殺すことが常態化して、それに慣れてしまっている子供が多い
──「雪」がとても印象的な作品でもあります。これはどこから?
僕だけなのかもしれませんが、鬼=雪深い場所というイメージが頭の中にあったんです。あとは「隠す」が本作のテーマでもあるので、何もかもを白く覆って隠してしまう「雪」というものは、テーマをビジュアルとして表現するうえでもぜひやってみたいという気持ちがありました。言語化しなくても、気持ちを隠す人々が集まる隠れたコミュニティの雰囲気を、ビジュアルを通じて感じてもらえるのではないかと考えました。
──おっしゃる通り、本作の根底には「気持ちを隠してしまう人たち」というテーマがあります。特に10代の思春期の子供たちが直面する問題でもありますが、スタッフの皆さんと10代の悩みについてリサーチや議論を重ねたそうですね。
そうなんです。スタジオコロリドは若い方がとても多い会社なので、その方たちに聞いたりもしましたし、あとは中学生くらいのお子さんがいるスタッフにも実感として思うところを伺ったりもしました。その中で出てきたのは、最近の子供たちは日常的にネットを使って学校や家庭での問題をシミュレーションしているので、昔のように直接的にぶつかったりもめたりすることを避けて、無難にやり過ごしているのではないか、という話でした。自分の本当の気持ちを押し殺すことが常態化して、それに慣れてしまっている子供が多いのではないかと。何より僕自身が10代の頃に同じような経験をしてきたので、それを掘り下げていくことで今回のテーマが定まっていきました。なので、結果的に柊はかなり少年時代の僕にも近いと思います。
──個人的に素晴らしいなと感じたのは、ディスコミュニケーションを扱いつつも、最終的に「もっと自分勝手に振る舞えばいい」というような安直な結論に着地しないところだと感じました。
そこはとても意識しました。気持ちを隠す鬼の世界は、繊細な人間たちの逃げ場所として設定しているんですけど、じゃあ逃げるのが悪いのかと言えば、僕はそれもアリだと思っていて。逃げてもいいけれど、逃げ続けてばかりはいられないよね、という話だと思うんです。柊がツムギと旅をする中で自分の問題に気付いて、最後にはお父さんに「話したいことがあるんだ」と言えるところまで前に進む。観ている人にも、柊と一緒にそこまで進んで、向き合えるきっかけになればという気持ちで作りました。
もしかすると今は全世界的に“空気を読まなければいけない”時代
──公開から1年以上が経ち、Netflixでも多くの方がご覧になったと思います。反響はいかがでしたか?
世界中の方に観ていただけているらしく、素直にうれしいです。先日、イギリスの記者の方と話した際に「日本では“空気を読む”という言葉があって、みんな自然にやっていることだけれど、イギリスにもそういう感覚はあるの?」と尋ねたら、「“Read the room”という同じような言葉がある」と教えてくれました。アメリカで実施したサイン会でも「自分と父親の関係にすごく似ていた」と言われたり。自分としてはグローバルというよりは、日本人の感覚に寄り添って作った作品ですが、海外の方にも伝わっているんだなと驚きました。もしかすると今は全世界的に“空気を読まなければいけない”時代になっていて、みんなが同じような悩みを持っているのかもしれませんね。
次のページ »
大人たちにもそれぞれ隠している気持ちがある