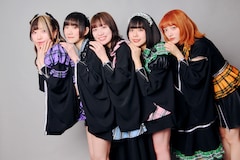米津玄師がPlayStationのCMソングとして書き下ろした新曲「POP SONG」を2月7日に配信リリースした。
TBS系ドラマ「リコカツ」の主題歌「Pale Blue」以来、約8カ月ぶりの新曲となる「POP SONG」。1月23日に本人が出演するPlayStationのCM映像がゲーム端末の中で公開されると、米津のインパクトのあるビジュアルや壮大なスケールの映像、ユニークなサウンドの楽曲が大きな話題になった。
ロマ音楽のような異国感のあるフレーズやキッチュな効果音が幾重にも折り重なる、かなりトリッキーな仕上がりとなった「POP SONG」。そんな新曲の制作背景から、ミュージックビデオと連動したCMのビジュアルイメージについて、ゲームカルチャーに対しての思いなど、さまざまな話を聞いた。
取材・文 / 柴那典
この10年で一番何もしなかった年
──前作「Pale Blue」のとき以来のインタビューになりますが(参照:米津玄師「Pale Blue」インタビュー)、改めて2021年はどんな年でしたか?
うーん、覚えてないですね。去年はここ10年の中で一番ミュージシャンとして何もしなかった年だったと思います。シングルは1枚出しましたけれど、ツアーもなかったし、音楽家としてはそれだけしか動いていない。30代になってひとつの節目を迎えたというか、一旦落ち着く年だったのかもしれないですね。まあ、意図的にそうしたというよりは、結果的にそうなった感じですが。
──1人で過ごすパーソナルな時間が多かった?
そうですね。家でなんとなく過ごす時間が多くて、映画ばかり観ていました。YouTubeの関連動画をたどっていくようなノリで昔の映画を掘っていったり、昔に観たけれどあまり内容を覚えていないものを改めて観たり、多いときには1カ月に50本くらい観ていたと思います。音楽じゃないところから音楽にフィードバックできないかと思って、映画をたくさん観ていた気がしますね。
「くだらない」はネガティブとポジティブの両義性のある言葉
──例えばどんな映画を観ましたか?
いろいろ観ましたけど、私利私欲で犯罪を犯すのではなく、自分の理想や信念みたいなものをこの世に顕在化させることを目的に罪を犯す悪役が出てくる映画ばかりを観ていた時期があって。その頃の体験が「POP SONG」を作るにあたって大きな影響を及ぼしている気がします。「劇場版パトレイバー」や「セブン」、黒沢清監督の「CURE」とか、そういう作品に共感を覚えることがあって、それを音楽でやれないかというところもありました。
──どういうところに共感を覚えたんでしょうか?
ここ最近に始まった話じゃないですけれど、例えばSNSを見ても、いつもいさかいが起きている。義憤という言葉でくくられるような、1つの方向に向かうなんらかの大きな流れがある。でも、その中を見てみると、ものすごく悪辣な言葉が目に入って「みんなどうかしてるな」と思うことがあるんですよね。誰も彼もまともに見えなくて、この世に生きている人間はみんなどこかイカれているんじゃないかと思ってしまう。でも、そういうものに注視しようとすればするほど視野が狭くなって、ふとした瞬間に「どうかしてる」と言っている俺が一番どうかしているんじゃないかとも思ってしまう。俺は一般的に見たら特殊な生活を送っているし、自分のような立場でいる人間は非常に少ない気もする。それでも「世の中でまともなのは自分だけなんじゃないか」という気分になることが多々あって、「POP SONG」は、その感覚をひっくり返した形として表現しました。
──価値の転覆ということですよね。挙げていただいた映画にもそういうモチーフがありますし、「POP SONG」を聴き終わったときにもっとも印象に残るフレーズとして「全部くだらねえ」という言葉があったんです。そこにも「価値をひっくり返す」というなんらかの共通するモチーフを感じました。
「くだらない」というのは、語義通り捉えるとものすごくネガティブな言葉ですけれど、自分にとってはネガティブなだけではなくて。立川談志も「人生は死ぬまでの暇つぶし」と言っていましたけれど、それってある種の救いの言葉だと思うんです。肩肘張って生きている人も「どうせ人生は死ぬまでの暇つぶしの連続なんだ」と思えば肩の力が抜ける。そんないい言葉でもあると思う。みんな生きることに必死すぎて、その反対にあるくだらない遊びのようなものを遠ざけようとするじゃないですか。でも、遠ざけようとすればするほど、翻って生きる意味すらわからなくなっていく。果たしてどれくらいの人間がそのことを意識しながら生きているだろうかということを考えたりします。
──歌詞には「君だけの歌歌ってくれ」というフレーズがありますよね。それと「全部くだらねえ」が対になっている感じもしました。
「全部くだらねえ」という言葉にネガティブな部分とポジティブな部分の両方があるのと同じように、この曲自体にも両義性を持たせたかったんです。両義性があるものが好きで、矛盾をはらんだものに魅力を感じるところがあって。「君だけの歌歌ってくれ」というのも、この曲のこのトーンじゃないとなかなか使わない、歌いたくない言葉なんです。お前だけのものが果たしてこの世に存在するのかと言われたら、それはないと思う。所詮1人でやれることは限られているし、1人の人生から生まれてくるものなんて、たがが知れている。それは自分に対しても、ありとあらゆる人間に対してもそう思うんです。だからこの言葉を曲の中にはめ込むためには、こういう形をとらなきゃいけなかった。「それもまた全部くだらねえ」という言い方をすることしかできなかったんだと思います。
次のページ »
変身→セーラームーン→POP SONG