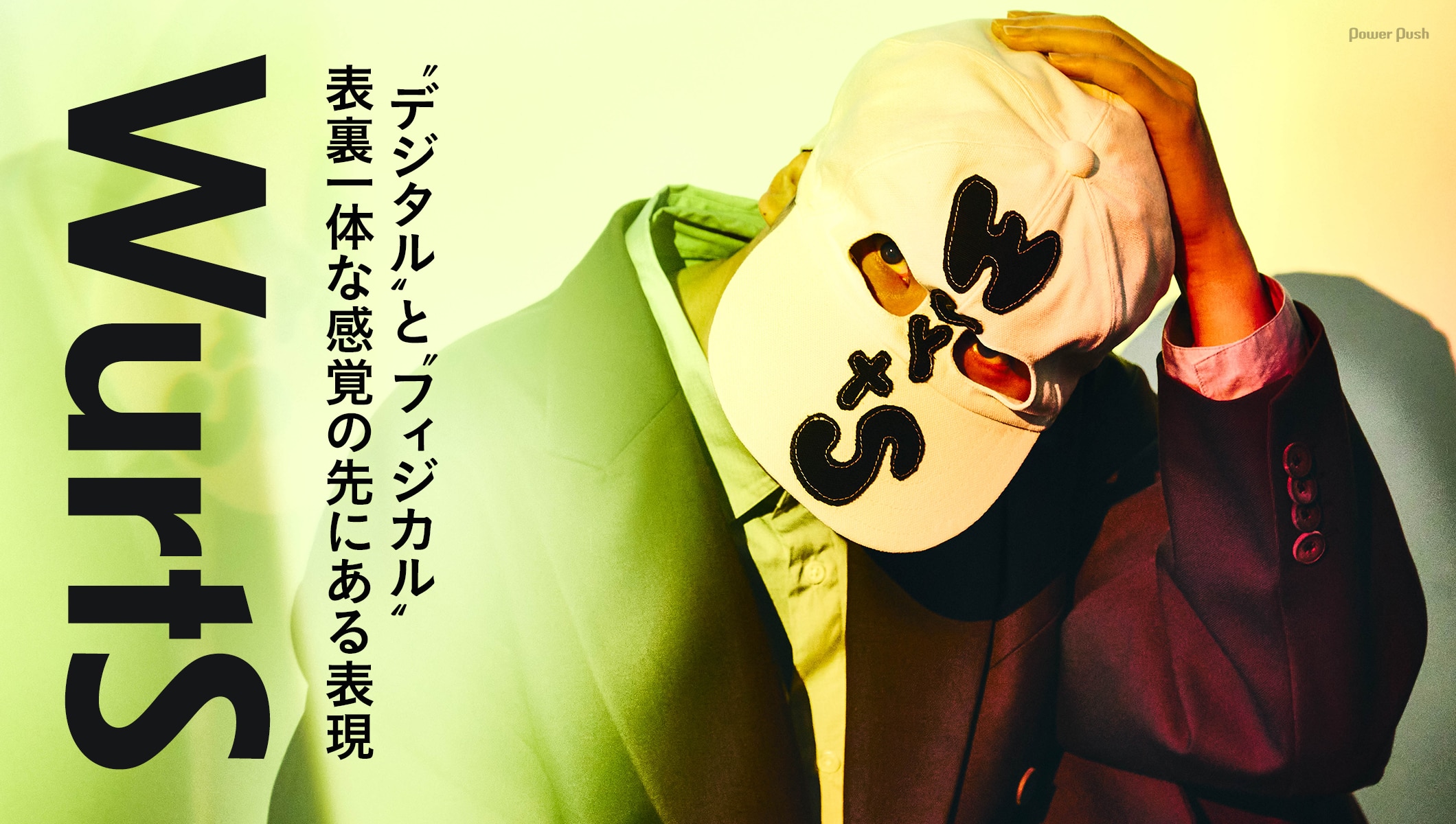WurtSが新作EP「デジタル・ラブ」をリリースした。
コロナ禍の2021年、インターネットを拠点にして本格的に活動を始めたWurtSにとって、“デジタル”は特別な言葉だ。2022年からようやくライブハウスやホール会場で少しずつライブ経験を積み重ね、“フィジカル”でのコミュニケーションを知ったWurtSは、今改めてデジタルの世界について考え、真正面から向き合っている。
ダンスミュージックを軸にロック、ヒップホップ、ソウルなどジャンルの垣根を超えた独自のポップミュージックを生み出しているWurtS。ライブでもアグレッシブなロックナンバーが続くパートや会場がダンスフロアと化すDJコーナーなど、1公演を通して多彩な面を見せている。“デジタル”と“フィジカル”の両方の感覚が、彼の音楽の大切なキーになっていることは間違いない。音楽ナタリーではWurtSにインタビューを行い、そんな彼の表裏一体の両面性に迫る。
取材・文 / 蜂須賀ちなみ撮影 / YOSHIHITO KOBA
「WurtSがちゃんと存在している」と思えた
──このインタビューは2025年10月末に行っていますが、ちょうど1年前に日本武道館公演「WurtS LIVE AT BUDOKAN」がありました。武道館公演はご自身にとってどんなライブでしたか?
僕にとって武道館は、まさにみんなが知っている大きな会場で。「これを超えるとアーティストとしてのステータスがもう一段階上がる」「また新しい景色が見える」みたいなイメージで捉えていたので、武道館公演をやること自体が目標だったんです。そんな中で実際に武道館公演を経験したことで、アーティストとして認められたような気持ちになりましたね。僕はネットアーティストとして実体のないような状態で活動を始めたけど、ライブをすることで、実体のある存在としてだんだん認知してもらえるようになりました。そして武道館で「WurtSがちゃんと存在している」と改めて思ってもらえた、そういうライブでした。
──認められたことで、音楽への向き合い方に変化はありましたか?
実体がない分、僕自身も聴いてくれている人の存在をあまり認識できていなかったんですよ。だけどライブを開催したら来てくれる人がいるし、活動を積み重ねていく中で自分も「お客さんがちゃんといるんだな」「WurtSを好きでいてくれる人がいるんだ」と理解できるようになったところもあって。今までは一方的に何かを届けているような感覚だったけど、武道館を経て、「もらっているし届けている」という双方向のコミュニケーションに変わったような気がしています。
──例えば、お客さんからどんなものを受け取りましたか?
もともとWurtSの活動は内向的だったので、クリエイティブの良し悪しも自分で判断することが多かったんです。だけど今は、ライブなどでお客さんの反応を直接見られるし、聴いてくれる人の感想や意見も聞ける。ツアーを回ったら「この地方ではこの曲が盛り上がるんだ!」という驚きもある。自分の中で咀嚼しながらしっかり聴いてくれている人、音に身を任せてノッている人……本当にいろいろな人がいるんです。ライブの録画を観て、お客さんがどう感じているかをしっかり受け取りながら、今は「WurtSの魅力ってなんだろう?」ということをみんなに教えてもらっているような感覚です。だからWurtSをより俯瞰的に見られるようになって、武道館以降は、聴いてくれている人を意識した物作りに変わりました。
──今年もたくさんライブをしていましたよね。1~2月の対バンツアー「WurtS LIVEHOUSE TOUR Ⅳ」、4月のファンクラブツアー「WurtS FANCLUB TOUR Ⅰ」、7月のPEOPLE 1とChilli Beans.との共催イベント「UPDATE」など。そのほかフェスやイベントにも出演されていて、今はホールツアー「WurtS CONCERT HALL TOUR II -DIGITAL LOVE-」を回っていらっしゃいます。
ライブはめちゃくちゃやってます。ライブの種類によって、自分のマインドもそれぞれ違いますね。
──さまざまなマインドでいろいろなタイプのライブを行うことが、ご自身にとって大事なのでしょうか?
そうですね。まず、対バンの一番の醍醐味は、お互いの相乗効果ですよね。お相手のアーティストさんのライブから刺激を得たうえで、そのあとに自分がライブをするというあの感覚は、ほかのライブではなかなか経験できないものだと思っています。PEOPLE 1とChilli Beans.との「UPDATE」に関しては、この3組がどういう絡み方をして、その場限りの面白いことがどれだけ起こるかを求めて来ているお客さんが多いのかなと。僕自身も自我を100%出すというよりは、3組の個性が混ざったときの化学反応を楽しもうというスタンスです。あまり主張しすぎないように、バランス感はすごく意識していますね。ファンクラブツアーは、自分がやりたいこと、今後トライしてみたいことを披露する実験場として捉えています。もちろん「ショーとしてしっかり作り上げたい」という意識もあるけど、「みんなの盛り上がり具合を計りたい」という気持ちが大きい。「この曲はここまで大胆にやってもいいんだ」とか、曲の可能性を広げる場所になっているような気がします。そして今やっているツアーのようなワンマンは、アーティストの“今”を伝える場所だと思っています。「今、WurtSが探している音楽はこういうものです」と提示するようなライブをしようというマインドですね。
──この1年のライブ活動を振り返っていかがですか?
やっぱり対バンツアーから始まったのが大きかったですね。フィジカルが強いアーティストさんもいれば戦略的なアーティストさんもいて、ライブを観ながらいろいろ分析したんですよ。出演してくださった方々のいいところを摂取して、次は自分がアウトプットできる場所が欲しい……というタイミングで、ファンクラブツアーがあったり、いろいろなイベントに出演させていただけたので。年始にインプットしたものをいろいろな場所で少しずつアウトプットできた手応えはあります。
“表裏一体”のデジタルとフィジカル
──そしてEP「デジタル・ラブ」が完成しました。充実した内容の作品ですね。
ありがとうございます。いろいろな人に助けてもらいながら作ったEPです。制作がすごく楽しかったですね。
──「デジタル・ラブ」というフレーズは、今開催しているホールツアーのタイトルにも入っていますよね。EPとツアーは紐付いているんですか?
そうですね。最初に「デジタル・ラブ」という言葉を思いついて、そこからEPを作り、EPから派生したツアーを開催しようという順序でした。ツアーが終わった2日後にEPがリリースされるんですけど、それはリリース前にEPの世界観を知ってもらいたかったからなんです。
──「デジタル・ラブ」というワードを思いついたのが、一連のアウトプットの起点になっていると。
Daft Punkの「Digital Love」という楽曲もありますし、もともと「デジタル・ラブ」という言葉は頭の中にあって。そんな中で僕のおばあちゃんとのコミュニケーションがきっかけで、デジタルというものについて、より深く考えるようになったんです。おばあちゃんはWurtSのファンで、僕の活動をいつも楽しみにしてくれているんですけど、スマホとかパソコンを触れない。なので、自分が地元に帰って、今の状況を伝えているんです。それってライブみたいだなと。
──というと?
今はスマホがあれば好きなアーティストの“今”をなんとなく追えちゃうけど、直接会って話すからこそのよさがあるなと思ったんです。会って話すからこそ伝わることもあるし、僕もおばあちゃんのことを知れる。そんなに頻繁に会いに行けるわけでもないから、この期間にあったことをギュッとまとめて伝えなきゃいけないんですけど、まとめる作業も楽しいんですよね。自分の振り返りにもなるし、「こういうことがあったな」という成長の実感にもつながるので。なので、近況を伝えながらも、自分もいろいろ思い返しているというか。その時間は楽しいし、有意義だなと思いますね。同じように、今はデジタルの媒体で音楽を聴いたりライブ映像を観たりすることができますけど、そこにはない楽しさがライブにはあるんじゃないかな……みたいな。僕自身「限られた時間でWurtSの今を伝えなきゃ」と試されている感じがするし、アーティストが本当に伝えたいものはタイムラインには載っていない気がするんですよね。
──大量の情報が流れ続けているから、核心が伝わりづらい側面はありますよね。
例えば言葉1つとっても、それがどういう意味なのか、どんなニュアンスで書いたのかは伝わりづらい。だけどライブだと自分の声で届けられる。その違いは大きいなと実感するようになりました。
──今はフィジカルのよさをメインに話していただきましたけど、「デジタル・ラブ」という言葉の通り、EP自体はデジタルを否定するニュアンスではないですよね。
そうですね。僕も普段からスマホとか電子機器で、いろいろな音楽やエンタメを楽しんでいるので。もしかしたら“表裏一体”なのかもしれないです。どっちも違うよさがあるよね、みたいな。さっきの話はちょっとアンチデジタル的だったから、表題曲の「デジタルラブ feat. 星街すいせい」とか、皮肉?と思われるかもしれませんが、そういうわけではなくて。僕が1回「デジタル・ラブ」という言葉を提示することで、聴く人にいろいろな角度から解釈してもらいたいという気持ちがありました。
デジタルの中で愛情が飛び交っている現象
──表題曲の「デジタルラブ feat. 星街すいせい」では、画面上に存在する相手への恋心が描かれています。
今はマッチングアプリとかいろいろなツールがあって、直接顔を合わせなくとも恋愛ができますよね。そういう新しい出会い方にフォーカスしながら書いた曲です。恋愛に限らず、デジタルの中ではいろいろな形の愛情が、ときには数字になってやりとりされているじゃないですか。
──そうですね。SNSのいいねの数とか、推しへの投げ銭の額とか。
そういう形で愛情が行き交っているのを見て「すごく興味深いな」「曲にしたいな」と思いました。この曲こそ、いろいろな解釈ができるんじゃないかなと考えながら作っていましたね。本当にそのまま素直に受け取ってくれてもいいし、皮肉に聞こえてもいい。ダンスミュージックなので、ライブだとフィジカルの動きが発生しますから、そこで新たな魅力に気付いてもらってもうれしいです。
──そんな曲を、ネット発のアーティストであるWurtSさんとVtuberの星街すいせいさんが歌っているという構造も面白いです。
星街すいせいさんに関しては僕が前から興味を持っていて、「何か一緒にできたらいいな」と思っていたんです。星街さんもネットから始まって、今はフィジカル的なライブ活動もされているじゃないですか。きっと両方のよさを知っている方だろうし、リアルなのか、デジタルなのか……今どこにいるのかが明確ではない存在という感じがする。だからこそ興味が湧きました。このタイミングで星街さんにお声がけしたということは、WurtSは今、デジタルでのコミュニケーションにすごく興味があるということだと思います。最近ずっとライブをしていて、リアルでいろいろな人と会う機会が多かったからこそ、そっちに興味がいったんでしょうね。
──なるほど。
そもそもVtuberとしてトップにいる方なので、楽曲に参加していただけてすごく光栄だなと思いますし、最初は「本当にいいのかな」という不安もありました。星街さんにとって、WurtSというアーティストはジャンルが違うというか、ちょっと距離の遠い存在だろうなと思っていたので。「僕の作る曲で星街さんの魅力を100%出せるかな?」というプレッシャーもありました。でも「デジタルの中でいろいろな愛情が飛び交っている」という僕からは不思議に見えた現象を描いた歌詞と、星街さんのミステリアスな雰囲気がマッチして、すごくカッコいい曲ができたなと思っていますね。
次のページ »
なとりくんの歌は、言葉がスッと入ってくる