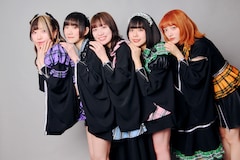amazarashiのニューアルバム「ゴースト」が4月9日にリリースされた。この作品は4月29日に行われる初の神奈川・横浜アリーナ公演「電脳演奏監視空間 ゴースト」のために制作された楽曲を収めたコンセプトアルバム。「電脳演奏監視空間 ゴースト」は2018年に東京・日本武道館で開催されたライブ「朗読演奏実験空間“新言語秩序”」の続編となる公演で、秋田ひろむが書き下ろしたストーリーをもとに現代の社会に対する問題提起、amazarashiが持つ音楽への思いを表現した世界が構築される。
アルバムリリースと横浜アリーナ公演の開催に際し、音楽ナタリーでは秋田へのメールインタビューを実施。「新言語秩序」続編の開催に至った経緯やアルバム「ゴースト」で編み出した世界、各曲に対する思い、ライブへの意気込みなどをつづってもらった。
構成 / 天野史彬
実態のない罪悪感が生きづらさの根拠、amazarashiの根源
──新作「ゴースト」は、4月29日に開催される横浜アリーナ公演「電脳演奏監視空間 ゴースト」のために書き下ろされたコンセプトアルバムであり、この公演は2018年に日本武道館で開催されたライブ「朗読演奏実験空間“新言語秩序”」の続編と銘打たれています。今改めて「新言語秩序」の続編を描こうと思った経緯を教えてください。
横浜アリーナでライブすることが決定しまして、どんなライブにしようかとみんなで話してました。集大成的な代表曲をそろえたライブとか、以前もやったストーリー的なライブとか、いろんなパターンを想像する中で「新言語秩序」の続編という案が浮かびました。「新言語秩序」は当時の時代の流れの中で「こんなふうになったら嫌だな」みたいな発想で書いたものだったんですが、今現在そういう嫌な時代になってしまったので、物語の続きとしてもう少し書き足すものがありそうだなと思ったのがきっかけです。それと、自分個人の現時点での思いを込められたらいいものになりそうな予感があって、続編という形を選びました。
──「新言語秩序」は、秋田さんが執筆された物語を軸としたライブであり、音源やライブ演奏だけでなく、アプリやショップなども駆使した、受け取り手が能動的に参加する試みが実験的で、観客に鮮烈なインパクトを与えました。あのライブを生み出した経験は、その後のamazarashiの活動、あるいは秋田さんご自身の創作や考え方などにどのような影響を及ぼしたと思いますか?
そういうプロジェクト周辺を含めた「新言語秩序」という作品は多くの人の力を借りて、僕個人の発想を超えた表現になったと思います。なのでそれ以降は、僕個人の力とはどんなものだろうという命題に立ち返った気がします。海外でのライブや、表現の最小単位にこだわったアコースティックライブ「騒々しい無人」とか、そのあたりの活動に大きく影響したと思います。今回は大きな会場にメジャーデビュー15周年というのも重なったし、規模が大きくてよりお客さんが楽しめるものにしたくて。それには僕1人では無理なので、また信頼できる多くの人たちの力を借りて準備を進めています。
──秋田さんご自身のコメントの中で、新作「ゴースト」の物語について「過ちを犯した過去、それと向き合う現在」という言葉がつづられています。「新言語秩序」は、ジョージ・オーウェルの小説「1984」にも通じる「言葉」が過度に規制されたディストピア世界を舞台とした物語でしたが、今作「ゴースト」のストーリーの軸となるのは、どのような舞台設定や登場人物たちで、ゴーストとはどのような存在なのでしょうか?
詳しくはライブ当日に知ってもらいたいので詳細はぼかしますが、閉鎖的な空間での監視社会を舞台に主人公が右往左往するというのが大枠のストーリーです。罪を犯したら罰せられるのは当然として、最近は感情を原動力にした外罰意識が目立ちます。芸能界でよくあるキャンセルカルチャーとか。今現在はどこからどこまでが罪で、どの程度の罰が適当であるのかが曖昧になっていて、さらに外枠にある社会規範までもが曖昧になっているように思います。そういう道徳ルールが過度に壊れた世界で僕だったらどう生きるか? どういう選択をするのか?というのが発想の出発点でした。
──「過ちを犯した過去に向き合う」という点について、「過ち」というテーマは人間の存在に深く根差したものであると同時に、今の社会の姿や、現実を生きる私たちが向き合うべき問題と密接にリンクしているように感じます。「ゴースト」のストーリーが生まれるに至った経緯や、なぜ今「過去の過ち」について書こうと思ったのか?という点について、社会的な観点と、秋田さんご自身のパーソナルな観点の両方を踏まえて教えてください。
僕が言う「ゴースト」というのはとても個人的なもので、あまり共感は得られないと思います。僕は昔から自分が悪いことをしてるという意識が強いんです。自分を俯瞰して見れば犯罪はしてないし、ごく普通にまっとうに生きてる人間だと思えるのですが、それとは別に拭い去れない罪の意識が常にあって、それに怯えて生きています。その実態のない罪悪感が僕の生きづらさの根拠でありamazarashiの根源でもあるんですが、今回はそこにフォーカスして作品を作りました。普遍的なところで言えば、過ちを犯してでも獲得したいものとは何か?という問いが物語の中心に位置しています。
──「新言語秩序」におけるオーウェル「1984」のように、今回の「ゴースト」をより深く広く感じるために、秋田さんが「これは手がかりになる」と感じる作品がありましたら、いくつでも構いませんので、教えてください。
いろいろ参考にした作品はあるんですが、ネタバレにならなそうなものだけ。「華氏451」「12モンキーズ」「かもめのジョナサン」「たったひとつの冴えたやりかた」などです。
歌詞には音楽への愛や感謝が多く含まれている
──本作についての秋田さんのコメントには「この物語には新しい音楽が必要だと感じました。amazarashiのこれからの音楽が必要だったのです」とつづられています。そしてシングルくらいのサイズ感を想定して制作を始めたところ、結果的に12曲入りのアルバムになった、と。それは、「ゴースト」という物語を表現するには、既存のamazarashiの楽曲だけでは補完しきれない何かがあった、ということなのでしょうか。だとしたら、その新しく必要としたエッセンス、今のamazarashiだからこそ描き得た部分とは、どのようなものだったのでしょうか?
本当のところ自分でもよくわかってないんですけど、「amazarashiのこれからの音楽」というのはとても意識しました。前作の「永遠市」で昔から想定してたamazarashiの音楽はやりきった感覚があったので、この先というものを常に頭の隅に置きながら制作してた気がします。1つのテーマとして描こうと思ったものに、“過去との決着”がありました。あとはより楽しいほうへ、わくわくする音楽、自分のテンションが上がる音楽を作る方向に向かいました。なので歌詞としても音楽への愛や感謝が多く含まれてる気がします。
──上の質問に付随しての質問ですが、アルバム「ゴースト」に収録された楽曲の中で、秋田さんご自身が「amazarashiのこれからの音楽」という側面を最も象徴していると感じる楽曲を挙げていただき、その理由も教えてください。
「小市民イーア」や「おんなじ髑髏」「アンアライブ」などでしょうか。別にこういうジャンルの曲をずっと書き続けるということではなく、音楽的にも新しいことに挑戦しつつ、それを楽しめる感覚がamazarashiとして新鮮なところだと思います。シングル「痛覚」に入っている「生活の果てに音楽が鳴る」もその一部です。より脳みそと身体が一体化するような、日常の感情と音楽が地続きであるような表現に向かっているんだと思います。
──コメントの中には「ゴーストはもっともらしい言葉で僕らの前進を阻み、暗い部屋に閉じ込めようと画策します。ですが十数年amazarashiをやってきたことで、僕はそれに対抗する手段を獲得しました」ともつづられています。amazarashiとしての十数年間の活動を自ら振り返ってみたとき、秋田さんが今、思うことや感じる手応えを教えてください。
自分としてはさんざんもがいた気がするんですけど、結局人間なんてそんなに変わらないので、持って生まれたものとどう付き合っていくか、突き放したり引っ付いたりして距離感を測っていくしかないんだろうなと思います。リスナーが増えて自信をもらえたことも多くありますが、それが同時に重荷になることもあるわけで、最終目標を見失わずにいようと努めています。僕の場合は笑って生きることと楽しく音楽をやることが最終目標で、それができないならいつでも辞めてやると思って活動してます。横浜アリーナが埋まるわけないと思ってたんですけど埋まりそうなので、支持してくれたお客さんには僕らを見出してくれた分のお返しはしたいと思ってます。
──十数年間の活動を重ねてきた中で、リスナーや社会への向き合い方に変化が生まれたと感じる部分があれば、教えてください。
初期はリスナーと同じ目線で感謝したり敵視したりしてた気もしますけど、今となっては同じような種類の人間の集まりなのかなと思ってます。僕はいい曲を作って発売して、お客さんはamazarashiの新作なら間違いないと思って買ってくれる信頼関係が重要だと思っているので、そこだけは裏切らないようにがんばってます。社会的にはだいぶ楽になりましたね。歳のせいもあるだろうけど、周りがみんな目上の人だった頃に比べれば楽にやれてます。あと面倒くさそうなところには首を突っ込まない処世術も手に入れましたし。
次のページ »
僕にとって生き方と死に方は同じ意味