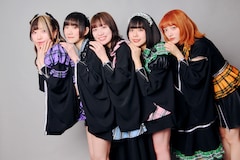7年ぶり7回目の日本武道館公演「This is ACIDMAN」を先日終えたばかりのACIDMAN。彼らが次なるフェーズに突入したことを感じさせるニューアルバム「光学」がリリースされた。
実に4年ぶりのフルアルバムとなる「光学」には、「ゴールデンカムイ」シリーズを盛り上げた主題歌やテーマソングをはじめとする大型タイアップ曲のほか、じっくりと時間をかけて作り上げられた新曲やインストゥルメンタルを収録。ゴスペルやファンクなど、これまでのACIDMANのイメージにはなかったサウンドも取り入れた、新機軸の作品が誕生した。また同日にELLEGARDEN、ストレイテナー、東京スカパラダイスオーケストラ、the band apart、BRAHMAN、Dragon Ashといったそうそうたるメンツが参加したトリビュートアルバム「ACIDMAN Tribute Works」も発表され、こちらも話題を呼んでいる。
結成30周年を2年後に控える中、バンドとしてますます円熟味を増す彼らだが、ニューアルバムではどんなコンセプトを掲げ、音楽とどのように向き合ったのか。大木伸夫(Vo, G)に話を聞いた。
取材・文 / 森朋之撮影 / 山崎玲士
時間をかけて音楽と向き合えた4年間
──13作目のオリジナルアルバム「光学」が完成しました。前作「INNOCENCE」以来4年ぶりのアルバムですが、構想はいつ頃から?
いつもそうなんですけど、アルバムを1枚録り終わる頃にはもう次の作品のイメージがあります。それに沿って曲をストックして、少しずつ形にしていくわけですけど、今回の場合はありがたいことに、制作中にビッグタイアップのお話が立て続けにあって。
──映画「ゴールデンカムイ」の主題歌「輝けるもの」、ドラマ版「ゴールデンカムイ」最終話のエンディングテーマ「sonet」、ドラマ「ダブルチート 偽りの警官」の主題歌「白と黒」ですね。
はい。僕らみたいなバンドにそんな大きなタイアップのお話はないだろうなと思っていたし、オファーをいただけたことがすごくうれしくて。「ここはしっかり集中して作ろう」ということでアルバムの制作を1回ストップさせました。結果、アルバム完成まで当初の想定より1、2年くらい長くかかったんですけど、その分作品の世界観を俯瞰できたし、4年という制作期間はちょうどよかったです。ライブも続いていて忙しかったのもありますが、じっくり時間をかけて曲と向き合えたので。
──特に「ゴールデンカムイ」関連の壮大な楽曲は、アルバム全体の世界観を広げていると思います。
すごく広がったし、豊かになりましたね。オファーがなかったら「輝けるもの」のような激しい曲は作らなかっただろうし。アルバムの中でとてもいいフックになってます。当初はアルバムの方向性が3つくらいあったんです。ポップな感じもいいなと思ったし、ファンキーな路線だったり、あとはアンビエントな雰囲気とか。自分としてはアンビエントの要素が強いかなと思っていたんですが、そのまま制作が進むわけではなくて。途中でやりたいことの優先順位が変わるんですよね。
愛と平和は今こそ大事にしちゃくちゃいけない
──アルバムはインストゥルメンタルの「光学(introduciton)」で始まり、「アストロサイト」につながります。「アストロサイト」はファンクテイストを押し出した曲ですね。
ACIDMANはもともとパンクをメインにやっていたバンドなんですけど、初期の頃からファンク的な曲も作っていました。今まではそのテイストをそこまで押し出してなかったけど、前のアルバム(「INNOCENCE」)くらいから少しずつそういう曲も入れるようにしていて。「アストロサイト」はギターから作り始めて、これは実質の1曲目に合うなと。
──今のACIDMANだから形にできたサウンドかもしれないですね。
そうですね。若い頃は背伸びしてる感じもあったと思うんですが、今は無理せず表現できるようになってきて。音楽の幅も広がってきたというか、「アストロサイト」みたいな曲はキャリアを重ねたほうがカッコよくやれる。「アストロサイト」に限らず、今作は自由度がかなり高いアルバムだと思いますね。リード曲の「feel every love」も、20代のときには作れなかったんじゃないかな。こういうゴスペルを取り入れた、新機軸の曲をしっかりやり切れたのもうれしいし、それもキャリアのおかげかなと。
──「feel every love」のアレンジにはUTAさんが参加しています。三浦大知さん、BE:FIRSTの楽曲などを数多く手がけるトップクリエイターですが、もともとつながりがあったんですか?
ディレクターに紹介してもらいました。「この曲、ゴスペルにしたいんだよね」という話をしたら、UTAさんがいいんじゃないかと。ゴスペル的なコーラスだけじゃなくて、いろんな音も取り入れてくれて、すごく素敵な仕上がりにしていただきました。「feel every love」は9年くらい前に作ったデモ音源がもとになってるんですが、そのときはドラムの打ち込みとピアノ、ギター、歌だけだったから、バンドでやるのは難しいかなと思っていて。でもすごく好きな曲だから取っておいたんですけど、ちょうど「ゴールデンカムイ」の主題歌のお話をいただく前くらいから改めて作り始めたんです。ベースとドラムのフレーズを考えてから、「これならACIDMANでやれそうだな」と。
──なるほど。どうしてゴスペル的なサウンドにしたかったんですか?
最初のデモの段階から、頭の中で4声、5声くらいのコーラスが鳴っていたんです。「We Are The World」じゃないけど、大勢の声で世界平和を歌ってるイメージがあって。「愛を告げにゆこう」という歌詞も最初からありました。
──今の世界に必要なメッセージですよね。
本当にそうですね。ここ数年、僕は世界の平和をさらに強く願うようになっていて。「情勢が不安定になっている」というニュースが多いし、不安を煽られることも多いと思うけど、僕は「平和まであと一歩だ」と勝手に考えているんです。第2次世界大戦のあと、戦争の数は確実に減ってきているし、もう少しで僕たち人類はひとつにまとまるんじゃないかなと。「feel every love」もそのための力になるだろうし──本当に一滴ですけど、この曲をきっかけに、愛や世界平和を願う歌がもっと増えたらいいなと思っています。愛とか平和って、ともすると陳腐な言葉に聞こえてしまうかもしれないけど、今こそ大事にしちゃくちゃいけない。僕らミュージシャンがそれを恥ずかしげもなく歌うことはめちゃくちゃ必要だと思ってます。
アルバム後半はディープなACIDMANの世界へ
──「feel every love」のあと、アルバムの後半はサウンドやメッセージがさらに深まっていくイメージがあります。
マスタリングのときに「前半と後半ではっきり分けよう」と決めました。アルバムの前半(「アストロサイト」「go away」)は勢いのある曲。その後、すでに世に出ている曲(「輝けるもの」「sonet」「白と黒」)があって、さらに「feel every love」で「ここからもっと深い世界に誘います」と宣言する。今の曲順になったのは制作の最後、締め切りのギリギリでしたね。
──ディープな世界への入り口は、8曲目の「1/f」(interlude)です。
最初はインタールードではなく、ちゃんとしたインストにしようと思ってたんです。ありがたいことに僕らはインストゥルメンタルでも評価していただいているので。でも、小手先でインストを作ろうとしている自分がイヤになっちゃって、「アルバムに必要なら作ろう。そうじゃなければ入れなくていい」と考えを変えました。そのときに生まれたのが「1/f」です。「1/f」は風の揺れや木漏れ日など、人が一番心地いいと感じる揺らぎを示す現象なんですが、光をテーマにしたアルバムにも合うし、アルバムの後半に入る前にひと呼吸置いてほしくて。次の「青い風」という曲にもつながってますね。
──ストーリーがありますね。「龍」もこのアルバムのポイントだと思います。まさに龍が空に昇っていく映像が浮かんできて。
ありがとうございます。「龍」はアンビエンス要素が強い曲で、アルバムの中でも特に響きを大事にしながら作った曲というか。始まりはギターと歌なんですけど、頭の中ではピアノだったり、アンビエントな音も鳴っていて……そのときにふと浮かんできたのが龍だった。龍って言葉として非常に強いし、神みたいな存在じゃないですか。曲名に使うべきじゃないよなとも思ったんだけど、浮かんできたものはしょうがない。歌詞にある「灰の中」は、戦争によって終わってしまった世界のことで。そこから龍が舞い上がって、天空を目指して昇っていく。龍は金粉を振り撒いていて、灰の中から子供たちが生まれてくるという、神話みたいなシーンを曲で描きたかったんです。自分のイメージをそのまま形にしたエゴの塊みたいな曲ですが、アルバムに入れられてよかったです。いい音で録れたし、すごく満足しています。
──弦楽器も入ってますか?
そう聞こえる音はギターとベースですね。演奏したときのアタックを減らして、弦のように聞こえるエフェクターを使ってます。普段通りの演奏と音では表現できないので、佐藤(雅俊 / B)くんに「こう弾いてほしい」と伝えて。めちゃくちゃ苦労しながらもやってくれました。
──1つひとつの音の響き、余韻が素晴らしいですよね。大木さんと交流があった、坂本龍一さんの晩年の作品を思い出しました。
坂本さんのことはずっと尊敬しているし、坂本さんの最後の作品(「12」/ 2023年リリース)は最高傑作だと思っていて。とても憧れていますね。この10年くらい、家にいるときはアンビエントばかり聴いているんです。音だけで感情が芽生えたり、不思議な感覚になったり。「龍」のような曲は今後もトライしたいと思っています。
──そして「光の夜」は、yamaさんへの提供曲。この曲をアルバムに収録したのはどうしてですか?
この曲を作ったのは2022年で、ちょうど今回のアルバムに向けて制作を始めた時期なんです。もちろんyamaさんのイメージで作った曲ですが、すごく気に入っていたので、自分たちでもやりたくなって。ACIDMANでセルフカバーした「光の夜」を、僕が監修しているプラネタリウム番組(「星はここにある~music by ACIDMAN~」)で使っているんですけど、試写で見たときも「やっぱりいい曲だな」と。自分で言うのもアレですけど、メロディがとてもいいんです。星に向かってずっと伸びていくようなメロディが書けたと思ったし、何より「光の夜」というタイトルが好きです。
次のページ »
ACIDMANの集大成「あらゆるもの」