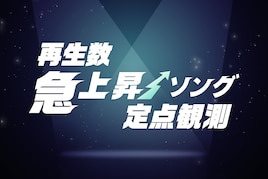Aimerが26枚目のシングル「太陽が昇らない世界」をリリースした。
シングルの表題曲は「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の主題歌。作詞を近藤光(ufotable)、作曲を椎名豪が手がけたこの曲は、人喰いの鬼の始祖・鬼舞辻無惨の本拠地である無限城で戦う鬼殺隊の隊士たちの心情を表現した1曲だ。
2022年に放送されたテレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編のオープニングテーマ「残響散歌」、エンディングテーマ「朝が来る」以来、約3年ぶりとなるAimerと「鬼滅の刃」のタッグ。鬼殺隊の思いを宿した、Aimerの唯一無二の歌唱にインタビューで迫る。
取材・文 / 須藤輝
コントラストのある世界をライブでいかに表現するか
──3月に開催された「Aimer Hall Tour 2024-25 "lune blanche"」のファイナル、僕も拝見しました。お客さんはもちろん、Aimerさん自身もすごく楽しそうに見えたので、相応の手応えがあったのでは?(参照:Aimerの2年ぶりホールツアーが閉幕、“月の満ち欠け”で心の光を表現)
手応えは、すごくありました。今までのツアーもそれぞれに、その時々の力をすべて出し切っていたけれど、今回は今の自分が感じていることや今みんなに伝えたいことを、自分の中できちんと消化したうえで表現できたかなって。例えば「SKYLIGHT」(2023年7月発売の7thアルバム「Open α Door」収録曲)をみんなで一緒に歌えるようにアレンジしたりするというのは、国内のライブではあまりやってこなかったことなんです。でも去年、海外ツアーがあって、そこでお客さんの反応を見ていたら、「残響散歌」(2022年1月発売の20thシングル「残響散歌 / 朝が来る」収録曲)をはじめ、いろんな曲を一緒に歌ってくださっていたんですよ。
──日本と海外でお客さんの反応が違うというのは、面白いですね。
自分としても、「ONE」(2017年10月発売の13thシングル「ONE / 花の唄 / 六等星の夜 Magic Blue ver.」収録曲)という曲を携えた武道館公演から始まった、ライブでみんなと感情を分かち合う場面をより色濃いものにしたかったんです(参照:Aimer初武道館で1万3000人を魅了「これからも皆さんと音楽と生きていきます」)。同時に、私は自分のちょっと尖っている部分もなくしたくなくて。だから最近のライブではやってこなかったピアノ伴奏のみとか、アコースティックなパートを復活させて、よりコントラストの激しいライブを目指しました。新曲の「太陽が昇らない世界」もそうですが、コントラストが激しい曲たちを1人の声で表現するのが自分の音楽の面白いところだと思っていますし、みんなが日々の中で抱えているポジティブ、ネガティブどちらの気持ちも一緒に消化できるライブにできたらいいなって。
──そういう気持ちのコントラスト、あるいはグラデーションを“月の満ち欠け”になぞらえ「lune blanche」(フランス語で“白月”を表す)というツアータイトルにしたとのことでしたね。
そうやって自分が音楽的にやりたいことと、みんなと一緒に音楽の中で体験したいことがちゃんと噛み合ったツアーを作れたという実感があります。
──一般的なアルバムのリリースライブだと、セットリストの大半はニューアルバムの収録曲で占められますよね。しかし、今言った月の満ち欠けをテーマにしたようなコンセプチュアルなライブは何が出てくるかわからないし、僕個人としては、まさか「誰か、海を。」(2014年9月発売の2ndミニアルバム「誰か、海を。 EP」表題曲)を聴けるとは思いませんでした。
私も「誰か、海を。」はまた歌いたいとずっと思っていて、ようやく「ここかな?」という機会が訪れたんです。ほぼピアノと私の2人で、自分としてもすごくスリリングでした。今回のツアーはほとんどすべて2DAYS、つまり1つの会場で2公演だったので、1日目と2日目でセトリをけっこう変えていて。実は「誰か、海を。」は1日目のセトリに入れていた曲で、ツアーファイナルである東京の2日目では「I beg you」(1月9日発売の16thシングル「I beg you / 花びらたちのマーチ / Sailing」収録曲)を歌う予定だったんです。でも、ファイナルだけはどうしても「誰か、海を。」も「I beg you」も歌いたくなって、2曲続ける形になりました。
──「I beg you」のトライバルなアコースティックアレンジも怖くてよかったです。音源化してほしいと思ってしまったぐらい。
うれしいです。アコースティックコーナーのアレンジは、バンドメンバーと一緒にスタジオに入ってセッションしながら練っていて。音数が少ないからこそ、1つひとつの音が映える。そういう音作りを前からやってみたかったんですよね。ライブの全曲でそれをやるのはすごく大変だけれど、いつか実現できたらいいな。私にとってライブはどんどん大切な場所になっているし、今回のツアーの撮りっぱなしの映像を見せてもらったとき「私、こんなに楽しそうにしていたの?」と自分でもびっくりして。先ほど言った、コントラストのある世界をライブでいかに表現するかというのもこれからの自分にとって大事なことだと思っているので、いろんな方法や編成、演出を追求していきたいです。
本能で歌っていく感じでした
──ここからは新曲「太陽が昇らない世界」について伺います。「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の主題歌で、作詞が近藤光(ufotable)さん、作曲が椎名豪さん、編曲が椎名さんと宮野幸子さんですが、曲を作るにあたって作詞作曲のお二人とはどんなやりとりを?
タイアップのお話をいただいてから、私が初めて近藤さんと椎名さんとお話したのは、たぶんレコーディングの少し前で。その段階でデモがこちらに投げられていて、それを録るにあたって「不安な点はあるか」「この曲をどういうふうにしたいか」といった話し合いをする場を設けていただいたんです。この曲の制作自体は近藤さんと椎名さんのお二人で、おそらく何カ月もかけて「ああでもないこうでもない」と試行錯誤されたんだと思います。私のところに来たデモにはナンバリングがされていたんですけど、相当テイクを重ねた形跡があったので。
──だいぶ揉んだんですね。
レコーディングのとき、椎名さんご自身も「最初に作ったデモから、全然違う曲になった」とおっしゃっていて、相当な紆余曲折があったんだなと。私がいただいたデモは、オケは打ち込みの状態で仮のボーカルが入っていたんですけど、その時点で普通のポップスではなかったというか。
──Aメロ、Bメロ、サビという一般的なJ-POPの構造とは違いますね。
私が今まで歌ってきたような曲の範疇の外にある曲だというのが、一聴して伝わってきて。この「太陽が昇らない世界」という曲にどうやって入っていけばいいのか、正直戸惑いました。選択肢がすごくたくさんあったので。
──結果的にAimerさんが選択した歌い方に、僕は食らったといいますか、取材用にいただいた音源を再生して1秒でブチ上がりました。頭サビからレベルメーターのピークを振り切っている感じで。
確かに、そうかもしれないです。
──「熱く熱くなれ」のロングトーン、およびビブラートも攻撃的ですごくいいなと。
デモをいただいてからレコーディングするまでの間に、どういうふうに歌うか自分なりに何度もシミュレーションしまして。そのとき、「太陽が昇らない世界」はライブっぽく歌ったほうがその真価を示せるんじゃないか、いかにエモーショナルに歌うかがシンプルに肝なんじゃないかと思ったんです。普段の私は歌の形をどう整えるかとか、どこでビブラートをかけるかとか、そういうことをけっこう理屈っぽく考えるタイプなんですよ。でも、この曲は今までの私からしたら規格外と言えるし、それゆえに今までのやり方でやらないほうがハマるのかもしれない。なので最終的には、レコーディングブースに入った自分から何が出てくるかに賭けてみました。いわば本能で歌っていく感じでしたね。
炭治郎たちが動いているのを見ながら歌えた
──今おっしゃった本能任せの、出たとこ勝負のようなレコーディングは珍しいですか?
初めてです。
──おお。
もちろん、今までも部分的に「ここは感情の赴くままに」みたいなことはあったけれど、曲の大部分を本能に任せたことはなかったですね。しかも、レコーディングに立ち会ってくださった近藤さんが「アニメの映像をブースで見られるようにできませんか?」と提案してくださって。レコーディングの途中で急遽、ブース内にモニターを用意して歌を録ることになったんです。そしたら、よりライブ感が増したというか。実際のライブでは、その場その場のお客さんやバンドのテンションとがっちり噛み合うボーカルが出てくる瞬間があって、そこにライブの面白さがあると思っているんですが、それに近いことがブース内で起こったんですよ。(竈門)炭治郎たちが動いているのを見ながら歌えたおかげで、その絵にふさわしい熱量を、理屈じゃなくて、自然と調節できました。
──アニメの映像を見ながら主題歌を録ることは、普通はないですよね?
ないです。先に曲を納品して、それに合わせて絵を付けていくのが一般的なので。でも今回は、近藤さんが「歌が最後のピースです」とおっしゃっていて。アニメーターの方々が魂を削って作ってくださったおかげで、曲が流れるシーンの映像はレコーディングの時点でほぼ完成していたんです。それが功を奏した格好になりましたし、私にとっても新鮮な経験でした。
──「ライブ感が増した」とのことですが、ビジュアルのあるなしは歌に影響するんですね。
影響しましたね。この曲は、「メーターのピークを振り切っている」と言ってくださいましたけど、振り切ろうと思えばどこまでも振り切れるし、逆に抑えようと思えばいくらでも抑えられるんですよ。要は、熱量の込め方がボーカリストに委ねられている部分が大きくて。特にサビの「元凶」って、音数で言えば「ターン、ターン」の2音しかないじゃないですか。その「ターン、ターン」の間や後ろをどう味付けするかはボーカリストの好みによるので、意外と自由度が高いし、ボーカルの表現次第で印象が変わるポイントがたくさんあるんです。そういうときに絵があると、どのぐらいのエモーションをぶつけるべきかを測る、1つの指標になりますね。
──今の「元凶」のお話、面白いですね。たった2音の味付けで曲の印象が変わるという。
逆に音数が多かったりテンポが速かったりすると、その合間にできる味付けは限られてくるので、その分「これしかない」というボーカル表現にたどり着きやすい場合が多いんです。でも「太陽が昇らない世界」は、オケは荘厳で展開もドラマチックだけれど、歌にはゆとりがある。だから私も歌っていて面白かったし、ライブ感を重視して歌うことに意味が生まれたように思います。今日お話ししていて気付いたんですが、この曲は、主題歌でありながら作品に溶け込むような劇中歌の要素も持っているというか……。
──ああ。作曲の椎名さんは、梶浦由記さんと共に「鬼滅の刃」シリーズの劇伴も担当されていますね。
そうなんです。そこに、「太陽が昇らない世界」が普通のポップスではない所以があるんじゃないか。ボーカルのライブ感というのも、ロックやポップスというよりはミュージカル的なダイナミズムにつながるところがあるし、そのライブ感の中でいかように感情を表現しても許してくれる懐の深さがある。それはなぜかというと、この曲にはそういった要素もあるからなのかなって、今思いました。
次のページ »
鬼殺隊の心情をより増幅して伝えなければいけない