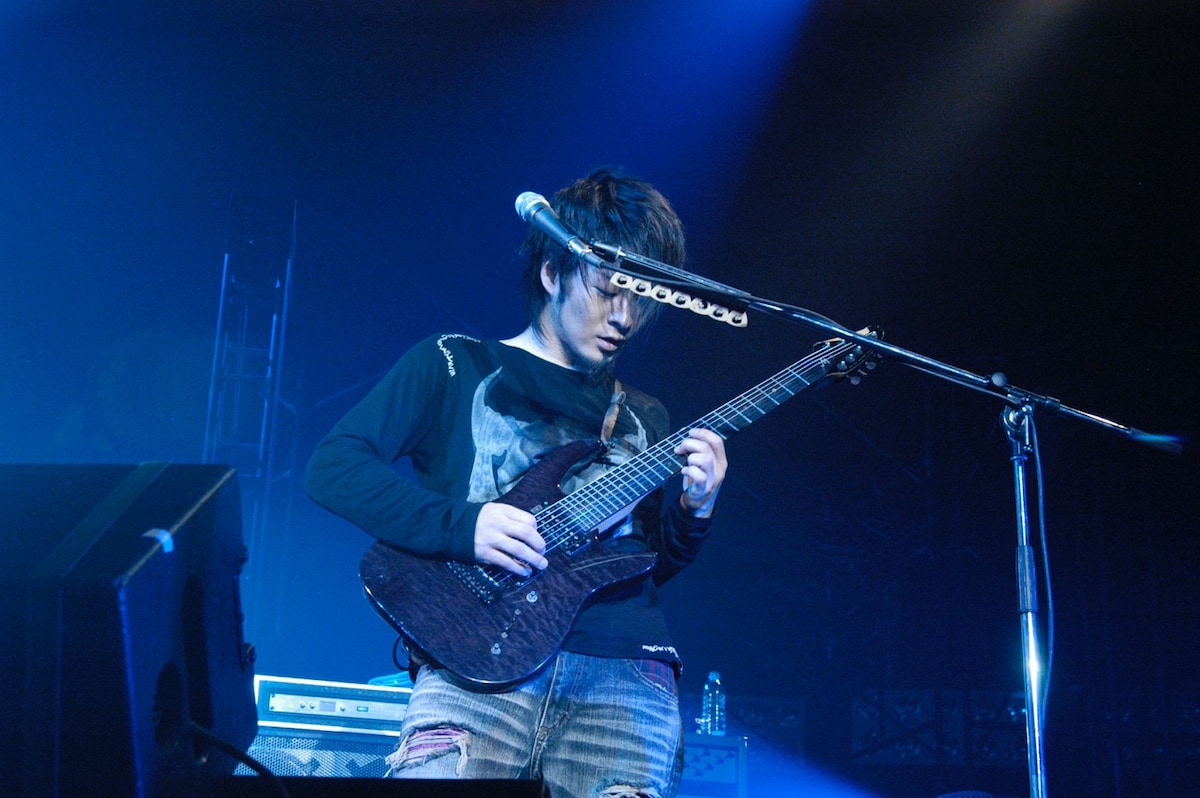1997年に地元茨城で結成され、2022年に結成25周年を迎えたMUCC。アニバーサリーイヤーにふさわしく新作リリースにライブツアーと精力的に活動している彼らが、過去アルバムの再現ツアー「Timeless」の第2弾を3月にスタートさせる。
今回のツアーでフィーチャーされるのは、2005年リリースの「鵬翼」と2006年リリースの「極彩」だ。「最終列車」「ココロノナイマチ」「謡声(ウタゴエ)」「優しい歌」といった、現在もファンに愛され続けている楽曲が生み出された2000年代中盤、バンドのフロントマンである逹瑯(Vo)はいったい何を考えていたのだろうか。当時の心境や、昨年12月に行われた再現ツアー第1弾で感じたことなどを聞いた。
取材・文 / 樋口靖幸(音楽と人)
今はあの頃の自分と笑顔を向き合うことができる
──前回のツアー「Timeless」はどうでしたか? ライブの軸になった「是空」や「朽木の灯」は、発表当時のバンドの内情が刻まれたアルバムでしたが。
やってよかったなと思います。いい意味で時の流れを感じることができたというか、あの頃経験したことすべてに意味があったんだなって。若い頃っていろんなことに一喜一憂するじゃないですか。すぐ絶望するし、頭にくるし。だから当時のMUCCって決して心地いい場所ではなかったけど、今はあの頃の自分と笑顔を向き合うことができるんで。
──当時は歌うこと自体がとてもつらそうに見えましたけど。
そこに時の流れを感じましたよね。昔は自分のことでいっぱいいっぱいだったから、MUCCを聴いてくれてる人たちのことまで気が回らなかったんですよ。自分みたいにキャパオーバーになってる人たちがいて、そういう人と共有できる音楽をやってたという自覚もなくて。
──それが今になって実感できたツアーだったと。
うん。だからすごく心地よかった。あの頃のしんどさにも意味があったんだなって。
──当時は歌の面でも苦労していた印象があります。
そうっすね。曲の構成とか歌のニュアンスは今のMUCCのほうが全然難しいけど、当時の曲はメロディがとにかく複雑だったんで、それを歌い切るのが大変で。まだ知識も経験もないバンドだったから、とにかく無理やり形にした曲が多かった。
──ちなみに「鵬翼」はバンドにとって転機となったアルバムですよね。それまでMUCCの軸となっていた音楽的なイビツさや難解さから解放されて、キャッチーな楽曲が並んだ作品というか。
でも今のMUCCと比べたら「ああ、まだこの頃は難しいことをやりたかったんだね!」みたいな感じに聞こえますね(笑)。今は難しいことをやってもシンプルに聴かせることができるぐらいのスキルがあるけど、あの頃はややこしいものをややこしいまま聴かせちゃうレベルで。キャッチーなメロディはあるにせよ、まだ小難しいことをやってましたね。
──例えば「鵬翼」に収録されているシングル曲として「最終列車」「雨のオーケストラ」「ココロノナイマチ」などがありますが、どれも当時のMUCCにしてはかなりキャッチーな楽曲で、驚かされた記憶があります。
確かにキャッチーではあるけど、シングルとしてはめっちゃ暗いですよ(笑)。当時の俺は「めっちゃ明るいアルバムができた」って思ってたけど、今聴き返してみると「暗いなー」って(笑)。
「ココロノナイマチ」はあの頃の自分にしか書けない
──「鵬翼」の頃から、逹瑯さんは音楽的にも歌詞の面でも、自分のカラーを打ち出すようになりました。
あんまり自覚はしてないですけどね。ただ、もともとシンプルな歌モノが好きだったんで、そういう部分がちょっと前に出てきたのはあるかも。とにかくこの頃は歌詞を書くのが一番大変だったんですよ。シングルの「ココロノナイマチ」から、岡野さん(プロデューサーの岡野ハジメ)と一緒に制作するようになったんですけど、それまでメンバー内だけでジャッジしていたものに、プロデューサーという第三者の意見が入ってきたこともあって。
──例えばどんな意見がありましたか?
「何を歌ってもいい、好きなことを歌えばいい。でも、せっかくキャッチーなメロディがあるんだから、それを生かすような歌詞を書け」って言われて。極端に言うと、もっとメロディが映える歌詞を書けっていうことで(笑)。
──それまでキャッチーさとは無縁のバンドでしたからね(笑)。
キャッチーなメロディにはキャッチーな言葉が必要だと。で、そう言われてすげえムカついたんですよ。言われたことにもムカついたし、それができない自分にもムカついて。でもそのおかげで、絶対キャッチーな歌詞を書いてやる!って気持ちになれたのがすごくよかったし、いい経験になりましたね。あのときそういうことを言ってもらえなかったら、ガキのままだったというか。なんとなく思ったことを言葉にするだけで終わってたんで。
──そんな苦労の末に完成した「ココロノナイマチ」では、どんなことを歌にしたんでしょうか。
あの曲に関しては、茨城から東京に出てきて何年か経って、変わってしまった自分……みたいなことを歌にしてて。「この街に来て、俺は何が変わったんだろう?」っていうセンチメンタルな気持ちですね。今だったら絶対こういう歌詞は書かないというか……なんか若いなあって感じ(笑)。でもMUCCって、そのときそのときのリアルな気持ちが歌になるんで、これはこれで当時の自分にしか書けない曲ですね。
──ラストに収録されている「つばさ」もそうですよね。バンドに対する未来とか希望をMUCCが初めて歌にした曲で。
これは最初ミヤが歌詞を書こうとしてたんだけど、メロディがすごくいいなと思ったんで俺が「書きたい」と言って。で、書かせてもらった記憶があります。
──リリースツアーファイナルの代々木第二体育館のステージでこの曲をシンガロングしていた4人の姿は、今でも忘れられないです。
はははは。そういえば当時事務所の社長が「もっとみんなでシンガロングできるような曲があったほうがいいんじゃないか?」と言ってたらこの曲ができたんですけど、「シンガロングってこういうことじゃないんだけど、これはこれでいいかもね」みたいな感じのことを言われた記憶がある(笑)。
──そういうところも含めて、「鵬翼」は聴く人が気持ちを重ねやすい歌が増えたアルバムだったんじゃないかと。
バンドにとって転機となったアルバムではあると思う。MUCCの世界観を深く掘っていくだけじゃなくて、そこから広がり始めたものというか。「こういう面も実はMUCCにはあるんだよね」という表現のきっかけになったところはある。ただ、それより前のMUCCってゴリゴリしたものとかドロドロしたものを周りから求められてるイメージもあったんで、もしかして物足りなく感じるんじゃないか?という不安もありましたよ。
──ライブにおけるバンドのスキルもこの頃から上がっていきましたし、メンバーそれぞれの音楽的な嗜好も見えてくるようになって。
ほんの少しだけど、俺の歌もマシになってきてるよね(笑)。たぶん、明確に自分が好きなものが芽生え始めたのがこの時期かもしれない。MUCCの世界観にただ合わせたり、MUCCのイメージに縛られて歌うだけじゃなくて、自分の中に「こういうものが好きだ」っていうのが出てきて、自分の中にあるMUCCのイメージをぶっ壊すにはちょうどいいアルバムだったと思います。
次のページ »
最近はバンド自体が明るい