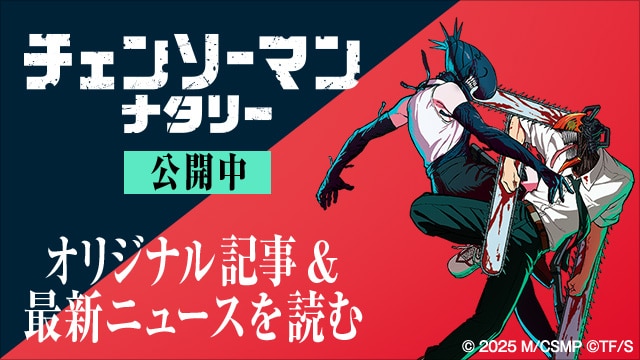マンガとは、“お育ちが出る”もの
──数あるエピソードの中でも、特に今回映画化された「レゼ篇」がお好きだと伺っています。先ほど「チェンソーマン」はホラーだとおっしゃっていましたが、「レゼ篇」にはデンジとレゼの“一夏の恋物語”という側面もありました。その点、これまで恋愛マンガを多く手がけてこられたおかざき先生にはどのように映りましたか?
夜の学校に忍び込んでプールで一緒に泳いだり、花火の下でキスしたり、ある意味では少女マンガの典型とも言えるシーンが多いですよね。それこそ、邦画にもよくあるような夏の青春のワンシーンでもあります。ですが、それがすべて伏線になっていて、最後にはバトルで一気に回収されてしまう。「えっ、これ伏線だったの!?」と驚かされました(笑)。例えばキスシーンも、そこから即バトルの幕開けになりますし、プールで一緒に泳ぐ場面もクライマックスへとつながっていく。少女マンガ的な恋愛要素が少年マンガ的な展開にすべて回収されていく様子が、映画という形で一気に見せられることで、より鮮烈に伝わってきます。まるで横から不意に殴られるような衝撃で、「すみません、侮っていました!」と言いたくなるほどでした(笑)。
──冒頭のデンジとマキマの映画デートシーンも印象的でした。特にマキマの「私も十本に一本くらいしか面白い映画には出会えないよ」から始まるセリフについて、同じく映画好きのおかざき先生はどう思われましたか?
とても好きなセリフです。人生の中で心に残る映画なんて、ほんの数本あればいい。その数本を胸に抱えて生きていける。そういうものだと思うんです。実際、人生を変える映画だってありますから。でも、年を重ねると、同じ映画でも最初に観たときとまったく違う印象を受けることが増えてきました。“映画に無駄はない”と言いますか、若い頃はあんなに胸を躍らせたのに今ではそうでもない……ということもあれば、その逆もあります。
──具体的にはどのような出来事だったのでしょうか。
例えば会社員時代、まだまだ若手だった私は「絶対にタランティーノを観てくれ! 本当にすごいから!」とか、「『トレスポ(トレインスポッティング)』は観ないと損ですよ!」と、上司に熱弁して薦めたことがありました。ところが実際に観た上司の反応は「うーん」といまひとつ(笑)。当時は不思議で仕方なかったのですが、今になってみると、あれは若い私たちにとって「ようやく自分たちのテンポの映画が出てきた!」という歓びだったんだなと。落ち着いた映画に慣れ親しんできた上司にとっては、きっと響かなかったのでしょう。そういうことが、30年の時を経てようやく理解できました。
──映画の当たり外れは、世代や時代によっても変わる。だからこそ、映画との出会いは尊いものなんですね。
そう思います。そして今、私が描いているマンガは、結局は昔観た映画や作品の寄せ集めのようなものだと思うんです。……これはいろいろなところでお話ししているのですが、マンガというのは“お育ちが出る”ものなんですよ。
──お育ち!?
マンガ家は、作品をすべて1人で作りあげます。カメラワークも演出も、スタイリングも、音はついていなくてもリズムまですべて自分で組み立てていく。だから、自分がこれまでに食べてきたもの、経験してきたものを出さないと描けないんです。それによって「この人はこういうものを食べて育ってきたんだな」という“お育ち”が、否応なく作品ににじみ出てしまう。マンガとは、そういった怖さを持った表現だと思います。
──映画が大好きなおかざき先生は、これまでに“食べてきた映画”が作品ににじみ出てしまうと。
そうなんです。そのせいか、これまで描いてきたマンガは「阿・吽」を除いて、ほとんど実写映画化のお話をいただいてきました。でも逆に、アニメ化のお話は一度も来ないんです。これはやはり、私自身がアニメをあまり“食べて”こなかったからだろうと感じています。昔、ゆうきまさみ先生の原稿の色付けをお手伝いしたことがあったのですが、そのとき構図の大胆さに衝撃を受けました。「なんて広い構図なんだろう」と驚いて先生に伺ったら、「いや、無意識にずっとこういう構図なんですよ」とおっしゃっていて。よくよく考えると、それはアニメ的な構図だったんです。
──アニメ的な構図とはどういったものを指すのでしょうか?
アニメではマンガと違ってキャラクターが実際に動くので、例えばドアから入ってくる動作などをきちんと画面に収めるために、余白を含めて広く構図を取る必要がある。ゆうき先生はまさにアニメ第一世代としてアニメに親しんでこられた方だからこそ、その感覚が自然とマンガに息づいているのだと気づきました。一方で私はデザイナー出身なので、どうしても構図を端正に整えてしまう。だからこそ、アニメ的な広がりのある構図はあまり描けない。そういう意味でも、自分が“何を食べてきたか”がマンガに如実に表れるのだと、改めて実感しました。
マンガ家はみんな“悪魔”なんですよね
──そう伺うと、マンガを読む目線が変わってきそうです。
ほかにもね、すごく印象的で怖い体験がありまして……。とある作家さんのお宅に遊びに伺ったときに、「うふふっ」てうれしそうにノートを見せてくださったんです。そこには、気になったマンガ家の作品を研究のために何話分も模写したものがぎっしり! 大学ノートが何冊も積み重なっていて、「おかざきさんのも研究させてもらいましたよ」と言われて、もう本当に背筋がぞっとしました(笑)。マンガ家はみんな“悪魔”なんですよね。あらゆるものを貪欲に食べて、自分の糧にしていく。1話をまるごと写してみると、その作家がこれまで何を食べてきたのかが見えてくるのだそうです。つまり、1話の中にはその作家の“お育ち”や食べてきたものがすべて詰まっている。そして、それをさらに“研究して全部食べちゃう”作家さんもいるんです。
──恐ろしくもあり、同時にマンガという表現の奥深さを改めて思い知らされるエピソードですね。ちなみに、藤本タツキ先生は何を“食べて”こられた方だと思いますか?
そんな! 下衆の勘ぐりみたいなことを!(笑) でもおそらく、「チェンソーマン」は絶対に「テキサス・チェーンソー・マサカー(原題)」から来ているでしょうし、藤本先生は本当に膨大な数の映画を“食べて”こられた方だと思います。私も映画好きですが、実はスプラッタ系の痛そうなホラーは苦手で避けてしまうんです。でも藤本先生はきっと、そういうジャンルまで含めて幅広く観尽くしている気がします。
──ファンの間でも、どの映画のオマージュなのか?と盛り上がることが多いようです。
これまでに食べてきた映画をあえて引用しているシーンも随所に見受けられますよね。しかも藤本先生の場合、食べたものをあえて消化しきらずに出しているような……。「わざとそのまま出しておくぜ」という置き方をされているようにも見えるんです。それを私たち読者が必死に拾って、「あ、これは〇〇の味だ!」と感じながらもぐもぐ味わっているような。そういう遊び心がある。とはいえ、週刊連載を続けながら映画を観る時間を確保するのは並大抵のことではありません。作業中に流し見する方もいますが、私は映画に見入ってしまって手が止まるタイプなので到底できない(笑)。だからこそ、あれほどお忙しい藤本先生がどうやって映画を観る時間を捻出されているのか、むしろ私の方が伺ってみたいくらいです。
──本当に映画がお好きなことが伺えますね。
先ほど、「チェンソーマン」は理不尽さを凝縮したホラーマンガであり、人はその理不尽さを物語として受け止めることで、“支え”や“耐性”へと変えていけるのだというお話をしました。藤本先生もまた映画を深く愛する方だからこそ、ホラー映画から多くを受け取り、癒されてきたのではないか……そう感じています。
プロフィール
おかざき真里(オカザキマリ)
長野県生まれ。マンガ家。高校在学中からイラストやマンガを投稿し、多摩美術大学卒業後は広告代理店の博報堂に入社。デザイナー、CMプランナーとしてキャリアを積みながら、1994年にぶ~け(集英社)にて「バスルーム寓話」でデビューする。2000年、結婚を機に博報堂を退職。「彼女が死んじゃった。」「渋谷区円山町」「サプリ」と、映像化作品を次々と生み出した。2014年から2021年にかけて月刊!スピリッツ(小学館)で「阿・吽」を連載。2017年からフィール・ヤング(祥伝社)で「かしましめし」、2022年から週刊ビッグコミックスピリッツ(小学館)で「胚培養士ミズイロ」を連載中。「かしましめし」は2023年にドラマ化を果たした。
関連特集

- 米津玄師「IRIS OUT / JANE DOE」インタビュー|2曲に刻んだレゼの魅惑とその足跡、宇多田ヒカルとの制作秘話を語る

- 川村元気が劇場版「チェンソーマン レゼ篇」を、林士平が「8番出口」を互いに絶賛!話題作を手がける2人の初対談

- 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」牛尾憲輔インタビュー|「レゼ篇」劇伴に宿した“振り幅のダイナミクス”
※10/03 13:00追記:記事初出時、「テキサス・チェーンソー・マサカー(原題)」のタイトル名に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
2025年10月9日更新