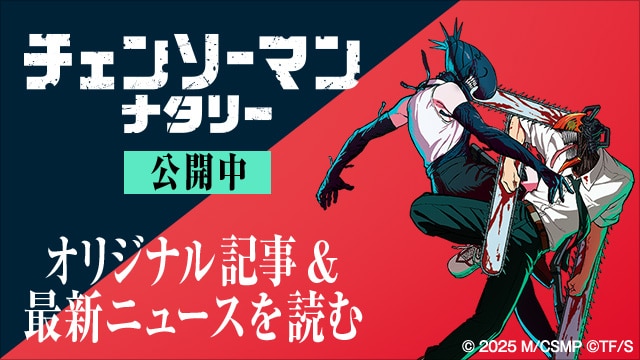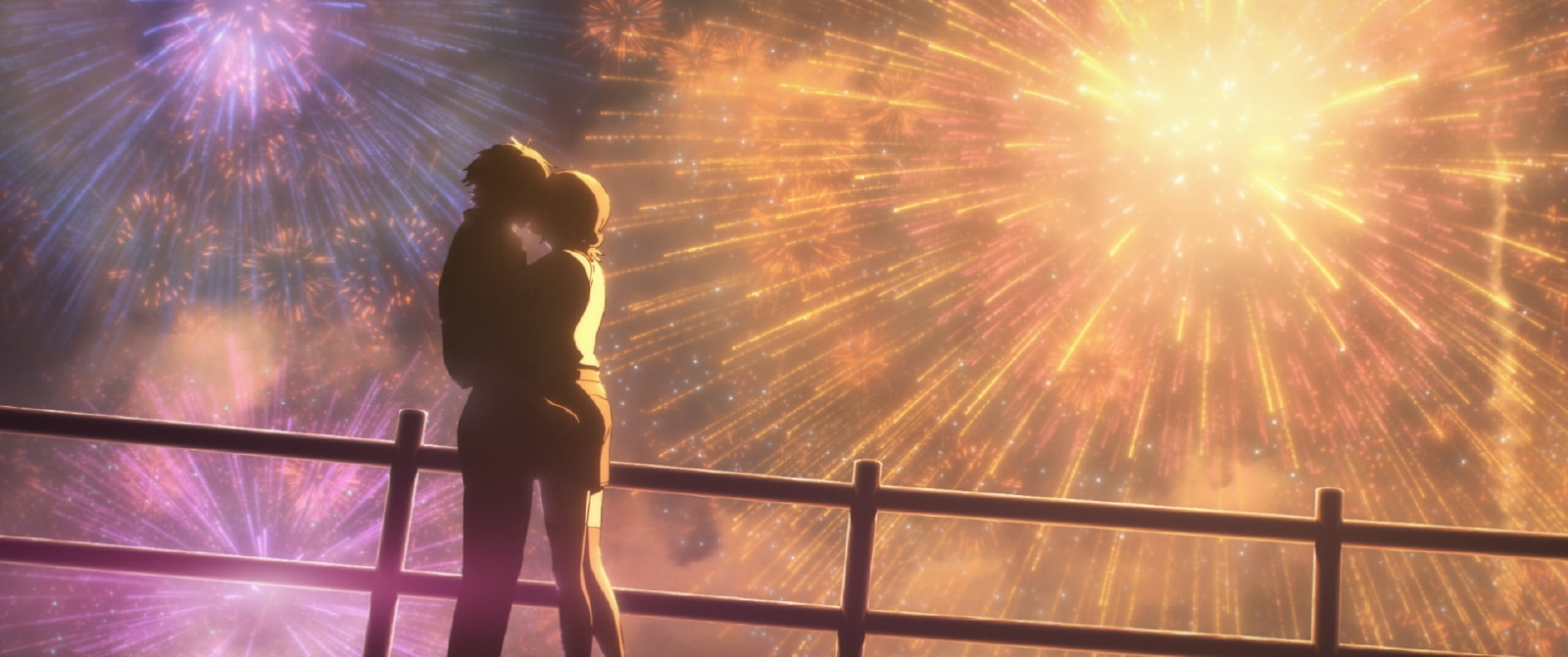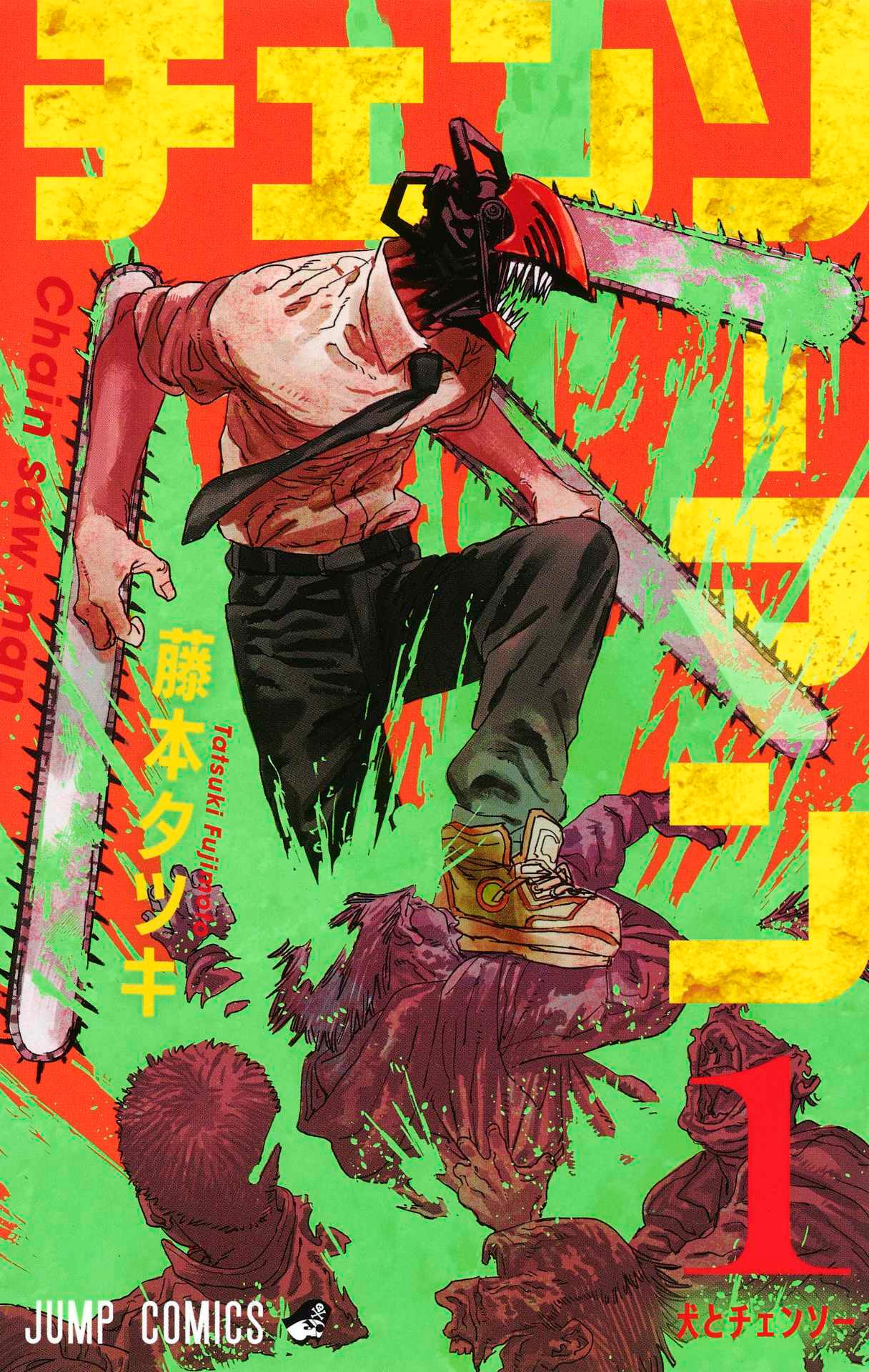現在、全国で公開中の劇場版「チェンソーマン レゼ篇」。公開から11日間で観客動員200万人、興行収入30億円を突破し、大ヒットを飛ばしている。同作は藤本タツキが描く「チェンソーマン」を原作に、連載当初から屈指の人気を誇るエピソード「レゼ篇」を映像化。物語は、悪魔の心臓を持つ“チェンソーマン”となり、公安のデビルハンターとして活躍する少年・デンジが、ミステリアスな少女・レゼと偶然出会ったところからスタート。デンジはレゼに翻弄されながら、予測不能な運命へと突き進んでいく。
ナタリーでは現在、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の特設サイト「チェンソーマンナタリー」を展開中。その一環として、「チェンソーマン」で「レゼ篇」が一番好きだというマンガ家・おかざき真里にインタビューを実施し、映画を鑑賞した感想を聞いた。かつて広告代理店でCM制作に携わっていた経緯を持ち、映画鑑賞も日々の趣味だと話すおかざきの目に、「レゼ篇」はどのように映ったのか。なお本記事には物語の顛末に触れる部分があるため、映画鑑賞後に読むことをオススメする。
取材・文 / ちゃんめい

座っているのがもどかしい! 映像と音楽が融合した“アニメーションの最高峰”
──まずは劇場版「チェンソーマン レゼ篇」をご鑑賞されてみて、率直にどんな感想を抱きましたか?
よく耳にする表現ではありますが、それでもやはり「これは劇場で観ないともったいない!」と思いました。今回は試写室での鑑賞でしたが、できればIMAXや4DXで体感したいですし、もし可能ならスタンディングOKな応援上映のような形で観てみたいとも思いました。
──スタンディングOKな応援上映、とは具体的にはどのような感覚だったのでしょうか?
私自身、ロックミュージシャンのライブが大好きでよく足を運ぶのですが、今回の劇場版はまさにライブの熱気を思わせるものでした。映像と音楽が全身に迫ってきて、座っているのがもどかしいほど。アニメーション映画としてのフォーマットを踏みつつも、冒頭から圧倒的なクオリティで、とにかく映像と音楽の融合が素晴らしい。「アニメーションの最高峰を観ている!」という感覚が冒頭から強烈に押し寄せてきました。
──オープニングで米津玄師さんの主題歌「IRIS OUT」が流れた瞬間、思わず体が揺れてしまいそうでしたよね。
そうなんです。もうじっとしていられないほどで、ライブで思わず跳ねたくなるような高揚感でした。そして、特に盛り上がったのはバトルシーンですね。原作を読んでいたので「ここから見せ場がくる」とわかってはいたのですが、そこでまさか米津さんの楽曲ではなく、マキシマム ザ ホルモンさんの「刃渡り2億センチ(全体推定70%解禁edit)」が流れるとは! あの瞬間、縦ノリの熱気に包まれて「みんな飛べー!」と煽られているようで、思わず座ったまま「うおーっ」と声が出そうになりました(笑)。
──確かに、そのシーンは映像と音楽の勢いが重なって、まさにライブを体感しているかのようでした。
さらに感動したのは、音楽と映像、そして効果音が1つひとつ完璧にシンクロしている点です。私自身かつて11年間CM制作に携わっていたのですが、「これはさぞ音を入れる作業が楽しかったに違いない」と思わず想像してしまうほど。作り手の楽しさが画面からも伝わってきて、観ているこちらまでワクワクさせられる思いでした。そして声優さんの声。クライマックスのバトルシーンは、いったいどうやって収録されたんでしょうね? 音を後から合わせているのか、それとも音と同時に収録しているのか……。いずれにしても、声そのものが音響の一部として組み込まれていて、まるで1つの音になっているように感じました。
──レゼの「ボンッ!」とかまさに。タイミングが気持ちいいほど、背景音楽とマッチしていましたよね。
本当にカッコよく決まっていて、「こんなの絶対に勝てないじゃない!」と思わされるほどでした。特にレゼの「ボンッ」という音は単なる効果音ではなく、世界観そのものを背後から操っているような迫力があって。音と視覚のすべてが一体となることで、レゼの武器のすさまじさが際立っていたと思います。そして何より胸を打たれたのが、最後に彼女が口にする「私も学校行った事なかったの」という一言です。映画で観ると、このセリフの響きが一層強く心に残りました。彼女は本当は、ごっこ遊びでもいいからデンジと一緒に学校へ行ってみたかった。その思いがにじみ出ていて、胸がぎゅっと締めつけられました。
──レゼの声を担当されている上田麗奈さんの演技力も相まって、一層心に迫るシーンになっていたと思います。
レゼは最初の登場からどこか“演技をしている”雰囲気が漂っていて、その不気味さにぞっとしました。電話ボックスで出会って笑い出す場面なども、まるで本当に訓練を受けた芝居のような印象があって。けれど、最後に発せられるあの一言だけは本音として響く。その瞬間、“声”に完全にやられました。もちろん、絵もストーリーも素晴らしいのですが、やはり曲や背景音、そして声……。音の力が本当に際立っていたので、改めてこの作品はぜひ音響設備の整った劇場で観てほしいと思います。
過渡期だからこそ生まれる、アニメならではの凄味がある
──ほかに、劇場版になったことで一層刺さったシーンはありましたか?
レゼが公安対魔特異2課の訓練所に襲撃してきて、副隊長と野茂さんが助太刀に入る場面ですね。もちろん原作を読んでいるのでその後の展開は知っているのですが、それでも「ああー!」とショックを受けずにはいられませんでした(笑)。マンガでは自分のペースでどんどんページをめくっていけるのに、アニメ映画では観客としてきちんとその一場面を“見せられる”。「ああ、よかった、助かった!」からの「……殺されてしまった!?」という落差が、より鮮烈に胸に迫ってきました。
──音の魅力を熱く語っていただきましたが、同時に絵の美しさも際立っていたと思います。どのようにご覧になりましたか?
花火やプールの水の表現などは本当に圧巻でした。特に前半のシーンでは、キャラクターの影などを必要以上に描き込みすぎず、あえて抑えたトーンでまとめていたように感じました。だからこそ、花火や雨、水といった自然の描写が際立ち、驚くほど繊細で美しかった。
──後半の車上でのバトルシーンも、映像ならではの迫力がありましたよね。
そのシーンも、まさにアニメならでは。技術の発展がめざましい昨今ですが、AI技術がどれほど進歩しても再現できないのではと思うほどの迫力がありました。今は手描きやCGなどさまざまな技術がミックスされている“過渡期”だと思うのですが、その過渡期だからこそ生まれる、アニメならではの凄味を強く感じましたね。実は私は子供の頃から、アニメを見ていても作画に夢中になる、いわゆる“作画オタク”でした。友達が声優の話で盛り上がっている中で「今日の作画監督は〇〇さんだったね!」なんて話しても、場がシーンとしてしまって(笑)。その頃からずっと、アニメを観るうえで作画に惹かれる感覚が強かったんです。だから今回も、絵の力にぐっと引き込まれました。最高峰の作画が、あの圧倒的な音と組み合わさって体験できる。映画としての感動はもちろんですが、まるでフェスやイベントに参加したかのように、約1時間半その場に立ち会った。そんな特別な体験をした気がしました。
「チェンソーマン」はまさに“ジャパニーズホラー”
──ここからは「チェンソーマン」という作品そのものの魅力について伺っていきたいと思います。おかざき先生は、かねてより藤本タツキ先生にご注目されていたそうですね。
実は私、試写会や試写後のインタビューは普段あまりお受けしないんです。仕事と子育てでなかなか都合がつかなくて……。もちろんデータをいただいて自宅で観るという選択肢もあるのですが、私は映画が大好きなので、だからこそ自宅でデータを観るのはどうしても“もったいない”と感じてしまって。それでも今回は、ずっと強く惹かれていた藤本タツキ先生、しかも大好きな「チェンソーマン」ということで、ぜひにと思いました。ちょうど一週お休みをいただけるタイミング(※1)でもあったので、朝イチでネームをすべて出し切ってから今回の試写会に臨んだんです(笑)。
(※1)現在、週刊ビッグコミックスピリッツ(小学館)で「胚培養士ミズイロ」を連載中。
──藤本タツキ先生を知ったのは、どの作品でしたか?
多くの方と同じだと思うのですが、ネットで1話が大きく話題になった「ファイアパンチ」です。案の定、1話を読んで本当に驚きましたし、初めて読んだときはあまりにも完璧すぎて「こんなに編集さんの手が入っている新人の第一作を、連載デビュー作として世に出していいのだろうか?」と思ってしまったほどです。見開きの使い方やストーリーテリングの運び方があまりにも素晴らしくて、「この作家さんはこの先どうなるんだろう」と心配になるほど。それくらい鮮烈さと完璧さに圧倒されました。
──その後もデビュー作に負けないほど、次々と話題をさらう作品を発表されていますよね。
「チェンソーマン」はもちろん、「さよなら絵梨」「ルックバック」といった短編まで、発表される作品は次々に圧倒的で素晴らしい。だからこそ、あのとき感じた衝撃は編集者の手によるものではなく、藤本先生自身が最初から持っていた力なのだと、改めて実感しました。発表する作品がことごとく圧倒的で、本当にすごい方だと思います。
──「チェンソーマン」を初めて読んだときは、どんな印象を受けましたか?
最初は「ダークヒーローっぽいな」とか、「ジャンプだからここまでできるんだな」と思いながら読んでいたのですが、読み進めるうちに、私の中で「チェンソーマン」はどんどん“怖い作品”になっていきました。私にとっては、まさにホラー映画……ジャパニーズホラーのように映ったんです。
──と言いますと……?
ジャパニーズホラーの怖さとは、一言で言えば“理不尽な目に遭うこと”。努力を積み重ねても報われず、すべてが一瞬で踏みにじられてしまう、その理不尽さこそがジャパニーズホラーの恐怖の根源だと思っています。私は子を持つ親として、子供たちができるだけ理不尽な目に遭わないようにと願っています。世の中はいいものであってほしいし、努力がきちんと報われ、積み重ねが無駄にならないものであってほしい……。だからこそ、「チェンソーマン」に描かれる理不尽さはより強く胸に迫ってきます。
──なるほど。
登場人物たちは大人びた一面を持ちながらも、どこか幼さを残している。その彼らが容赦なく理不尽に巻き込まれていく姿は本当に恐ろしく、今回の「レゼ篇」もまさにそうでした。戦いそのものが理不尽であり、それを受け入れていることすら理不尽。構造全体が理不尽、つまりホラーなんです。だから私にとって「チェンソーマン」は、ただのバトルマンガではなく、ホラーマンガそのもの。しかも、その理不尽さをスタイリッシュに、カッコよく提示してくるからこそ、一層恐ろしく感じます。
──「チェンソーマン」はホラー……とても腑に落ちました。
ホラーという物語は、理不尽な現実とのバランスをとるために存在しているのだと思います。理不尽さを物語として受け止めることで、それを“支え”にしたり“耐性”にしたりできる。ホラー小説やホラー映画が好きな人は、きっと世の中の理不尽に対して自分なりの癒しを得ているのではないでしょうか。そして「チェンソーマン」には、その理不尽さが凝縮されています。だからこそ圧倒的に怖いのです。
次のページ »
マンガとは、“お育ちが出る”もの
2025年10月9日更新