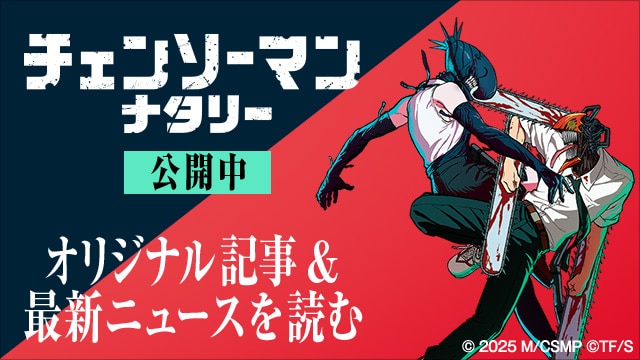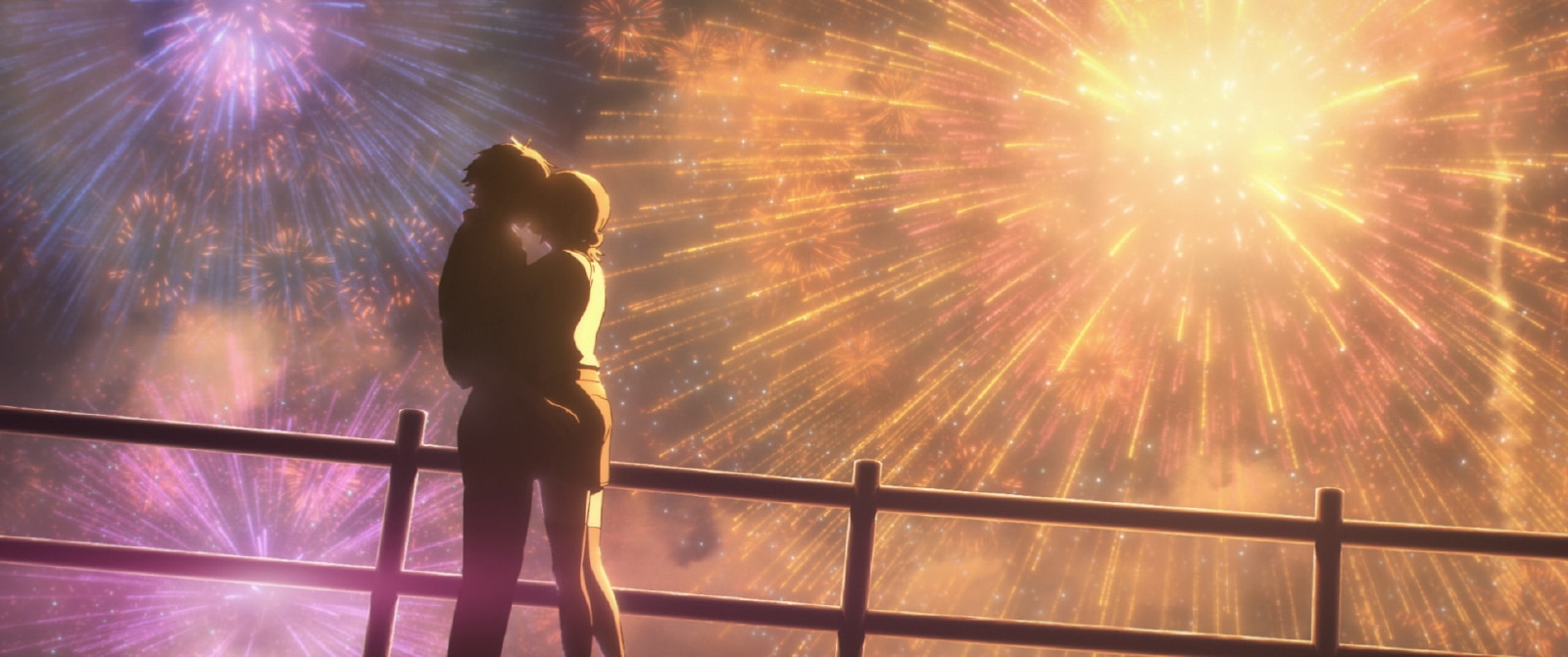劇場版「チェンソーマン レゼ篇」が全国の劇場で公開されている。
藤本タツキのマンガ「チェンソーマン」を原作に、作中屈指の人気エピソード「レゼ篇」を映像化した今作。悪魔の心臓を持つ“チェンソーマン”となり、デビルハンターとして活躍する少年・デンジが、偶然出会ったミステリアスな少女・レゼに翻弄されながら、予測不能な運命へと突き進んでいく。
この作品を音楽で彩るのは牛尾憲輔。テレビシリーズから引き続き劇伴を担当した牛尾は、テレビシリーズのときとは異なるアプローチで劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の音楽を作り上げたという。
映画の公開を記念して、音楽ナタリーでは牛尾にインタビュー。劇伴制作の背景をたっぷりと聞いた。
取材・文 / 秦野邦彦

「なんだかもうメチャクチャだ!」を音楽に
──牛尾さん単独でのナタリー登場は2016年のアルバム「the shader」(agraph名義)リリース時以来ということで、「チェンソーマン」の劇伴についてお話を伺うのは今回が初となります。まずは、2022年のテレビシリーズの音楽を依頼されたときの印象からお聞かせください。
緊張しました。「週刊少年ジャンプ」作品(※第2部からは「少年ジャンプ+」で連載中)という王道のど真ん中……まあ、改めて読み直すと「これ本当に王道?」って気もするんですけど(笑)、巨人の4番みたいな打席を任されて、普段やってる自分の音楽性を鑑みても「私でいいんですか……」と。実際できるかどうか迷ったんですけど、大塚学社長をはじめMAPPAの皆さんがとても熱意を持って口説いてくださったので「一緒にがんばりたい」と思いましたし、原作を読んだときに「これめちゃくちゃだな」と感じたんですけど、それがすごくよくて。この印象を楽曲のコンセプトに据えたら楽しそうだなと思ったのがお受けした理由です。
──テレビシリーズはコミックス5巻中盤までの内容ですが、音楽制作はどのように進められたんでしょうか?
まずは「チェンソーマン」という作品の根底に流れるものをすくい上げる、土台になるコンセプトを作ろうと思いました。「レゼ篇」のセリフにも出てきますけど、「なんだかもうメチャクチャだ!」というのはこの作品を代表する言葉だと思うんです。ヒロイン級の女の子が全員デンジを殺そうとしているとか、毎ページくらいの勢いで誰か死んじゃうとか。デンジの思考回路もぶっ飛んでるし、その意味のわからなさみたいなものが根底にあるというのがまず1つ大事で。それを忘れなければ何をやってもいい……って言い方は変ですけれども、そのうえにいろんなキャラクターを置けば、今まで僕が培ってきたけれども作ってこなかった音楽ができるなという感覚がありました。僕は劇伴をやるときは毎回「こういうことがやりたいです」というイメージアルバムを作って提示するんですけど、今回もそのようにしたらスタッフの皆さんがすごく好印象を示してくれたので、そのまま作っていった感じです。
──LAMAのメンバーでもある田渕ひさ子さんがギターで参加した「edge of chainsaw」というインダストリアルな楽曲が印象的に使われていましたが、牛尾さんとしては珍しいアプローチだと感じました。
「edge of chainsaw」は制作作業が進み、資料もいろいろと上がってくる中で作った曲で。チェンソーマンがカッコよく登場するときに「チェンソーマン!」みたいなテーマ的な曲が1つあったほうがいいな、欲しいなと思ったんです。僕は普段メロディというものが好きではないのですが、珍しくやりたくなってしまって。原作含め、スタッフの皆さんと作ってきたものに背中を押してもらって書いた感じです。田渕さん本人はチェンソーというより日本刀みたいな人ですが、ああいう切り裂く感じがすごく合うので、ぜひお願いしたいと思って。今回の「レゼ篇」でもたくさん弾いてもらっています。
もし自分が「レゼ篇」の音楽をやるなら
──テレビシリーズでは本作の音楽制作のために開発されたAIツールをフィーチャーしたことが話題になりましたが、「レゼ篇」でもそういう技術的な挑戦はされたんですか?
実は、今回AIは以前作った素材以外ほとんど使ってないんです。というのも、「チェンソーマン」の劇伴の話をいただいたときに、けっこう早い段階で「『レゼ篇』は映画がいいんじゃないか」という仮の話が出ていたんです。そういう話もある中で、もし自分が「レゼ篇」の音楽をやるなら大編成のオーケストラを使いたいと考えていました。なので、ロードマップとしてテレビシリーズでそういうことをやるのは我慢しようと思って、あまりオケを使わなかったんですよ。物語の序盤は、まだ“最初の一歩”でいい。そこから「レゼ篇」になり、その先はもっと様相が変わっていくんですけど、そういったサーガをとらえたとき、今回の「レゼ篇」は第1部の中でも突出して叙情的なパートなので、AIでカオティックな部分を出すよりも情緒に委ねたほうがいいと思って、カオティックな要素をトゥーマッチにしないように気を付けていました。
──物語が進行していくのに合わせた構想が最初の時点からあったんですね。
テレビシリーズはそこまで恋愛的な要素が強くないですけど、今回は「初恋」「夏」といったはかないテーマで曲が作れるという部分がまず1つあり、さらには技術面でも大きい音から小さい音まで使っていいという劇場映画だからこその要素も強かったです。大編成による音楽を鳴らしてしかるべき環境ですし、もっと言うと今の劇場のスピーカーってとても音がいいので、ものすごく些細で繊細な音も使えるわけです。その振り幅のダイナミクスは、今回の「レゼ篇」においてすごく効いてくる要素だし、テレビシリーズで作った土地に種を植えて、開いた“花”が大方の想像とは違う姿になるというのは非常に大事なポイントだと思います。
レゼのバックグラウンドを示すために
──今回の「レゼ篇」の音楽はどのように制作していったんでしょうか。
全体としては、“ボーイ・ミーツ・ガール”に始まり、マキマさんとレゼとの間に揺れるデンジの葛藤とプールのシーンでのトランジション(カットとカットを自然につなぐための効果)から、チェンソーマン対ボムっていうのが大きな流れです。繊細に小さく始まった音が叙情的な意味でプールのシーンで花開き、そこからはバトルという流れなので、音色とか楽器の使い方、コードといった音楽的な部分は尻上がりに攻撃的になっていくんですけど、マキマさんとデンジが映画館デートをする序盤のシーンのラスト、2人が1本の映画を見つけるシーンでかかる「our films」ってタイトルの曲はすごく繊細に作れたと思います。あれはもともと「映画内映画のサントラとして作ろう」と𠮷原達矢監督、音響監督の名倉靖さんと話していたんですけど、最終的に映画内映画のサントラなのか、それを観ているデンジとマキマに当たっている劇伴なのかわからないぐらいがちょうどいいかなと考えました。結果として一連の映画のシーケンスから現実に戻っていくトランジションになったので、よい発想だったなと思います。
──プールのシーンで流れる「in the pool」が切なくて非常に印象的でした。
あの曲は、もともとレゼのテーマ曲の1つとして作ったものです。2023年12月の「ジャンプフェスタ 2024」で劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の制作決定が発表された際のトレーラーの曲は、のちに「Reze」というタイトルになる曲の原型なんですが、その時点でプールの曲の原型もできていて。この2曲を並べて「どっちがレゼの曲としていい?」と𠮷原監督、プロデューサー含めみんなに選んでもらったんです。僕と𠮷原監督はプールの曲がいいと思ったんですが、ほかのプロデューサー陣は「これはレゼをすごく表してると思うけど、初歩としてはディープすぎるからこっちじゃない?」と。「なるほど、それは確かにそうかも」と納得して、多数派に選ばれた曲がのちに「Reze」になるんですけど、僕と𠮷原監督はプールの曲のことを“俺らの曲”と呼んで「“俺らの曲”は絶対本編で使おう!」とずっと話していました(笑)。
──それくらい思い入れがあったと。
最終的に「in the pool」は一連の大きい組曲になりましたけど、最初はもっとこま切れになる予定だったんです。レゼの「少し冷やしますか」というセリフからの流れがあって、プールのシーンがあって、効果音で終わるみたいなことをスタッフに言われていたんですけど、僕としては組曲にして大編成のオーケストラでやりたいと思っちゃったんですね。それをスタッフに提案して、打ち込みでモックアップを作って聴いてもらったらすごく好評だったので、そのまま作らせてもらいました。
──オーケストラアレンジはどのように進んだんですか?
今までで一番規模の大きい編成でしたね。単純なものは打ち込みでできちゃうんですけど、もともとの自分のベースがテクノだということもあって弦の譜面を書くところまではできないので、ピアノでメロと構造を書いたものをアレンジャー兼オーケストレーター(オーケストラの各パートごとにアレンジして楽譜に仕上げる音楽家)の方にお渡しして作ってもらいました。そういうときも渡しっぱなしにせずスタジオで一緒に作業するんですけど、僕の変な発想も面白がってやってくれる仲間だったので、すごく助かりました。あとこれは話すと長くなるんですが、プールに入ってレゼとデンジが向き合ってからは、その後ろでずっと近現代ロシアのピアノコンツェルトのような響きが鳴っているんです。レゼのバックグラウンドにある冷たい気候みたいなものが忍び寄ってくる感じを描きたくて。オーケストレーターの方と打ち合わせしながら作っていったんですが、とてもうまく組み込んでくださって、とてもいいシーケンスになりました。最初はドキドキする繊細な曲だけど、後半重苦しい寒さがやってくる……レゼの背景を表現できていて、功を奏したかなと思います。
──レゼがロシア語で口ずさむ「ジェーンは教会で眠った」(藤本タツキ作詞、牛尾憲輔作曲)にもハッとさせられました。
あの歌詞は原作に出てきた通りで、吹き出しに音符マークが付いているからたぶん歌だろうということで僕が作曲したんですけど、ロシア語なので大丈夫かなという不安もありました。知らない言語だと変なところで文章を切ることもありうるじゃないですか。例えば「うしお・けんすけ」って歌詞があったとして「うしおけ・んすけ」という譜割になると意味がわからなくなってしまうので、そうならないよう事象的な意味でも整合性を取りつつ、ロシア民謡みたいな雰囲気で、かつ映像の尺的に80秒ぐらいであの量の歌詞を入れるというミッション・インポッシブルをこなさなくちゃいけないから大変だったんですけど、レゼ役の上田麗奈さんにすごく上手に歌っていただいてよかったなと思いました。サントラにも入っているので、そのまま素でも聴いてほしいです。
──ロシアの音楽って、構造的に説明しようとしても難しいですよね。
トロイカやゲームの「テトリス」のオープニングテーマ(「コロブチカ」)など有名なものもいくつかあるんですけど、楽理的にわかりやすく明確な特徴があるわけではないんですよね。あまり音が動かなくてもの悲しい、みたいな。どうすればロシアっぽくなるかの試行錯誤はけっこう大変でした。そこから祭のシーンで流れる「slow summer eve」に関しては僕がとても好きな雰囲気の音色を上手に作れたし、トランジションで不穏な空気に変わっていく流れもよくできたんです。ピアノの音をサンプリングして、次第にハードなテクノ(「sweet danger」)になっていくという。
次のページ »
バトルシーンの“ライブセット”
2025年10月9日更新