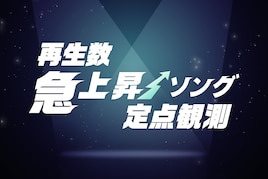人を分断する表現はしたくない
──そもそも、「フィリップ」の物語がご自身の歌とフィットするイメージが湧いたのはどうしてだったんですか?
中野 今までもけっこうなアップ&ダウンがあって、でも「悩んでいたことは幻だったのかもしれない」と思える部分もある。心のスイッチ1つで世界は違って見えることもあるのかもしれない。それに気付くのって、楽しいことだから。
──中野さんがおっしゃったことは、以前のインタビューで常田さんがmillennium paradeのことを「百鬼夜行」と例えていたことに通ずる話だなと思って。はぐれものたちの居場所だったり、オルタナティブな者が存在表明をできる場所だったり……オルタナティブと呼ばれる価値観をそのままメインストリームに持っていくという矜持でつながっているというか。
常田 うん。やっぱ裕太くんとは根本が似てますよね。違う道を歩いてきても、共通する根幹がある。だから今回のリリックもいいっすよね。根本が変わらないし、俺にもしっくりくる。実際に作るものや目線の変化はあっても、根本的には変わらずに成長できていると実感できる機会だった気がする。
──人間臭さや生々しさに向き合ったり、それを大衆に刺さるものにしたいと思ったのは、自分たちの根本をダイレクトに伝えたいという気持ちからですか?
常田 どうだろうな……単純に俺は「ポップアートをやっている」という自覚が強くあって。裕太くんも、文学的なスキルみたいなものがズバ抜けていて。でも、その芸術性とだけ向き合って生きていても、例えば田舎の両親とは話す内容がズレてくるじゃないですか。そこを全部無視していいかと言ったら違うし、自分が確かに出会ってきた人たちを遠ざける表現はしたくないなって思ったんですよ。millennium paradeというプロジェクトだろうが、King Gnuだろうが、人を分断する表現はしたくない。それはけっこう自分の中で大きい感覚なんですよね。
──むしろオルタナティブとかポップみたいな線引きをぶっ壊していくことが目的のプロジェクトですよね。ただ、millennium paradeにおける大衆性やポップさというのは、例えばKing Gnuとは違う視点で捉えられていると思うんです。そのあたり、常田さんはどう思いますか。
常田 もちろん価値観は1人ひとり違うから、大衆という雑な言い方はあまりしたくないんですけど……だからこそ、俺が生きてきた中で触れてきた人とか、人と話した質感とか、鳴らした音に対する相手の顔色だったりとか、全部が大事なんですよ。その中で培われた感覚を取り入れていくことが結果的に大衆性につながると思ってるし、millennium paradeに仲間をどんどん迎え入れていくのも、そういうことなんです。大衆的というのは、自分が今までつながってきた仲間や人に対して「誰にでも話せる言葉」「誰にでも鳴らせる音」っていう感覚ですかね。
──ポップアートとひと言で言っても、アバンギャルドなままの美しさもあるし、一方で、生活に入り込んでいろんな価値観をひっくり返すものもあるじゃないですか。でも、millennium paradeの表現はあくまで自分の見てきた景色に根ざしているものだと。プロジェクトのコンセプトとして「Be Punk」を掲げているのも、単なるカウンターを意味するんじゃなく、真っ当な存在表明としてのものなんだろうなと。今のお話を聞いていて思いました。
中野 人間のグルーヴってさっき言われてましたけど、結局は生活の中にある真実から外れたら芸術やアートじゃなくなっちゃう気がするんですよ。
常田 そうだね。
中野 あくまでそこにあるものをどれだけ結晶化できるか。ひと言で言ってしまえばすべて清濁併せ持った生活だし……俺は田舎で育ったし、貧乏だったけど、今もそこに接続する感覚を常に持ち続けています。そういう意味では俺も「大衆」という言い方じゃなく、実家のじいちゃんばあちゃんとか、そこにある生活に通じる感覚のほうが強いんですよね。それこそ大希もそうだろうけど、純芸術とか純文学とか純音楽から始まって、さらには無闇にパンキッシュだった時期から変化して、今一番必要なものを正しく結晶化して収めることができるようになったんだと思う。
純粋なまま表現を突き詰めたい
──表現している以上、そしてポップアートを作っている以上、お二人の活動は日本の音楽とか芸術に対する問題意識も多分に孕んでいると思うんですが、音楽や文化の受容のされ方に対するカウンターだけじゃなく、自分たちの表現が時代に対してダイレクトに問題提起をすべきという意識はあります?
常田 うーん……俺はあんまりないかも。
中野 俺もないかもな。
──表現は表現のまま純粋に存在すればいいと。
中野 勉強に関しては、人の歴史は長くあるわけだから、文明史から追って、時代を捉え直したり分析したりはします。ただ表現という意味でいうと、結局はこの時代にスッと存在して、そのときそのときで、正しく収めていくという意識なんですよね。例えばエゴとしてリリックを書きたいとか、エゴとして芝居をしたいとかじゃなく、やるべきだからやるという感じ。もっと純粋なものなんです。……それが結果的にレベルなものに見えたり問題提起になっていたりすることはあると思う。それこそこの曲で、フィリップに対して語りかけている言葉って広く波及し得る内容かもしれない。社会的な問題や運動……そういった部分とも接続していける表現になれば理想的かなって。
常田 そうだね。感じたこととかやったことが、自然と誰かにクエスチョンを投げかけていることになることはある。ただ、さっき話したみたいに、あくまで自分の大事な人たちとつながっているという感覚が先だし、その中で生きてる感覚が自然と社会性を帯びていくだけというか。ボブ・ディランが新聞を読んで「この事件を曲にしよう」と思ったみたいな、そういう作為的なところはない。もっと自然な表現がしたいんですよね。
──どうしてこんなことを聞いたかというと、MVも含めてものすごく痛烈な曲だと思ったからなんです。特にコロナ禍において顕著になった社会的な分断と、他者の声を一向に受け入れられない人間に対する警鐘が歌の中にも映像の中にもたくさん入っているなと。
常田 うん、そうとも捉えられるなと俺自身も作ってるときに思いましたね。ただ、作為的なものはないんですよ。裕太くんも、意図的にカウンター的なアティチュードを入れて表現したわけでもないって言ってるし。
中野 そうだね。確かにMVの表現と合わせて観ると社会的なメッセージを投げかけているように映るんだけど、俺は、むちゃくちゃ透明なものを投影して、風が吹いているようなイメージでまず詞をあげたので。
──「Philip」で書かれている「小川のそばに俺たちがいられるように──」「小石を投げ込むと、そこに沢山の輪っかが広がっていく。小石たちは下へと沈んで、無名になって、静寂に包まれる」「輪っかが広がって、俺たちの近くの人たちに優しく触れているよ」という意味の歌詞は、人々の主義主張に簡単に名前を付けたり、個々を見ずに人をひと塊にすることで分断が深まったり、という社会の現状を鋭く示唆していると思いましたし、その一方で特定のイデオロギーに染まらず自分の大事な人を守って生きていくことが何よりの主張なんだという気持ちも感じて。今日話してきたことが凝縮されているように感じました。
中野 ……すごいところに食い付いてきましたねえ。
常田 ははははは(笑)。
中野 小石の話をすると3時間くらいかかりますよ! まさに、いろんな思いが一番詰まっているところなんですよ、そこ。
──millennium paradeが「Be Punk」という言葉を掲げてきたことにも、ヒップホップやフリージャズと共鳴してきた部分にもつながると思うんですが、「Philip」は、名もなき者だとしても、社会的な枠に自分を収めなくても、真っ当に生きていくことこそが何よりのパンクであり解放なんだと感じる楽曲でした。
常田 ただただ音楽の勉強をしてきた人間からすると、単純に音楽を突き詰めたいと思い続けてきたんです。でも、特にこの国には「純粋に芸術を突き詰めたい」と考える人の居場所がなくて。その現状の捉え方こそが、音楽業界全体と、自分との意識の圧倒的な差を感じるポイントなんですよ。純音楽と、いわゆる世の中に受け入れられている音楽との間に、橋もかかってないくらいの状況だからね。でも俺がやりたいのは……「そのままでいいんだよ」と言える表現というか。そのままがカッコいいのに、常識や世間からの見え方によって形を変えなければいけなくなってる。でも俺は、純粋なままの表現を信じてるんです。そういう思いがあって、音楽も映像も、昔からの意志を共有できている仲間たちで制作陣を構成したんです。
──自分の表現がオーバーグラウンドでひと通り勝てた実感があるからこそ、1周しての原風景回帰というか。
常田 みんな、そのままデカくなってきた人たちだから。その純度のままでいいじゃんって俺は言いたいんだよね。音楽にしてもアニメーションにしても、「こんなのやってても食っていけないよ」みたいな芸術を志す人は今も山ほどいるはずで。だけど、そこにしか宿らない強さが絶対にあるんだと俺は信じてる。millennium paradeというプロジェクトも、その純粋さを信じてるんですよ。
中野 大希はmillennium paradeを「いろんな仲間に来てもらえる広場だ」と言ってて。そこに誘ってもらえて、楽しかった。
──まさにmillennium paradeは「場所」なんですね。自分を解放できる場所が精神的にも物理的にも減っている中で、あらゆる価値観を拒絶しないための場所。
中野 そこに参加できて光栄です。それに尽きるかなあ。あと、最後にひと言言っておきたいのは……。
常田 ん?
中野 曲に犬の鳴き声が入ってたのわかります? あれ、俺なんです。
常田 最後に言うのがそれか。
中野 現場で褒められたからね、大希に(笑)。「裕太くんの犬の鳴き声のクオリティやばくねえか!」って。
常田 ……ごめん、それ忘れてたわ。
中野 おい!(笑)
次のページ »
常田大希×佐々木集×山田遼志インタビュー