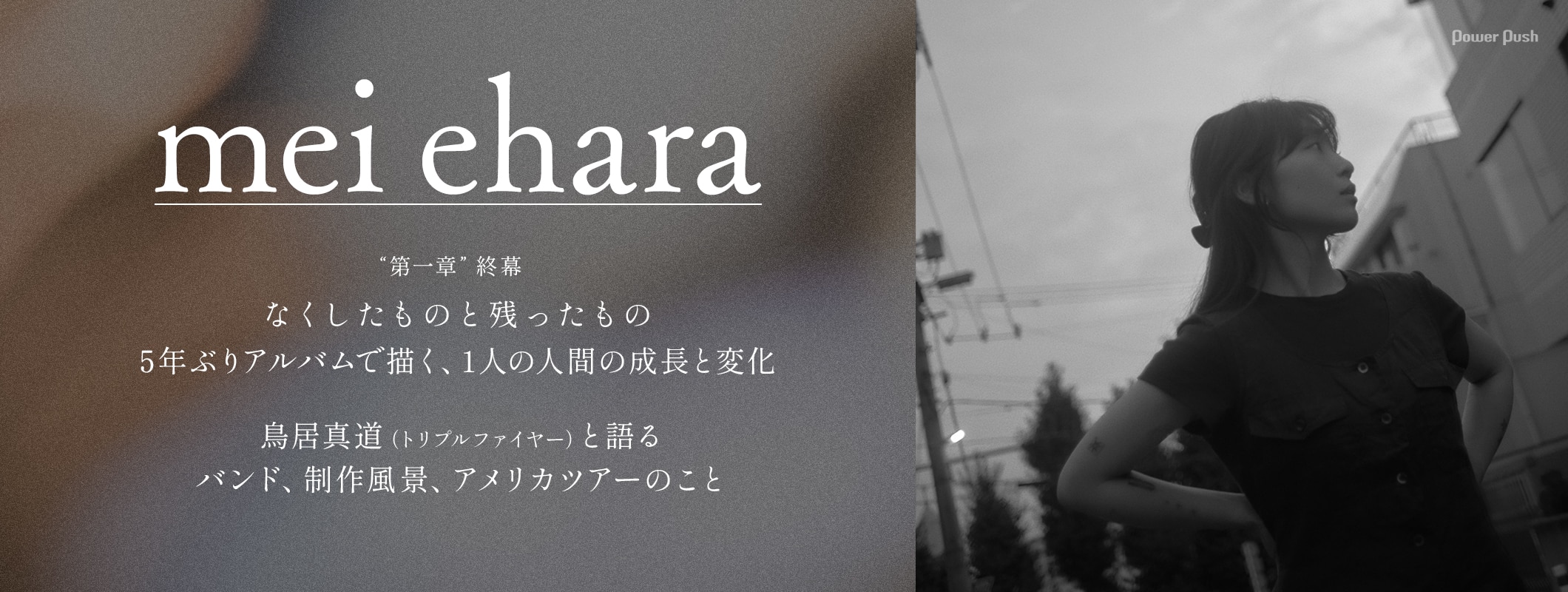自分の音楽をシェアしたい
──例えば今回のアルバムに入っている「会いたい」には、「今 あなたに会いたい」というフレーズがあります。meiさんがこれほどまでにストレートに「会いたい」と歌うことは今までなかったのではないでしょうか。
そうですね。作詞のうえでのもう1つの変化として、ストレートな言葉で歌う「会いたい」のような曲を作ってもいいと思いました。今回のアルバムは頭から最後まで通して聴いてほしいので、アルバム全体のストーリー性やムードの流れを考慮すると、こういうストレートかつシンプルな曲は生きると思います。
──映画で言えば、中盤のこのあたりに恋愛のシーンが入ったらいいんじゃないかというイメージ?
場面が変わる感じですね。LPではB面の1曲目になるので、盤をひっくり返して「会いたい」で空気が変わるかなと思いました。自分が理解できればいいという作詞方法から少しだけ離脱している部分、そしてこの曲のようなストレートな表現は、だんだん部屋からリビングへ、さらに庭へと移動している感じ。私自身が聴く人と一緒に音楽を楽しみたいという気持ちが多少芽生えているのかもしれません。
──そういう気持ちは以前はなかった?
なかったと思います。私が音楽を作るのは「自分が楽しいから、作業が好きだから、自分のためにやっている」という気持ちが大きいので、すごく内向きなんです。
──それが変わってきたのは何がきっかけだったのでしょうか。海外でツアーをやったことが大きい?
単純にライブの数も増えて、人に見てもらうことや評価されることに少しずつ慣れてきたのかもしれません。慣れてきた結果、共有したいという気持ちが少しだけ出てきたのかも。一番大切にしたいことはメロディやアレンジ、演奏がいいことですが、言葉についても好きだと思ってもらえればうれしいです。
──なるほど。
あと、これまで自分の実体験をもとにして作りたいものを作っていたんですが、音楽を作ることが仕事になった結果、家にこもって机に向かっている時間が増えていって、日常生活の中でだんだんと曲作りのきっかけになるような出来事、事件が落ち着いてきたんですよね。日常生活の中で起きていないことについても書く特訓をしたいと思うようになって、それに取り組みながらここ数年は客演でお題のある他の人のトラックにメロディと作詞をしたりしていたので、だんだんとフィクションに慣れてきた感じもありました。今回のアルバムは自分のことが6、7割、フィクションが3、4割ぐらいのバランスになったんじゃないかと思います。
──ちなみに、meiさんが歌詞を書くうえで大事にしていることは?
やっぱり言葉の選び方です。私、短歌が好きなんですよ。
──それはすごく感じます。
短歌は五・七・五・七・七の文字数制限がある中で、普遍的な言葉を使いながら「その視点はなかった!」と思うような作品を作る必要がありますよね。そういう部分に惹かれるんです。作詞をするときはリズム感も大切です。なので短歌はとても参考になります。そしてメロディ一音一音に対してどの母音が合うか。
──音の響きを重視していて、言葉の意味はあとからついてくる?
その場合もありますし、メロディを先に作って、そこに「この曲はこういうことについて歌いたいな」と考えることもあります。そういうときはまず、口から出任せで何かを歌っていくんです。その中に言いたいことの核となる言葉が出てくることもあるし、苦し紛れに出た言葉の帳尻を合わせながら整えていくこともあります。
タイトル「All About McGuffin」に込めたもの
──アルバムタイトルにある「マクガフィン」は、物語を進行させるためのアイテムや目的のことを意味する言葉ですよね。このテーマはどのように浮かび上がってきたのでしょうか?
「マクガフィン」は「大事かもしれないけど、最終的にそこにたどり着くためには代替も可能なもの」という意味も持っています。例えばインディ・ジョーンズが探し求めてる聖杯や、スパイが必死に守っているアタッシュケースがあたります。結局物語を進める上ではそれが別のものであってもいいということです。ただ、大事ではないかと言われたら、大事なわけです。今作は、私が音楽的に切り捨てたものとこだわって入れたものが混在して構成されていると思います。余計なものだと思って削り落としたと思っても、こだわって入れたもののほうが余計なものかもしれない。そう考えたときに「マクガフィン」という言葉が浮かんできたんです。「なくしたものも残っているものも含め、私のもの」という意味で、このタイトルを付けました。
──meiさんの人生におけるなくしたもの、残ったものでもある?
それもありますね。第一章の締めくくりに際して私の人生を振り返ってみると、これまで囚われて悩んでいたことや出来事を、現時点に立っている自分にとっての「マクガフィン」と言えるとも思いました。自分が人生で追いかけてきたもの、重要じゃなかったもの、新しく入ってきたもの、そういうものも含めてアルバムタイトルを決めました。ここ数年で自分自身が成長したり、悩みが解決したからこそ、見えてきたテーマだったと思います。
──なるほど。
アルバムを作り上げるうえで必要な記憶やイメージを掘り返していくと、幼少期にテレビゲームを起動したときに表示されるスタート画面が真っ先に浮かんできて印象に残りました。私はNINTENDO 64、ゲームボーイやPlayStation、セガサターンの時代のゲーム音楽が好きなので、その影響が作品にいつも反映されています。ループパターンが好きなのもその理由だと思います。今回のアルバムは全体を通してストーリー性のあるものにしたかったので、映画や物語的なイメージの一方で「ゲームをスタートしてクリアしたあとのエンドクレジット」を見ているような感覚を盛り込みたいと思いました。収録曲最後の「エンディングテーマ」を聴き終わって、また1曲目の「オープニングテーマ」に戻ったとき、クリア後に再びスタート画面に戻っていくような感じです。そうすることで、物語、人生で得た教訓が繰り返されることを表してもいます。でもそれはネガティブな意味ではなく、前に進んでいこうとするポジティブさ、ロールプレイングゲームのような高揚感を出したかったんです。あくまで私の感覚ですが。
──ジャケットのアートワークには、ブルックリン在住のイラストレーター / タトゥーアーティストのパトリック・エデルによる描き下ろしイラストが使われています。どこか寓話的で、アメリカの絵本のようなイメージを持っていましたけど、言われてみるとゲーム的でもありますね。
そうですね。パトリックにアートワークを依頼したとき、アルバムのコンセプトについて説明をして、その中で先ほど話したようなゲームの話も伝えました。特に「ゼルダの伝説 時のオカリナ」が好きなので、その要素を入れたいと。もともとパトリックの作品が好きでしたし、私が今作のアートワークに求めているイメージにぴったりだと思ってお願いしたんですが、話してみると私と趣味が似ている部分があって、「『ゼルダ』は俺も好きだから大丈夫だ」と言ってくれて。本当にスムーズにアートワークが決まりました。