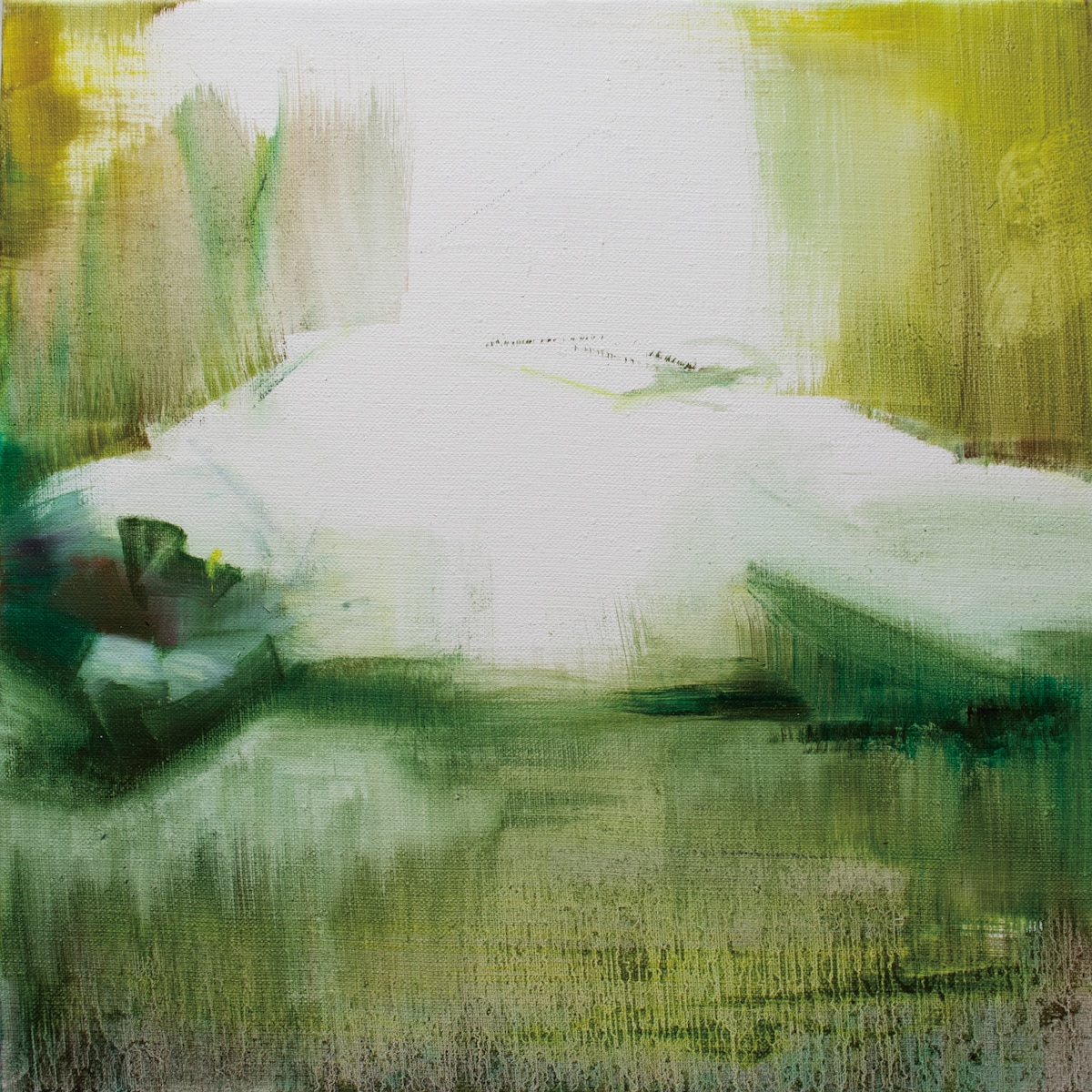小林私が新作アルバム「中点を臨む」をリリースした。前々作「光を投げていた」、前作「象形に裁つ」に続き、抽象度の高いタイトルが付けられている。
音楽ナタリーでは小林本人にインタビュー。この1年間、主催ライブをはじめとした精力的な活動を経て変わったこと、根底にある不変の哲学など、小林私の現在地を語ってもらった。
取材・文 / 天野史彬
楽で暇な人生が一番
──前作「象形に裁つ」をリリースされてから約1年が経ちましたが、この1年間で小林さんはタイアップや自主企画ライブなど、さまざまな経験をされてきていると思います。ご自身にとって、どのような1年間でしたか?
キャリアの中で一番曲を書いていない1年だったと思うんですよね。本来の僕のあるべき姿である「曲を書く」ということが、自主企画とかいろいろあってあまりできていなかったので。来年からは、もうちょっと暇になりたいなと思います(笑)。
──暇がいいですか(笑)。
YouTubeのショート動画をダラダラ眺めていて気が付いたら3時間経っていた、みたいなのが僕の人生の理想形なので。がんばってグッズのデザインを2時間かけてやって、それが終われば次の仕事があって……という生活は、「有意義に過ごしちゃったな」みたいな気もします。仕事があって、それを1個1個こなしていくと、1日の終わりに達成感はあるんですよ。でも、「俺はこんなことをするために生まれてきたのではない」とも思う。もっとゲームとかをして時間を無駄にしたかったな、と。そういう1年間でした。
──今は、いわゆる「タイパ」とか「コスパ」を重要視する人たちも多い気がしますが。
僕は、1回も努力する隙がないくらい楽で暇な人生が一番最高なんじゃないか?という思想を持っていて。「今日もずっとゲームをしていたらすごいランク上がっちゃったぜ」みたいな時間の流れ方のほうが、僕的には精神衛生上いい気がします。曲も暇な時間の連続から生まれるんです。
──ライブなどで多忙な1年間を過ごす中で、「曲を書きたい」という欲求を改めて感じられましたか?
そうですね。ライブをやっているときに「なんでこんなことをやっているんだろう?」と思うので(笑)。ミュージシャンの在り方はそれぞれだと思うんです。フェスで盛り上げることが本懐の人もいれば、家の中で完結させたい人もいる。自分は年々「ライブなんてやらなくていいな」と思いますね。去年の暮れに「長い一日」というライブをやって、今年に入って「小林私の五日間」という僕の大喜利力だけで突き進んだライブをやって……後悔はないですけど、膝から崩れ落ちるくらい疲れました。やるとなったら、ちゃんとやりたいじゃないですか。ちゃんとやると、疲れるんですよね。
──疲れるくらいのものを作りたくなってしまうということですよね。
なるべくラクしたいですよ。なるべく汗をかかずに生きていきたい。自分が出せる力の60パーセントくらいで10割こなせる仕事が、その人に向いている仕事だと思うんですけど、今の自分は毎回120パーセントくらいでやってしまっている(笑)。あと、この1年は「時間は有限なんだ」と思いました。
──時間が足りなかった。
そうですね。同時に、時間の長さを感じた1年でもありました。「この日にこれをやらなければいけない」ということが連続して、気が付けば1カ月、3カ月、半年、1年……と経っている感じ。思い返せばあっという間だけど、毎日やることがあると効率的に過ごさなければいけない分、1日が長く感じるというか。
──そうした「長いのにあっという間」みたいな時間感覚のズレは、例えば新作アルバム「中点を臨む」の収録曲「加速」という曲で表現されていたりしますか?
「加速」は新幹線に乗っているときに「新幹線はえー」と思って(笑)、そこから歌詞の1行目と2行目を書いて作り始めたんです。そもそも音楽って時間芸術なんですよね。絵画なら1秒見ることも1時間見ることも1年かけて見ることも、ひとつの鑑賞体験としてそこまで差はないと僕は思うんですけど、音楽は、その曲が3分なら3分間聴かないと鑑賞体験をしたとは言えない縛りがどうしてもある。その音楽という時間の縛りがあるフォーマットの中で「速度」を表してみたくて。それもBPMのような物理的な速度ではなく、言葉の上での速度を出してみたかったんです。
バラバラなアルバム
──もう少しライブの話を伺いたいのですが、改めて「小林私の五日間」を振り返ってみても、小林さんにとってライブは自分という「個」を増幅して見せる場所ではなく、自分以外のいろんな人が表れては消えていくような、あくまでも「空間」を作るという点に重きが置かれているような気がしました。
あまり意識しているわけではないですけど、自分の中にもともとある思想として「個が現れる前提に他者がある」というのがあって。個と個のアウトラインが押し合うことで、お互いが現実世界に存在している……そんな感覚があるんですよ。なので、自分が個としてどうこうというよりは、周りの空間があって、その隙間に自分の形があるという感覚のほうがしっくりくるんです。
──レトロリロン(「中点を臨む」の収録曲「空に標結う」の編曲を担当)のような「バンド」という表現形態の人たちに触れたときに感じられることはありますか?
「バンドの音が欲しい」とか「バンド形態がカッコいい」というより、「俺たちで一緒に作品を作っていこうぜ」と言える友達がいるのがいいなあって、涎を垂らしながら見ている感じですね。「俺も友達と何かもっとやりたかったな」と思う。例えば事務所に入るみたいなことでも、1人だったら「自分対事務所」になるけど、バンドを組んでいたら最低でもメンバーの人数分は味方がいるわけだから。「それはいいなあ」と思いますね(笑)。
──新作「中点を臨む」は、前作に引き続き曲ごとにさまざまなアレンジャーの方と制作されていますが、アコギの音がフィーチャーされている曲も多いし、アレンジャーの方々の小林さんへの理解が作品を経るごとにより深まっている気がします。他者と一緒に音楽を作るという豊かさが小林さんの作品の中でどんどん増しているように感じますが、ご自身ではどのように感じますか?
そうですね、今回のアルバムで言うと、レトロリロンやMega Shinnosukeさんはもともと友達だったのでお願いしましたし、白神真志朗さんやSAKURAmotiさんは前回もお願いしているので、得意なことがわかったうえで改めて「この人たちにお願いしたいな」と思って声をかけました。Ganbare Masashigeさんは遠方に住んでいるのでしばらく会えていなかったんですけど、今回の「冷たい酸素」という曲は「Masasigeさんに頼んだら面白くなりそうだな」と思って。そういうことを考えると、「今までよりはビジョンが見えたうえで頼めるようになってきたな」と思います。Bialystocksの菊池剛さんも、対バンしたうえで「めっちゃ曲いい!」と思ってお願いしているし。
──「中点を臨む」には8曲が収録されていますが、それぞれの楽曲が音楽的に別のベクトルを向いていて、そこが個人的にはとても好きなポイントです。例えば1曲目「空に標結う」はレトロリンとともに作られたバンドサウンドの楽曲ですが、それが終わると唐突にMega Shinnosukeさんが作詞作曲を手がけたクラブミュージック的な音楽性を持つ「私小林(produced by Mega Shinnosuke)」が始まったりする。そうやって、8曲というアルバムとしてはコンパクトなフォルムの中で、「バラバラなものたちが、バラバラなまま存在している」ということが肯定されているような感覚がある。この肯定感が、とても小林さんらしいなとも思います。
今回はタイアップ曲の「空に標結う」と「鱗角」を入れるという前提があったんですけど、この2曲は僕としても「ラグナクリムゾン」というアニメに比重を置いて書いた曲だったし、この2曲の時点でバラバラだったので。「誰かに提供してもらった曲を入れたら面白いんじゃないか」というアイデアもそもそもあったし、前提の時点で「まとまりのあるアルバムにはならないだろう」と思っていました。実際、結果的にバラバラなアルバムになりましたね。そこに関しては意図的な部分はあったと思います。
──もちろん、この先小林さんが長大なボリュームのフルアルバムを作る可能性もあると思うんですけど、今の小林さんの表現は、カタルシスを感じさせるように起承転結のある物語を描くというよりは、断片的な日々や感情が並列して存在している、その状態を捉えているというほうがしっくりくるのかなと改めて思いました。
そうですね……例えば、面影ラッキーホール(Only Love Hurtsの旧名)のような物語歌詞が僕は好きなんですけど、面影ラッキーホールは1曲1曲に世界観があって、それがすべて地続きになっているわけではないですよね。ああいう表現に惹かれているところはあって。トリプルファイヤーも、吉田靖直さんの小市民感が通底して現れてはいつつ(笑)、毎回歌っているのは全部違う場面という感じがしますよね。あれは言うなれば、「人生」という物語歌詞だと思うんですけど、僕の好みはそっちなのかなと思います。
真ん中には何があるんだろう?
──「中点を臨む」というタイトルは前作の「象形に裁つ」に引き続き、「小林私は何をやっているのか?」ということを言葉にしているように感じました。それと同時に、前々作の「光を投げていた」からタイトルがだんだんと主体性を帯びてきているように感じます。このタイトルはどのようなイメージで付けたんですか?
タイトルはずっと同じことを言っている感じなんですよね。「光を投げていた」は、当時、趣味で不確定原理のことを調べていたことや、大学の受験期にデッサンを描きながら反射光のことをやたら考えていたこともあって、他者との関わりにおける「光」に興味があったんです。「自分が何かを知覚するということは、自分は光を投げているということなんだな」という気付きからあのタイトルになった。「象形に裁つ」の頃は、自分は不定形なもののアウトラインをいろんな方向から知覚することで、何かの形や、その奥にある本質的な部分を見ているんじゃないかと感じていて、あのタイトルになった。ずっと言っていることは一緒なんです。自分の外側の世界との関係性を、俺は今どういうふうに見ているんだろう?ということを言っています。
──そのうえで、「中点を臨む」にはどのようなニュアンスを込めていますか?
今回は「アウトラインを追った先に何があるんだろう?」という問いかけが、俺の中で流行っていたということですね。自分の曲を振り返ったとき、ずっと遠回しに何かを言っているような気がしていて……というか、それは自分で思ったというより人から「わかりにくい」と言われたりすることによって感じたことなんですけど。その「わかりにくさ」って何に起因しているんだろう?と考えたとき、断言する歌詞が自分の曲にはないことに気が付いたんです。「空に標結う」と「鱗角」はタイアップということもあってあえて断定的にしているんですけど、基本的に、僕の曲は断言をしない。「じゃあなぜ、断言しないんだろう?」ということを考えたとき、外側を追うことで、中央にあるものを探しているんだろうなと思ったんです。伊能忠敬が日本の端っこを歩き続けることで日本の形を知った、みたいなイメージで、「外側を追っていく作業をすれば、真ん中の形を知ることができるだろう」みたいな思想が自分の中にある。そもそも小心者なので、断言ができないんですよ(笑)。
──「断言したい」という気持ちもどこかにはあるんですか?
憧れはありますね。例えばback numberの「瞬き」という曲は幸せとは何かを断言することから始まりますけど、「ああいう曲を書きてえな」と思いつつ、「書けねえなあ」と思っています。
──そして外側を追うことで、結果として中点を知ろうとしている。
真ん中には何があるんだろう?って。「俺は何が言いたいんだろう?」ということすら曲を書きながら自分で探している感じですね。
次のページ »
音楽のことしか書けなくなったら終わり