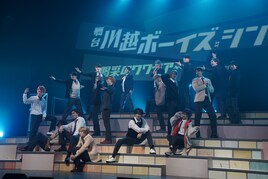ひょんなことから川越学園のボーイズ・クワイア部に入部することになった男子高校生たちの成長を描くTVアニメ「川越ボーイズ・シング」。その劇中のボーカル曲や劇伴曲を多数手がけ、キャストの歌唱指導までを担当したのが、ボストン在住の音楽家 / プロデューサー・YUKI KANESAKAだ。本場のクワイアにも通じるブラックミュージックのエッセンスを加えながら、メンバーそれぞれの個性が躍動感たっぷりにひとつになるような楽曲に仕上げたKANESAKA。そんな彼に、楽曲の制作過程や、キャスト陣の成長などについて聞いた。さらにKANESAKAとともに、音楽のクレジットに名を連ねたシンガーソングライター・シンリズム、合唱曲の作曲家として知られる横山潤子からはコメントが到着。3人のみならず、国内外の多くの才能が集ったアニメの楽曲の魅力を、彼らの言葉から紐解いていこう。
取材・文 / 杉山仁撮影 / Sarasa Uchiyama(YUKI KANESAKAインタビュー)
「音楽を作る時間」を大切に、わちゃわちゃしながら進めていった
──YUKI KANESAKAさんは今回、楽曲制作やアレンジだけでなく、キャストの皆さんの歌唱指導など、幅広い役割を担当されたそうですね。
僕は今回、作詞作曲やアレンジ、歌唱指導、オーケストレーションのようなものまでさまざまな役割を担当させていただきました。今取材を受けているのが僕のボストンの自宅にあるレコーディングスタジオ・Hummingbird Recordingsなんですが、ここでさまざまな楽器を演奏しましたし、同時にゲスト演奏家の方たちも、自分が思ういい人選でお願いをしています。
──まずはオファーが来たときのことを思い出していただけますか?
「竜とそばかすの姫」などで名を馳せる岩崎太整という僕の心の師のような作曲家がいまして。彼を経由してオファーをいただき、ボストンに住みながら日本の皆さんと密にやりとりしてレコーディングしました。今回は楽曲制作や歌唱指導など担当する役割も多かったですし、キャストの皆さんだけではなく、他校のクワイア部の皆さんも含めてボーカルを録る人数が本当に膨大でした。多様なレコーディングのタスクを進めていったので、オファーをいただいた時点で「これは忙しくなるだろうな」と思いましたね。
──最初から、さまざまな面で音楽に関わってほしいという依頼だったんですね。
そうですね。自分としても「こんなのはどうですか?」「僕だったらこういうことをやりたいな」と、いろんなアイデアを提案しました。もちろん、いただいた音楽のメニュー表にはすでに必要なものが書いてありましたし、僕以外にも横山潤子先生やシンリズムさんが参加していますが、僕はいろいろなアイデアが溢れてしまうタイプの性格なので(笑)、「じゃあ僕はこういうことをやりたい!」と、メニュー表にあったこと以外にもいろんな提案をしたんです。それもあって、オーダーを受けて楽曲を作ったりするだけではなく、まるで砂場で子供が遊ぶかのように、真っ白なキャンバスに自由にペイントさせてもらった感覚がすごくありました。完成版で聴いていただいているアニメの放送尺以外にも、いろんなアイデアや化学反応がたくさん生まれました。
──皆さんで一緒に音楽の方向性を作っていくような感覚もあった、と。
はい。例えば、エンディングテーマの「Ride Out the Fall」では、キャストの皆さんのおしゃべりを取り入れていて、その部分はクワイア部のメンバーになりきってアドリブを入れてもらっています。深川和征くん演じるカーティス(鈴木カーティス / マジック)に流暢な英語をしゃべってもらったり、小原悠輝くん演じる白鳥(修治)にラップしてもらったり、木村昴くん演じるあだちが「だからカーチャン、、、、」とハイテンションで言っていたり。ほかにも、鵜澤正太郎くん演じるだんぼっちがメンバー紹介をしていたり、金子誠くん演じるオトメが、終始みんなのテンションに置いてけぼりにされていたり、中西南央くん演じるITが、セリフで勝手に振り付けをしていたり、ソロをやったりするときも、ただ楽譜に書いてあることだけではなくて、そのキャラクターたちとして遊んでもらいながら収録しました。この作品は高校生をテーマにした作品ですが、僕らが高校生の頃を思い出しても、明日何が起こるかなんてわかっていなかったと思うんです。ですから、音楽でも、そういった雰囲気でアドリブを入れてもらおうと。
──青春や成長を描く作品に合った制作方法がとられていたのですね。
それに、この作品はコロナ禍のど真ん中で制作が始まったので、一時はレコーディングがなかなかできなくなった状況を経て、「やっとみんなで音楽ができるぞ!!」という気持ちを感じていました。そこで僕としては、ボストンのスタジオからではありますけど、例えば「だんぼっち、もうちょっと、はっちゃけて歌ってみてよ!」というように、クワイア部のみんなと一緒に音楽を楽しむような気持ちを大切にして、トップライナーと言われる歌のラインを考えてくれるメンバーたちにも、消毒は徹底したうえでスタジオに来て演奏をしてもらったりしました。そんなふうに、かけがえのない「音楽を作る時間」というもの自体を大切にするような雰囲気で制作を進めていったんです。
──皆さんの制作現場もまるで部活みたいですね。
まさにそんな雰囲気でした(笑)。みんなでわちゃわちゃしながら制作していきましたね。
──横山さんやシンリズムさんの担当楽曲に比べて、KANESAKAさんが担当された楽曲はブラックミュ―ジックのグルーヴが感じられるものが多い印象です。この辺りは、KANESAKAさんご自身の個性が出ているように感じます。
そうですね。僕自身、ブレイクダンスをしていたり、いまだに週末はクラブに行ったりしているような人間ですし、アメリカにはジュークジョイント(生演奏で音楽が楽しめるジュークボックスがあった酒場の名残)のような場所が今でもあります。僕はティーンエイジャーの頃からそういう場所で仕事をしてきたので、教会のゴスペル文化だけではなく、そういった場所でエレピ(エレクトリック・ピアノ)を弾いたりドラムやベースでジャムりながら、おじいちゃんやおばあちゃんがオーティス・レディングやダニー・ハサウェイを歌ったり踊ったりするような風景が当たり前の中で育ちました。ですから、グルーヴやフィール、そしてみんなでタイミングを整えすぎずに踊ったりするようなダンサブルな文化は、僕の中に常にある要素なんだと思います。例えクラシックなものをやったとしても、どんな音楽をやったとしても、こういった感覚が、僕の中に流れているんだと思いますね。
AIには決してできない、汗ばむ瞬間を作りたい
──今回、クワイア部を描く作品だからこそ意識したことはありますか?
それは「バラつき」です。一般的に、音楽のプロダクション・制作では縦の線を定規で揃えるようにメロディやリズムを整えがちです。特に日本の音楽のプロダクションは、その部分が長所でもあり短所でもあると思っていて。でも僕の場合は、全員を十把一絡げにして整えるよりも、それぞれに異なる1人ひとりの個性が合体したときに聴こえる声の幅感のようなものを大切にしました。例えばですが、実際に高校生が全体で声を合わせて歌っても、すべてが完璧に揃うより「バラついているところもあるけれど魅力的だな」ということのほうが、その時期にしか出せない彼らならではの魅力になると思うんです。僕はそういう部分を伝えられるようにアレンジをする役割なので、1回目のバラつきと2回目のバラつきがちょっと違ったり、同じフックを歌っていても後半のほうでもっと盛り上がって「ちょっと熱くなってるぞ!」と感じられたりすることのほうが、音楽として魅力的だと思っていて。アニメの音楽でも、キャラクターにソウルを吹き込んでいる人たちがぐっと汗ばむような瞬間を作りたいと思っているんです。それはAIには決してできないことだと思うので。
──それがクワイア部の楽曲のいきいきした魅力につながっているのですね。具体的に楽曲の制作エピソードを伺っていきたいのですが、最初に「On the Set」(川越学園ボーイズ・クワイア部の練習曲)はいかがですか?
この曲は、僕の中でリファレンスとしてイメージしていた楽曲があって、それはファレル・ウィリアムスの「Happy」(ゴスペルソングに触発されて生まれた、クラップやコーラスなどを加えたソウル~ファンク調のポップ曲)でした。でも、あの曲って打ち込みのピアノが使われていて、「ドンチャチャドンチャ」というリズムも、マシンでループした音になっていて。
──ファレル・ウィリアムスのプロダクションは、ドラムサウンドは特に顕著ですが生音風の音とマシン感とのバランスを意識したものが多いように感じられますね。
僕もそう思います。でも、それは彼のやり方で、僕の場合は、もっと生のエレピの少し歪んだ音を加えています。歪まないエレピを使って小綺麗に整えるのではなくて、ちょっと歪ませることで、より人間味を詰め込んでいるんです。あと、「On the Set」では双子の日向兄弟がラップを披露しているんですが、そこに大げさな要素を加えると逆にラップが立ったりするので、演奏をなくしてみたり、逆にタムで「ドンドン!」と派手に音を鳴らしてみたりしています。これはもう、「このほうがかわいいからやっちゃえ!」と(笑)。ループしたトラックにラップを乗せる従来の作り方ではなくて、ラップができあがった段階でアレンジをわちゃわちゃと変えていきました。
そのうえで、歌詞には現代において変わりゆくものと、変わらないものを心の中に大切にしてほしい、というちょっとしたメッセージも加えています。「いろんなことがあったけどさ、またみんなで音楽を一緒にできて最高だね」という当時の気持ちも込めつつ、「ずれていたって、なんかいいじゃん。カッコいいじゃん!」という魅力を入れられたらな、と思っていました。
レコーディングを通して感じたキャスト陣の変化
──「Shake It till Make It」(川越学園ボーイズ・クワイア部の練習曲)についてはいかがでしょう?
この曲は、僕の大学時代の同級生で、今はジャスティン・ティンバーレイクやブルーノ・マーズと仕事をしているThe Regiment Hornsにホーンセクションをお願いしていて、トップラインを書いてくれたFraser Wattも、僕がバークリー音楽大学で教えていた元生徒です。ストリングスは、同じボストンに住んでいるアンドリュー・コウジ・テイラーと、彼の甥っ子のHanna Taylorにお願いをしました。ハープも最近まで僕の生徒だったTrina Egnerに入ってもらっています。こうしたメンバーに、場合によってはリモートでお願いしたり、僕がマイクを持って音を録りにいったりしながら、レコーディングを進めていきました。
曲名は、アメリカにある「がんばっていればなるようになるよ」というニュアンスの「Fake it till you make it」という慣用句をもじった、「真似しながらでも、やっていけばなんとかなるさ」という、クワイア部のみんなに向けた言葉になっています。この言葉は、実は僕の妻(Saucy Lady:ボストンを拠点に活動するシンガーソングライター、DJ、プロデューサー)が一緒にオンラインライブをしていたときにダジャレで言った言葉だったんですが、今回楽曲を作るにあたって「これだ!」と思って採用しました。
クワイア部のキャストの皆さんも、最初は歌に慣れていない方もいましたが、歌唱指導の中でちょっとずつ慣れて、うまくなっていって。その姿も、歌詞の中に込められています。今回レコーディングした曲の中でも、最初の頃に録ったものと最後のほうに録ったものでは、やっぱりみんなの歌も随分変わっていきました。「みんなちょっと慣れてきたのかな?」とか、「IT、ド頭から決めるねえ!」とか、「だんぼっち、リズムがよくなってる!」とか……。レコーディングを通して皆さんのいろんな変化を感じました。
次のページ »
完璧じゃない、だからこそこの作品に合うと思った