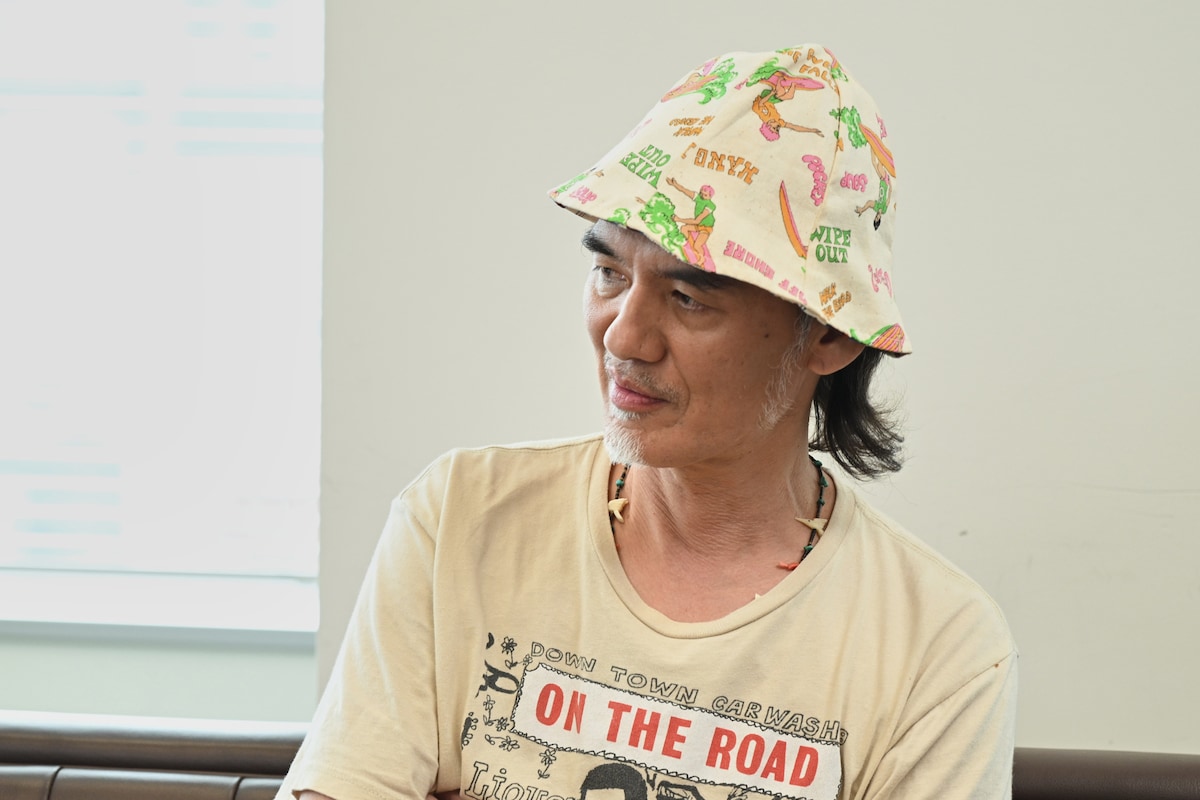両バンドが乗り切った危機的状況
──昨年リリースのアルバム「Sustainable Banquet」に収録された「Boogie-Oogie」には、EGO-WRAPPIN'として中納さんがボーカル、森さんがギターで参加されましたね。
吾妻 ここはひとつ、NHK連続テレビ小説「ブギウギ」の主題歌を歌ったよっちゃんにちなんで、ブギウギ商法にあやかろうとしまして(笑)。
中納 ブギウギ商法(笑)。
吾妻 「Boogie-Oogie」もよっちゃん、森くん含めてワンテイクでOK。まるで50年代のレコーディングスタジオのような光景でした。
森 そうなんですよ。僕はバッパーズのレコーディングに興味津々やったから、もっとスタジオにいたかったんですけどね。
吾妻 我々は1979年からブギウギ的なものを演奏しているんですが、なんとかブームにしがみつこうとして毎回振り落とされてきた(笑)。80年代に白人が演奏するジャンプ&ジャイブがちょっと流行ったりしたこともあって……。
渡辺 ジョー・ジャクソンとか、俺たちのレパートリーをやりやがって(笑)。
吾妻 New York Dollsのデヴィッド・ヨハンセンのBuster Poindexterとか、Van Halenにいたデイヴィッド・リー・ロスだってジャンプブルースを歌ってた。「ついに来たか! よし、俺たちも」と、その都度勢いづくんですが、波は来なかった(笑)。
森 ジャンプブルースやジャイブのバンドって日本ではどのくらいいるんですか?
吾妻 全国でうちを入れて3バンドくらいかな。Drinkin' Hoppysという我々が卒業した大学の20コくらい下の後輩がやっているジャンプブルースバンドがおりまして。Drinkin' Hoppysのアルバムに、民謡クルセイダーズのメグさんが江利チエミのジャズナンバーを歌う「Sha Ba Da Swing Tokyo」というのがあって、その録音およびミックスは私が手がけているんですが、彼らは仕事をしながら活動していて、働き盛りなのでライブは年に2、3回くらいかな。あとは大阪のLoose Hepcatsというバンドくらいですかね。80年代には福岡にUptown Orchestraというビッグバンドもいたんですが。
森 ビッグバンドは大変ですよね。うちら、2人でも大変やのに。
吾妻 危機的な状況になったことはある?
森 解散まではいかないけど……。
中納 ギリギリくらいまでなら……。
吾妻 あるんだ?
中納 そういうときは、いい思い出を追憶して乗り切りました(笑)。
森 バッパーズは解散の危機はありましたか?
吾妻 ウーム、ないこともない。しいて1つ挙げるとするならば、大学の学祭のオールナイトライブのときですかね(笑)。
渡辺 まだ若かったからできたんだろうけど、夜中のライブというのは解散を招きかねなかったね。眠いし、待ち時間は長いし。
森 僕らのときはそれがクラブでしたね。
吾妻 その昔、80年代あたりはオールナイトの学園祭というのが多かったんですよ。
結成から40数年ほとんどライブハウスにしか出ていない
渡辺 2枚目のアルバム「HEPCATS JUMP AGAIN」(1988年)のジャケ写は多摩美のオールナイトライブのときに大学の教室で撮影したんだよね。
吾妻 当時はジャンプブルース原理主義者だったから、昔のアルバムをリイシューしたような感じにしたいと、ベースの牧裕が通勤のときに紙焼き写真をポケットの中に忍ばせて昔風の質感に仕上げてくれた(笑)。
渡辺 いい感じで写真が色褪せてね(笑)。今みたいにパソコンでちょっとイジるだけでセピアカラーに仕上げることができない時代だったから。ちょうど、そのアルバムを出した頃からライブの本数が少し増えた。渋谷にCLUB QUATTROができたのも同じ年だね。クアトロではそれ以来、ほぼ毎年ワンマンをやらせてもらってる。
吾妻 地方のライブも徐々に増えていった。大阪ならBIGCATが多いかな。福岡のブルーノートに出たこともあった。年に一度くらい地方に行くと、やたらはしゃいじゃってね。
渡辺 ただ、俺たちは結成から40数年ほとんどライブハウスにしか出ていない。
吾妻 ホールはMt.RAINIER HALL(SHIBUYA PLEASURE PLEASURE)と、渋谷区文化総合センター大和田・伝承ホールくらい。そろそろお客さんもスタンディングがキツくなってきたからと、着席ライブを始めた各地のビルボード公演もコロナ前の2019年から。ホールツアーをたくさん経験されている先輩のお二人に、ホール公演のコツをおうかがいしたい。
森 僕らはキネマ倶楽部や日比谷野外音楽堂と並行してホールツアーをやっていて、お客さんのノリはそんなに変わらないけど、最近はホールでは座って聴いてほしい曲を意識して演奏するようになりましたね。
渡辺 今年の春にやったEGO-WRAPPIN'の「HALL LOTTA LOVE ~ホールに溢れる愛を~」を神奈川県民ホールで拝見したんですが、素晴らしかったな。
中納 ありがとうございます。うれしいです。
渡辺 ちょっとオルタナティブな感じの曲も面白かったし、ホールでもお客さんの熱狂ぶりは変わらなかった。
森 ホールでは定番の曲だけでなく、アルバムの中のちょっと埋もれがちな曲を演ってみたりしますね。夏の野音なら踊れるノリノリの曲を多めにするとか、会場によって変化をつけるのが楽しいんです。
吾妻 なるほど。参考にしよう。
中納&森が感じるバッパーズの魅力とは
森 吾妻さんたちの世代はやはり、ブルースの影響が大きいですよね?
吾妻 「ブルースを聴かないヤツは人間ではない」という時代に青春を過ごしてきたのでね(笑)。
渡辺 それは吾妻の周りの30人くらいじゃない?(笑)
吾妻 日本のブルースブームは京都から火が点いたと言われていて。ちょっと前まで日本の大学院に留学で来ていたジョナサンというスウェーデン人がいるんですが、彼の卒論のテーマが「日本のブルース文化」。彼は京都に根付く日本のブルースに触れて、衝撃を受けたとか。
渡辺 その卒論に出てくるのか、Mitsuyoshi Azumaも(笑)。
森 僕らの世代は、ブルースは後追いの人が多いと思います。僕は吾妻さんを知ってからより興味が出てきたし、ブルースの解釈や聞こえ方が変わったような気がします。
──同じミュージシャンのお二人から見てバッパーズの魅力とは?
森 ギタリストとして、バンドリーダーとして吾妻さんは憧れの存在ですし、ライブの豪放磊落なパフォーマンスは誰にも真似ができない。バッパーズの楽曲には、ジャンプ、ジャイブ、ブルース、ジャズなどさまざまなジャンルの音楽が入っていて、ウキウキするし、オモロいし、ロマンチックなところもあって。
中納 バッパーズは好きな音楽を自由に表現し続けていることが素晴らしいと思うし、何かに抗っている強さを感じるんです。それこそが音楽の本来持っている一番の強さなんじゃないかと。
森 それを難しい表現ではなく、ユーモアたっぷりに楽しく聴かせてくれるところが最大の魅力なんとちゃうかな。バッパーズは音楽が好きなら誰でも好きになってしまうバンドやと思います。
中納 前からお聞きしたいことがあったんですけど、吾妻さんって歌詞を考えるときはどういう順番で書いていくんですか?
吾妻 強い言葉を思いつくと組み立てやすいかな。「やっぱり肉を喰おう」とか「俺のカネどこ行った?」とか、そういう言葉が出てきたら、そこからでっち上げていく。
中納 バッパーズの曲って、歌詞がリズムにちゃんと乗っているから、言葉がすっと入ってくるんですよね。
吾妻 もしかしたら、若い頃からブルースの英語の歌詞を自分で聞き取ることを趣味にしてきたというのは大きいかもしれない。
中納 吾妻さん、英語が堪能なんですか?
吾妻 全然。だから辞書を引きつつ、やっと聞き取れたときのカタルシスがたまらない。でも、ブルースって、けっこうクダらない歌詞も多いんですよ。その影響は大。ブルースは歌の音楽ですからね。亡くなった小出斉くんの著書「意味も知らずにブルースを歌うな!」にあるように。
中納 バッパーズは海外の楽曲をよくカバーしていますけど、英語詞を日本語にするセンスも独特ですね。
吾妻 日本語の曲や自己流の訳詞をするようになったのは、ブルースの歌詞の面白さをわかってほしいという気持ちがあったから。70歳くらいになるまではストレートなブルースを日本語にできるだろうと思っていましたが、まだできない。
中納 日本語でこんな愉快な歌詞を歌っているというのは驚きでした。でも一度、バッパーズのライブで私が「やっぱり肉を喰おう」を歌いたいと言ったら、「あの曲は女性にはふさわしくない」って却下されましたけど(笑)。
次のページ »
21年ぶりに出演したフジロックを振り返って