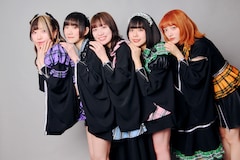東北訛りもカラーの1つ
──今おっしゃった「Unbalance Addiction」「Honey Bee」に加え、既存シングル曲「I'm GAME!」や「Stella」が並ぶアルバム後半はめちゃめちゃ高低差のある流れですよね。
「Honey Bee」と「Unbalance Addiction」はどうつなげるかすごく迷ったんですけど、逆にここまではっきりと温度差があるのもこのアルバムの魅力につながるのかなと思って。「私、ここからここまでできちゃうんだよ!」と感じてもらえたら、素直にうれしいです。
──実際、アルバムが進むにつれて「次はどんな曲が来るんだろう」というワクワク感が味わえました。「Honey Bee」は歌ってみていかがでしたか?
今まで挑戦したことのない曲調だったので、難しさはもちろんあったんですけど、実際に歌ってみるとすごく楽しかったです。作曲チームの皆さんがレコーディングに立ち会ってくださったのですが、ノリノリで「いいね!」とか「かわいーっ!」と言ってくださって(笑)。リラックスしてレコーディングに臨めました。そのときに「髪の毛結び直してリラックス / 部屋着になって優勝chill out」の「部屋着(へやぎ)」を私が「や」の部分を強調して発音したのに対して、「(平坦な発音で)“へやぎ”じゃない?」という指摘を受けたんですよ。
──アクセントの付け方が話題になったと。
私は宮城県出身なんですけど、「もしかしたら東北の訛りかもね」という話になったんです。
──確かに、関東だと平坦な発音をすることが多いですね。
やっぱりそうなんですね。そのスタジオにもう1人、東北出身の方がいらっしゃって、その方も私と同じアクセントだったので「やっぱり訛りかもしれないですね。どうします? 録り直しますか?」と聞かれたんですけど、最終的には「せっかく立花さんの色を出したアルバムなんだから、その訛りを生かしましょう」と、そのまま残してもらったんです。キャラクターとして歌うんだったら直したほうがいいんでしょうけど、立花日菜の作品だったら訛りも個性になるし、曲の雰囲気も相まって遊びにつながっている感じが面白いなと思いました。あと、ラップってアクセントをどのくらい崩していいんだろう?と悩むこともあったので、いろいろと勉強になった1曲ですね。
頭の中で歌詞の世界を映像化
──ユルさの伝わる「Honey Bee」とは対照的に、「Unbalance Addiction」は激しさを伴うアッパーチューンです。テンポが速いので、歌うのが大変そうですね。
カッコいい曲なんですけど、歌うのが本当に難しくて。ライブで披露するのがちょっと不安ですが、バチッとハマったらすごくカッコいい目玉楽曲になると思うので、ライブで歌う自分の姿をイメージしながらレコーディングに臨みました。
──この曲もそうなんですけど、いろんなタイプの曲調に合わせてなのか、それとも曲に引っ張られてなのか、立花さんの声の表情も曲ごとに異なっているように感じます。
例えば「めっちゃ低い音で歌うぞ」という意識をして声を変えているつもりはないんですけど、たぶん歌い方は曲調に引っ張られて変わっていて、それで声も自然と曲に合わせて寄っているのかもしれません。立花日菜として歌う以上、声を作る必要はないんですけど、逆にそこは悩むポイントでもあって。ただ、カッコいい曲だからあえて声を低く作るとか、かわいい曲だから高めで歌うとかはなくて、「自分の出しやすい音で歌う」というのは意識しているので、そこのちょっとした変化を感じていただけたのならすごくうれしいです。
──歌うときは、その曲の主人公を意識したり演じたり、そういう感覚もあるんでしょうか?
イメージで言うと、自分でミュージックビデオを撮っている感覚に近くて。頭の中で歌詞の世界を映像化して、それが曲によってはMVのようだったり、ライブ風景だったりするんです。なので、アニメタイアップ曲を歌うときは、アニメのオープニングやエンディング映像を「こういう感じかな?」と勝手に想像しながら歌ってます(笑)。
──そのへんは俯瞰で見てらっしゃるんですね。
そうかもしれません。だから、あとからその曲のMVを実際に撮ることになると、自分が最初に想像した絵と違っていることもあって、新しい魅力を見つけた気持ちになれます。
初の作詞曲「この場所で、また」に込めたものは
──ご自身で作詞を手がけた「この場所で、また」は、曲との向き合い方がほかとは異なるのかなと思います。
全然違いました。今までの曲は資料をいただいてから歌詞やメロディを覚えて、曲の世界を映像でイメージして歌うんですけど、この曲は自分が書いた、自分の思いを歌うので、レコーディングのときはとても恥ずかしかったです。あんまり集中できなくて、少し自意識過剰になっちゃいました(笑)。でも、すごく新鮮な体験をさせてもらったなと思います。
──作詞はこれまでもしていたんですか?
作詞の経験はなかったんですけど、学生の頃から文章を書くのが好きで、作文とかポエムはよく書いていました。
──では、自分の思いや考えを言葉にすること自体は、難しいことではなかった?
「この場所で、また」は「ライブの最後に歌えるような曲」をイメージして曲を作ってもらったんですが、歌詞で自分が伝えたい大きなテーマや使いたい言葉はわりとスッと出てきました。ただ、第一稿をプロデューサーさんに提出した際に、最初は私に向けた目線で、最後はもっとみんなに語りかけるような目線にしてほしいと、指摘されたんですね。「この言葉はちょっと違う表現にしてみたいです」とか「同じニュアンスで別の言い回しに直していただきたい」とか、あとからはめていく作業が一番難しくて、改めてプロの方は引き出しがいっぱいあるんだな、すごいんだなと実感しました。
──自分の中で一度できあがったものを、書き換えたり組み替えたりするのってなかなか大変な作業ですからね。
「1番で言いたいことをまとめきって、2番では違うことを書こうかな」とか大改造が発生すると、複雑なパズルみたいになってくるんですよね(笑)。元の形に戻してみたり、さらに書き換えてみたり……最終的に整合性を取る作業に一番時間がかかった気がします。
──そして、完成した歌詞をレコーディングで歌うことになると。
普段は仮歌を聴いて曲を覚えるんですけど、「この場所で、また」に関しては仮歌をほかの人に歌ってもらうのも恥ずかしくて。ずっと「仮歌いらないです!」と言っていたんですけど、私以外の方にも共有しなくちゃいけないから一応作ることになりました(笑)。とにかくこの歌詞を人に見られるのが最初は嫌で、今でもまだ恥ずかしいです……。
──でも、このインタビューが公開される頃にはアルバムが発売されて、「この場所で、また」を多くの人が聴いているわけですが(笑)。
そうなんですよ!(笑) でも、ファンの皆さんは優しいし、どんな言葉であれ私が歌詞を考えたことに対して「いいね!」と言ってくれると信じています。曲を発表していろんな感想が届いたときに、やっと自信につながったり新しい魅力を見つけられたりするんじゃないかなと、今は思っているところです。
──「ライブの最後で歌う曲にしたかった」ということですが、「この場所で、また」というタイトルを含め、立花さんとファンの皆さんの“再会の約束”への思いが込められた、大切な1曲になりそうですね。
だといいな。私自身は「ライブめっちゃ楽しい!」とポジティブな気持ちだけでステージに立てるタイプではないし、ときには「もう立てないかも……」とネガティブな気持ちになることもあるので、「この場所で、また」という曲が、私がまたステージに立てる勇気にもつながったらいいなと思っています。日常生活で大変なことがあって、元気をもらうためにライブに来てくれる人もいると思うんですけど、私自身もライブを通じてみんなから元気をいっぱいもらっているし、みんながいるからまたその次につながっているわけで。そういう気持ちを少しでもみんなに伝えられたらいいなと思ってこの歌詞を書きました。
アーティストとしての理想像
──「この場所で、また」は、“アーティスト立花日菜”として真の意味での第一歩となるこの1stアルバムの、締めくくりにぴったりな内容だと思いました。
ありがとうございます。プロの作家さんたちが作った素晴らしい楽曲の最後にこの曲が来ることで、ちょっとだけホッとしたところもあって。と同時に、いろんな人に支えられて今この場所にいるんだなって、改めて実感した1曲でもあります。
──そういう意味でも、名刺代わりの1枚ができましたね。
アーティスト活動もそうだし私自身の人間性もそうだし、立花日菜をわかりやすい形で表したお気に入りの1枚になりました。
──12月28日には1stライブの開催も決定しています。
当日は絶対に緊張すると思うんですけど、道に迷ってしまったり苦しくなったりしたら自分が書いた「この場所で、また」の歌詞を思い出して勇気をもらおうと思っています。今は一生懸命がんばることしかできないし、準備期間に入ったらプレッシャーも感じるとは思うんですけど、最終的にみんなと楽しむことができたらそれで大成功だっていう考えは根本に持っていたいです。もし失敗してもその失敗を「懐かしいね」って言えるくらい大きくなっていけたらいいなと思います。
──1stアルバム、1stワンマンライブと新しい経験を経て、ここからアーティストとしての意欲もどんどん増していくのかなと思います。ここから3年後、5年後と将来どんなアーティストになっていたいですか?
変わらず楽しく活動できるのが一番かなと。気合いを入れまくったライブも素敵だと思うんですけど、私自身そういうことが苦手なので(笑)。みんなに部屋着で遊びに来てもらったり、「今日は気分がちょっと落ち込んでるから、日菜さんのライブを観に行こう」ぐらい気軽な気持ちで来てもらって、少しでも心を軽くして帰れる場所を作れるようなアーティストになりたいです。