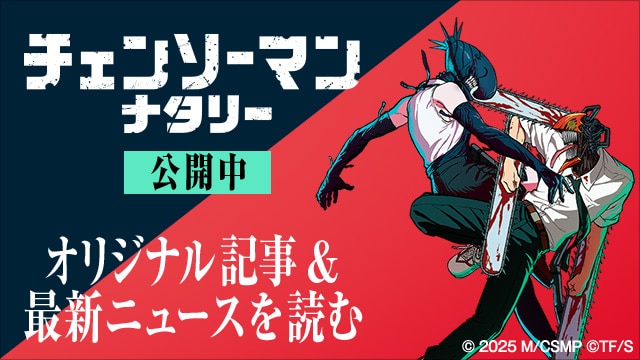バトルシーンの“ライブセット”
──バトルに突入してからはテクノアーティストである牛尾さんの本領発揮ですね。
制作側のリクエストを受けながら、音響監督とどこにどういう曲を当てはめていくかを考えるんですけど、後半に突入するとその先はずっとバトルだから緩急が付けられなくて「どうしよう」と思いました。なんていうか、DJのやり始めにありがちな“ずっとピークタイム”状態になっちゃうと、観ているお客さんも疲れちゃうし、飽きるし。緩急のダイナミクスがなくなると何を見たか覚えてない、引っかかりのないバトルシーンになっちゃうので、ある程度方向性を持ちつつ、しっちゃかめっちゃかにならないプランニングを考えるのは難しかったです。でも、振り返って考えればダンスミュージックのライブセットは……僕はDJはやらないのでライブセットという表現をしますけど、今回のような緩急の作り方を意識してたなと思います。
──なるほど! ライブセット的な流れはすごく納得です。
テンポがドタバタしちゃうと連続性がなくなるし、突飛なことばかりしちゃうと観ている人がついて来れないと思うので、ある程度テンポ感を保ちながらリクエストで作ったものも入れ込みつつ、最後までつないでいく。そういう観点からいくと、自分にできることはやはりテクノっぽい方向になるんですよね。「チェンソーマン」の土台の中ならできると思ったのは、昨年アムステルダムや「SONICMANIA」などでやったソロライブのおかげです。あれで「チェンソーマン」をベースにしたストラクチャーの作り方が染み込んでいたので、そのテンションのまま物語の疾走感を表現したら面白いかなと思いました。今回の映画って実は100分しかなくて、後半のバトルもそこまで長くないんです。その尺感でバトルのシークエンスを構築して最後にピークを持ってくる作り方は自分のライブセットをベースに考えました。だからサントラではやらなかったですけど、途中画面が真っ暗になるシーンで音がフィルターでこもるのも作曲の段階から見越して作っていて、ダビングという最終ミックス作業のタイミングでそういうふうにしてほしいとお願いしたんです。フィルターで音をこもらせるのもダンスマナーですよね。クラブに行ったことがある人ならわかると思うんですけど。
──映画を観ていて「これ、クラブじゃん!」とテンション上がりました。
あそこはフィルターだけじゃなく低域も調整してもっとモコモコいうようになってて。深夜3時とか4時にLIQUIDROOMのフロアの扉が閉まってるときの「これ開けたらヤベーことになってるぞ!」って音漏れ感覚を作れたらカッコいいなと思って。本来は映画音楽の現場で作曲家が卓をいじるってあまりやっちゃいけないことなんですけど、エンジニアさんに「すみません! ここ、こうしてください」とお願いして。そこをパート演出した重次(創太)くんも「耳鳴りみたいなことをやりたい」と話していたので、いろいろ試行錯誤した結果、正解の形になってよかったなと思います。そういうダンスマナーによるミックス作業が後半ずっと続いて、テンポがだんだん上がっていく感じでしたね。「edge of chainsaw」がオーケストラの大編成で鳴ってザ・映画!みたいな感じになったあと、最後に海辺で戦うときはドラムンベースになり(「dance with chainsaw」)、海に落ちて2人きりになるとプールに戻っていく(「in the sea」)という大きな構造のサウンドトラックになりました。
──映画館のいい音響だと、2回目以降の鑑賞は牛尾さんの100分のライブセットとして楽しむこともできますね。
やっぱりダンスミュージックマナーを知ってるとそういう作り方をしたいじゃないですか。ビートだけにハマる瞬間も欲しいし、ドラマティックなセットにしたい。電気グルーヴとライブ現場でご一緒させていただいていることも僕にはすごく大事なことなので、ダンスミュージックマナーで作らせてもらえたのはよかったです。アニメ映画でダンスミュージックをやろうとすると、石野卓球さんの「IN YER MEMORY」(1995年公開の大友克洋原作・総監督「MEMORIES」メインテーマ)を思い出すんです。ああいう感じの曲にヤられ続ける10代だったので。果たして自分がそういう10代を生み出せているかと思うと……とにかく真面目にやるしかないですね。
これまでの経験則が結び付いて
──「レゼ篇」の音楽は、牛尾さんの劇伴デビュー作「ピンポン THE ANIMATION」(2014年)から現在に至るまでのダンスミュージックと叙情性がとてもいい形で融合している印象を受けました。
たまたまですけど、今回の音響監督の名倉さんは「映画 聲の形」(2016年)と「リズと青い鳥」(2018年)のときのミキサーさんなんです。もちろん全体の方向性については名倉さんの統制下で進めるわけですけど、僕は“名倉音響組”のスタッフで、名倉さんは僕のことをすごくわかってくれているので、ある程度の裁量を渡してくださいました。ライブセットの場合、どこに何をどういうふうに当てるかってすごく大事じゃないですか? それって一般的には劇場作曲家の領分を超えていて、本来は音響監督さんとか選曲さんの仕事なんです。「ピンポン THE ANIMATION」「DEVILMAN crybaby」のダンスミュージックとしての音楽的側面は自分の今まで培ってきたものだし、名倉さんの信頼のもとそれをやらせてもらったことも、全体を構造的に作れたことの要因の1つかもしれない。あまり集大成という言葉は使いたくないですけど、これまでのいろんな経験則が結び付いて今回結実したことはよかったなと思います。
──「レゼ篇」を観ている間、リズミカルにページをめくってコミックを読み進めていくような感覚があったんですが、𠮷原達矢監督の演出に関してはどう思われましたか?
𠮷原さん、すごいなと思いました。時間の使い方がポップなんです。ダビング作業をしているときに「𠮷原さんってジャンルで言うとなんの人なんですか?」と聞いたんですね。アニメに携わる人はそれぞれ得意不得意があると思うんですけど、𠮷原さんはテレビシリーズではアクション監督だったから「やっぱりバトルが俺の腕の見せどころじゃい!って感じなんですか?」と尋ねたら「いや、牛尾さん。私はずっとギャグアニメをやりたいだけの人なんです」って。「えっ、そうなの!?」と驚きました。
──𠮷原監督はこれまで「波打際のむろみさん」(2013年)や「夜ノヤッターマン」(2015年)を手がけていますが、「チェンソーマン」の現場でそういう言葉が出てくるとは意外です。
でも、振り返ってみると確かにそうなんです。カッコいいカット割とかシーンもできるんだけど、テンポ感やタイム感はギャグなんです。それがさっき言った、ポップな時間のコントロールにつながるわけですけど、まとめ方とテンポ感がうまい。ポン、ポン、ポン、バンでワーッ!っていう、起承転結のある4コママンガみたいなカット割りをするから、間の取り方とか笑い待ちみたいなところが必ずあるという。ダビング作業中に𠮷原さんが出す指示がすごくいいんです。僕にはない視点があって。本当にすごい人だと思いました。
──自分は体感的に劇場版「チェンソーマン レゼ篇」は何回も繰り返し観たくなる映画だなという印象を持ったんですが、それは藤本タツキさんの持つギャグセンスに通じるテンポ感だったからかもしれないですね。
そう思います。それを理解できたので、次またやらせてもらえたらもっと面白い曲を書くようにします。
──原作の藤本さんは1992年生まれとまだお若いですし、この先どこまで行くのか気になります。牛尾さんは1983年3月1日生まれですが、同じ月にダンスミュージックの金字塔であるNew Orderの「Blue Monday」がリリースされたことは運命的なものを感じますね。
83年ってファミコン発売とYMO散開の年なので、けっこうテクノ当たり年だと信じてます(笑)。あとはシンセでいうと、DX7(FM音源を採用した世界初のフルデジタルシンセサイザー)発売かな。
──ハウス / テクノシーンを支えたドラムマシンTR-909も1983年発売ですね。その後の音楽界を大きく変えた年でもあると。近年、打ち込み系のミュージシャンがメジャーな映画音楽を手がけるケースも増えてきましたが、「トロン:アレス」の音楽を手がけたトレント・レズナーとアッティカス・ロスのコンビなんて非常にシンパシーを感じるチームではないでしょうか。
だいぶ恐れ多いですけど(笑)、勇気付けられます。僕はオーケストラの譜面を1人で書けるわけじゃありません。アカデミズムを経ない、アンダーグラウンド出身者でありつつ、劇伴作曲家をやらせてもらっていますけど、トレント・レズナー、ジャンキーXL、惜しくも亡くなられましたがヨハン・ヨハンソンの活躍を見るともう少しがんばれるかな、と思います。さらに僕の世代のルドウィグ・ゴランソン(1984年生まれ)は、最初からそこに垣根がない。すごくいい時代ですよね。
──そう思います。
それもテクノロジーの発展とともに起きた出来事だと思うんです。僕は坂本龍一さんが亡くなられたあとに坂本さんのことを語る機会が多く、関係者の方にいろいろお話を伺っているんですけど、映画「ラストエンペラー」(1987年)の時代はカットが変わるたび楽譜と計算機とにらめっこしながら作業をやらないといけなかったのが、今はもうコンピュータ上で瞬時にできちゃう。そういう時代に仕事ができる年齢でいられるのはすごくありがたいことだし、とても楽しいです。AIもあり、この先はどうなっていくのやら、ですけど。
──牛尾さんの劇伴担当作品は今後もNHK連続テレビ小説の「ばけばけ」、来年1月スタートのテレビアニメ「違国日記」、2月公開の劇場版「僕の心のヤバイやつ」と控えています。
年明けの1月くらいまでずっと締め切りが続く感じです。ちょうど「ばけばけ」の最初の締め切りと「レゼ篇」の締め切りが被っていたんです。もちろん単体で作業する時期は必ず取るようにしているので、ずっと並行してとかはないんですけど、たまたまそういうタイミングがあって。その時期は爆弾殺戮ショーの曲を書きながら、一方で温かい食卓のお味噌汁がおいしい曲とかを書いていて、頭の中が分裂しそうになりました。あしゅら男爵みたいな顔して曲作ってました(笑)。
──劇伴依頼のリクエストがひっきりなしで大変だと思いますが、ますますの活躍を楽しみにしております。
ありがたいです。ただ、さっきも言った通りアンダーグラウンド出身なので、名のある劇伴作曲家みたいな実感はないんです。なので偉そうにならないように心がけています。
──今後の夢としては、やはりフェイバリットを公言されているグザヴィエ・ドラン監督との仕事ですか?
そうですね。共通の知り合いがいるので音源を送ったことはあるんですけど、ドランさんは映画監督としては休業状態に入ってしまったので。でも、いつかお話ができたらいいなと思っています。
プロフィール
牛尾憲輔(ウシオケンスケ)
2003年よりテクニカルエンジニアとして石野卓球、電気グルーヴ、RYUKYUDISKO、DISCO TWINSの音源制作やライブをサポート。2007年に石野卓球主宰レーベル・platikから発表されたコンピレーションアルバム「GATHERING TRAXX VOL.1」にkensuke ushio名義で参加し、2008年にはagraph名義として初のソロアルバム「a day, phases」を、2011年には2ndアルバム「equal」をリリースした。その一方でナカコー、フルカワミキ、田渕ひさ子とともにLAMAを、ミト(クラムボン)とアニソンDJユニット2 ANIMEny DJsを始動させたほか、CMやアニメ作品などに楽曲を提供するなど多方面で活躍。2014年4月には「ピンポン THE ANIMATION」で初めて劇伴を担当した。2016年2月に3rdアルバム「the shader」を完成させ、同年9月には映画「聲の形」の劇伴を担当。2018年にはNETFLIX「DEVILMAN crybaby」、映画「サニー/32」、映画「リズと青い鳥」、映画「モリのいる場所」の劇伴を担当した。2020年にはNETFLIX「日本沈没2020」の劇伴が大きな反響を呼び、全米でもCDが発売、配信される。2022年1月には、音楽を担当したテレビアニメ「平家物語」が放送開始。さらにはテレビアニメ「チェンソーマン」の音楽担当を務める。2025年9月公開の劇場版「チェンソーマン レゼ篇」でも音楽を担当した。ほかにもNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の音楽など、その活躍は多岐にわたる。
2025年10月9日更新