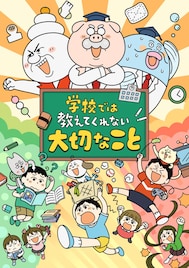小林有吾が週刊ビッグコミックスピリッツ(小学館)で連載中の「アオアシ」は、Jリーグの下部組織・Jユースを舞台にしたサッカーマンガ。サッカーを愛する中学3年生・青井葦人(アシト)が、東京シティ・エスペリオンFCのユース監督・福田達也に才能を見出され、数多の壁にぶつかりながら、チームメイトと切磋琢磨し成長していくさまを描く。2022年にTVアニメ化され、第2期の制作も決定したばかりだ。
そんな小林が、2018年に月刊少年マガジン(講談社)で連載開始した「フェルマーの料理」の題材は、サッカーとは打って変わって“料理”。数学者を志すもその道を挫折した天才数学少年・北田岳が、野望を抱く謎多き天才シェフ・朝倉海と出会い、料理人としての能力を開花させていく。2023年に高橋文哉と志尊淳を主演に迎えてTVドラマ化されたほか、7月からTVアニメがテレビ朝日系全国24局ネット「IMAnimation」枠で放送される。
コミックナタリーでは「アオアシ」と「フェルマーの料理」、両作品の魅力を徹底解説した特集を展開。各作品の魅力や見どころはもちろん、2作品の共通点など、さまざまな視点から掘り下げていく。合わせて原作者・小林有吾からのコメントもお届けする。
文 / ナカニシキュウ
“小林有吾節”が生み出す「アオアシ」と「フェルマーの料理」
「フェルマーの料理」と「アオアシ」は共通点の多い作品である。作者が同じなんだから当たり前だろうと言ってしまえばそれまでだが、絵柄やテイストの類似のみにとどまらず、物語構造や人物配置、興奮ポイントの作用の仕方に至るまで、マンガ作品としての読み味が非常に近いのである。かたや料理、かたやサッカーと、ほとんど共通項がなさそうな題材を扱っているにもかかわらず、同じような楽しみ方ができてしまうということだ。その共通項こそが紛れもなく、“小林有吾節”と言っていいのではないだろうか。
小林は専門性の高い題材を求道的に突き詰める精密な描写と、そこで繰り広げられる複雑な人間模様やきめ細かな心理描写、手に汗握るヒリヒリしたストーリー運びに定評のある作家だ。例えば「フェルマーの料理」はグルメマンガではあるが、まるでスポーツマンガやバトルマンガを読んでいるかのような錯覚を起こすほどに熱くなれる作品であり、まずその意味において「アオアシ」と共通する。王道の熱血少年マンガが好きな人であれば料理に興味がなくとも楽しめることは間違いなく、むしろ興味がない人ほど「料理ってこんなに熱くなれるんだ!」と大きな衝撃を受けることになるだろう。
手始めに、両作の概要を簡単におさらいしておこう。まず「フェルマーの料理」は、“数学”と“料理”を掛け合わせた異色のグルメマンガ。ちなみに料理を題材とする小林作品は過去にも「てんまんアラカルト」があり、「アオアシ」にも料理を軸としたスピンオフ短編が存在する。
言うまでもないかもしれないが、「フェルマーの料理」という作品タイトルは「フェルマーの最終定理」から取られている。この定理が成立することを予想したピエール・ド・フェルマーの死後330年を経た1995年にようやく完全に証明された、“数学界最大の謎”とも称された壮大かつロマンチックな命題だ。この有名な数学用語と「料理」という一見ミスマッチな語を組み合わせることで「ん? どういうこと?」と読者の興味を引く仕掛けになっており、このタイトル自体が一種の伏線として機能している。
主人公は、幼少期から偉大な数学者になることを夢見てきた高校生・北田岳。日本数学オリンピック選考会で挫折を味わった彼は、大学受験を前に進むべき道を見失ってしまう。そんな彼の前に偶然現れた若き天才シェフ・朝倉海に才能を見出され、岳は料理の世界へ足を踏み入れることに。“卓越した数学的思考を料理に生かす”という独自のスタイルを武器に、海の無茶な要求に悪戦苦闘しながらも、着実に努力と工夫を重ねて成長していく──。
一方の「アオアシ」は、Jリーグの下部組織にあたるユース(高校生年代)チームの世界を舞台にしたサッカーマンガだ。プロサッカーや学校のサッカー部ではなく、Jリーグユースを扱う作品が存在しないことに疑問を持ったスピリッツ編集部が、小林にこの題材での執筆を持ちかけたのだそう。
Jリーグ加盟クラブには、ユース年代以下の下部組織を保有することが義務づけられている。プロに直結する育成モデルを整備することで、日本サッカー全体の競技レベルを底上げしようというのがその狙いだ。そこにはおそらく、学校の部活動としてのサッカーとは明確に異なる世界があることだろう。つまり、同じ“高校生のサッカー”であってもJリーグユースと高校サッカーとでは生まれるドラマの種類がまったく異なることが予想され、それゆえの題材指定であったことが推測できる。
主人公のアシトは、作中で強豪Jクラブと位置づけられる東京シティ・エスペリオンFCのユースチームに所属してプロを目指す高校生。身体能力や技術力では周囲の選手たちに劣るものの、フィールド全体の選手の位置関係を把握できる特殊な空間認識能力(作中では「俯瞰の目」または「イーグルアイ」と呼ばれる)を先天的に備えている。そんなアシトの才能を見出したエスペリオンユースの監督・福田達也や、その福田が信頼を寄せる伊達望コーチ、そして個性的なチームメイトらとぶつかり合いながら、アシトは少しずつその才能を開花させていく──。
これら両作は、一体どんなところがどう共通するのか。ここでは次の3つのポイントに絞って解説していきたい。
①「数学×料理」「主人公がディフェンダー」トリッキーな題材が面白い
第1の共通点として挙げたいのは、作品の根幹をなすテーマ設定にひとひねりあるところだ。
“数学×料理”を描く「フェルマーの料理」
「フェルマーの料理」においては、なんといっても「“数学”と“料理”を掛け合わせたグルメマンガ」という概要文がまず異彩を放っている。最初に本作についてそう説明されたとき、筆者と同様に多くの読者が何を言っているのかわからなかったはずだ。何しろ主人公の岳自身も、師匠となる海から「お前の数学的思考は料理のためにある」と断言された瞬間には狐につままれたような表情を浮かべていたほど。しかし一読すればわかる通り、本作では本当に数学と料理とが有機的に絡み合うのである。
岳は料理のできあがりを“答え”と捉え、そこから逆算して“式”つまりレシピを組み立てる(作中では頻繁に「方程式」を「レシピ」と読ませている)。例えば岳が料理の材料や調理工程を推測するシーンでは、一心不乱に数式を書き殴りながら「『豚肉』『蟹』……食材のそれが集合…『数字』だとする」「これに『煮る』とか『焼く』とか 調理法がたぶん『関数』なんだ」などと口走り、瞬く間にオリジナルの方程式を完成させてしまう。そして見事、料理の全貌を解き明かしてみせるのである。
高校時代に数学のテストで100点満点中8点を叩き出した実績を誇る筆者は、作中に描かれる数式の妥当性を検証する術を持たない。しかし、経験と感覚がすべてだと思い込んでいた料理という分野をここまで数値化して理詰めで見せてくれる描写には、「“数学で料理”ってそういうことか!」と思わず膝を打つほかなかった。客が手にするフォークの温度にまでこだわるくだりや、イノシン酸とグルタミン酸の数値から“旨さ”を導き出そうとする描写なども同様だ。きっと多くの読者に新たな視点をもたらしてくれることだろう。
「アオアシ」の主人公はディフェンダー
一方の「アオアシ」においては、“主人公がディフェンダー”という設定のユニークさが際立っている。一般的にサッカーマンガではフォワードや攻撃的ミッドフィールダーなど前線で得点を挙げるポジションの選手が主役を張ることが多く、ボランチ以降の守備的なポジションが主人公に与えられるケースは稀である。逆に、ゴールキーパーを主人公にした作品のほうがイメージしやすいくらいだ。
もともとはフォワードの選手としてエスペリオンユースに入団したアシトだったが、ある日突然、福田からディフェンダーへの転向を命じられる。最初は強く抵抗するアシトだったが、仕方なく守備を学んでいくうち、どんどんその奥深さや楽しさに目覚めていく。しかも、懇切丁寧な戦術描写によって読者はサッカーにおける守備の考え方をアシトとともに学んでいくことができ、サッカー観戦の楽しさが倍増するという副産物まで得られてしまうのである。
連載当初は「ディフェンダーが主役で面白いマンガになるの?」と心配した読者も少なからずいたのではないかと思われるが、それはそのまま「フェルマーの料理」における「“数学×料理”が題材って、それ面白いの?」という疑念に通ずるものがある。そして、その疑念に対して徹底的に専門性を掘り下げた描写と卓越した筆力で満額回答を示しているという点においても、両作は完全に一致する。
もっと言えば、主人公が大きな挫折から新たな道へ飛び込んで成長していく物語構造にも同じことが言えそうだ。岳が数学者になる夢を断念して料理の世界へ身を投じていったように、アシトはフォワード失格の烙印を押されたところからディフェンダーとしての才能を開花させていく。自分では思ってもみなかったところに意外な適性が見つかることは実生活においても往々にしてあることで、多くの人に勇気と希望を与えるストーリーラインと言えるだろう。
②天才主人公×天才師匠という構図
2つ目の共通点は、主人公とその師匠的存在がどちらも天才タイプであることだ。
数学の天才 北田岳とカリスマシェフ 朝倉海
「フェルマーの料理」においては、“料理のイメージを数式としてひめらく”という特殊能力を持つ未完の天才・岳に対し、彼を導く役割を担う海はカリスマ天才シェフとして描かれる。この両名が織りなす緊迫感あふれる師弟関係も、本作の大きな魅力の1つだ。
海はいかにも天才シェフ然とした超然たる振る舞いで、岳に対して次々と無理難題を課していく。必要以上の助言は決して与えず、あくまで自力で答えを見つけだすことに価値を見出しているようだ。凡人の感覚からすると「とはいえ助言が必要最低限にも足りていないのでは?」と思ってしまうほどの突き放しっぷりにも見えるが、その態度がさらに彼の天才性を際立たせている。天才なんだから仕方ないのである。しかも岳も岳で、天才さ加減においては引けを取っていない。
海の求める水準にどうしても達することができず、岳は常に極限まで苦悩することになるのだが、破滅寸前のギリギリのところで必ず何かをひらめいて窮地を脱するのである。その際に描かれる、岳の脳内を大量の数列が駆け巡る鮮烈な心象風景は特筆に値する。それは“天才にしか見えない景色”であり、本作における重要な興奮ポイントの1つと言えるだろう。
そしてそんな2人は、固い握手とともに「俺たちは料理を以て神に挑む」と常軌を逸した野望を口にするのである。天才と天才が師弟としてぶつかり合うときの常人離れしたヒリヒリしたやり取りに、ぜひ圧倒されてみてほしい。
俯瞰の目 青井葦人×元天才プレーヤー 福田達也
「アオアシ」では、かつて天才プレーヤーとして鳴らした指導者・福田が、不敵な笑みを浮かべながら荒削りな天才少年・アシトに次々と難易度の高い課題を与え、追い詰めていく。この構図は、わかりやすく岳と海の関係性にそのまま重なる。
福田も海と同じように何を考えているのか掴みかねるところがあり、時として致命的なまでに言葉が足りない。なぜなら天才だからである。作中で最も大きな福田の“無茶振り”は前述したディフェンダー転向指令と言えるが、それ以外にもアシトたちに無理難題を要求する場面は多数存在する。その要求の裏にある意図は決して口にせず、アシトらが自力で答えにたどり着くことを期待しているのも海とまったく同様である。
そして、岳が料理のイメージを数式としてひらめくのと同じように、アシトの脳内にはフィールドを俯瞰したイメージが浮かびあがり、それによって危機を察知したりチャンスの芽をいち早く感じ取ったりする。その“天才にしか見えない景色”の鮮烈なビジュアル表現は、両作に共通する特徴的な高揚ポイントだ。それを契機にギリギリのところで窮地を脱する流れも含め、題材がまったく異なるにもかかわらず得られる快感の種類が酷似しているのは非常に興味深い現象と言える。
③とにかくアツい“バトル”シーン
3項目はこれだ。無論「フェルマーの料理」は料理マンガなのでバトルシーンなど存在しないわけだが、それに匹敵する激アツシーンが大きな見どころとなっている。
「フェルマーの料理」は実食シーンがアツい
努力の末に一段階覚醒した岳が新たな方程式(レシピ)を披露する実食シーンこそ、「フェルマーの料理」における最大の見せ場と言っていい。バトルマンガでいえば、苦しい修行を乗り越えた主人公が新たな技や戦い方を強敵相手にお見舞いするシーンに相当するからだ。このシーンを見るためにそれまでの苦しい場面を読んできたのだ、と言っても過言ではないほどのカタルシスが得られる瞬間である。
岳の料理を供された者は、まずその香りに驚愕する。そしてひと口含んだ瞬間に恍惚の表情を浮かべ、その料理のどこがどう優れているのかを事細かに多彩な表現で興奮気味に言語化し始めるのである。
それはまさにバトルマンガにおける“外野の実況解説”に類似するもので、鳥山明「DRAGON BALL」で言えば天津飯らが主に担っていた役回り。的確な分析や理路整然とした感想を述べるセリフでページの大部分が占められていくさまは、文字が多すぎてしんどいレベルをはるかに超越してもはや快楽ですらある。「もっと言葉の限りを尽くして岳を褒め称えてくれ!」という気持ちにさせられること請け合いだ。
「アオアシ」は当然試合シーンがアツい
サッカーマンガにおける“バトル”シーンといえば、それは言うまでもなく試合のシーンである。練習で習得した技術は、実際のゲームで実践することによって初めて本当の意味で身につけられるもの。その“試合内での気づき”が「アオアシ」では丁寧に描かれていくため、前述した“岳が新レシピを絶賛されるシーン”とまさに同種の快感を得ることができる。
たとえば東京VANSユースとの激闘において、アシトたちは事前にロープをつないで猛練習した「コンパクトな守備」の“本当の意味”を知る。福田の狙いがハマり、エスペリオンイレブンは面白いように相手のボールを奪えるようになり始めるのである。そこで思わずアシトが「めっちゃ楽しいやん。守備………!!」とうっとりした様子でつぶやくカットは、作中屈指の鳥肌シーンだ。このように、興奮ポイントが必ずしもゴールシーンとは限らないところが、本作が“本当にサッカーを描いている”ことの証明にもなっている。
ところで、サッカーマンガの最大の見せ場が試合のシーンになるのはある意味当たり前のこととも言えるが、それと同等の熱量が料理というフィールドにおいても実現しているところに「フェルマーの料理」の非凡さがある。手に汗握る興奮の展開が“人が料理を食べる”というだけの場面においても成立してしまう異常性は、賞賛されてしかるべきものではなかろうか。
「アオアシ」を楽しめている人ならまず間違いなく「フェルマーの料理」も楽しめる
ほかにも、ヒロインが天真爛漫タイプ(魚見亜由/一条花)と理論派タイプ(武蔵神楽/海堂杏里)の2人体制であることや、近寄りがたい孤高の存在(広瀬一太郎/栗林晴久)など、サブキャラクターたちの立ち位置にも多くの相似形が確認できる。主人公と立場の近いお調子者ポジションを担う乾孫六と大友栄作に至っては、アニメ版のキャストが同一(いずれもCV:橘龍丸)であるという符合も見られ、大変興味深い。
よって、もし周囲の友人などから「『フェルマーの料理』ってどんなマンガ?」と聞かれた際には、「極論すれば『アオアシ』の料理バージョンだよ」などと大胆な回答を繰り出してみることをオススメしたい。「アオアシ」を楽しめている人であれば、まず間違いなく「フェルマーの料理」も同じように楽しめるはずだからだ。
また余談ではあるが、「フェルマーの料理」には海、布袋、寧々といった「てんまんアラカルト」と同一のキャラクターが複数登場する。さらに、「てんまん」の主人公・七瀬蒼司の存在に言及されるシーンもある。明確なシリーズ関係というわけではないので「てんまん」を読まずとも「フェルマーの料理」は十分楽しめるが、興味のある読者はチェックしてみるのもいいだろう。
たくさんの方が待っていた「アオアシ」セカンドシーズンの26年スタートが決定しました。
動くアシトがまた見られる喜びを感じると共に、ずっと待っていてくださったアオアシファンの皆さんに、良かったね、ありがとうと伝えてあげたいです。
そんな興奮を前に、今年25年は「フェルマーの料理」の年とさせてください。
「アオアシ」を週刊で描きながら少しずつ描きためたこの作品もアニメ化!
いよいよ7月からスタートします。
アニメに合わせ、なんとか最新刊も描き上げることができました。
「アオアシ」も「フェルマーの料理」もどちらも大事な作品です。両方の世界に没頭してくださるならこんなに嬉しいことはないです。
みなさん、葦人と岳をぜひよろしくお願いします!
プロフィール
小林有吾(コバヤシユウゴ)
愛媛県出身。月刊少年マガジン(講談社)で「水の森」「てんまんアラカルト」を連載したのち、2015年に週刊ビッグコミックスピリッツ(小学館)で「アオアシ」を連載開始。同作は2020年に第65回小学館漫画賞の一般向け部門を受賞したほか、2022年4月にはTVアニメ化も果たした。2018年に「アオアシ」と並行して月刊少年マガジンで「フェルマーの料理」を連載開始。同作は2023年にTVドラマ化されたほか、2025年7月よりTVアニメが放送開始される。