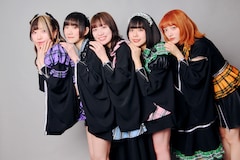2017年に「INTENSE / MELLOW」、2022年に「IN MY OASIS Billboard Session」というセルフリメイクアルバムを発表するなど、節目の年には自身のキャリアを振り返ることを続けてきたINORAN。そんな彼から新たな再録アルバム「ニライカナイ -Rerecorded-」が届けられた。
タイトルが示すように、本作は2007年7月に発表され、現在に至るまでファンの間で人気の高い4thソロアルバム「ニライカナイ」の再録盤。過去と今のINORANの両方が同居した、温故知新を体験できる内容だ。それにしても、なぜ、INORANは今「ニライカナイ」と向き合うことにしたのか。LUNA SEAの再現ツアーや過去作の再レコーディングはどのような影響を及ぼしたのか。そんな疑問をぶつけるべく本人に話を聞いた。ちなみに、インタビューが行われたのは8月19日。そう、LUNA SEA公認コピーバンドLUNA CHEEが突如としてお茶の間に登場した日でもある(参照:LUNA SEA公認のコピーバンドがマクドナルド新CMに登場、ボーカリストは加藤清史郎)。今回の取材は避けては通れないこの話題から始まった──。
取材・文 / 西廣智一撮影 / 森好弘
歳を重ねることの意味
──まず最初に、今日はこの話題に触れないわけにはいかないというトピックがありまして。この取材当日の朝に公開されたマクドナルドの新CMについてです。
あれは完成度がすごいですよね。
──若い頃にINORANさんをはじめLUNA SEAに触れてきた人たちが今や大人になり、一緒にお仕事をしたい、ということで今回のようなコラボレーションが実現することも多いかと思います。
それが歳を重ねることの意味なんじゃないですかね。例えば、F1ドライバーだってメジャーリーガーだって一緒で、キャリアを長く積み重ねてきたからこそのご褒美なのかなと。
──と同時に、INORANさんたちも今の年齢になったからこそ、こういうコラボを面白がって受け入れられるようになったのではないでしょうか。今よりも尖っていた20代の頃に同じようなオファーがあったとしたら、さすがに実現していなかったと思いますし。
そのへんの判断は今以上にシビアだったでしょうしね。歳を重ねていろんなことに対しておおらかになったから、こういうパロディも面白がって受け入れられるようになりましたし、やるからには真剣に向き合ってくれることが相手側から伝わるからこそ「やりましょう」と言えるわけで。もちろん、そうじゃないものもたくさんありますよ。それは仕事だけでなく、例えば友達との間でも好意的に冗談を言うのか、いじめとか嫌がらせみたいな意味を込めた冗談なのかで全然違うじゃないですか。今回のマクドナルドさんとのコラボはそのへんの見極めがしっかりできていたし、俺自身もしっかり楽しめたし、結果として両方がWin-Winになる。その判断能力の精度が今よりも高くなかった若い頃だったとしても、今回みたいなケースだったらやっていたと思いますよ。
──何年か前にバラエティ番組「かまいガチ」から生まれたコピーバンド、GACHI SEAとのコラボも同じだった?(参照:LUNA SEA「復活祭」でRYUICHIが新たな歌声披露、アンコールでGACHI SEAと一夜限りの共演)
そうですね。相手側の愛や誠意が感じられたら、それが自分たちの世界の中になかったものだとしても、好意的に受け入れたいなと思っています。
LUNA SEAでの試みをソロでも
──いきなり取材の趣旨から脱線してしまいましたが、ここからは最新作「ニライカナイ -Rerecorded-」についてお話を伺っていきます。2007年に発表した、ソロとして4作目の「ニライカナイ」というアルバムをリレコーディングした理由、今作の制作に至った経緯を聞かせていただけたらと思います。まず、LUNA SEAが近年行ってきた「MOTHER」や「STYLE」といった過去作のリレコーディングや、それに伴うリバイバルツアー「DUAL ARENA TOUR」「ERA TO ERA」が今作制作のヒントになったそうですが。
LUNA SEAの一連のプロジェクトに関しては、走り出す前と走り終えたあととでは感じ方が全然違っていて。リレコーディングやリバイバルツアーをすることで、こんなにも想像をしてなかった世界が見られるんだと驚いたんです。それをソロでもやってみたら面白いんじゃないかなと思ったのが制作のきっかけです。
──そこでなぜ「ニライカナイ」という作品を選んだか、ですよね。
「ニライカナイ」は以前から好きだという声をファンの方からたくさんいただいていたんですよ。多くの人から「INORANらしいアルバムだね」と言われていたんですけど、その感想がずっと気になっていたので、やるならこのアルバムかなと。
──なるほど。このアルバムが発売された2007年は、INORANさんにとって転換期だったような気がしていて。2005年にTourbillonを結成して、FAKE?からの脱退を発表。Tourbillonと並行して2006年にソロでも作品を発表し、2007年にはLUNA SEA一夜限りの復活を発表という大きな動きがあった中から生まれた「ニライカナイ」に、ファンの皆さんがINORANらしさを見出したのはなんとなく理解できます。
そういう時期に生まれたアルバムなので、当然そのあたりの出来事も無意識にうちに反映されていると思いますし、自分自身も音楽で何を表現したいのかが明確だったんでしょうね。
──ここ数年、INORANさんはインタビューで「今まで見たことのない地平を見たい」と常に前を見据えた発言をしていましたが、今回のリレコーディングはある意味では過去を振り返る作業でもあります。前へ進み続けていることを選択してきたINORANさんにとってLUNA SEAでの経験は、振り返りたくなるほど大きなものだったわけですね。
「MOTHER」や「STYLE」のリレコーディングで経験したことは衝撃に近いものがあって。先に進むのになぜ過去の曲を演奏し続けるのか、その意味を再考できるいいきっかけになったんですよ。
──一度たどった道筋を振り返ることで、「もしあのときこっちのルートを選んでいたら、また違った景色を見られたかもしれない」といった楽しみも得られる?
そうですね。それはやっぱり直感的には感じていて。だからこの作業を選んで、進めたということです。
一番感情が動いた瞬間
──INORANさんはこれまでも、「INTENSE / MELLOW」や「IN MY OASIS Billboard Session」といったリアレンジアルバムを制作してきました。両者とも原曲とは違ったアレンジを加えることで、その楽曲の新たな輝き方を追求してきたわけですが、今回のように1つのアルバムをまるまるリレコーディングするとなると、また違ったことが求められるのではないでしょうか。
まさしくそうだと思います。各アルバムから数曲ずつ取り上げてリアレンジした2作とは違って、今回はアルバム単位でリテイクするので、アルバム全体が持つ世界観をどう捉えて、それを今の形で表現するかが求められる。だから、考え方が全然違うんですよ。
──しかも、レコーディングに参加するミュージシャンが18年前とは異なるので、必然的に音も変わってくるわけですし。今作では近年ずっと一緒に活動されているリズム隊のu:zoさん(B)、Ryo Yamagataさん(Dr)と制作に臨んでいますが、事前にお二人に「こうしてほしい」と伝えたことはあったのでしょうか?
いや、ほぼほぼないですね。オリジナルの音源を聴いてもらってから、レコーディングしただけで。そのままやる必要もないし、2人に「そのままやりたい」とも言ってないし、「ここは変えてくれ」とも言ってない。2人が思うままに弾いてくれればいいかなと思ってました。
──これまでライブで披露してきた曲もあるので、そこを踏まえてレコーディングした?
それはありますね。ライブでプレイしていく中でどんどん変わっていったところもあるので、そのへんは反映されているんじゃないかな。
──僕は18年前、オリジナルバージョンをリアルタイムで楽しんでいた側の人間ですが、今回のリレコーディングバージョンは、作品が持つ世界観はオリジナル版を踏襲しているんだけど、出音の1つひとつのきめ細やかさやミックスの感じがしっかり2025年の音に変わっていて。新作と向き合うような感覚でこのアルバムを楽しむことができました。
それこそが自分がイメージしていたことだったので、うれしいですね。
──今回の制作において、INORANさんの中で18年前のオリジナル版制作時のことを思い出したり、あるいは18年前との変化や違いを感じたりする瞬間はありましたか?
音を録っている段階では「このとき、こうだったよな」ということは、そんなに思い出さなくて。というか、あえて思い出さないようにしていたのかな……そのへんちょっと定かではないですけど、一番感情が動いたのはミックスチェックのときかな。ミックスした音源を聴いて「このとき、こんなことを思いながら作ってたよな」とか「この歌詞を書いたときは、こんな感情だったな。この曲のボーカルを録ったときはこんなことを考えていたな」とか、いろいろ記憶がよみがえってきました。曲によっては当時と同じ感情でレコーディングに向き合ったものもあるけど、逆に当時とはまったく違う気持ちが生まれたものもあるので、そこは面白かったですよ。そう考えると、録っている最中は今その瞬間の感情を大切にしていたのかもしれませんね。
次のページ »
キャリアを重ねたINORANが手にしたもの