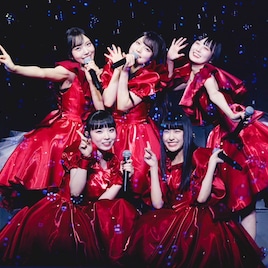「過去も全部連れていきたい」って今は思うんです
──作品の話に戻ると、新作のタイトル「Flos Ex Machina」は「機械仕掛けの花」という意味だそうですが、どのような思いで付けられたタイトルなんですか?
中村 「Deus Ex Machina」という言葉があって。「機械仕掛けの神」という意味の舞台用語なんですけど、今回のタイトルは、その言葉のオマージュなんです。演劇で収集の付かないカオスな状況になったときに、機械仕掛けの神が出てきてすべてを丸く収める。そういう演出方法を「Deus Ex Machina」というんですけど、物語にとって「神」という存在があるのだとしたら、私たちは、物語にとっての「花」でありたい。そういう気持ちから「Flos Ex Machina」というタイトルにしました。どんな状況であっても華やぐ一輪の花でありたいし、その花は誰かにとっての革命になるかもしれないし、大きな光になるかもしれない。そういうものって、どんな人生にも必要なものだと思うんです。でも、そこらへんに転がっていても気付かないことも多い。今回、“今”を大切にするような曲が多くなっているのも、そういう理由があるからだと思うんですよね。
──「今を大切にする」、その言葉を受けてあえて最初に聞きたいのですが、今作は、最後を飾るのが最初期からの代表曲と言える「迷路」であることもすごく大きなポイントだと思うんです。初出のバージョンから歌詞も変わっていて、今のCö shu Nieの表現として「迷路」が収録されている。この曲を今回収録しようと思ったのはなぜだったのですか?
中村 純粋に、「今しかないな」という感じでした。明確な理由があったというよりは、感覚だよね?
松本 うん、そうだね。
中村 ライブでは毎回のようにやってきたし、Cö shu Nieと一緒に育ってきた曲なので。でも、最近はライブができないことも多かったので、この「迷路」という曲がみんなの日常にもっと溶け込んでほしいという欲が出たのかもしれないです。曲って、リリースしてみんなの耳に届いたら手放せるイメージもあるんです。“私の曲”が“みんなの曲”になるというか。そういう儀式をもう一度ちゃんと行いたかったんだと思います。4月からのツアーでは、「迷路」はもうみんなの曲であってほしいなと思うし。
──バンドによっては、こうした初期からの代表曲を出し惜しむ場合もありますけど、Cö shu Nieは「共有したい」という気持ちが強かったんですね。
中村 そうじゃないと、毎回ライブでやらないですよ。みんなの眠れない夜に「迷路」が流れてほしいし、思い出して温かくなってほしい。「言葉をちゃんと伝える」と決めたときから、私の中で音楽は「共有するもの」なんです。そこにあるのが棘であれ、温かさであれ、一緒に傷ついて、一緒に温まる。私にとって音楽はそういうものなので。
松本 特に「迷路」は「飛び切り届けたい曲」という感じなんですよね。「とにかく、みんなに聴いてほしい」という思いでここまで育ってきた。
──「迷路」が最初に生まれたときのことは覚えていますか?
中村 覚えてます。今でも、作った部屋の色味とか家具の置いてあった場所とかまで覚えてます。
松本 僕は最初にこの曲をみんなで合わせたときのスタジオの感じを覚えてる。
中村 私も覚えてる。「迷路」は、「箱舟を作りたい」という気持ちで作った曲なんです。今はお客さんの身の上話を聞くことも多いから、「生まれたからには、ちゃんと救われて生きていきたいよね」と思うけど、「迷路」を作ったときは自分を救うことに必死だったのかもしれない。
松本 自分でも不思議なんですけど、「迷路」は勝手にアレンジができたんです。Aメロとか、なぜこれができたのか今でもわからないくらい勝手に生まれた。なぜかこれが弾けたっていう(笑)。そういうのって、この曲だけなんですよね。「この曲のアレンジ、なんでこれだけスルスルできたんだろう?」というくらい早かったし、説明できないくらい勝手に音が生まれた曲で。再録するにあたって、ストリングスを加えたり、コード感の微調整をしたりしましたけど、アレンジはほとんど最初と変わってないです。あと、余談ですけど、この曲はCö shu Nieで初めてレコーディングした曲なんです。当時、どうしてもいい音で録りたくて、レコーディングの前日に今使っているベースを買ったんですよ。そういうところも思い出深い曲ですね。
中村 「サドウスキーじゃないとダメだ」って言ってたね。懐かしい。今回のレコーディングも、「迷路」はあっという間にできたんですよ。でも、曲が完成してから聴き返したときに、柄にもなく、この10年間のバンドの歴史が思い出されてしまって。こんな経験は「迷路」以外にないだろうなと思う。
松本 ないだろうね。僕もミックスチェックをしているときに、思い出があふれすぎて。「あんなことあったなあ」と思い出してました。
──歌詞に関しては、これまで「やり直せない過去も致死量の酸素も不要 忘れてしまいたいよ」と歌われていた部分が、このアルバムでは「やり直せない過去に想いを馳せたっていい 一緒に連れていくよ」と変わっていますね。
中村 真逆のことを言っていますよね。この曲の歌詞はもともと、ライブで口を突いて出てきた言葉の延長線上にあったもので。最初は「忘れてしまいたいよ」と言っていたけど、そう言っているうちは、忘れられないなと思って。それに、「過去も全部連れていきたい」って今は思うんですよね。間違いを犯してこなかったわけではないけど、今まで自分なりに筋を通してちゃんと生きてきたことの証明として、過去も全部連れていきたいなと思うんです。
──かつて形にした曲を何度も変奏し、そのときそのときの思いを刻むことができるのはCö shu Nieの強みですよね。
中村 そうですね。過去に言った言葉に縛られずに、ちゃんと今思ったことを素直に表現するのは作家として大事なことだと常々思っています。だって、リンゴを好きな日もあれば、お芋を好きな日もある(笑)。それが人間だと思うので。
「歌は主役」という感覚が出てきた
──今作には「red strand」「undress me」「miracle」「give it back」「SAKURA BURST」といったシングル曲も収録されています。これらの楽曲を聴くと、改めて近年のCö shu Nieの進化を感じるんですよね。例えば、「miracle」や「give it back」は、歌の響きが特に素晴らしい印象があって。きっとCö shu Nieにとっての“歌”の捉え方が、ここ数年で変わったんだろうなと思ったんです。
松本 そうですね。歌に関して僕が監督を近くで見ていて思ったのは、もともと監督はピッチをきれいに合わせるタイプだし、技術的な面はずっとできていたんですよ。でも、歌に対しての意識や心持ちが、この数年で変わったんだと思うんです。歌の序列が変わったというか、「歌は人の心に触れる一番のものなんだ」という意識が芽生えたんだと思う。
中村 そうだと思う。私はそもそもインストの音楽をよく聴くし、“音”が好きで音楽を聴いていたから、ずっと歌も楽器の一部だと思ってきたんですよ。でも、歌詞を重んじるようになったこともあって、歌は、スピーカーの向こう、ヘッドフォンの向こう、イヤフォンの向こう……そこにいる人に言葉を届けるツールなんだと思うようになったし、「歌は主役」という感覚が出てきたような気がします。歌に関しては、「miracle」も転機だったような気がしますね。
──「miracle」はどのようにして生まれた曲だったんですか?
中村 この曲は、映像イメージから出てきたんですよね。イメージとしては、機械やAIが出てくるSF的な世界観で、歌詞も最初はもっとSF寄りだったんですよ。あと、私は(オーラヴル・)アルナルズの作品なんかが好きなんですけど、例えば、椅子の引きずる音とか、そういう音まで入っている作品ってありますよね。
──ありますね。些細な物音とか、環境音まで閉じ込めている作品。
中村 ああいう、空間芸術、時間芸術としての音楽の存在が、私は尊くて好きで。そういう表現をしてみたいと常々思っていたんです。その思いと、自分の中にあった映像イメージが重なってできたのが「miracle」です。ちょうどその頃「弾きたい」と言っていたべーゼンドルファーというピアノがあったので、それを弾いて、鳴りを全部閉じ込めて音源にしようって。なので、「miracle」には余計な仕掛けがないんですよね。空間を共有するような音源が作りたかった。
──なるほど。「undress me」は音と歌が縦横無尽に動き続けているような曲で、初めて聴いたときに衝撃を受けました。
中村 「undress me」を作った頃に聴いていたのが、A.G.クックやソフィー、Arcaのようなハイパーポップの系譜の音楽だったんです。「こういうふうにポップスにアプローチするんだ」ってすごく面白いと思ったし、自分と波長が合うなと思ったんです。私がずっとやってきたことの延長線上にあるものだなとも思ったし。なので、「undress me」は、そういったハイパーポップの音作りに影響を受けた部分はあると思いますね。シンプルな空間があって、そこに音が存在して、生きている……そんな感覚。
──確かに、「PURE」(2019年12月発売のアルバム)の頃のCö shu Nieのサウンドはさまざまな音が隙間なく入り乱れて景色を作り出しているような印象でしたけど、今作のサウンドメイクは、曲によってはより隙間のある、空間的なものになっていますね。音がない空間からも、音が鳴っているように感じるし。
中村 今まで耳を埋め尽くすように音をたくさん詰め込んできたのは、「バンドはカッコよくてなんぼ、スター性があってなんぼ」という感覚があったからだと思うんです。でも、バンドとしてのカッコよさとハイパーポップの空間的なサウンド作りはCö shu Nieの音楽でなら両立できるんじゃないかと考えるようになって。「青春にして已む」はアレンジの段階でパート自体少なかったんですけど、まだ抜くかというくらい音を抜きました。歌を聴かせたい曲は特に、ビートに隙間があってもいいんじゃないかという気持ちもあって。もちろん今までのように音が縦横無尽に埋め尽くされている曲もあるし、今回のアルバムはどっちも楽しめるものになっていると思います。
──松本さんはこうしたサウンドメイクに対してベーシストとしてどのように向き合いましたか?
松本 僕は、監督がハイパーポップを聴いているのを見て、これを自分なりに落とし込むにはどうしたらいいか、考えましたね。特にArcaがそうなんですけど、リズムが生きているんですよ。小さい粒が弾けて、その連続性によって、リズムが生き物になっている。Cö shu Nieというバンドとして、そこにどうやってアプローチしようかという部分は考えました。神経を筋肉でつないでいくような感覚で、小さい粒をベースが接着して馴染ませていかないといけない。それに、打ち込みだけど、打ち込みじゃないように聞こえるようなニュアンスもすごく研究して。ロックなビートは変わらずですけどね。
中村 ロックはいいからね。ロックはルーツだから。
松本 うん。培ったものは捨てず、新しいものは模索していった感じだと思います。
私たちは初志貫徹
──サウンド面もそうだし、アニソンという側面もそうだし、今Cö shu Nieの音楽は海外にもすごく開かれていると思うんです。だからこそ逆に、「日本で生まれた表現である」という側面で、Cö shu Nieの中に色濃く残り続ける要素もあるんじゃないかと思っていて。ご自身たちで、Cö shu Nieの“日本らしさ”として感じる部分はありますか?
中村 ほとんどそうだなと思っています。日本語で歌っているし、だからこそ、日本語のメロディになっている。曲の構成もそうだし。それ以外にも、言葉にするのが難しいんですけど、「日本でバンドをやってきた」という感覚は、自分たちの作品からは出ていると思うんですよね。インディーズで、日本のライブハウスでやってきたバンドの感じというか。
松本 僕も、日本のインディーズバンド感みたいなものは抜けてないなと思う。自分としては「もっと違うものになったらいいのにな」と思う部分もあるけど、どうしてもこびりついたものは変わらない感じがしていて。
中村 しゅんすはしゅんすだから。変わらない鉄の男。それに、しゅんすのリズムの跳ね感は、むしろ海外っぽいでしょ?
松本 うん、リズムはたぶん日本っぽくない。ルーツはディスニーのミュージカルだし。でも、何かしら……。
中村 わかった。武士道みたいなものじゃない? 私たちの世代で、バンド1本でやっている人たちって、ほとんどいないんですよね。バンドだけじゃなくて、いろんな活動をして輪を広げていく人たちが多いけど、私たちは初志貫徹っていう感じだから。そういう魂の部分は、昔気質のバンドマンっぽいのかも。そういう部分が消えないものになっているのかもしれない。
松本 確かにね、その匂いなのかもしれない。
次のページ »
ベースが“毒”の役割を果たさないといけない