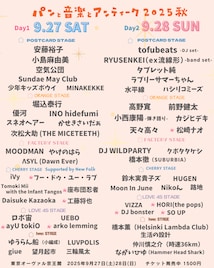優河 単独インタビュー
シンガーソングライター・優河のルーツ
──音楽ナタリー初登場ということで、まずは優河さんのシンガーとしてのルーツから教えてください。
音楽をやり始めたのは中学生のときに組んだバンドが最初です。パートはベースだったんですけど、ちょっとだけ歌ったことがあって、それを聴いた母親が「高校に上がったらボイトレに行ってみたら?」と提案してくれて。当時はボイトレの先生の勧めでキャロル・キングやベット・ミドラーのような女性シンガーの曲をカバーしてました。そのあとに音楽の専門学校に行って、先生に「ギターも弾けるようになれ」と言われて、Peter, Paul and Maryの曲をカバーしたりするようになって。自分でも曲を書き始めてからはアメリカのインディシーン、ノラ・ジョーンズ、シャロン・ヴァン・エッテン、Bon Iverとかを聴くようになり、そこで自分のやりたい音楽が見えてきた感じです。あとは、アイルランドの旋律もすごく好きで、ダミアン・ライスとかリサ・ハニガンとかもよく聴いて、アイリッシュバンドのTricolorさんと一緒に演奏したりもしてました。
──キャロル・キングといえば、優河さんはNetflixオリジナルドラマ「全裸監督2」の劇中歌として「It's Too Late」をカバーされていましたよね。
ちょうどキャロル・キングの「ビューティフル」というミュージカルを観たあとすぐで「この作品いつか絶対挑戦したい」と思って。ボイトレの先生に譜面を一式もらっていて、その次の日くらいにオファーがあったんですよ。なので、すごくびっくりしたんですけど、うれしかったです。
──海外のシンガーソングライターがルーツにあるようですが、日本語で歌うにあたっての影響を受けたアーティストはいますか?
細野晴臣さんや大貫妙子さんは、すごくきれいな日本語を、日本語という感覚を強調しすぎることなく使っていらっしゃると思って、そういうところを目指していけたらいいなと思ってました。日本語はすごく平面的だけど、それがすごく美しく聞こえるところがあるはずで、そこを崩さずに、自分のものにしていけたらなと。
ミュージカル出演で邪念が取れた
──「言葉のない夜に」は4年ぶりのフルアルバムとなります。制作にはいつ頃から、どのように向かっていったのでしょうか?
2019年くらいから、気持ちがずっと落ちてる感じだったんです。自分のやりたいことも、やるべきこともわからなくて。なんだったら「自分は求められる存在なのかな?」とか考えたりして。
──2019年ということはコロナ禍の影響ではなく、それ以前からそういう状態だったと。
そうなんです。自分が作る曲にも自信が持てなくなっていて、ずっとふさぎ込んでいたんですけど、そんな中でミュージカル(2020年に上演された「VIOLET」)のオーディションのお話をいただいて。まったく知らない世界だったので、大きなチャレンジではあったんですけど、そこで自分のいらないものが全部取れたというか、自分がアーティストとして頑なに守っていたものって、すごくどうでもいいことだったなと思ったんです。それは自分が決めていただけの殻で、それを守るために「〇〇はやらない」みたいなことって、すごく無駄な選択だったなと。でも、自分の体の隅々まで使って、歌そのものを届けるミュージカルをやったことで、いろいろな邪念が取れたというか。そこでまたコロナが来て、アップダウンはあったけど、今考えるとずっと上り調子で、そこまで落ちなかったなって。
──今振り返ると、落ち込みの原因は何だったと思いますか?
リアクションを求めすぎていたのかもしれないです。どれだけ聴かれてるとかがわかりやすく数字で入ってきて、そこを気にしないメンタルにはなれなかったというか。自分に自信がないから、その支えを外側に求めていたのかもしれない。自分の自信のなさを相手にもらう評価で埋められる気がして、でも実際はそうではなくて……だからつらかったんだと思います。
──でも、ミュージカルで自分の歌を見つめ直して、それを聴いてくれる人がいて、少しずつ鎧を脱いでいって。そこからもう一度自分の創作にも向き合えるようになっていったと。
そうですね。ミュージカルがきっかけで、ボイトレにもう一度通い直して、歌と向き合えたことはすごく大きかったと思います。
自分を肯定してくれる存在の大切さ
──アルバムを制作するにあたっては、魔法バンドの存在も大きかったのではないかと思います。
そうですね。さっき「ミュージカルをやってからはずっと上り調子」と言いましたけど、自分の歌には自信が付いたものの、自分のクリエイティブ、ソングライティングに関しては悩んでしまって。でも私があまりに悶々としてるから、バンドのメンバーが「とにかく1曲作ってみよう」と言ってくれて、もう1回アーティストとしての自分を立て直していく作業を去年の頭くらいからしました。その頃はメンバーにすがる思いで……メンバーは自分のやりたいことに賛同してくれる人たちだと思うから、メンバーを通じて自分を見ることができて、すごく重要なコミュニケーションだったと思います。
──自分で自分を肯定するのは簡単なことではないから、自分を肯定してくれる他者の存在はすごく大きいですよね。
こういう時代だから、自分が求めなくてもいろんな意見が入ってくるじゃないですか。それが自分に向けられたものじゃなくても、いろいろ気にしてしまって、「この人すごいね」みたいな話があると「自分にはないな」と、つい比べちゃいがちで。だからこそ自分を肯定できる環境を作ることはすごく大事だなって、バンドのメンバーと制作して改めて思いました。
──「とにかく1曲でも作ってみよう」と気持ちを切り換えて、最初にできたのが去年配信リリースされた「夏の窓」だったわけですか?
いや、最初にできたのは「WATER」ですね。「夏の窓」も同時期に作ってはいたんですけど、方向性が全然決まらなくて、いろいろやりながら変えていって。レコーディングの中盤くらいで「疲れたけど、あともう1曲録ろう」となったのが「夏の窓」でした。ちなみに、そのとき1回夕飯を食べたんですけど、ドミノピザのニューヨークサイズを頼んで、ピザとコーラを胃の中に流し込んだら、みんなハイな感じになっちゃって、そのままのテンションで録った「ドミノバージョン」っていうのがあるんです(笑)。それを経て、現在の落ち着いたバージョンになりました。
──ドミノバージョン、いつか聴きたいです(笑)。「夏の窓」も含め、今回のアルバムでは岡田さんがソングライティングの面でも大きく貢献していますよね。先ほど「自分のクリエイティブにはなかなか自信を持てなかった」という話もありましたが、今回はその部分でメンバーの力を借りつつ、これまで以上に「歌」を大事にした作品でもあったのかなって。
そうですね。当時は何か自分ができることを少しでもいいからやりたいという感じだったから、岡田くんとかにまず土台を作ってもらって、そこに言葉やメロディを乗せてみるということを少しずつ、リハビリみたいにやっていった感じでした。やっぱりミュージカルを経験して、今回はまず自分の歌に重きを置いていたので、それ以外の部分では自分発信じゃないものでも素直に受け入れられて、それがすごくよかったなって。
──以前までは「自分で曲を書いて歌う」ということに対するこだわりが強かった?
やっぱり、どこか自信がなかったんでしょうね。そうじゃないと成り立たないと思っていたというか、「全部自分でやれば大丈夫かな?」みたいな感覚だったんだと思います。ミュージカルを経て、その部分の考え方が変わったのもすごく大きかったですね。
次のページ »
優河のボーカルの魅力