桑田佳祐、最新テクノロジーに触れる
──“受け入れ”とも言えるその実感は、アルバムにも多分に反映されていますよね。といったところで、このインタビューでは何曲かピックアップしながらアルバムについても伺っていきたいんですが、1曲目を飾る「恋のブギウギナイト」(2024年6月配信リリース)は“スタートになった1曲”と言えるのではないでしょうか。改めてこの曲について聞かせていただければと思います。
アルバムの中では、3番目か4番目にできた曲で。この曲にはね、まさに新規のプロジェクトを始める覚悟があったんです。1曲目を作るにあたって、これまでとは違うアプローチから入れないかなと思っていて。うちのオペレーターを長年やってくれている角谷(仁宣)くんに、「今度スタジオに入るからドラムループみたいなものってある?」と頼んだら、5つか6つ用意してくれたんです。いろんなものがあるんですよね、今の世の中には(笑)。テンポは全部同じものなんですけど、それを聴きながら「これいいね」「面白いね」と言い合い、そこからドラムをループさせながらギターを奏でて。EDMじゃないですけど、我々の時代としてはディスコ的なノリというか、そのノリで構築していきました。角谷くんとキーボーディストの片山敦夫さんと一緒にデモテープ制作のような状況から作っていったんです。
──最初にビートありきだったんですね。
いや、ドラムループありきでやっていったんですけど、ドラムだけじゃなくて、シンセの音などいくつか同時に音が走っていたんです。それを聴いて、自分の中に音像が刷り込まれるじゃないですか。だから、今度はそれに合わせてメロディを作っていくという。そういった作り方は前にもしたことがあったけど、私にとっては使われていたループが“最新式”だったんですよね。
──なるほど。
その作り方に助けられたのも、アルバムのとっかかりとしてはよかったのかなと。
──この曲でアルバムがスタートすると、聴いている側としても「今のサザンはこの“肉体性”なんだな」とプレゼンテーションを受けるといいますか、最初に感じられるところがありますよね。
こういうテンポ感でディスコ風、EDM風に寄せていって、歌詞なんかもそこはかとなく作っていきまして。仮歌もそれにだんだん寄っていく中で「Seventeen」とかね、「Space and Time」とかね、自然と出てきたものが最終的に歌詞に入りました。
──なるほど。感覚的には「できあがっちゃった」ということなんですかね?
そうですね。今の人たちがEDMをどう解釈してどう楽しんでいるのかはわからないんですけど、我々の世代だと、60年代、70年代のディスコ……例えばKC and the Sunshine Bandとかね、「Play That Funky Music」(Wild Cherry)的なね。ああいう、男女の情けない物語のようなものもあって。「ディスコ行っちゃって、酒飲んで、マブイ女がいてさ~」って、そういうストーリーみたいなものはどうしても入ってくるんですよ。だから、情けないけどちょっと陽気な感じと言うんですかね。あと、KC and the Sunshine Bandや「Play That Funky Music」、A Taste of Honeyの「Boogie Oogie Oogie」(邦題「今夜はブギ・ウギ・ウギ」)とか、そういうものを聴いたときに我々がどう感じていたのかということをなんとなく思い出して。「夜の時間帯だからちょっと悪いことしようか」みたいなね(笑)。「バレなきゃいいじゃん」「お酒が醒めると後悔するよ」とかね、そういう方向に向かっていくんですよね。「Play That Funky Music」の「Play that funky music white boy~♪」が、男女が渋谷のディスコに10人いたら、「そこ行くネーちゃんヤッホー♪」っていう替え歌につながるような、ちょっと“不埒”な感じがあるんですよ。あと、今回のレコーディングで「すごい時代だなあ」と思ったんですけど、実はギターのカッティング音がね、全部キーボードなんですよ。
──そうなんですね。それはまたレアな話で。
本当に勉強になりましたね。片山さんにキーボードで弾いてもらったものを、ギターのカッティングとしてこの曲では採用していて、テンション含めて自分が弾くよりも、この曲にふさわしい音だった。今のテクノロジーはすごいですね。
書かされるように生まれた「桜、ひらり」
──続きまして、3曲目の「桜、ひらり」についてお聞きしたいと思います。これもまたサザンの新たな名曲と言うべき1曲で。この曲に関しては、石川へ向かう映像で構成されたビジュアライザーとは切り離しては語れないものです。今開催されているツアーは石川が初日でしたし、曲作りにあたって能登半島地震への思いが根本にあったんでしょうか。
うん。最初は、16ビートっぽい跳ねた曲を作ろうと思ってたんですけどね。歌詞ができてからいろいろ変わっていって。ツアーをやりましょうとか、映像を作りましょうとか、アルバムを作っているといろんなアイデアが出るんですよね。私も歌詞を作るうちに、能登半島地震であったりその被災地であったりのことを思い浮かべ始めたんです。それを歌詞にしたためて。作詞も作曲もそうなんですけど、「こういうテーマで書こう」という狙いはいつもなくて。僕の場合はご存知のように、やりながらいろいろ浮かんでくるものですからね。完成してから数日後に歌入れをしようと決めて、じゃあ歌詞をどうしようかな、というときに能登のことが思い浮かんだ。そういうアイデアは、いろんなことが同時に進んでいく中でのスピード感が呼び起こすものかもしれない。タイミングが違えば違う歌詞になっていたかもしれないですね。今回のように「桜、ひらり」に被災地のことが歌詞として落とし込まれたのには、我々がサザンとして動いているプロジェクトの中での普段の会話や人間関係が絶対に作用していると思うんです。
──“呼ばれた”ような。サザンの曲にはそういう一面がありますよね。
うん。偶然だけれど、そこには絶対に必然性があるに違いない、と。僕たちもずっと地下室にいて音楽を作ってるわけじゃなくて、いろんな情報を意識しながら、今の時代に「何かを発信しよう」「ファンの皆様に会いに行こう」となる中で、こういう曲も必要だったんだと思います。最初から「こうしよう」と思って書き始めたわけではないんですけど、なんか書かされるんですよね。
──まさに書かされた、呼ばれた曲という感じがします。本当に素晴らしい曲だと思います。
ありがとうございます。
「あの感じやろうよ!」
──続いて9曲目に収録されている「夢の宇宙旅行」は、スタッカートの効いた鍵盤の音で始まる、ある種“サザンの王道”を更新する楽曲と言ってもいいですね。
デモテープを作って、(松田)弘を呼んでドラムを録ろうとなったときに、デモテープを聴いた彼が「デヴィッド・ボウイとかエルトン・ジョンね!」と当たり前のように言ってきて。「ジャンヌ・ダルク(によろしく)」もそうでしたけど、弘からはそういう固有名詞が出てくるんですよね。
──「あの感じね!」という。
うん。そういうのを模倣と言うんですけども(笑)。
──いやいや、サザンは「あの感じね!」をやり続けてきたところもすごいと思うんですよね。そして、今回のアルバムは特にその感覚で作られた楽曲が多い気がしました。「あの感じやろうよ!」という感覚を自分たちに許すというか、まずは「やってみよう!」と。
うんうん。そういう意味では、アルバム制作時にあまり背負うものがなかったかもしれませんね。
──そこがこの作品を語るうえでは重要なポイントなのではないかと思います。
ポップミュージックの世界で長年生業とさせてもらっている人間としては、自分の憧れを隠さないで制作するのは一番楽しいことですからね。
──この曲はミュージックビデオも制作されています。どういったコンセプトだったんですか?
まずアイデアとして出てきたのが、デヴィッド・ボウイとかT. Rexとか、いわゆるパワーポップであったり、グラムロック的なもの。The Beatles解散以降のちょっとグラマラスな時代と言うんですかね。ウルフカットで、コンタクトレンズをして、ハイヒールを履いて、ファッションはラメラメでみたいな。1970年から73年くらい。当時は日本の歌謡界もそうだし、洋楽の世界も宝物いっぱいの時代だったと思うんです。とにかくあの頃に戻ろうと。
──その通りのMVになっているんじゃないでしょうか。
それは果たしてどうでしょうか!(笑)
次のページ »
音楽は癒しでもあり、精神的支柱になる


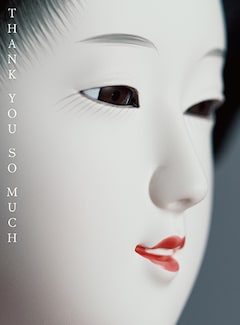
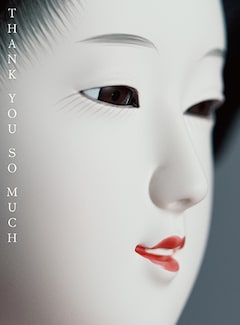
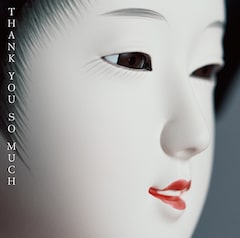
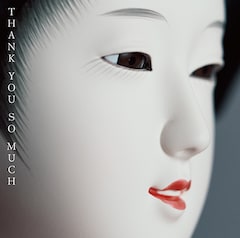













![[週間アクセスランキング]フジロック行ってみるか](https://ogre.natalie.mu/media/news/music/2026/0220/frf26_KeyVisual_0220.jpg?impolicy=thumb_fit&width=180&height=180)






