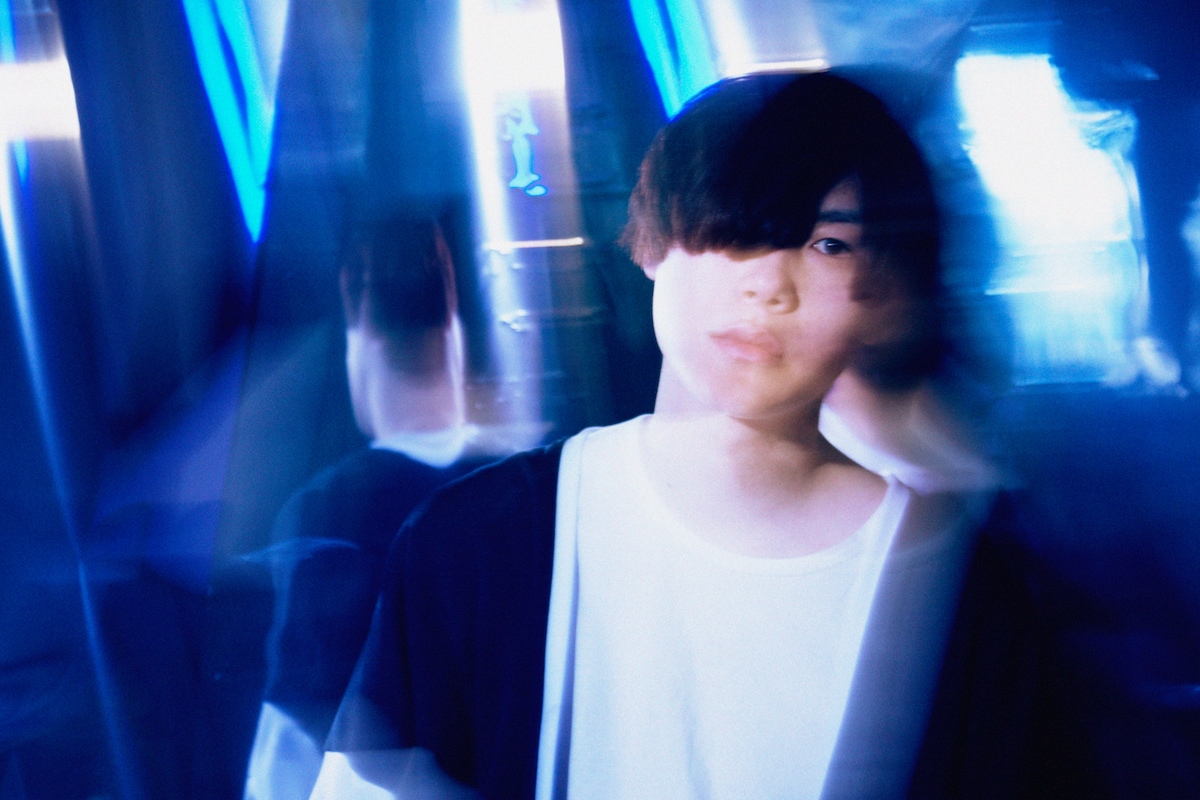PELICAN FANCLUBがメジャー1stアルバム「解放のヒント」を3月2日にリリースした。
メジャーデビューから約3年を経て放たれたアルバムには、「三原色」「ディザイア」「Who are you?」「星座して二人 feat. 牛丸ありさ」といったシングル曲を含む全16曲を収録。混沌としながらも希望を内包した世界が広がる、PELICAN FANCLUBならではのフルアルバムとなっている。エンドウアンリ(Vo, G)はアルバムリリースを発表する際に「この作品は僕のことを歌っている。しかし、同時に君のことを歌っているのかもしれない」とコメントしていた。音楽ナタリーではエンドウ本人に“自己愛”をテーマにしたというアルバムについて話を聞いた。
取材・文 / 蜂須賀ちなみ撮影 / 斎藤大嗣
自分にとっての“解放のヒント”になったアルバム
──約5年ぶりのフルアルバムが完成しましたね。エンドウさんにとって、そしてPELICAN FANCLUBにとってどんなアルバムになりましたか?
自分でも日々繰り返し聴いているんですが、楽曲それぞれをすごく愛せるアルバムになりました。次の作品に向かうモチベーションもすでに上がっていて。そういう意味で今まで以上に通過点だと感じるアルバムだし、それこそ自分にとっての“解放のヒント”になったなと思いますね。
──PELICAN FANCLUBならではの世界観を表現すること、そして聴き手へメッセージを投げかけること。それらが高次元で両立できているアルバムだと感じました。例えばリード曲の「俳句」は、どういうところからイメージを膨らませていったんですか?
スカイツリーの見える隅田川で、屋形船を眺めながら曲を書いていたんですよ。そしたら両国橋でパトカーがサイレンを鳴らして通り過ぎたんですが、この少し異質な状況を音で表現できないかと思って作った曲です。
──だから和楽器の音色が取り入れられているんですね。群像劇のようなテイストで今作をまとめる最終曲「少女A」も印象的でした。
ライブを観たり音楽を聴いたりしていると、アーティストやミュージシャンが主役だという感覚に陥りがちじゃないですか。その感覚も正しいかもしれないけど、ステージに立っている僕らと同じようにライブに来ている人も主役だと思う。そのことを表現するために、音楽を中心にさまざまな人が交わるような、脇役のいない曲を作りたかったんです。
──「俳句」と「少女A」は2020年11月の「PELICAN FANCLUB DX ONEMAN LIVE "NEW TYPE"」から披露していましたよね。それに、今「少女A」について話してもらった内容に近いことをMCでも言っていましたが、もしかしてあの頃にはアルバムの構想は見えていたのでしょうか?
いや、当時は新曲ができたから僕らの近況を伝えるために演奏したまでで、アルバムの構想はまったくありませんでした。あったのは、どういうサウンドにしようかというイメージだけでしたね。
バンドであるということは、約束や責任だと思っています
──サウンドについては、前回のインタビューで「2020年以降、リズムとシンセから曲を作ることが多くなった」と言っていましたよね。
そうですね。ギター、ベース、ドラムという型にはあまりこだわらなくなりました。PELICAN FANCLUBという1つの個体を見せるうえで、バンドサウンドの型にはまることに僕は違和感を抱いていたんです。サウンドの変化にはそういった心境の変化が表れているんじゃないかと思います。例えばRadioheadの「OK Computer」「Kid A」も、ロックバンドが電子的なアプローチに振り切った例ですよね。当時聴いた人がどう思ったのかはわからないですけど、今となってはあのアルバムはオルタナティブの金字塔として知られています。そういった型にハマらない作品はバンドやミュージシャンのような発信者側が作っていくものだと思うし、僕らも今作はジャンルなどにとらわれず、自分たちにとって気持ちいい音をただ追求しました。
──その結果としてデジタルサウンドを導入するようになったと。
というよりかは、「ギターだからギターらしい音を出すべき」といった線引きを排除していったという言い方のほうが近いかもしれないです。デジタルサウンドのアプローチが増えたとはいえ、レコーディングはすごくフィジカルなものだったんですよ。例えば、もともとシンセで作っていた音をあえてギターで再現したりしていて。普通にシンセで弾けばいいのに、って思いますよね。
──そうですね。
でも、楽しいんですよ。どうしてこんなことをするのかというと……ある種フェチみたいなものなので、理解されないかもしれないんですけど、僕は誰にも伝わらない努力が美しいものだと思っていて。それを作品に詰め込むのが僕の美徳なので、今回はかなりそういった表現も組み込みました。
──ちなみにギター、ベース、ドラムによるサウンドにこだわらないならば、PELICAN FANCLUBがバンドである所以はどういうところにあると思いますか?
バンドであるということは、約束や責任だと思っています。1つの集団に所属して、1つの目標に向かうことを約束する。そうなると、メンバーそれぞれに役割があると思うし、そこに所属する個人は“何をやってもいい”ということにはならないと思うんですよ。その責任の中でどう音楽を表現するか。それがバンドだと思っています。
“もう1人の自分”に届けるような作品
──アルバムの話に戻りますが、「そろそろアルバムが作れそうだ」というイメージがつかめたのはいつ頃でしたか?
シングル「Who are you? / 星座して二人」を出してからなので、2021年の夏以降でした。「星座して二人」のゲストボーカルとしてyonigeの牛丸ありささんを呼んだり、僕らの所属レーベルKi/oon Musicのプロジェクト「Room=World」でASIAN KUNG-FU GENERATIONの「新世紀のラブソング」をカバーしたり、サウンドの変化を如実に表現していた時期でしたね。それまではアルバムを通して何を届けたいのかが明確にわかっていなかったんですけど、10曲、15曲、20曲……と作っていく中である共通点を見つけて。それは、自分を愛するための歌であるということ。その共通点に気付いたとき、「これはアルバムにできるな」と思いました。なので、今回のアルバムは自己愛がテーマです。もう1人の自分という架空のアバターのようなものを作り上げて、そのアバターに届けるようにして作品を作っていきました。
──確かに、他者との関わり合いよりも、個人や自分自身にフォーカスした曲が多いですね。
はい。今回は“誰かに対して愛を”ということはほぼ歌っていないです。「俳句」でも歌っているように、人の目を気にするより、自分の目を気にしたほうがいいんじゃないかと僕は思っているんですよ。なぜかというと、他人と比較して得る自信はどうしても崩れてしまうから。そもそもいろいろな他人がいるのに、そこと戦おうとするのは違うと思うんですよね。だけど、自分自身から生み出される自信を持てたとすれば、周りのことなんてどうでもよくなるはずで。
──インターネットでの炎上や誹謗中傷も、結局はみんなが他人の話をしているからこそ起こるものではありますよね。
本当にその通りです。人を傷付けることで悦に浸っている人もいるから、あれはもう終わらないんじゃないかと思うんですけど……でも、「そんなことより自分を愛せ」と言いたくなります。
──収録曲の中には他者の存在を感じさせる曲もあるものの、アルバム全体のテーマが“自己愛”なので、「他者とはそれぞれに自分の人生を生きていたらいつの間にか出会っていた」という温度感なんですね。
そうですね。「少女A」を最後にしたのは、自分が思っていることはほかの誰かにもつながっているんだということを最後に言いたかったからで。自分のことを思うからこそ初めて人に心を解放できる、だからこそ自分のことを歌う、というのがこのアルバムだと思っています。
──そういう意味で「Astro Girl」にある「消失点」というワードも象徴的であるように感じました。「Astro Girl」の歌詞を書いたのはカミヤマリョウタツ(B)さんですよね。メインソングライターのエンドウさんではなく、カミヤマさんから本質を突くワードが出てきたことに驚いたのですが、エンドウさんはこの曲についてどう思いましたか?
僕はこの歌詞を読んだとき、カミヤマが書いてきた素のままのものが一番いいものだと思いました。僕がこのアルバムで表現したいテーマ、PELICAN FANCLUBとして表現したいテーマともすごくマッチしていたし、「これは絶対にこのまま音源にしたい」と伝えてそのまま収録しましたね。
──「Boys just want to be culture」のインタビューでカミヤマさんが「僕はPELICAN FANCLUBの差し色」と言っていましたが、今では「この曲はエンドウさん」「この曲はカミヤマさん」といった境目が曖昧になりつつあるように感じました。
本当にそうですね。やっぱりバンドで見ている景色が近いからこそ、誰が作詞したのかわからないくらいの状態になっているんだと思います。それこそPELICAN FANCLUBとしての“約束”が果たされている。だから僕もすごく好きな曲ですね。
次のページ »
自分の過去にライトを当てることができた