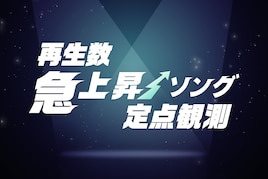「阿吽のビーツ」「懺悔参り」「ハレハレヤ」といったボカロ曲で人気を集めた羽生まゐごが、これまでの作品とは一線を画すコンセプチュアルアルバム「魔性のカマトト」を完成させた。
この作品は羽生自らが執筆した小説、瀬川あをじが手がけるミュージックビデオなど、多数の創作物と音楽をかけ合わせることで1つの物語を構築するアルバム。大正から昭和初期を舞台に描かれたこの物語は、若き絵描きの青年・カマトトを中心に、あんず、町子、林檎の3人がそれぞれ1人の男性を思う恋物語が描かれている。音楽ナタリーでは楽曲制作および小説の執筆を終えた羽生にインタビュー。「魔性のカマトト」という作品を通じて羽生が伝えたかったことはなんなのか。その思いに迫る。
取材・文 / 倉嶌孝彦

時代背景は大正時代から昭和時代の初期にかけて。アネモネ港を中心に栄える街では、交易物が行き交い、さまざまな人が往来する。物語の中心となるのは、絵描きの青年・カマトトと、彼を慕うあんず、町子、林檎という3人の女性。アルバムには3人がそれぞれの視点でカマトトを思う歌が並ぶ。なお初回限定盤に付属する短編小説には、歌詞では語られなかったそれぞれの思いも書かれている。


- カマトト
- アネモネ商店街にアトリエを持つ絵描きの青年。
巷では神出鬼没の二枚目男と噂になっている。

- あんず
- カマトトから絵を学ぶために弟子入りした女学生。
カマトトに特別な感情を抱いている。

- 町子
- 商店街のたばこ屋の看板娘。
抜けた性格が故にみんなから愛されている。

- 林檎
- 商店街を牛耳る大商人の娘。面倒見がよくがんばり屋。
カマトトと一緒に暮らしている。


曲と曲の間をつなぐ小説が必要だった
──「魔性のカマトト」は楽曲だけでなく、小説や動画、イラストなどさまざまな表現をかけ合わせたコンセプチュアルな作品ですよね。この構想が生まれたきっかけはなんだったんでしょうか?
前作「浮世巡り」の存在が大きいですね。「浮世巡り」を作り終えて感じたのは、音と歌詞だけの表現では限界があるということでした。もちろんアルバムという形で曲をまとめることで表現できたものはあったんですけど、「浮世巡り」の次の構想として出てきた「魔性のカマトト」という作品を作るにあたっては、音と歌詞以外の表現が必要だと感じた。だから「魔性のカマトト」は、まずイメージボードのような舞台背景を作り始めて、そこから音や小説を作っていったんです。
──なぜ小説という表現になったのでしょうか?
イメージボードをもとに「魔性のカマトト」という1つの作品世界が形になったとき、音楽だけだとその世界の一部分しかすくい取ることができないと感じたんです。1曲で表現できるのは、1人の人間の1つの時間軸に限られてしまう。だから曲と曲が存在する中で、その間を埋める役割として今回は小説を書いてみました。
──ちなみにこれまで小説を書いたことはありましたか?
今回が初めてですね。小説という形にこだわったわけでもなくて、必然的に小説が生まれた感じがします。こういう作品が思い浮かんだ以上やるしかないというか、「魔性のカマトト」という作品に“書かされた感覚”なんですよね。ただ小説を書き始めてみたら、書くのが本当に楽しくなってきて。曲を作るのももちろん楽しいんですけど、小説を書いてみたらそれ以上の興奮があったので、自分の中の新しい部分を発見した感覚がありました。
現代に通じる悩みを探して
──小説のあとがきでは「魔性のカマトト」の時代背景が、大正から昭和にかけてのものだと説明されています。なぜこの時代を選んだんでしょうか?
江戸時代頃をイメージして作った「浮世巡り」よりも現代的な要素を取り入れたかったのが大きな理由ですね。大正時代というのは和と洋が入り混じった時代で、人の考え方も混沌としていたと思うんです。江戸時代を舞台にしていたら表現できなかった世界観や人間の深みは、現代に近付いたほうが表現しやすいと思ったんです。
──小説のあとがきには「当時の時代背景が現代にも通じる」とも書かれています。どういうところに現代との共通点を感じましたか?
背景から説明すると、日本が大きな戦争をする前というのが大きいですね。戦争中は人間関係で悩むだろうとか、文化や人について考える余裕があまりなかっただろうと想像していて。だとしたらそれより前の時代で、いろんな価値観が交わりながらも、道楽や快楽が多い時代というのは大正時代なんじゃないかなと考えたんです。快楽が多いからこその悩みもあり、それは現代に通じる部分があったと思うんですよ。
歌の中に一瞬見えた闇
──今作の大きな特徴の1つがボーカリストの起用ですよね。
「魔性のカマトト」の構想が決まった段階で、ボカロを使う選択肢はなかったんです。ボカロのいいところって、冷たいところなんですよ。打ち込みをベースにした冷たい音楽にはボカロの冷たい声が合う。「浮世巡り」というアルバムにはボカロが適していたんですけど、「魔性のカマトト」は人間の喜怒哀楽を生々しく深堀りしてくような作品にしたかった。変な話ですけど、「魔性のカマトト」という作品が「“語り手”としてボーカリストを探せ」と、僕に向けて訴えかけてくるような感覚があったんです。
──ボーカリストとして起用された猫屋敷さんは、一般的には名の知られていないボーカリストですよね。猫屋敷さんのどのようなところに惹かれたんでしょうか?
歌がうまいか下手かは最初からどちらでもよくて、役として「魔性のカマトト」という作品にハマるかどうかが大事だったんです。今作には女の子が3人登場するんですけど、彼女たちの気持ちをうまく舵取りしてくれるかどうかをすごく重視していました。猫屋敷さんの歌声を聴いたとき、かわいらしい歌声の中に一瞬、人間の闇みたいなものが見え隠れしたんです。そこがすごくいいなと思いました。
──レコーディングではボカロを使ってボーカルを組み立てる作業とは違った苦労があったんじゃないですか?
大変でしたね。歌ってもらう前に作品世界のことやそれぞれの登場人物の性格とか心境、そのときのシチュエーションをすべて説明しないといけないわけですから。現実の恋愛の話に落とし込んだほうがわかりやすいところもあると思って、猫屋敷さんの経験談なども聞かせてもらいながら「そのときの気持ちを思い出して歌って」みたいなアドバイスを送ることもありました。ただそうやって作品について1つひとつ話していくのも新鮮で楽しい作業でしたね。
──「世界で一番じゃない貴方を愛したら」にはSouさんがボーカリストとして参加しています。カマトトの心情の担い手としてSouさんを選んだのはなぜですか?
Souくんはすごくモテるんですよ。
──なるほど(笑)。
Souくんはいろんな人に好かれているから、カマトトという登場人物と似ているところがあると思って。先ほど猫屋敷さんには歌ってもらう前にいろいろと説明したと言いましたが、実はSouくんに対しては作品のこと、カマトトのキャラクターのことを細かく伝えていないんですよ。Souくんは演じる必要がなくて、そのまま歌ってくれれば僕のイメージするカマトトが表現できる。こんなこと本人に言ったら「こんな人間じゃねーよ!」と怒られそうですが……(笑)。僕の思い描いていたカマトトに命を吹き込んでくれて、Souくんには本当に感謝しています。
次のページ »
現代が生んだ“歪んだ存在”