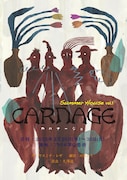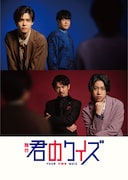どうやったらより“生”に見えるか
──本作では、小山さんが「チック」でも使われていたライブ映像が多用されています。ライブ映像があることで、観客は俳優の演技を多角的に観ることができますね。
ライブ映像はドイツ演劇でよく使われていますが、私もドイツ語圏の作品を演出するとき、あったほうが面白いと思うことも多いです。不思議なのですが、客席から舞台上の俳優を直接観ているよりも、ライブ映像を通して観たほうがよりリアルに感じられるときもある。これは私たちが映像に慣れ親しんでいるからなのか、その理由自体ははっきりわからないのですが。あと、ライブカメラだと俳優も予期できないことが起こるんです。日によって角度がちょっと違ったりとか、そこで本当のライブ感を提示することができる。
──演劇が持つ一回性が、より強調されるんですね。
そうですね。また「暴力の歴史」の演出ではマイクが使われますが、これも似た効果があるのではないでしょうか。演劇作品を制作するにあたって、「どうやったらより“生”に観せられるか」ということが、私たち世代の課題ですね。ほかのメディアがすごく発達して、演劇の必要性が薄まってきた時代に、わざわざ劇場に足を運んでライブ感を感じられないんだったら、何を感じるんだろうと思うので。
オスターマイアーが名門エルンスト・ブッシュで培ったもの
──今作では、主人公を演じる1人の男優以外、3人の俳優が複数の役を演じます。その演じ分けや、細かな場面転換をスタッフなしでこなすなど、難易度の高い演出に難なく応える俳優陣のレベルの高さに驚きました。
ドイツの俳優はとにかくセリフ術と身体能力が卓越していて、例えば傾斜のあるセット上を、高いヒールを履いた状態で駆け上がれたりする。ドイツの俳優を観ていると、ただただ見事だなあと思います(笑)。特にオスターマイアーがいつも一緒にやっている、シャウビューネ座付きの俳優たちは名優ぞろいなので、俳優の力で見せている部分も大きいかと。「暴力の歴史」には参加していませんが、オスターマイアーとよくタッグを組んでいるラース・アイディンガーという俳優がいます。彼は舞台俳優としても高い技術を持っているのですが、映画スターとしても人気で、日本の演劇界には彼のファンとオスターマイアーのファンがたくさんいます。
──チケットが入手困難なことで有名な、オスターマイアー演出の「ハムレット」や「リチャード三世」でも、アイディンガーは主演を務めていますね。
知り合いの美術家が、チケットが取れなかったけど現地に行って、劇場前で「チケット譲ってください」の看板をずっと持って1日中立っていたという話をしていました(笑)。演劇を観るためだけにドイツへ行っている人は私の周りでも多いです。
──そんなオスターマイアーの突出したセンスは、一体どこから来るのでしょうか。
オスターマイアーもアイディンガーも、エルンスト・ブッシュというベルリンにある演劇学校出身なのですが、この学校、異常な狭き門なんですよ。オスターマイアーが卒業した演出コースは、合格者数が1桁なうえに、そこにドイツ全土、世界中から応募が来るからすごい倍率で。学校では演出コースと俳優コースの生徒が頻繁にコラボレートして作品を作っていくのですが、彼らの発表を観るとめちゃくちゃ面白い(笑)。創作の中でも、1つの作品をどう解釈するのか、徹底的に議論するんです。オスターマイアーの、“作品をどう切り取って現代に通じる上演にするか”というセンスが研ぎ澄まされている理由は、そういった経験の積み重ねにもあるのかもしれないですね。
“知っているけど難しい”古典を、新解釈で
──演劇学校の話が出ましたが、ドイツは演劇教育が盛んなイメージがあります。小山さんはドイツ・ハンブルクご出身ですが、演劇にはどのように触れてこられたのでしょうか。
演劇の授業があったり、劇場に定期的に足を運ぶ機会はありました。観るのは「カエルの王様」とか子供向けの演目なのですが、州立劇場のすごく上手な俳優たちが演じているのでかなり本格的で。劇場という存在は決して遠いものではなかったです。
──小さい頃からレベルの高い演劇作品に触れられるのは、貴重な経験ですね。
以前、ハンブルクのタリア劇場で、ニコラス・シュテーマン演出のフリードリヒ・フォン・シラー作「群盗」を観たとき、高校生の集団が来ていて。開演前に騒いで、近くに座っていたお客さんに「静かにしなさい」って怒られたりしていたのですが(笑)、上演が始まると、みんな夢中で観劇していたんですね。彼らと帰りの電車が一緒だったのですが、「あれはなんでこうなったんだろう」とか「ここが面白かった」とか、さっそく感想を言い合っていて、聞いていて興味深かったです。知っているけど難しい古典だなと思われるような作品を、ドイツの演出家は新しい解釈で、現代的に演出するので、作品への興味も湧きますし、子供たちにとっても刺激的な体験になる。
──劇場側も若い観客に観てもらういい機会になりますし、互いにメリットがありますね。小山さんは、ドイツでの生活がご自身の演劇観に影響を与えていると思うことはありますか?
小さい頃からドイツにいたから、どうしても影響は受けてしまっていますね。ドイツだとオペラも、古典的な作品を蛍光灯の明かりだけでやる、みたいな挑戦的な作品が多いので……(笑)。パリに行くと、美しいクラシカルな衣装のオペラもやっていて、「いいなあ」とは思うんですが、その影響は受けられなかった(笑)。
次のページ »
社会と演劇を結ぶもの













![新国立劇場[演劇] 2019 / 2020 シーズン 小川絵梨子×長塚圭史×小山ゆうな 座談会](https://ogre.natalie.mu/media/pp/static/stage/shinkokuritsu1920_1/thumb_inbox_600.jpg?imwidth=240&imdensity=1)