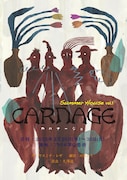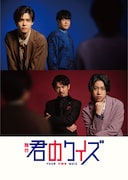東京文化会館が2021年度から展開している「シアター・デビュー・プログラム」。このプログラムでは、東京文化会館が幼少期に音楽ワークショップや子供向けコンサートに触れた子供たちのための“次なるステップ”として、多彩なアーティストを起用した青少年向けの舞台芸術を企画・制作している。
2024年7月にお目見えする新制作「木のこと The TREE」は、脚本・演出にブス会*のペヤンヌマキ、音楽監督・作編曲・ピアノに林正樹を迎えた、演劇とジャズのコラボレーション作品。自身が暮らす街の道路計画を巡り、樹木の伐採問題を目の当たりにしたというペヤンヌが“居続けること”や“共生”をテーマに書き下ろした本作に、確かな演技力と柔軟な感性を持つ南果歩が挑む。
ステージナタリーではペヤンヌと南の対談を実施。ペヤンヌと、彼女のラブコールを受けて「出演を即決した」と笑う南が、5月中旬、芽吹きつつある創作の様子を語った。
取材・文 / 大滝知里
大駱駝艦と全身金粉姿で踊ったペヤンヌマキ、演劇の真理を悟る
──ペヤンヌマキさんは、2022年に「虫めづる姫君」の台本で「シアター・デビュー・プログラム」に参加されました。「虫めづる姫君」は、「木のこと The TREE」(以下「木のこと」)にも出演される舞踏家・我妻恵美子さんが演出・振付・舞踏を担当し、加藤昌則さんが音楽監督・作編曲・ピアノを手がけた作品でしたが、当時、「シアター・デビュー・プログラム」に参加されてどのような印象を持ちましたか?
ペヤンヌマキ 平安絵巻「虫めづる姫君」を子供向けの作品にするということで、「舞踏だけでなく、言葉もほしい」と、台本の依頼をいただきました。毎月1回、音楽家の加藤さんと我妻さんと私で、セッションをするように1年かけて作品を作り上げていったのですが、その過程がすごく面白くて。実は昔、我妻さんが所属されていた大駱駝艦が開催している白馬村の合宿に参加したことがあったんです。大自然の中で素っ裸の全身に金粉を塗って踊ったのですが、それが、その後の私の人生を左右するような体験でした(笑)。そのときに学んだのが、舞踏の原点は“自ら踊るのではなく、空っぽの袋として、外からの影響で踊らされるものである”ということ。これは演劇でも大切にしているものだなと思って。そういう考え方を持つ舞踏の我妻さんと、「虫めづる姫君」でご一緒できたことも、とても良い経験でした。「虫めづる姫君」で打ち出していた、“人間も虫もみんな同じ”というテーマにも共感しましたし、そのテーマは「木のこと」にも通底すると思っています。人間も生態系の一部で特別ではないという見え方ができる作品を作れたらと。
──南さんは「木のこと」のオファーを受けた際、どのような思いが巡りましたか?
南果歩 ペヤンヌさんの作・演出だったので、「やろう」と思いました(笑)。10年くらい前にペヤンヌさんが主宰されているブス会*の公演をザ・スズナリへ観に行ったんです。東京新聞に記事が載っていて、「面白そうだなあ」と思って、次の日に1人でふらっと劇場へ行ったんですよね(笑)。実際に観たら「こんなことを考えている人がいるんだ!」と、私が一方的にペヤンヌさんのファンになりました。以降はいろいろ観させていただいています。
ペヤンヌ 「お母さんが一緒」という、2015年に上演した三姉妹の家族の話でしたね。私は南さんを舞台でずっと拝見していたので、突然来てくださったことに「まさか南果歩さんが観に来てくださるとは」とびっくりしました(笑)。南さんはどんな年齢の役でも変幻自在に演じていらっしゃる、雲の上の存在のように感じていたのですが、私が書くような半径数メートル以内の物語にも興味を示してくださったのが意外でしたし、うれしかったです。
南 さっきペヤンヌさんが、金粉姿で大地を踏みしめて踊る、外からの影響を受ける状態でいるというお話をされていて、面白いなと思ったのが、私も外からの影響を受けたいタイプなんです。わーっとのめり込む人間に見られがちなのですが、たぶん空っぽの状態でいる時間のほうが長くて。だからお芝居を続けているんだろうと思いますし、外からの影響を欲しているんだと。面白そうなことに触れて、「いつか芽が出たら良いな」くらいの気持ちで、自分の中にストックしているんですよね。今回も出会いから数年経ってペヤンヌさんから声をかけていただいて、「芽が出た!」とうれしく思っています(笑)。
少女を演じるなんて、演劇にしかできないこと(南)
──ブス会*「お母さんが一緒」でお会いして以来、いつか南さんと舞台を作りたいというお気持ちはあったのですか?
ペヤンヌ いつかご一緒できればとは思いつつ、ご一緒するならどういうお芝居が良いだろうという妄想は、心の片隅にありました。私自身、この数年で作風が変化していて、南さんが観に来てくださった当時は会話劇や一幕芝居が多かったのですが、コロナのときにはドキュメンタリーの映像を撮ったりしました(参照:ペヤンヌマキが岸本さとこに密着した選挙ドキュメンタリー「○月○日、区長になる女」上映会)。20年くらい自分が気に入って住んでいる杉並区の緑豊かな地域のアパートが、道路計画によって立退区域にされていることがわかりまして。住民の声を聞かずに都と区が進めている計画に憤りを感じたことがきっかけで、カメラを回し始めました。その中で出会った住民の方が「自分が生まれたときに植えてくれた木は絶対に守る」とおっしゃるのを聞いて、立ち退き問題に直面した西荻窪の遊空間がざびぃで都市計画道路についての舞台をやったんです(参照:ブス会*の新作「The VOICE」開幕、ペヤンヌマキ「見たことのない作品になりました」)。そこから、“人々の声から紡いでいく作品”を作りたくなったという経緯があって、「南果歩さんとやるなら、今だ」と強く思ったんです(笑)。一幕芝居の会話劇よりも大きなスケールで、語りに力があってどんな年齢の役でも演じられる南さんとぜひご一緒したいなと思いました。
南 すごくうれしいです。
──「木のこと」では、ある女の子が生まれたときに植えられた1本の木が、女の子を含む三世代にわたって、その土地や地域に生きる人々の姿を見つめる様子が描かれます。台本を読まれた感想を教えてください。
南 めちゃくちゃ面白いです! だって私が少女を演じるって、そんなの演劇でしかできませんから(笑)。少しずつ出来上がる台本を読むにつれ、ペヤンヌさんの目線が人間ファーストではなく、1本の木を拠点に、人間のエゴや思想だけでは自然界は回っていかないというメッセージを強く、でも優しく語りかけてくれていることがわかるんです。今回は「シアター・デビュー・プログラム」ということで、特に小さなお子さんも観に来られると思いますが、子供たちが楽しめる作品は、結局は大人の鑑賞にも耐えうるものになります。私は、初めての体験は早ければ早いほうが良いと思っていて。例えば、修学旅行で京都に行って、当時は何もわからずに見ていた建造物が、大人になって再び訪れたときに“答え合わせ”ができる。そういうことってたくさんあると思うんです。だから答え合わせの機会を増やすためにも“何事も体験すること”が大切で。今回、子供たちが気兼ねなく観劇できる場で、自然と人間の共存を題材にした作品を上演するのは、ぴったりだなと思いました。
“語り継がれていく”昔話の成り立ちを作りたい(ペヤンヌ)
──“共生”や“共に居続ける”というテーマと、木と少女の交流を具体的にどのように見せるのか、作品の構想を教えてください。
ペヤンヌ 木の時間と人間の時間を考えたときに、木からすると人間は移り変わりが激しい、人間の時間は速いということが念頭にあったのですが、実際に台本を書いてみると、想像以上に人間の時間的感覚が速かったんです(笑)。するとなおさら、自分たちとはまったく違う時間軸で生きる木を、人間が街路樹などで勝手に植えては切っているという事実に疑問もあって。舞台上では、木だけが変わらずにそこに居ることを見せ、さらに木の役を我妻さんに演じていただくことで、木が生き物であるというということを、見た目にもわかりやすく提示しようと思っています。
南 人間の時間って本当に瞬きのように過ぎていくんですよね。私が演じる少女は年を取って結婚し、いろいろな経験をするんですけど、人間と樹木という違いはあれど、自分が生まれたときに植えてもらった木と心を通わせる時間を過ごすんです。先ほど言った通り、少女を演じることも楽しいけれど、木との対話も楽しくて。何より自分と共に育っていく木と対話するというシチュエーションが、とても素敵に描かれているんです。
ペヤンヌ 1本の木を軸に、周囲の話が展開し、南さんの語りが入って、物語として“語り継がれていく”形にしたくて、新作だけど、昔話の成り立ちみたいなものを感じ取ってもらえると良いなと思っています。最近、人間の生物としての感覚が失われていっているんじゃないかと思うことがあって。
南 こちら側の?
ペヤンヌ そう。私が山に囲まれて育ったからかもしれないのですが、もっと土を踏んで原始的な生活をしていたら、木は簡単に切ってはいけないと肌でわかる気がするんです。都会に住んでいるとその感覚が失われちゃうから、都市開発も都合良く進められてしまうのではないかなと。演劇を観ることによって原始的な肌感覚を少しでも取り戻してもらえたらと思っています。
次のページ »
芝居、ダンス、音楽のセッションが劇場中に広がる作品に