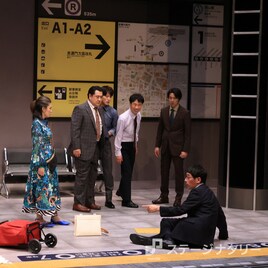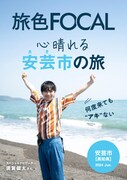半径5cmのお話ばかりじゃ物足りない
──加藤さんは舞台での活動と並行し、テレビドラマの脚本も多数手がけています。古田新太さん主演の「俺のスカート、どこ行った?」ではゲイで女装家の高校教師を巡る学園もの、稲垣吾郎さんらが出演した「きれいのくに」では美容整形が当たり前となった世界が舞台になるなど、トリッキーな設定の中で描かれる普遍的なテーマが話題を呼びました。一方の舞台では、友達や親子、夫婦といったごく日常的な関係性の中にある“異常性”が暴かれていくストーリーが高い評価を得ています。メディアによって意識的に書き方を変えているのでしょうか?
変えています、やっぱりドラマと舞台では観客の条件が違うので。ただどちらも共通しているのは、“大きな物語”を描きたいということです。“大きな”と一口に言うと雑ですが、それは信じやすさの強度だったりいろいろあると思っていて、大きな物語を描くために、小さな話から出発して大きな話になったり、大きな話から始めて小さな話になったりというように、配合を変えながら作劇しています。例えば昔は、大雨や嵐のように人間の力ではどうしようもないものに対して祈りを捧げていました。自分たちの力ではどうしようもないものに対して心の安定を図ろうと、神様を信じるといった大きな物語が必要だった。でも時代が進むにつれて、祈るだけじゃ効果がなくて非効率だし無駄だからと、傘を持ったほうがいいとか、非常食を備蓄しようとか、現実的な対策を求めるようになってきた。すると、大きな物語を信じる理由も必要性もなくなって、半径5cmくらいの小さなお話のほうが信じやすいし、信じられるようになり、必要とされるようになったと考えています。それが、コロナ禍によってまた、いわゆる陰謀論のような大きな話をみんなが信じるようになってきた。自分たちの力ではどうしようもない事象を、自分がわかる範囲の話に落とし込んで、心の安定を得ようとしているのだと思いますが、その変化がすごく人間らしいと思います。
また、映像と演劇ではその信じやすさの強度だったり、大きさみたいなものを確保する部分は違うので、「メディアによってアプローチを変えています」と一口に言っても変わるかどうかは難しいです。そもそも変化し続ける物語の持つ役割というものも、時代も含めて、改めて自分のためにも考えないといけない。ただただ世間や社会に言いたいことがあるなら、ネットでコラムを発表するほうがコスパは良いと思います。メディアを問わずそこは考え続けていきたいです。
──大きな物語に対する意識は、演出面でも強く感じます。加藤さんはとても忍耐力のある劇作・演出家だなという印象があって。小さな盛り上がりを小出しにして観客の集中力をつなぐのではなく、最後の画を見せるまで集中力を途切れさせない空間を作り出しますよね。例えば「たむらさん」は二人芝居でしたが、大半が橋本淳さん演じる田村の語りで構成され、豊田エリーさんは舞台の奥のキッチンで、客席に背を向けたままずっと料理をしていました。料理ができあがっていく時間の流れと、「いつになったら女性は話し出すのだろう?」という緊張感、そしてずっと呑気な回想を繰り広げていたはずの田村が、徐々に深刻な語り口へと変化していくスリリングさに圧倒されました。
確かにそういう描き方が好きかもしれませんね。近年、映画やドラマは、物語の冒頭3分で事件を起こす傾向があるじゃないですか。もちろんそうしないとお客さんが付いてこないという問題もあるので、鶏が先か卵が先かって問題かもしれないですけど。
“面白がれるものが増える場所”を目指して
──映像でも舞台でも、作品がどんな日常から生まれるか、どんな日常と接続していくかということが、加藤さんの作品にとって非常に重要だと思います。コロナ禍によって日常が変化しつつある今、描きやすくなったことや描きにくくなったことはありますか?
僕自身にとっては、これまで見えていなかった部分が見えたりして、この状況変化がそれほど嫌だとは思ってないんです。ただ、時代によってお客さんの作品の受け取り方が変化するように、物事の捉え方が変わってしまったとは感じます。そこにアジャストすべきなのか、それともいずれコロナは終焉を迎えるであろうと考えて、アジャストせず普遍的なものにもっとこだわるべきなのか……そこに迷いはあります。
──今回の「友達」に、現在の状況を反映させる予定は?
それはないです。
──また昨年、た組でも配信公演を実施され、2020年5月の時点では「僕個人的には、このプラットフォームに作家が求める創作に必要な性質が担保できるのであれば、もっといろいろ試していいと思いますし、個人的にはまだ試すつもりでいます。いずれこの形の発表が何と呼ばれるようになるのかはわかりませんし、試していった結果、僕の求める性質の担保はできなかったからもう二度とやりませんとなるかもしれません。演劇は演劇でまた劇場でやりたいです」と書かれていました(参照:それぞれの思いを胸に動き出す、劇作家、演出家、俳優、ダンサー、プロデューサーたち)。その後、劇場公演も実施されていますが、演劇というメディアに対しては現在、どんな可能性を感じていますか?
難しいですね。作品を作るたびに自分にとっての演劇の輪郭がはっきり見えたり、逆にぼやけたりするんですけど……どうなんだろう。個人的に僕が演劇を求めてしまうのは、やっぱりコミュニティの問題なのかな。演劇の要素として、“場の共有”ということがかなり高いんだってことを再認識しました。そういったコミュニティの共有を、僕は演劇に求めているのかもしれません。
──インタビューの冒頭で、「友達」を通して、定義された言葉の意味の反転について考えたいとおっしゃっていました。この1年、“演劇”の定義もいろいろと問い直されたと思いますが……。
そうですね、すごく揺らぎましたね。僕自身も作品を作るたびに演劇の定義が更新されたりしています。ただ、僕は演劇をやったり、観劇することで自分の中に新しい物差しが増えていく感じがあって。共感だけが演劇の価値基準になるのは寂しいし、演劇が“面白がれるものが増える場所”であり続けられれば良いなと思います。
- 加藤拓也(カトウタクヤ)
- 1993年12月26日、大阪府生まれ。脚本家・演出家・監督。劇団た組主宰、わをん企画代表。17歳でラジオ・テレビの構成作家を始める。18歳でイタリアへ渡り、映像演出と演劇について学び、帰国後、劇団た組。(現在は劇団た組)を立ち上げた。2017年、「壁蝨」で若手演出家コンクール2017の優秀賞を受賞したが辞退。2018年、「平成物語」でドラマ初脚本を手がけ、第7回市川森一脚本賞にノミネートされた。近年の舞台作品には、三島由紀夫没後50周年企画「MISHIMA2020」の「『真夏の死』(『summer remind』)」(作・演出)、シス・カンパニー公演「たむらさん」(作・演出)、劇団た組「私は私の家を焼くだけ」(脚本・演出)、映像作品には、テレビドラマ「俺のスカート、どこ行った?」(脚本)、「不甲斐ないこの感性を愛してる」(監督・脚本)、「カフカの東京絶望日記」(監督)、「死にたい夜にかぎって」(脚本)などがある。
次のページ »
広瀬アリス&岩井秀人が明かす「私が知っている、加藤拓也の横顔」
2021年7月21日更新